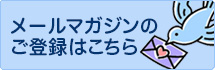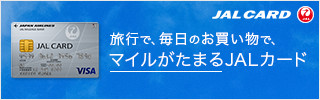2011年2月/第89回 フィドルの越境者たち
ヴァイオリンを民俗音楽で使う場合に、英語で「フィドル」と呼ぶことがある。
楽器自体や奏法に、大きな変化があるわけではない。どちらかといえば「気分」の問題だ。フィドルの方が、俗っぽい。
近代になって、メロディとリズムの分業が進んでいくうちに、音楽は自由な躍動感を失っていった。整備され、クリーンにはちがいないが、生命力や訴求力の点で、物足りなく感じられるときがある。
かつてはサラサーテやクライスラーなど、たくさんの華やかなスターがいたのに、その後のヴァイオリンは、次第に地味な楽器になっていった。そのことと、分業制の進行とは、けっして無縁ではない気がする。
もともとヴァイオリンは、メロディを歌うだけでなく、リズム楽器でもある。フィドルと呼ぶとき、そこには野性の匂いと敏捷な肉体が、感じられる気がする。
このところ、フランスを中心に、ヴァイオリニストたちがさまざまな越境を試みている。コパチンスカヤは、民俗音楽の演奏者である両親とともに、母国モルドヴァの音楽をひいたアルバム「ラプソディア」をつくり、映画「オーケストラ!」で吹替え演奏をしたサラ・ネムタヌは、「ジプシック」でロマの音楽を奏で、また弦楽四重奏のエベーヌ四重奏団は、映画音楽などを集めて「フィクション」という1枚にまとめ、美声まで披露した。
けっしてお遊びではなく、自分たちのルーツを省察することで、音楽家としての姿勢そのものを提示しようとする覚悟が、それぞれに感じられるのがいい。かれらのこれからが、ますます楽しみに思えてくるのだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン