コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」
<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>
ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー
第185回/ネック問題 [鈴木裕]
|
日本語の「ネック」。意味としては、「首」や「首の部分」というのがまず出てくる。「ネックレス」や「ハイネック」のように他の言葉と接続して使われることも多い。そして2番目の意味が「ボトルネック」を省略した言葉で、「物事の障害になっていること」だ。この二つめの意味の話。 オーディオシステムにもネックが存在している時がある。たとえばCDプレーヤー、プリメインアンプ、スピーカー。この比較的シンプルなシステムでも、プレーヤーとアンプの間を接続するケーブルがネックになっている場合、そこを性能のいいものに変更することによって、再生音は良いものになる。あるいは、CDプレーヤーとかアンプ自体がネックになっていることもあるだろう。どこがそのシステムの「ネック」になっているか把握できると再生音のグレードアップを効果的に行える。 と、わかったようなことを書いているが、うちのオーディオでネックになっていた問題が解決して音が2倍ほども良くなった。もちろん、一般的には5%とか10%とか、あるいは電源系などでは30%改善する時もあるが、100%アップということなのだ。我ながら浅はかな言い方だとは思う。海援隊の「あんたが大将」の歌詞ではないが、自慢話は嫌われるのであまり書きたくないのだがこんなに良くなる例もあるということでご報告申し上げたい。 |
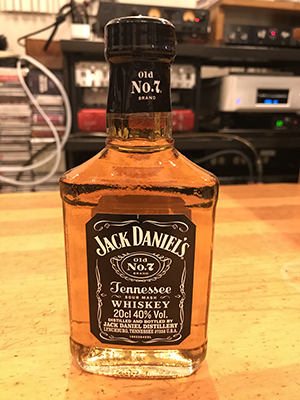 ボトルのネックは瓶の上の部分のこと。もしここが太ければ、中身はドバーッと出てしまう。ウィスキーの場合、それは困るので細くなっているのだろう。オーディオの信号ケーブルだと……。 |
 パラメトリック・イコライザーとパワーアンプの間に使ってきたケーブル。左からスタジオ等で使うカナレの線材、ベルデンの非オーディオ用、そしてMITのバランスケーブルにXLR-RCAの変換アダプターを付加したもの。ここがネックだった。 |
その後、いろいろな音楽を聴いてきた。中学生の頃から聴いてきたレコードや、かつては良く聴いたCDの100枚とか200枚である。あるいはハイレゾのサンプリング周波数の高いもの。特徴的な音調、サウンド。演奏の温度感の高いもの、低いもの。いろいろと聴いたのだがそのうちにひとつの不満が鎌首をもたげてきた。壺からコブラが顔を出すようなものだ。ペロペロとふたつに分かれた舌を出して、左右を見ている。気になる音の成分が共通していて、気になりだすとやはりこれを放置しておくわけにはいかない。原因はあそこだ。間違いない。わかっていながら自分自身に嘘をついてきた。自分自身を偽って生きてきた。 うちのシステムにはプリアンプとパワーアンプの間にパラメトリックイコライザーが入っている。マスタリングスタジオなどで使うアヴァロン・デザインのAD2055。業務用なので、入力も出力もXLR端子しか装備していない。それに対して、サンバレーのパワーアンプSV-2PP(2009)の入力端子はRCA端子のみ。これが以外と小さくない問題だった。送り出し側はXLRで、パワーアンプの入り口はRCA。しかも4..5m程度の長さが必要で、電磁波対策もしっかりしているもの。ここのケーブルがネックだった。 |
その次に使っていたのはスタジオなどで標準的に使われているカナレのケーブル。これに該当する端子を付けて作ってもらった。まじめな音で低域の音像の形などはきちんと出るのだが、いかんせん音の色彩感や音像のフォーカスの合い方、空間表現力などに不満が残った。ひとことで言ってパッとしないのだ。これで音楽制作をやっているのだから十分なクォリティが確保されているとおっしゃる方もいるが、比較するといろんなポイントで伝わっていない要素がわかってしまうのがオーディオの恐ろしいところ。
|
次に導入したのがベルデンのケーブル。非オーディオ用の配線材だという。これに端子を付けて作ってもらった。低音の音像感が芳しくなく茫洋としてしまうが、中高域にはそれなりの精彩感があり、フォーカスは悪くなかった。3年くらい使ってきたが、うちのオーディオのさまざまな要素が良くなって来る中で取り残されたパートだった。ネックはここ、間違いない。わかってはいた。わかってはいたがついつい日々の何かに追われて流してきた。 |
 Salum T(セイラムT)で作ってもらった、XLR-RCAのケーブル。 |
低域の剛性感が上がるのは予想していたが、それによって中域も高域も実体感が上がって、音像の3次元的なボディ感や定位がものすごく良くなっている。また、そういったものが見えてくる空間自体の透明度、静けさ。さすがのシールド性能であり、タイロンという特別な絶縁体の効力も著しいのだろう。楽器の響き成分やホールの鳴りが見事に見えてくる。鮮度感の高さ、瑞々しさも5ランクくらい上がって、音の表面のツルツルしていたり、ザラザラしていたりという質感表現力も抜群だ。
|
そしてそういったオーディオ的な精緻な情報量と共に感動するのは、音の勢いが凄いこと。全体的に密度やエネルギーの総量が上がっていることとも関係している。グランカッサとシンバルが強打した時の迸ってしまう感じには唖然とさせられる。また、低域のエネルギーも高く、ティールからアヴァロンに変更して、最低域のレンジやフローリングの床を揺らすような馬力が下がってしまっていたのが復活している。 |
 ここのところ、スピーカーやボトルネックとなっていたケーブルが変わって、音がどんどん良くなっているうちのシステム。 |
全体的な音としてはリアルで生々しい音。変な言い方だが、再生音という感じではなくなってきた。音楽に近く、現場にいる感じが強い。中学生の頃から聴いているストラヴィンスキーの《春の祭典》、ブーレーズ指揮クリーブランドの1969年の録音を、レコードとCDとSACDでしつこく聴いてみたりもするのだが、歪みっぽい成分を持っていないのでどんどんボリュームが上がってしまう。その時のエネルギッシュで怒濤の再生音たるや。45年くらいこの録音を聴いてきているが、ほんとはこういう演奏だったんだという感慨にふけったりもする。現代オーディオ、どんどん精緻で高級な方向に行っているが、膨大な情報量を持ちつつも、このヴァイタリティのある奔放な音は何なのだろう。 結果として頭の方に書いたように、倍くらい音が良くなったという阿呆な言い方に。どれだけこのパートがボトルネックだったのか。大げさだが、ケーブル一本で人生が変わった。CDプレーヤーからスピーカーまでの流れをセイラムTで統一、徹底することの威力に打ちのめされている。 |
コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー















