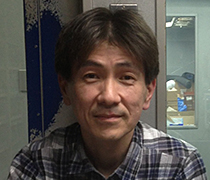コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」
<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>
ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー
第219回/"オーディオ"概念の下限を思い切って引き下げてみる [炭山アキラ]
第211回で、鈴木裕さんがオーディオ初心者の皆さんへ向けて、含蓄に富んだ話をなさっている。便乗して"業界安い方担当"の私も、「オーディオ趣味の取っかかり」について話していきたいと思う。
(2019年5月10日更新) 第218回に戻る 第220回に進む
お持ちの機器との接続方法|
中高年の思い出話で申し訳ないが、私の少年時分には「免税ステレオ」と呼ばれるジャンルの製品群があった。AM/FMチューナー内蔵アンプの天板にレコードプレーヤーがマウントされた一体型のセンターコンポに、ごく簡素なスピーカーが2本というセットである。なぜ"免税"かというと、1989年に3%の消費税が導入されるまで、ぜいたく品には10~20%程度の物品税が課されていた。確かオーディオでは15%だったように記憶している。ところが、この税には除外規定があって、例えばオーディオなら完成品は課税、パーツを自分で組み立てるキット商品は非課税だった。また、セットで1万2,000円を下回る製品も非課税となり、それで1万2,000円以下のセット・ステレオが「免税ステレオ」と呼ばれていた、というわけだ。 もちろん、アンプにラジオとプレーヤーがつき、スピーカーまでセットでそんな価格だから、センターコンポの筐体はペナペナの樹脂製だったし、スピーカーだってごくごくシンプルなフルレンジ・タイプがほとんどだった。そんなもので「オーディオ」などといっていいのか? と思われるかもしれないが、私にいわせれば、あれはまごう方なき「オーディオの入り口」だった。 |
 物品税がなくなって久しく、もちろん今は"免税ステレオ"も過去のものとなったが、往時の面影を最も色濃く残すのは、このティアックLP-R520であろう。プレーヤーとAM/FMワイド対応ラジオチューナーはもちろんのこと、カセットにCD-Rデッキまで装備されているから、当時のものよりずっと豪華版ではある。残念ながらスピーカーまで一体化されているから、「腕前で音質向上する」余地は免税ステレオより小さいが、それでも一聴して「おっ!」と思わせるサウンドを持つ。
物品税がなくなって久しく、もちろん今は"免税ステレオ"も過去のものとなったが、往時の面影を最も色濃く残すのは、このティアックLP-R520であろう。プレーヤーとAM/FMワイド対応ラジオチューナーはもちろんのこと、カセットにCD-Rデッキまで装備されているから、当時のものよりずっと豪華版ではある。残念ながらスピーカーまで一体化されているから、「腕前で音質向上する」余地は免税ステレオより小さいが、それでも一聴して「おっ!」と思わせるサウンドを持つ。 |
|
これは私の持論なのだが、オーディオは「何を使うか」よりも「どう使うか」が死命を制すると考えている。今は購入後にしっかりとインストールとセッティングまで請け負ってくれるショップが増えたから、"ちゃんとした"オーディオをそろえていらっしゃるマニアはほぼ心配ないのだが、オーディオというものは置き方やちょっとしたアクセサリー類の活用で天と地ほどにもその再生音が変わってしまい、ただ買ってきてその辺にポイと据えてやるだけでは、まずその実力は発揮できておらず、いいところ1~2割程度と考えてよい。 裏返していうと、それは「オーディオの再生音はユーザーの腕次第」ということでもある。もちろん制限はあるが、ユーザーの腕前で音質アップを図ることができる最下限のステレオ装置として、免税ステレオが存在していたといって差し支えないのではないかと思うのだ。例えばスピーカーの置き方をほんの少し見直してやるだけで、免税ステレオは明らかに音が変わることが分かった。「手をかけてやると音が良くなる」ということが分かれば、オーディオという趣味の入り口に立ったも同然だ。私自身も、免税ステレオでこそなかったが、当時隆盛を極めていたFM雑誌のオーディオコーナーに記されていたスピーカー・セッティング記事を読み、自宅のシステムコンポをセッティングし直したら、その音の変化・向上に茫然としてしまったことが、この業界へ深入りするきっかけとなった。 また、免税ステレオで多用されていたフルレンジ・スピーカーというものは、低音も高音も制限があるし、まぁ安っぽい音のものが多いというのも否定はしないが、一方でマルチウェイ・スピーカーにとって必要悪というべきクロスオーバー・ネットワーク素子が存在しない、という大いなる利点を持つ。 |
 製品数自体は決して多くないが、本格オーディオへ属する製品にもフルレンジ・タイプは存在する。写真のデンソーテン「Eclipse TD」スピーカーは、フルレンジ・ユニットを強固で大重量のベースへマウントし、発音の基点を明確にしつつ振動を速やかに床、あるいはスタンドへ逃がすという作りを持つ。世界の一流エンジニアが小型モニターとして採用している逸品である。
製品数自体は決して多くないが、本格オーディオへ属する製品にもフルレンジ・タイプは存在する。写真のデンソーテン「Eclipse TD」スピーカーは、フルレンジ・ユニットを強固で大重量のベースへマウントし、発音の基点を明確にしつつ振動を速やかに床、あるいはスタンドへ逃がすという作りを持つ。世界の一流エンジニアが小型モニターとして採用している逸品である。
|
マルチウェイのスピーカーは、コンデンサーやコイル、抵抗器などを使って、ウーファーなら中~低音、トゥイーターなら高音を選択して入力してやる必要がある。それをやらなければ、ウーファーの高域が出っ放しだと音が大きく濁り、トゥイーターの低域を切ってやらないとあっという間にボイスコイルが焼き切れてしまうのだ。 こういったネットワーク素子は、スピーカーユニットにとって不必要な帯域を排除するだけでなく、全帯域が素子を通ってしまうものだけに、楽音にも少なからざる影響を及ぼす。それゆえ"必要悪"と呼ばれてしまうのだが、その一方でフルレンジ・スピーカーは、原理的にネットワーク素子の悪影響がなく、それだけ軽々と音離れ良く、どちらかというと生々しい音の再生を得意にする傾向がある。ごくごく安物の免税ステレオから、時に「おやっ?」と思わせるボーカル再生が聴こえることがあったのは、このためだ。 いやはや、マルチウェイとフルレンジについて書き始めると、本当に切りがない。本稿のテーマから外れてしまうので、これ以上はまた回を改めることとしよう。 |
|
もう物品税が廃止されてからでも今年で30年、こんなご時世にも免税ステレオ的なセットものコンポーネンツは、いまだ生き残っている。それも2~3万円から買えるだなんて、時代の推移を考えても信じられないような思いだが、それらでもその気になれば十分、私が冒頭に提示したところの「オーディオの入り口」へ立つことはできる。例えばスピーカーを床の反射を受けない高さに上げてみたり、簡単なインシュレーター(まずは硬貨でもよい)を挟んでみたり、センターコンポやスピーカーの筐体を鳴き止めしてみたり、そうしてやるとこんな"安物"でも、明らかに音が向上することが分かる。 何のことはない、そういう実験をもう4年も繰り返しているのが、私と荒川敬さんの番組「オーディオ実験工房」である。もちろん数百万円の装置にも役に立つ実験を続けている自負はあるが、大半の実験は同時に「オーディオ入門」クラスにも役立つものと信ずる。 これまで「オーディオって難しそうだし、高くつきそうで……」と二の足を踏んでおられた人は、ぜひ「ギリギリからの第一歩」を踏み出してみられてはいかがだろうか。息の長い趣味として、結構楽しめると思うし、私個人も協力を惜しまない。疑問が浮かんだら、番組宛てに質問のお手紙やメールを頂ければ、番組で取り上げるなり個人的に回答するなりさせていただくことをお約束しよう。 |
 往年の免税ステレオは20世紀の終わり頃へかけて「ミニコンポ」へ変貌を遂げ、スマホとイヤホン全盛となった現代にも、ある意味でその命脈は続いている。写真はオンキヨーのミニコンポX-U6だが、単体ではCDとラジオが聴けるほか、USBメモリを挿したりBluetoothで飛ばしたりしてMP3音声を聴くことも可能となっている。それで2万円くらいで買えるのだから、その廉価ぶりにもたまげる。それでいて、スピーカーのセッティング変更や、ちょっとしたインシュレーターなどの使用で、音質をグッとアップさせられるのだから、絶対的な器の大小は致し方ないにしても、「オーディオの第一歩」としては認めてよいのではないかと、個人的には考えている。
往年の免税ステレオは20世紀の終わり頃へかけて「ミニコンポ」へ変貌を遂げ、スマホとイヤホン全盛となった現代にも、ある意味でその命脈は続いている。写真はオンキヨーのミニコンポX-U6だが、単体ではCDとラジオが聴けるほか、USBメモリを挿したりBluetoothで飛ばしたりしてMP3音声を聴くことも可能となっている。それで2万円くらいで買えるのだから、その廉価ぶりにもたまげる。それでいて、スピーカーのセッティング変更や、ちょっとしたインシュレーターなどの使用で、音質をグッとアップさせられるのだから、絶対的な器の大小は致し方ないにしても、「オーディオの第一歩」としては認めてよいのではないかと、個人的には考えている。
|
コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー