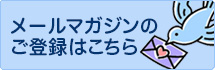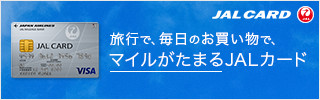<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>
ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー
第275回/自分が喉の乾いた馬だった話[鈴木裕]
イギリスの諺に「馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない」というのがあるが、いまの日本って音楽に囲まれるように生活していて、音楽が不足している感覚はない。でもいい生演奏に接したり、いいオーディオでいい録音を再生すると、実は自分が音楽に飢えていたことを自覚する、という話。
まず、10月2日(金)~4日(日)。”サントリーホール ARKクラシックス”と題されて、8つのコンサート/リサイタルが大ホールと、小ホールであるブルーローズで開催された。4日のマチネ「ベートーヴェン 室内楽名曲選」を聴きに行って全体に良かったのだが、その中の小林美樹(vn)と田村響(pf)による「ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」」が個人的にはツボだった。ブルーローズの木製の壁の響きともあいまって、倍音をたくさん含んだふくよかなヴァイオリンの音色が衝撃的に良かった。1楽章冒頭の♪ラ~ ソファミファソファミレド~♪という歌いだしからして虜に。いわゆる鷲掴みだが、つかまれたのは鼓膜なのか肌の皮膚感覚なのか、はたまた聴覚を情報処理する大脳の古皮質か。枯れていない楽器をドミナント弦(G線、D線、A線の、弦の芯がナイロン製の構造のもの)で鳴らし切った、現代のヴァイオリンの美音を初めて聴けたような気がした。その歌い口の濃さ、”歌”自体の瑞々しいセンスももちろん素晴らしかったのだが。
|
|
 小林美樹さんのウェブサイトの表紙より。番組にもげストに来ていただいた(ユーチューブでのコメントなどはこちら)。
小林美樹さんのウェブサイトの表紙より。番組にもげストに来ていただいた(ユーチューブでのコメントなどはこちら)。
|
 加藤訓子さんたちによる”TRIBUTE TO MIYOSHI「三善 晃 マリンバの世界」”。加藤さんの成熟したプレイと若手たちのダイナミックな演奏の対比が印象的だった。
加藤訓子さんたちによる”TRIBUTE TO MIYOSHI「三善 晃 マリンバの世界」”。加藤さんの成熟したプレイと若手たちのダイナミックな演奏の対比が印象的だった。
|
|
11月5日トッパンホール。マリンバ奏者の加藤訓子と若手の3人による”TRIBUTE TO MIYOSHI「三善 晃 マリンバの世界」”も、音楽の何たるか、マリンバという楽器の意味について新鮮な発見があった。若手奏者たちによる若さいっぱいに叩くマリンバはまさしく叩きつけるという意味での打楽器で、強い点が連続するフィジカルな音響に聞こえたのに対し、加藤訓子が演奏していた楽器は同じマリンバなのに、メロディと和声を表現するための音楽的な何かだった。ピアノもある種打楽器だが、通常はそういう言い方をしないし、弾き方をしない。そういう意味での余韻の長い楽器としてのマリンバ。要は強く叩きすぎず、センシティブなタッチで弾いている、ということなのだが。加藤訓子が弾くと音にスラーがかかる、という言い方をしてもいい。しかも音響自体を聴かせたいのではなく、そこから喚起されるイメージというか、ステンドグラスの原色を重ねて複雑な色合いに混ぜこんでいくさまを聴かせるような営み。この想像力に訴えかけてくる音色の綾が実に美しかった。なぜイギリスのレコードレーベルからこの10年間で6枚のアルバムをリリースできているかの理由を体感させてくれた。
|
11月の19日(木)と20(金)の2回、よみうり大手町ホールで開催されたのが、久石譲によって“現代の音楽”をナビゲートするコンサートシリーズ「
MUSIC FUTURE vol.7」。その20日を見ることが出来た。いわゆるミニマルミュージック的な要素の多い、リズミックな曲が多い構成でカラダが動いてしまうのを我慢しながら楽しめたコンサートだった。
冒頭は久石譲の作曲による「2 Pieces 2020 for Strange Ensemble」。15人程度の室内オーケストラだが、メンバーそれぞれがとても積極的。中でもトランペットとトロンボーンの二人がマウスピースのみで吹くメロディが何か笙(しょう)の響きのようにも聞こえてきて、日本のいにしえの時代からの時間を感じさせた。2曲目のジョン・アダムス「Gnarly Buttons for Clarinet and Small Orchestra」。3楽章構成の曲だがあえて俗な書き方をすると、1楽章のショスタコーヴィッチの室内楽的な感じのところからバルトーク的な騒然としたサウンドになり、そこから扉が開いて、かつて見たことがないような絢爛たる世界が出現するさまに陶然とした。あるいはこの曲ではクラリネットコンチェルト的な面もあるのだが、このソロを吹いたマルコス・ペレス・ミランダが最高だった。テノール歌手が演奏会形式の歌唱でもついオペラの舞台での動きをしてしまうように、音楽をカラダの動きも伴って表現する濃密なプレイ。バンドマスターの西江辰郎はじめ、新日フィルのメンバーが多かったが、あとで調べてみるとマルコスもその副首席クラリネット&バスクラリネット奏者。何か最近の日本のオケの積極性の理由を垣間見れた気がした。
|
|
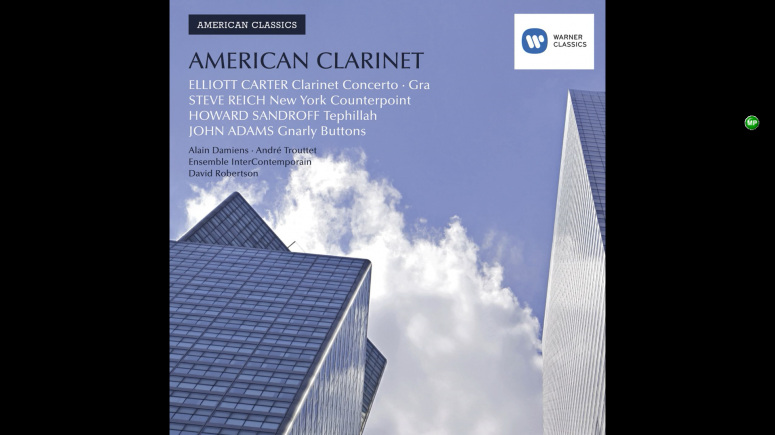 ジョン・アダムスのGnarly Buttons, for clarinet and small orchestra (1996)。3楽章から構成されている。ユーチューブで違う奏者たちの演奏を聴ける。I. The Perilous Shore、II. Hoedown (Mad Cow)、III. Put your loving arms around me
ジョン・アダムスのGnarly Buttons, for clarinet and small orchestra (1996)。3楽章から構成されている。ユーチューブで違う奏者たちの演奏を聴ける。I. The Perilous Shore、II. Hoedown (Mad Cow)、III. Put your loving arms around me
|
 ニコ・ミューリーのBalance Problems。ユーチューブでの動画はこちら。
ニコ・ミューリーのBalance Problems。ユーチューブでの動画はこちら。
|
|
休憩を挟んでのニコ・ミューリー「Balance Problems for Chamber Ensemble」。舞台左からヴァイオリン、フルート、クラリネット、ヴィオラ、トランペット、チェロ、ギターという編成からの緻密にして開放的なサウンド。ブライス・デスナー「Skrik Trio for Violin, Viola and Violoncello」はタイトル通り、弦楽器3人の編成だが、奥にチェロの富岡廉太郎がまっすぐ客席側に向き、それに直角に左にヴァイオリン西江辰郎、右にヴィオラ中村洋乃理が対峙するような配置。ソーシャルディスタンス的な意味からいうと一番やってはいけない位置関係だが、そのがっぷり四つな配置の必然性を感じさせる気の入ったプレイ。
|
そしてラストは再び久石 譲「Variation 14 for MFB」。かつての”現代音楽”はストイックで土門拳の写真集のようなコントラストの強い雰囲気の曲が多かったが、ここで聴けた”現代の音楽”はある種官能的でダンサブルで、現代のダークな色味も混ざりつつもカラフルだった。曲も良かったが演奏自体がきわめて積極的で、それは客席も巻き込んでオーディエンスもグルーヴを生み出して参加しているかのようなコンサートだった。
清水葉子さんがコラムでゲルギエフ/ウィーンフィルのコンサートに行ったことを書いたことに付随して「咳もしない、うたた寝もしない、無駄な物音も立てない。演奏も凄かったけど客席の集中力もハンパなかった。」と記したているが、演奏者、オーディエンスの両者が生の音楽に飢えていたからの何かだったのかもしれない。生きた音楽の威力を感じさせてくれたし、実は自分の耳だか心だかが音楽に飢えていたのを知らされた。
|
|
 清水葉子さんのコラム「ウィーン・フィル〜コロナ禍の来日公演」
清水葉子さんのコラム「ウィーン・フィル〜コロナ禍の来日公演」
|
(2020年11月30日更新)
第274回に戻る 第276回に進む
 小林美樹さんのウェブサイトの表紙より。番組にもげストに来ていただいた(ユーチューブでのコメントなどはこちら)。
小林美樹さんのウェブサイトの表紙より。番組にもげストに来ていただいた(ユーチューブでのコメントなどはこちら)。 加藤訓子さんたちによる”TRIBUTE TO MIYOSHI「三善 晃 マリンバの世界」”。加藤さんの成熟したプレイと若手たちのダイナミックな演奏の対比が印象的だった。
加藤訓子さんたちによる”TRIBUTE TO MIYOSHI「三善 晃 マリンバの世界」”。加藤さんの成熟したプレイと若手たちのダイナミックな演奏の対比が印象的だった。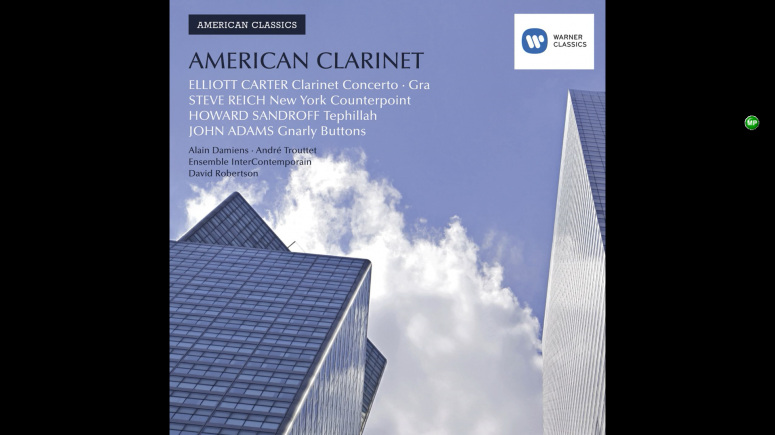 ジョン・アダムスのGnarly Buttons, for clarinet and small orchestra (1996)。3楽章から構成されている。ユーチューブで違う奏者たちの演奏を聴ける。I. The Perilous Shore、II. Hoedown (Mad Cow)、III. Put your loving arms around me
ジョン・アダムスのGnarly Buttons, for clarinet and small orchestra (1996)。3楽章から構成されている。ユーチューブで違う奏者たちの演奏を聴ける。I. The Perilous Shore、II. Hoedown (Mad Cow)、III. Put your loving arms around me ニコ・ミューリーのBalance Problems。ユーチューブでの動画はこちら。
ニコ・ミューリーのBalance Problems。ユーチューブでの動画はこちら。 清水葉子さんのコラム「ウィーン・フィル〜コロナ禍の来日公演」
清水葉子さんのコラム「ウィーン・フィル〜コロナ禍の来日公演」