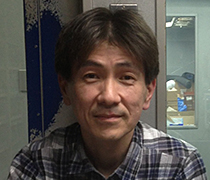コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」
<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>
ミュージックバード出演中のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー
第279回/目方の軽いは七難隠す!?[炭山アキラ]
|
昨2020年も押し詰まった12月28日に発売された季刊アナログ誌の第70号で、当コラムでもおなじみの田中伊佐資さんを司会に、小原由夫さんと私の3人で、トーンアームについて鼎談している。おそらく「アナログに最も金をかけている」小原さんと「最も金をかけていない」私が入った鼎談だから、話が噛み合わずシッチャカメッチャカになるかと思いきや、伊佐資さんの絶妙な司会ぶりもあって、かなり実りの多い内容になったと感じている。 個人的に面白かったのは、小原さんがメカニズム的に気に入ったら使ってみたくなって購入するとおっしゃっているのに対し、私が「気に入ったカートリッジを万全に生かすため」の"カートリッジの乗り物"としてのアーム選びを提唱していることだ。これはどちらが正しい、間違っているというものではなく、小原さんがアームを「愛着のある"趣味の対象"」として見ているのに対し、私はどちらかというと実用品というか、カートリッジをより好ましく支える"実直な道具"を求めている、という風に解釈することができる。 オーディオにこだわる趣味人としては、もちろん小原さんの方が"正しい"姿勢なのだろう。しかし、私はどうも身に染み付いた貧乏性というか、いや、実際に貧乏なのだが、理論と現認でギリギリまで見定めてからでないと、特に高額なものへ手を出すことは憚られるのだ。おそらくこの性分は、今ほど貧乏でなくともそう大きく変わらなかったことであろう。 |

季刊analog誌Vol.70。手前味噌ながら冒頭の3者鼎談も読み応えがあるし、日頃あまり取り上げられることのないトーンアームを相当の物量で大特集しているのは圧巻である。ぜひお手に取っていただけると幸いだ。 |

ViVラボラトリーのリジッドフロート・7インチタイプ。この短さは、ピュアストレート・アームでなければ成立しないのではないか。いろいろな意味でギリギリの設計だが、これでなければ味わえない音の世界が厳然と存在する。 |
とはいうものの、現用プレーヤーのパイオニアPL-70を中古購入した時は、たまたま入った今はなきオーディオユニオンの淵野辺店で目に入り、ちょっと持ってみたところで見た目以上に重かったから、その場で即決した。散々実験に供して原形をとどめなくなったプレーヤーが遂に故障し、レコードが聴けなくて困っていたこともあったが、「プラッターさえちゃんと回るなら、アームは自分で作ることもできるからいいや」というのが即決の理由だった。重量級のカウンターウエイトとアームの高さを変更する際に必要なレンチが欠品し、あとで気づいたがアームパイプが歪んでいるという程度の悪さながら、4万円もしない底値状態だったということもある。 「自分で作ることができるアーム」というのは、鼎談の記事中にも写真を掲載してもらった故・江川三郎氏のガラス製ピュアストレート・アーム(の劣化コピー)である。アームがダメになっていれば作る気でいたが、幸いパイプこそ曲がっていたもののサポートは至って健全で、カートリッジの水平を取るのに難儀しつつ、また重量級カートリッジを装着するために、カウンターウエイトへ脱着可能な鉛シートを製作してやったりと、散々苦労しながらも、購入から30年以上使い続けることとなった。一度大規模な修理に出してはいるが、おかげで生産から41年を経て、今なお絶好調の個体である。 |
|
でも、今になってみると、私は貧乏でよかったと思う。そうでなければ、こんなに自分の手を動かしていろいろな実験を繰り広げることはなかったろうし、現在の本職につながるノウハウの蓄積も、ずっと浅いものとなっていたに違いない。現に、まだノウハウなどないに等しかった20代の頃に作り上げた初代の鳥型バックロードホーン(ユニットはテクニクス7F10)と、ピュアストレート・アームを装着した件の実験台プレーヤーを、床に打った釘の上へ載せた時には、ナローレンジで迫力こそイマイチだったが、ことスピード感と音場感、音楽の実体感にかけては、凡百のセットを吹き飛ばすような音を聴かせてくれていた。私の基礎は、まさにそこで培われたといってよい。まったく、人生万事塞翁が馬だな、とつくづく実感するものがある。 |

リジッドフロートほど"攻めた"音作りでなくとも、シャッキリ生きの良い音を味わわせてくれるのが、こちらフィデリックスのゼロ・サイドフォースである。17万8,000円と、今どきのアームとしてはかなり安い方に属するのもありがたい。 |
いや、何も伊佐資さんの選択が間違っている、というつもりはない。誌面でも展開されているが、これは「スポーツカーか、大型セダンか」という選択の問題で、お2人と私の求めている音の世界がまるっきり違うからこうなった、というに過ぎない。

ピュアストレートは試してみたいけれど、アームを交換するのは難しいという人にはこちら、MITCHAKU-Zがお薦めだ。一般のオフセット・アームへ取り付けたらピュアストレート動作になる、という魔法のようなシェルで、自重16gで1万4,850円と、比較的手を出しやすい製品だから、一度試してみてほしい。 |
亡くなられた自動車評論家の大御所、徳大寺有恒氏が常々書かれていた「スポーツカーの定義」がある。ごく大雑把にいえば、俊敏に走ることを最優先として、他を犠牲にすることを厭わない車、というようなことだ。つまり、居住性に優れた大きな車室や荷物を載せやすい大きなトランクを備えるのではなく、その分を削ってでも可能な限り軽量化し、より出力の大きなエンジンとグリップの良いタイヤのためにスペースを使うのがスポーツカーだ、といってしまってもそう大きな間違いではなかろう。 これとよく似たことが、「リジッドフロート」の7インチにもいえる。他社製品ではほぼあり得ない極端に短いアームは、あまつさえピュアストレートであるだけに、ごくほんの僅か調整が狂うだけでひどいノイズが乗り、カートリッジによってはトレースできないものがあるなど、ある意味非常に神経質なアームである。 |
これは、言い換えれば「変態ソフトでなければそこまでの俊敏さは必要ない」というか、むしろソフトによっては聴き疲れを誘発することにもなりかねない、ということだ。お2人がロングアームを選ばれるのも、無理はないというものである。
|
思えば、私は少年期から「よりハイスピードに、より鋭く」という方向で自分のオーディオを詰めてきた。全くの偶然ではあったが、それに江川流のアナログ対策と長岡流のバックロードホーン(BH)スピーカーが大きな役割を果たしてくれた。私が知る限り、どれほど高級なBHであっても、決して世のハイエンドSPのような"高級な音""絢爛豪華な音"は出ない。しかし、大半のスピーカーが束になってかかっても、このスピード感と力感、生々しさを出すことはかなわないのではないかと、「井の中の蛙」という声がかかることを覚悟しつつ、個人的には信ずるところだ。 これは、何も単なる思い込みでいっているのではない。一般的なマルチウェイに用いられるウーファーとわが愛するフルレンジとでは、振動板の目方が大きく違うのだ。数値を拾いやすいのでフォステクスのユニットを例に採ると、ウーファーのFW168HSの実効振動板質量(m0)は25g、フルレンジFE168NSは8.5gだから、3倍近くも違うのだ。これがまさに数値通りに効いて、フルレンジはウーファーで聴くことの叶わないスピード感を奏でるのである。 |

ピュアストレート・アームを標準装着したプレーヤーといえば、ヤマハのGT-5000あたりが有名だが、何とDJプレーヤーの今はなきベスタクスが、多くの製品でピュアストレートを採用していた。写真はPDX3000。激しいDJプレイでも、ピュアストレートで針は飛ばなかったということであろう。 |
また、シングルアンプ方式に比べて膨大なコストと手間、音決めのセンスを要求するにもかかわらず、ネットワーク素子の代わりにチャンネルデバイダーで帯域を分割する「マルチアンプ」方式に、少数ながら熱心に取り組むマニアがおられるというのも、ネットワーク素子がいかに大きな害といわざるを得ないか、という傍証でもあろう。そんなクロスオーバーの弊害が存在しないか、あるいはごくごく僅かのマイナスにとどまるのがフルレンジである。

フォステクスのBH向け16cmフルレンジ・ユニットFE168NS。私は「グース」と名付けた鳥型BHを製作したが、実にパワフルで深々と鳴る好ましきユニットという印象だ。 |
そんなフルレンジの中には、比較的穏やかでノンビリした音を出すものもあれば、わが「ハシビロコウ」のように強烈なパワーとスピードを持つものもある。そういう傾向は全体的な設計で決まってくるものだが、中でも一番"効く"のはマグネットの大きさ、もっと正確にいえばボイスコイルにかかる磁束密度の高さだ。 実のところ、磁束密度は高ければよいというものでもない。特に高すぎると中~高域の能率がアップし、解像度が上がって切れ味が研ぎ澄まされていくが、それにほぼ反比例する格好で低音はどんどん出なくなっていく。つまり、普通のキャビへ収めると中~高域ばかり張り出した、ウーファーの壊れた3ウェイのようなスピーカーの出来上がり、というわけだ。 そんなユニットからどうにかこうにか中~高域と同レベルまで低域を引っ張り出すため、ユニット背面に巨大なホーン=アコースティックな拡声器を背負わせたのが、ほかならぬバックロードホーンというキャビネット形式である。2~3mもの長大なホーンを潜り抜けてきても、本質的にハイスピードなサウンドのフルレンジの低音はやはりハイスピードで、振動板の重いウーファーから出る低音とは一線を画すものがある。 |
|
そして、ここでもアームで引用した「スポーツカーの定義」と類似した状況がある。ハイスピードとハイパワーを追い求めて、巨大なキャビネットのために部屋のスペースファクターは大いに犠牲となる。わが「ハシビロコウ」は、20cmフルレンジ×1本に幅54.1cm×奥行56.3cmという化け物のようなキャビネットを宛がっている。 また、「ハシビロコウ」のサウンド傾向はお世辞にも「ゆったりくつろいで聴く」タイプではなく、精神を研ぎ澄まして音楽と対峙しながら聴くタイプである。長岡氏がご自分のBHを「髪の毛一筋ほどの違いを何倍にも拡大して見せる、ある種の測定器」と評されていたが、けだし名言といえよう。 これらの項目は、すべてスポーツカーの定義と相通ずるところがある。加減速、道の凹凸、そして旋回に伴うGを克明に感じながら操縦することこそ、スポーツカーの醍醐味であろう。 一方、誌面でも言及されているが、お2人は大型サルーンでゆったりと運転を楽しむようなオーディオを構築されているようだ。これは、音質的な好みもあるが、「どんな音楽を楽しまれているか」というのも大きな項目なのではないかと思う。 |

同じフォステクスのウーファーFW168HS。口径はFE168NSとほぼ同じだが、振動板の質量が3倍ほども違う。同じパワーを入れても、振動板の動きやすさが違うのは自明であろう。 |

わが愛車スズキ・アルト(Fグレード)。現在新車で買える最も廉価な、そして最軽量の乗用車といってよかろう。何といっても、同じ軽規格のスポーツカー・ホンダS660ですら830kgもあるのだ。同じターボエンジンで比べても、アルトワークスは670kgだから大人2人分は優に軽い。もっとも、サーキットを走れば重心の低さからS660が圧倒するようだが。 |
伊佐資さんも小原さんもジャズやロックがお好きなようで、一方私は皆様ご存じの通り"変態ソフト"をこよなく愛する。前者はくつろいで聴くものであろうし、日常にささくれた精神を癒す働きもあるだろう。一方後者は峻険な立ち上がりとDレンジの広さを全身に浴びるために聴く。「精神がささくれてナンボ」なのである。アメリカの大型セダンで峠道を走る人は少ないだろうし、マツダ・ロードスターで高速ばかり走っていてもつまらない。煎じ詰めれば、そういうことなのだろうと思う。 ならば炭山は実際の車もスポーツカーに乗っているのか、と問われれば、残念ながらそんな甲斐性はなく、ごく廉価な軽自動車である。しかし、「金がないから軽」というだけではなく、積極的に選んだ結果でもある。今乗っている現行スズキ・アルトのグレードF(5AGS)は公称で重量が620kgしかなく、軽ならぬ登録車でこれに匹敵する重量というと、それこそケータハム(調べたら、さらに100kg軽かった!)などの飛び抜けたライトウエイト・スポーツカーくらいしか存在しないのだ。 |
特に、個人的に励行している「周辺交通へ与える負荷の少ない運転」には、こんな車でも大いに役立っている。絶対的な重量の軽さから、動力性能がプアでも市街地での発進加速や旋回にはあまり不自由せず、後続車のドライバーへ与えるストレスは最小限に抑えることができているだろう。
改めて書き進めていると、私はつくづく「軽い方」が好きなんだなと実感する。そういえば、1月25日放送の「オーディオ実験工房」で軽量ヘッドシェルを特集しているが、あれは私1人で暴走して立てた企画だ。殊に本職としては、われながらかなり過激な方向へ進んでいると思う。一般のオーディオマニアは「こんなバカなオーディオをやっているヤツがいる」とお笑い下さい。そして、数は少ないと思うけれど同好の皆様、これからもともにこの道を進んでいきましょう。
(2021年1月8日更新) 第278回に戻る 第280回に進む
コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー