コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」
<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>
ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー
第49回/ヴィンテージ・スピーカーから「なんちゃってハイレゾ」まで [村井裕弥]
ヴィンテージ・スピーカーが好きだ。高能率で、反応が俊敏。多少じゃじゃ馬かもしれぬが、fo.Q(フォック)を貼る、DEQX(デックス)でピークを抑える等、いまならいくらでも打つ手がある。半世紀前のアンプでは真価を発揮できなかったが、いまのアンプなら十全に鳴らせる製品も多い。 |
 JBLハーツフィールド (鶴岡市オーディオラボオガワ) |
 シーメンスのグランフィルム・バイオノール 中央のフロントロードホーンだけではありません。 壁のように見えるすべてがスピーカー本体です (広島市サウンド・デン)  JBL4350が小さく見えます (熊本県阿蘇郡オーディオ道場) |
さて、「そんなヴィンテージ・スピーカーでハイレゾを再生すると」というのが今月最初のテーマだ。手っとり早く結論を言ってしまうと、ヴィンテージ・スピーカーで再生しても、ハイレゾのメリットは十分味わうことができる。いや、かえってよくわかることもあると筆者は感じている。 |
10年以上前の話だが、江川三郎先生のイベントで、こんな体験をしたことがある。マイク、A/Dコンバーター、D/Aコンバーター、アンプ、スピーカーを用意し、マイクに向かってしゃべる。それをリアルタイムA/D、D/A変換してスピーカーから再生したのだが、32kHzサンプリング16bitの音を聴いた参加者たちは凍りついた。「俺たちはふだんBS放送(当時のAモード)でこんながさつな音を聴かされているのか!?」と。そして、サンプリング周波数とbit数を上げていくうち、場はなごんでいった。そのときの上限は192kHzサンプリング24bitであったと記憶するが、そこまで行って、やっと「ふつうに聴けるようになった」という感じ。「音楽再生のためには、もっと上級のフォーマットが欲しいね」という声がごく自然に飛び交った。 |
 リアル・タイム・リスニング法を実演する江川三郎先生 (2001年6月21日) |
そういえば先日とあるスタジオで、録音中の音(マイク→アンプ→スピーカー)と録音後の音(レコーダー→アンプ→スピーカー)の音を聴き比べた。フォーマットは96kHzサンプリング24bitであったが、「それでもこんなに情報が省略されてしまうのか」と哀しくなった。
スタジオといえば、10年以上前、HDDに入っているマスターの音とプレーヤーで再生したSACDの音を聴き比べたこともあった。担当者は「ほうら、おんなじでしょう」と誇らしげだったが、音はまるで違った。鮮度が落ち、情報量が減り、ガッツが後退。「ディスクを高速回転させて、そのデータをリアルタイムで読み取るって、やはり無理あるのでは」と考えるようになったのはそのときからだ。
この1か月間で考えさせられたことはほかにもたくさんあるのだけれど(リマスター盤における音圧競争や音割れの問題など)、うまくまとめられそうにないので、割愛させていただく。
ラストに取り上げるのは、いわゆる「なんちゃってSACD」「なんちゃってハイレゾ」。CDフォーマットのマスターを元に作られたSACDやハイレゾのことだ。ネット上では後者を「ニセレゾ」と糾弾する声も散見される。昨年「バナメイエビなのに、車エビと表示するのはいかがなものか」「冷凍物なのに、鮮魚とは何事か」といった食材偽装問題がクローズアップされたが、あれと同じような不快感を抱く方がかなりの割合でいらっしゃるということだろう。
わが家にも「なんちゃってSACD」はたくさんあるから、10日ほど前から集中的に聴いてみた。そして得た結論は、CDやハイレゾと同じで、「なんちゃってSACD」にも当たりとハズレがあるということだ(しかしその成功率はかなり高い)。
以前どこかに書いたと思うが、CDのリッピング・データをAudioGateでDSD化すると、5割から7割くらいの確率で音質向上が認められる(あくまでもわが家での話)。その変化は、「CD化によって切り捨てられてしまったと思っていた情報」が実はどこかに隠れていて、それがよみがえってきた、そういう印象なのだ。
 かつてCDに明記されていたDDDマーク。オリジナルマスターからすべてデジタルであることを謳っている 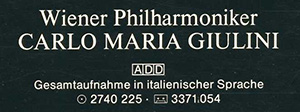 ADDマーク。オリジナルマスターがアナログであることを示す |
筆者のような素人が、無料ソフトを使ってDSD化しても、それだけの効果があるのだ。ましてプロがプロ用機やプロ用ソフトを使ってDSD化すれば、より効果が大きいのは自明だろう。 |
|
30年くらい前CDのケース裏には、DDDとかADDとかいった表示があったし、SACD黎明期にも「DSDレコーディング」「DSDミキシング」「DSDマスタリング」といった表示があった。昔できたのだから、いまできないわけがない。 |
 初期のSACDには、こうやってケース外側に、オリジナルマスターの規格が明示されたものもあった。どうしてこれを続けられないのか |

|
【新刊「これだ!オーディオ術2 格闘編」8月発売!】 8月、2冊目の単行本『これだ!オーディオ術2 格闘篇』(青弓社)を出すことになりました。5年前に出した初単行本では、「オーディオは、買い物で終わる趣味じゃない」を強くアピールし、「2009年まで、自分がオーディオとどう取り組んできたか」をレポートしましたが、その基本線は変わらぬものの、今回は ○ アナログ再生にどう取り組んできたか ○ 少しでもアナログに近い音を再生するため、何をしてきたか について書いています。 |
○ 格安アナログプレーヤー活用法
○ PCオーディオとの出会い
○ 英語にもパソコンにも弱い人間が、ネットワーク・プレーヤーの初期設定にチャレンジ
など、前著より皆さまのお役に立てる内容が多いのではと思います。
あと、オーディオ誌でない媒体に書いたアクセサリー記事等も転載。読み物としても、実用書としても通用する内容を目指しました。まずは書店で手に取ってみてください。(村井)
コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー















