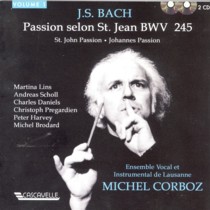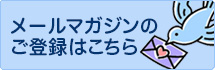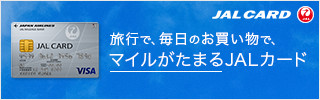ヒラリー・ハーンは1979年生れだから、今年ちょうど30歳ということになる。
クラシックの演奏家としては、まだまだ若い。しかし、彼女がバッハの無伴奏ヴァイオリン曲集で鮮烈なCDデビューを飾ったのは97年で、早くも12年前のことになる。以来12年、途中ソニーからグラモフォンへのレコード会社の移籍はあったが、発売されるCDはつねに話題盤となり、レコーディング・アーティストとしては名実ともにもはやヴェテランといっていい。
彼女が録音してきたのは、たんに名曲を並べるのではなく、ひとひねりしていて、しかも一貫性のある構成をもったアルバムである。新譜の「バッハ ヴァイオリン&ヴォイス」もそうで、受難曲やミサ、カンタータなどのバッハの宗教曲のなかから、ヴァイオリンが人間の声とからむ部分を抜き出して1枚にまとめたものだ。
ひょっとするといまの彼女は、自分のヴァイオリンと声との共演に興味を持っているのかもしれない。今年1月の来日でもシンガーソングライターと共演するリサイタルを行なって、クラシック好きを驚かせていた。
そのヴァイオリンに、ケレンは微塵もない。完璧な、陶磁器のようになめらかな響きで演奏すること自体が、それだけで一つの凄味に達する、希有のスタイルである。そこに人間の声や多人数のオーケストラが加わったとき、音楽はどんな表情をみせるのか。それがいまのハーンのテーマなのかも知れない。
前述の新譜と、クライツベルク指揮ウィーン交響楽団と共演した、シベリウスの協奏曲のライヴ。この二つの演奏に、ハーンの現在をお聴きになってみてほしい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン