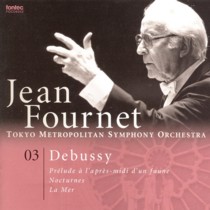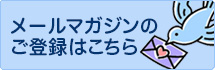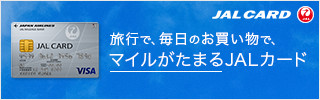長野県松本市は日本アルプスへの入り口で、美しい山並みに囲まれた信州の町。ここにあった旧制松本高校(信州大学の前身)の愉しい伝統は北杜夫の『どくとるマンボウ青春記』に活写され、現在も保存されている校舎と、隣接する旧制高等学校記念館を通じて、そのよすがをしのぶことができる。
長野駅からその旧制松本高校校舎のある「あがたの森公園」を結ぶ直線道路の、ちょうど中間に建つのが、まつもと市民芸術館。
ここはサイトウ・キネン・フェスティヴァルの会場の一つで、今年はヤナーチェクの傑作オペラ「利口な女狐の物語」が上演された。また、長野県松本文化会館ではオーケストラ・コンサートが行なわれ、下野竜也指揮の「わが祖国」や小澤征爾指揮のマーラーの「巨人」ほかという、2つのプログラムが演奏された。さらに毎年恒例の武満徹メモリアル・コンサートや「ふれあいコンサート」などの室内楽演奏会、子供のためのオーケストラ演奏会や青少年のためのオペラなど、さまざまな演奏会が8月中旬から1か月にわたって開かれた。
松本市でこの音楽祭が始まったのは、1992年。毎年オペラや大規模な声楽曲とオーケストラ演奏会を中心として、今年で17回めを数えることになった。松本市民だけでなく日本各地からやってくる聴衆に根づく一方、中継や毎年つくられるCDを通じて、広く親しまれる催しとなっている。
ミュージックバードではその演奏会、さらにはCDも大挙してお送りしているので、どうぞこの機会に。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン