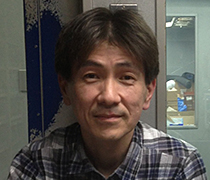オーディオ評論家が太鼓判を押すハイレゾアルバムをジャンルを問わず紹介。
| No. | ▼画像をクリック(音源を購入できます) | アルバム名 | 演奏者 | レーベル | コメント |
| 1 |  | A Bridge of Dreams | Paul Hillier , Ars Nova Copenhagen | | 一聴すると古楽の詠唱のように聴こえるが、これは現代作曲家ルー・シルヴァー・ハリソンの楽曲を、ポール・ヒリアー/アルス・ノヴァ・コペンハーゲンが演奏したものである。教会の響きを思わせる深いエコーも良い。 |
| 2 |  | Be Glad Then, America | The President's Own United States Marine Band | Altissimo | アメリカ海兵隊音楽隊が、米英作曲家の吹奏楽作品を演奏したアルバム。演奏はやや即物的だが実に闊達で、さすが全米一の軍楽隊と称されるだけのことはある。録音も鮮明で大スケール、オーディオ的快感が味わえる。 |
| 3 |  | タルカス | 佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・オーケストラ | AVEX ENTERTAINMENT | 佐渡裕の棒になるシエナ・ウインド・オーケストラの演奏には、これまで数々の奇跡的な名演が残されているが、この音源はそれらの中でも白眉といいたい。ワイドでパワフルで輝かしく、吹奏楽録音の手本としたい1作だ。 |
| 4 |  | Variation5 | Arnold, Francaix, Hindemith & Nielsen: Quintets | Berlin Classics | アーノルド、フランセ、ヒンデミット、ニールセンの室内楽曲、それも木管アンサンブルという、非常にマニアックな楽曲を集めたアルバムだが、意外と楽しい曲が多い。小編成だが録音は鮮明で楽器の表情がよく分かる。 |
| 5 |  | Catalani: La Wally | Susanna von der Burg , Paulo Ferreira | Capriccio | カタラーニのオペラ「ワリー」としては珍しい、21世紀に入ってからの新録である。マイナーレーベルの録音だけにやや安っぽい響きも散見されるが、声の質感、コーラスのスケールは立派なものだ。生々しさを楽しみたい。 |
| 6 |  | Hieroglyphen der Nacht | アニヤ・レヒナー, アニエス・ヴェスターマン | ECM Records | ウクライナの作曲家シルヴェストロフ80歳記念アルバム。チェロ1台と2台の曲集で、アルコとピチカートの淡々とした演奏が続く。ビブラートは少なく、楽器そのものの澄んだ響きとECMならではの深い残響が美しい。 |
| 7 |  | GNOSIS | David Virelles, Roman Diaz , Nosotros Ensemble | ECM Records | キューバ出身のピアニスト、ダヴィ・ヴィレージェスを中心とした、ジャズ・アンサンブルである。ラテン・フレーバーを振りかけた欧州ジャズと現代音楽の狭間、という楽想がいかにもECM的だ。録音もクールで深い。 |
| 8 |  | Provenance | Bjorn Meyer | ECM Records | ビョルン・マイヤーはスウェーデン・ストックホルム出身のベーシストで、今作は珍しいベース・ソロ作品である。ソロといっても逆回し的なエフェクトが随所に込められ、音像は前後左右に動き回る。面白い演奏と録音だ。 |
| 9 |  | Gyorgy Kurtag: Complete Works For Ensemble And Choir | Asko/Schonberg, Netherlands Radio Choir | ECM Records | ハンガリーの作曲家クルターグの室内楽曲と合唱曲を集めた全集的な音源で、擦弦楽器でも時に驚くようなパルシブなパッセージが入る。寡作の大家が世に送った、磨き上げられた作品の精粋を味わうことができる。 |
| 10 |  | Nuit blanche | Tarkovsky Quartet | ECM Records | 仏のジャズ・ピアニスト、クチュリエが敬愛する映画監督タルコフスキーの名を冠したカルテットで演奏する欧州ジャズ。旋律のラインとハーモニーのコードは曖昧で、現代音楽的でも、またタルコフスキー的でもある。 |
| 11 |  | Tigran Mansurian: Requiem | アレクサンダー・リーブライヒ指揮ミュンヘン室内管弦楽団, ロシア国立室内合唱団 | ECM Records | アルメニアの作曲家マンスリアンによるレクイエム。小編成のオケと合唱による演奏で、マイクはこの手の教会音楽としてはやや近めだが、それだけに楽員や合唱団の人数が分かるような演奏と歌唱が眼前で展開される。 |
| 12 |  | Daylight Ghosts | Craig Taborn | ECM Records | 米国人キーボード奏者クレイグ・テイボーン率いるサックスを含めたカルテット・ジャズ。米国人リーダーだがそこはECM、「静寂の次に美しい音楽」の真骨頂を聴かせる。現代音楽やポップスの最先端も包含したジャズだ。 |
| 13 |  | On Behalf Of Nature | Meredith Monk Ensemble | ECM Records | 声の魔術師メレディス・モンクの織り成すボイス・パフォーミングのタペストリー。昔に比べると幾分丸くなったが、それでも20世紀の終わり頃より盛り返してきた。これが気に入ったら80年代以前の彼女も聴いてほしい。 |
| 14 |  | Danca Das Cabecas | エグベルト・ジスモンチ | ECM Records | ジスモンチはアルバム「Solo」を故・長岡鉄男氏が「外盤A級セレクション」で取り上げられている。アイアート・モレイラを連想させる密林の音を模したサウンドから始まり、残響たっぷりのクールな音楽が展開する。 |
| 15 |  | Arvo Part: The Deer's Cry | Vox Clamantis , Jaan-Eik Tulve | ECM Records | エストニアのヴォーカル・アンサンブルが同郷の大家ペルトの作品を歌う。時にアカペラで、時に小編成の伴奏を伴っての歌唱だが、時に手のひらへ宇宙を収めるようなペルトの音楽世界を、非常にみずみずしく伝えている。 |
| 16 |  | Koryun Asatryan: Saxophone | Koryun Asatryan | Genuin | 1985年米国生まれの若き天才が、サクソフォンをこれでもかと吹き鳴らす。といっても力任せではなく、楽器の限界に挑戦するような特殊奏法のつるべ打ちだ。リードの不整振動のような音も美しく聴かせるこの人はすごい。 |
| 17 |  | 天正遣欧使節の音楽 | アントネッロ | OMF | 日本人3人組の古楽合奏団アントネッロが、「もし17世紀初頭頃の天正遣欧使節団が日本の音楽を持ち込んだら、彼らが日本へ音楽を持ち帰っていたら」と仮定して編んだ曲集だ。実体感あふれる音像と澄んだ音場がいい。 |
| 18 |  | フリー | アイアート | CTI | アイアートは長岡鉄男氏も何枚か取り上げられているが、これは彼がCTIに移籍した初期の音源で、「Return to Forever」の再現に始まり、彼ならではの密林のざわめきを模した音も端々で楽しめる。 |
| 19 |  | ヴァージン・ランド | アイアート | CTI | ジャズ、ロック、ファンク、アフロビートに彼独特の密林のざわめきを模したパーカッションが加わった、摩訶不思議な音楽世界。いろいろなジャンルの音楽ファンに、何らかのエッジを残してくれるのではないか。 |
| 20 |  | 陽炎の樹 | 大井剛史指揮 東京佼成ウインドオーケストラ | Pony Canyon | 世界有数の吹奏楽団・東京佼成ウインドオーケストラが、日本人作曲家が21世紀に遺した作品を集めた曲集。ポップな曲からハードな現代音楽まで曲想は彩り豊かで、強烈な名演奏と演奏会場の空気まで収めた録音が魅力だ。 |
| 21 |  | アメリカの風 | シズオ・Z・クワハラ指揮 東京佼成ウインドオーケストラ | Pony Canyon | 新進作曲家シズオ・Z・クワハラが"世界の名器"東京佼成ウインドオーケストラを振る。今作は米国作曲家の作品をそろえた選集だが、白眉はトラック7「春になって、王達が戦いに出るに及んで」。強烈な演奏と録音だ。 |
| 22 |  | 3つの世界:ウルフ・ワークス(ヴァージニア・ウルフ作品集)より | マックス・リヒター | Deutsche Grammophon | いわゆる「ポスト・クラシカル」にカテゴライズされる1作。英国の女流詩人V. ウルフの詩に閃きを得たマックス・リヒターの曲集で、小編成かつ穏やかな曲想ながら、時折ビックリするような低音が入り、再生は難しい。 |
| 23 |  | ディスタント・ライト | ルネ・フレミング | Decca | 当代最高の歌手ルネ・フレミングが、バーバーとノルウェーの現代作曲家ヒルボリ、そしてビョークの楽曲を歌う。曲は現代作品もとっつきやすく、歌唱はもちろん最高、録音も素晴らしい実体感と厚みが魅力だ。 |
| 24 |  | Le Sette Stelle | センティエリ・セルヴァッジ合奏団 | Deutsche Grammophon | 表題は「七つの星」という意味のイタリア語。同国の現代作曲家の器楽作品を集めた音源で、センティエリ・セルヴァッジ合奏団は非常に闊達な演奏を聴かせ、録音はやや即物的ながらDGらしい深みも随所に聴かせる。 |
| 25 |  | フランス・オーケストラ名曲の祭典 名曲全集IV | 大井剛史指揮 東京佼成ウインドオーケストラ | King Record | 「カルメン」や「アルルの女」といった、フランスの定番曲を収めたアルバムだが、若き天才・大井剛史マエストロが振ると、耳慣れた音楽がかくも生きいきと響くのか、と驚かされた1作。クラシック入門にもお薦め。 |
| 26 |  | Light of the Ancients | Christopher Hardy | Blue Lotus Records | ハーディは長く日本で活動する米国人打楽器奏者で、これまで内外の奏者と数多く共演してきた。今作は彼のソロ名義で、軽やかでよく伸びる太鼓や金属打楽器群が、広大な音場へ拡散していく。再生の難しい作品である。 |
| 27 |  | spatial view | | 音の風景 | 「音の風景」は小後摩幸雄(おごま・ゆきお)氏の個人レーベルで、これまでは知る人ぞ知る存在だったが、e-onkyoで扱われるようになった。濃厚な自然の音場から近づいてくる汽車の音を再生し切るのは極めて難しい。 |
| 28 |  | 恐山/銅之剣舞 | 芸能山城組 | Victor Entertainment | 筑波大学の大橋力(おおはし・つとむ)元教授が、山城祥二の名で結成した音楽集団「芸能山城組」のデビュー作。強烈な厚みとおどろおどろしい声は、「音量を上げるとパトカーが飛んでくる」と長岡鉄男氏に評された。 |
| 29 |  | 輪廻交響楽ハイパーハイレゾエディション | 芸能山城組 | Victor Entertainment | 「翠生」「散華」「瞑想」「転生」の4楽章よりなる組曲で、特に1曲目冒頭の強烈な低音アタックと、続いて始まるリスナーの周囲をぐるぐると回るコーラスの、完全な再現は猛烈に難しい。リスナーが試されるソフトだ。 |
| 30 |  | Symphonic Suite AKIRA 2016 ハイパーハイレゾエディション | 芸能山城組 | Victor Entertainment | 「輪廻交響楽」に心酔した原作者の大友克洋が山城祥二氏に依頼、完成された「交響組曲」で、これを基にサントラが作成された。超ワイドレンジかつパワフルで音場は広大無辺、これほど再生の難しいソフトもそうはない。 |
| 31 |  | 超絶のスーパーガムラン | ヤマサリ | Action Research | ガムランの音源はビクター、キング、米ノンサッチ、仏オコラなどからいろいろ出ているが、ハイレゾではなかなか見当たらない。この音源はややソフトだが、超高域まで伸びたガムランこそハイレゾで聴きたいものだ。 |
| 32 |  | 武満徹のうた | 石丸幹二&つのだたかし | Sony Music | 武満のリートはさまざまな歌手に歌われているが、これはつのだたかしのリュートをバックに、ミュージカル歌手の石丸幹二が歌うという異色版だ。スイートな武満のメロディが何となく中世欧州の世俗音楽的に響いてくる。 |
| 33 |  | Unifys | onomono | | DJのO.N.Oによるミニマル・テクノ作品。ただのダンス・ビートではなく、随所にパルシブで強烈な音の成分が散りばめられている。近所迷惑にならない範囲で、できるだけ低音を伸ばした装置を用い、大音量で鳴らしたい。 |
| 34 |  | Welcome to Jupiter | 矢野顕子 | Victor Entertainment | 2015年のアルバムで、現在のところ矢野顕子の最新スタジオ・アルバムである。1曲目の冒頭、凄まじい低音と音程の揺らぎで、まるで現代音楽を聴いているような錯覚に陥る。彼女の健在を強く印象付けるアルバムだ。 |
| 35 |  | Pickard: Sixteen Sunrises, Symphony No. 5 & Concertante Variations | Martyn Brabbins, BBC National Orchestra of Wales | BIS | ピッカードは英国の作曲家で、トラック5「16の夜明け」は日本の名古屋フィルが委嘱し、本作でも棒を振ったブラビンスが初演を担当した曲という。演奏は堅実で闊達、録音はBISらしい鮮明で広大な音場感が魅力だ。 |
| 36 |  | Tales of Sound and Fury | Camerata Nordica | BIS | タイトルはシェークスピア「マクベス」からの引用で、曲はテレマンとビーバーのものだが、フーコーの「狂気」をテーマに編曲されている。冒頭から猛烈なパーカッションが耳を揺さぶり、歌唱のインパクトもすごい。 |
| 37 |  | Flaminis aura: Works by Tommie Haglund | Tommie Haglund | BIS | ハーグルンドはスウェーデンの作曲家で、「絶えず変化を繰り返す宇宙が鳴り響くイメージ」と称される。広大で静寂を感じさせる音世界に、突如として惑星衝突を思わせるインパクトが現れる。再生の難しい音源である。 |
| 38 |  | Ligeti: Concertos | Christian Poltéra ,BIT20 Ensemble , Baldur Brönnimann , Joonas Ahonen | BIS | リゲティの没後10年を記念した音源である。弱音が延々続くかと思わせて、一気に強烈なトゥッティへ駆け上がったり、単音で構成された曲と極めて複雑な音形が並んだり、作風も録音も極めてDレンジの大きな音源だ。 |
| 39 |  | Sofia Gubaidulina: Sonnengesang (Live) | Philipp Ahmann , NDR Chor | BIS | グバイドゥーリナの世界初録音を含む合唱曲の選集。伴奏にオルガンやパーカッションが起用されており、とてつもなくレンジは広い。コーラスはちょっとでも歪みがあるとてきめんに荒れるから、吟味した装置で楽しみたい。 |
| 40 |  | Fagerlund & Aho: Bassoon Concertos | Lahti Symphony Orchestra , Okko Kamu , Dima Slobodeniouk | BIS | 現代フィンランドの俊英2人がバスーンのために書き下ろした珍しい協奏曲集である。バスーンの演奏可能な全帯域を使い、音程はグリッサンドで音列の間を浮遊する。バックの演奏も非常に複雑で、再生は大変難しい。 |
| 41 |  | Berlioz: Symphonie Fantastique (Transferred from the Original Everest Records Master Tapes) | London Symphony Orchestra & Sir Eugene Goossens | Everest Records | 米エベレスト音源は「コロボリー」が白眉だが、高崎素行氏が紹介されているので、私は違う音源を。この「幻想交響曲」は特に第5楽章の鐘を聴いてほしい。強烈にパワフルな音で、吹っ飛ばされること請け合いである。 |
| 42 |  | Shostakovich: Symphony No. 9 & Lieutenant Kije Suite (Transferred from the Original Everest Records Master Tapes) | London Symphony Orchestra & Sir Malcolm Sargent | Everest Records | エベレストからもう1枚。この音源はショスタコーヴィチの9番が良い。明るく大迫力の演奏で、「第九」に期待したソ連首脳を軽やかにはぐらかした、ショスタコーヴィチのニヤリと笑う顔が見えてくる演奏と録音だ。 |
| 43 |  | Sera Una Noche | Sera Una Noche | MA Recordings | M・Aレコーディングズのタッド・ガーフィンクル氏は、世界を股にかけて有望なミュージシャンと録音会場を探し、最高の音楽と録音の音源を供給してくれる。このアルバムは響きたっぷりの現代タンゴである。 |
| 44 |  | Sera una Noche - La Segunda - | Sera Una Noche | MA Recordings | 現代タンゴバンド、セラ・ウナ・ノーチェの2ndアルバム。独自の「ラインレベルマイク」を採用した録音は高解像度でS/Nが良く、今作は前作よりさらに深い響きに満たされた、現代タンゴの展開が素晴らしい。 |
| 45 |  | Korvits: Moorland Elegies | Estonian Philharmonic Chamber Choir , Tallinn Chamber Orchestra , Risto Joost | Ondine | エストニアの作曲家コルヴィッツによる、合唱と室内管弦楽のための曲集。非常に美しい不協和音に全編彩られた、聴きやすい現代音楽である。再生装置次第で、合唱の人数が見えてくるような解像度を聴くことができる。 |
| 46 |  | Tuur: Peregrinus ecstaticus - Le poids des vies non vecues - Noesis | Christoffer Sundqvist , Finnish Radio Symphony Orchestra , Hannu Lintu , | Ondine | エストニアの作曲家トゥールは、求心力が強くドラマチックな曲想というイメージの作曲家だが、本作はクラリネット協奏曲的な構成で、やはり強弱、緩急のつけ方は実にドラマチックだ。オーディオ的にも大変面白い。 |
| 47 |  | Saariaho: Emilie suite, Quatre instants & Terra memoria | Karen Vourc'h , Orchestre Philarmonique de Strasbourg , Marko Letonja | Ondine | フィンランドの女流作曲家サーリアホの新しい作品を集めた音源。リートの入ったオケ作品で、弱音でも大スケールのオケを従えてソプラノが太く実体感たっぷりに歌う。広大な音場に漂う深く渋い音響が耳に快い。 |
| 48 |  | Cantigas de Santa Maria | Hana Blazikova , Margit Ubellacker , Barbora Kabatkova , Martin Novak | PHI | 中世スペインで、聖母マリアに対する信仰を歌った「聖なる恋歌」を集めた音源で、ハナ・ブラジーコヴァがゴシック・ハープを弾き語る。教会で収録されただけに残響は豊かで、澄み切った声とハープが空間に散っていく。 |
| 49 |  | Lincolnshire Posy | Dallas Wind Symphony, Jerry Junkin | Reference Recordings | パーシー・オールドリッジ・グレインジャーの吹奏楽名曲をダラス・ウインド・シンフォニーが演奏した音源。リファレンス・レコーディングスだけに、広大な空間感と猛烈な低音、楽器の音色の自然な厚みは比類がない。 |
| 50 |  | From the Age of Swing | Dick Hyman | Reference Recordings | ピアノや編曲、指揮と多彩な活動で知られるジャズ・ジャイアント、ディック・ハイマンがスウィング・ジャズをリファレンス・レコーディングズの高品位録音で残したのだから素晴らしい。残響たっぷりのジャズである。 |
| 51 |  | The Virtuoso Ophicleide | Trio Aenea | Ricercar | オフィクレイドはテューバの前段階というべき金管楽器で、今のサックスにトロンボーンのマウスピースを取り付けたような格好だ。非常に難しい楽器だが、素晴らしい演奏が聴ける音源である。録音も明快なハイファイだ。 |
| 52 |  | 三枝伸太郎 Orquesta de la Esperanza | 三枝伸太郎 Orquesta de la Esperanza | RME Premium Recordings | 新進作曲家による、ラテン風のフレーバーが香る曲集。大きな特徴は、シンタックス・ジャパンがRMEのデジタル機器を用いて録音したということだ。実体感が濃厚で、録音現場の床の硬さまで分かる優秀録音である。 |
| 53 |  | ARKETYPOS | アルケティポス・トリオ | ALFA MUSIC | ネットで検索してもほとんど出てこないような新進アーティストによるジャズ・トリオで、基本はギター・ジャズである。どこかECMを彷彿とさせるひんやりとした空気感まで込みの「熱くないジャズ」が味わい深い。 |
| 54 |  | ファンタジー・コンチェルタンテ | 岩黒綾乃 | MEISTER MUSIC | ユーフォニアムは決して知名度の高くない楽器だが、その温かく深い音色は一度聴けば耳に残るのではないか。岩黒綾乃は同楽器の世界有数の奏者で、トーンマイスター平井義也氏により、柔らかく表情豊かに収められた。 |
| 55 |  | Modernists | Alarm Will Sound , Alan Pierson | Cantaloupe Music | ポップスや映画などのフラグを随所にちりばめ、訳の分からない音楽を決然と構築している、という感じのアルバム。英語の朗読なども大量に収められ、意味が分かるとより楽しめるだろうにと臍を噛む。好ましきゲテモノ。 |
| 56 |  | John Adams: Scheherazade.2 | Leila Josefowicz, St. Louis Symphony & David Robertson | Nonesuch Records | 現代アメリカを代表する作曲家ジョン・アダムスが「シェラザード」の世界に啓示を受けて製作された楽曲で、バイオリン協奏曲的な構成を持つ。楽曲、演奏、録音とも豪胆で深みがあり、聴き応えたっぷりの名曲である。 |
| 57 |  | City Noir | John Adams, St. Louis Symphony, David Robertson | Nonesuch Records | かつてミニマル系の作曲家と目されたアダムスだが、2014年に作曲された本作はジャズの色濃い影を宿しつつ、シンフォニックなクラシック作品にまとめ上げられている。セントルイス交響楽団の演奏も闊達で大迫力だ。 |
| 58 |  | La Spagna: A Tune Through Three Centuries | Madrid Atrium Musicae , Gregorio Paniagua | BIS | 長岡鉄男の外盤A級セレクション第1集の5番、「ラ・スパグナ」として紹介された音源である。数年前にSACD化も成り、長岡ファンには最もなじみの音源といえよう。広大な音場感と異様な生々しさが楽しめる音源だ。 |
| 59 |  | 屋久島 ナチュラルサウンド(自然音) | | ディジフュージョン・ジャパン | 屋久島の自然音を192/24品位で収録した「成分無調整サウンド」である。反応の良い装置で再生すると、川が流れ、鳥が鳴く屋久島の環境に、部屋中が満たされる。この自然さをどこまで再現できるかは、あなた次第だ。 |
| 60 |  | 伊福部昭「協奏四題」熱狂ライヴ | 井上道義指揮 東京交響楽団 | King Record | 井上道義が東京交響楽団を従え、伊福部昭の協奏曲へ挑む。「ラウダ・コンチェルタータ」に始まり、「リトミカ・オスティナータ」に終わるという、超マニアックな布陣だ。演奏は闊達、録音は高解像度で見晴らし良し。 |
| 61 |  | Trumpet Japonesque (PCM 96kHz/24bit) | 神代修 | Studio N.A.T | 元N響主席奏者津堅直弘はじめ、新旧6人の邦人作曲家によるトランペット作品の饗宴。演奏はソリストとして世界的に活躍する神代修が担当する。トランペットは柔らかで華麗、伴奏ピアノもやや控えめだが実体感は強い。 |
| 62 |  | Hommage a Boulez | ダニエル・バレンボイム指揮ウェスト=イースタン・ディヴァン・オーケストラ | Deutsche Grammophon | 2016年に90歳の生涯を閉じたブーレーズの追悼に編まれた音源だ。盟友でもあった名手バレンボイムが、若いオーケストラとともに彼の作品を丹念に紡ぐ。音場感と音像の遠近感に優れ、楽員の配置がはっきり分かる音源だ。 |
| 63 |  | Bartok: Concerto for Orchestra (Transferred from the Original Everest Records Master Tapes) | Houston Symphony Orchestra & Léopold Stokowski | Everest Records | 米エベレストはステレオ初期に数々の"偉業"というべき名録音を残した社で、ストコフスキーの作品も結構ある。おそらく、これはその中でも最も良好な録音で残された音源であろう。繊細かつ豪快な演奏が実に素晴らしい。 |
| 64 |  | 蜘蛛の糸 芥川也寸志の芸術1 管弦楽作品集 | 本名徹次指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 | King Record | 20世紀の終わり頃にCDで初出のこの音源は、長岡鉄男氏が絶賛され、わが愛聴盤でもある。時を経てDSDで再マスタリングされたこの音源は、CD時代より遥かに空間感に優れる。芥川を得意とする本名の指揮も素晴らしい。 |
| 65 |  | 日本管弦楽名曲集[日本作曲家選輯] | 沼尻竜典指揮 東京都交響楽団 | Naxos | 片山杜秀氏が選定され、膨大な数がリリースされた「日本作曲家選輯」の、記念すべき第1作。近衛編のオケ版「越天楽」は、その完成度に今さらながら溜息が出る。演奏は勢いがあり、録音も音場感を上手く捉えている。 |
| 66 |  | この地球を神と崇める | 大井剛史指揮 東京佼成ウインドオーケストラ | Pony Canyon | 大井剛史と東京佼成ウインドオーケストラによる、歴史に残る名演。どれも素晴らしい演奏だが、特に5~7曲目が強烈だ。録音はコロムビア塩澤利安氏による微に入り細を穿つもの。1人でも多くの人に味わってほしい。 |
| 67 |  | 富嶽百景 | 鬼太鼓座 | VICTOR STUDIO | 鬼太鼓座の演奏をマルチマイクで近接収録、マルチトラックの76㎝アナログテープへ収められたマスターから、ハイレゾへ起こされたものである。強烈なアタックと地を揺るがすような超低音再生を両立するのは大変難しい。 |
| 68 |  | 怒濤万里 | 鬼太鼓座 | VICTOR STUDIO | 前作「富嶽百景」は大規模マルチマイク録音だったが、本作は2chの一発録音である。鬼太鼓座もレコード会社も最も脂の乗っていた頃の録音で、できたら両方とも所有して、じっくりと聴き比べてみたくなる作品だ。 |
| 69~77 |  | 名車図鑑 | | オンキヨー | JAFのサイトにもよく似た音源がアップされているが、あちらはローカットされていて、明らかに迫力が減退する。こちらは生形三郎氏がバイノーラルで録音したトラックで、加工されていない分かなり生々しい音が聴ける。 |
| 78 |  | 日本の音風景/デジタルサウンドSL【K2HD】 | Victor Sound Effect Team | VICTOR STUDIO | 1996年に発売されたCDのマスターから、K2HD技術によりハイレゾ化されたSLの生録。彼方からやってきて至近距離を通り遠ざかっていくSLのとてつもない大迫力サウンドはもちろん、周辺の環境音も実にいい。 |
| 79 |  | Vers la LUMIERE | Jens Harald Bratlie | 2L | ピアノとエレクトロニクスによる作品集だが、教会で収録されたこともあって残響は非常に豊か、しかしピアノの音像がモヤつくことがない。最低域まで大変な量感とスピード感を両立したこの音源を再生し切るのは難しい。 |
| 80 |  | Endless | テイル・オブ・アス | Deutsche Grammophon | テイル・オブ・アスはイタリア出身のDJユニットで、ベルリンを中心に活躍している。デビューアルバムがDGからと、異色の経歴だが、曲を聴けば納得、クラブというよりネオクラシカルに近い。物凄い低域にご注意。 |
| 81 |  | 時のまにまにII 春夏秋冬 | 井筒香奈江 | | 井筒香奈江のアルバムはどれも高音質だが、どれか1枚となると個人的にはこちらを採る。井筒が歌へ一番没入し、歌以外の世界が消失した、究極に凝縮された世界観がこのアルバムには存在する。ある意味恐ろしい作品だ。 |
| 82 |  | Exploring the World | Ensemble Reconsil | Orlando Records | 何とCDにして14枚組という大部の音源で、14カ国の現代音楽家と、演奏者の自国オーストリアの音楽を紹介する、という趣のライブ音源である。ライブでも演奏の傷は目立たず、録音も鮮明で良い。価格の安さにも驚く。 |
| 83 |  | I Ching (PCM 96kHz/24bit) | 前田啓太 | Studio N.A.T | ノアゴーの代表作「イーチン(易経)」と、クセナキスの「ルボンa/b」、そして「サッファ」を、若き演奏家が叩きまくる。極めてアタック鋭くハイスピードの打楽器をどこまで再現できるか。再生側が挑まれる音源だ。 |
| 84 |  | Alexej Gerassimez - Percussion | Alexej Gerassimez | Genuin | こちらも若きパーカッショニストが、自身を含めた若い世代の作曲家の作品を演奏した音源で、マリンバやグロッケンを含めた多彩な打楽器の粒立ちを存分に再現するのは大変に難しい。音楽的にも面白いアルバムである。 |
| 85 |  | Xenakis: IX | 加藤訓子 | LINN RECORDS | マリンバ奏者として世界に知られる加藤訓子がパーカッション全般を演奏した初のアルバムだそうである。全6パートをすべて加藤が収録した「プレイヤード」が面白い。潤いたっぷりの音場に弾け飛ぶパルスを楽しみたい。 |
| 86 |  | Berio / Xenakis / Turnage: Trombone Concertos Dedicated To Christian Lindberg | Christian Lindberg | BIS | 天才トロンボニスト、リンドベルイがベリオ、クセナキス、タネジの協奏曲を演奏、いずれも本人へ捧げられた曲である。録音はBISらしい鮮明かつ奥行きを伴ったもので、リンドベルイの妙技を堪能することができる。 |
| 87 |  | Poulenc: Gloria - Honegger: Symphony No. 3, "Liturgique" (Live) | Royal Concertgebouw Orchestra, Mariss Jansons | RCO Live | プーランク「グローリア」とオネゲルの交響曲第3番「典礼風」のカップリングという、ちょっと珍しい音源。演奏はマリス・ヤンソンスらしい溌剌としたもので、ライブ音源とは思えない鮮明さとスケール感が良い。 |
| 88 |  | モノ=ポリ | 松平敬 | オフィスENZO | 現代声楽にこの人ありといえば松平敬だが、本作は彼が全パートをアレンジし、歌い、エレクトロニクスをつけ、ポストプロダクションまで行った大変な労作である。声は濁りなく、時に入るパーカッションは異様な迫力だ。 |
| 89 |  | 究極の風物音シリーズ 花火 Vol.1 | 生形三郎 | 音楽之友社 | オーディオ評論家で録音家の生形三郎氏が録音と編集を手がけた花火の音だが、奉納の一覧を述べるナレーションがアットホームな感じで面白い。世界最大の花火も入っているが、小さな玉でも音量には十分注意してほしい。 |
| 90 |  | 三十絃 | 宮下伸 | VICTOR STUDIO | 三十絃は宮下伸の父親、初代宮下秀冽が考案した楽器で、親子2代で奏法を磨き上げてきた。まるでピアノの低音弦を直接叩くような迫力のパルシブな低音が耳を襲い、とても琴の一種とは思えない。聴く側も気迫が必要だ。 |
| 91 |  | Carl Vollrath: Warrior Monks | Ales Janecek | Navona | ヴォルラスは米の作曲家で、今作はクラリネットとトランペットのための管打楽との協奏曲が連なっている。ソリスト、指揮者、楽団ともさほどの知名度はないが、演奏は達者で、録音も鮮明なソロと分厚いトゥッティがいい。 |
| 92 |  | Color Theory | Prism Quartet | XAS Records | サックス・カルテットとパーカッション・アンサンブルが紡ぐ21世紀の音楽。サックスは冒頭から微妙な微分音で脳みそを引っかき回し、打楽器は時に吹っ飛ばされるような、またか細く風に飛ばされそうな音を奏でる。 |
| 93 |  | Glenn Kotche: Drumkit Quartets | So Percussion | Cantaloupe Music | オルタナロックバンド、ウィルコのドラマー、グレン・コッチェがソロとしてリリースした本作は、ミニマル/ポストクラシカルにロック色を加えたパーカッション&エレクトロニクス音楽だった。演奏/録音とも鮮明だ。 |
| 94 |  | World of Percussion | Thierry Miroglio | Naxos | 6人の作曲家によるパーカッション音楽の集成だが、いずれも世界初演で、21世紀になってアコースティック・サウンドとエレクトロニクスとの混淆がより高度に進んでいることが強く認識できる。レンジは極めて広い。 |
| 95 |  | ウイ・ナウ・クリエイト | 富樫雅彦 | Victor Entertainment | 1969年ジャズディスク大賞受賞作品。非常に素っ気ない音の作りで、サックスなど意図的に汚い音で録音しているのではないかと思うが、奏者の息遣い、阿吽の呼吸で行く先が決まるフリージャズの醍醐味を巧みに捉える。 |
| 96 |  | Milhaud: L'Orestie d'Eschyle | Lori Phillips | Naxos | CDにして3枚組にもなる大部の劇音楽だが、それをミシガン大学の交響楽団と合唱団が見事に紡ぎ上げているのに感銘を受けた。録音もオケは奥行き深く、ソリストは眼前に浮かぶ、音楽を理解しやすいスタイルが好ましい。 |
| 97 |  | Aho: Symphonic Dances / Symphony No. 11 | Lahti Symphony Orchestra , Osmo Vanska | BIS | カレヴィ・アホは現代フィンランドで最も意欲的な作曲家の1人で、本作は「交響舞曲集」と交響曲第11番を収めたものだ。交響曲第11番はクロマータ打楽器合奏団が参加し、強烈な彩を加える。Dレンジは極めて大きい。 |
| 98 |  | Chaya Chernowin: Wintersongs | International Contemporary Ensemble | Kairos | イスラエル人女流作曲家チェルノヴィンは、"暗闇の恐怖"を思わせる楽曲など、とかく人を不安にさせる、しかしとても強い吸引力を持つ作風の人だ。今作も心かき乱し、しかし音楽を停めることができない。すごい音楽だ。 |
| 99 |  | Pierluigi Billone: ITI KE MI & Equilibrio. Cerchio | Marco Fusi | Kairos | イタリア人作曲家ピエルルイジ・ビローネの、ビオラとバイオリンのソロ作品集。「意地でも普通の音は出さないぞ!」という決然とした意志を感じさせる、特殊奏法のオンパレードである。1曲が長く、聴き通すのも大変だ。 |
| 100 |  | 邦人作品集 | 渡邊一正指揮 シエナ・ウインド・オーケストラ | avex-CLASSICS | 吹奏楽界では割合と著名な曲が並ぶ音源だが、業界外ではほとんど知られることのない曲ともいえる。渡邊一正&シエナの輝かしく闊達な演奏と録音で、もっともっとたくさんの人に聴いてもらいたい名曲ぞろいなのである。 |
| 101 |  | Pecou: Les liaisons magnetiques | Ensemble Variances | Aeon | 仏人作曲家ティエリー・ペクは、洞窟の中を思わせる深い静寂から、時折強烈な衝撃波が全身を襲うような作品が多いように思う。油断のならない人だ。Aeonレーベルは優秀録音が多いが、本作もまた見事な録音である。 |
| 102 |  | More Field Recordings | Bang on a Can All-Stars | Cantaloupe Music | セクステット「バング・オン・ア・カン」が多数の作曲家とともに、さまざまな具体音や電子音などを基に奇妙な音楽を紡いでいく。現代音楽の中でも訳の分からなさは天下一品といえるが、またそこがたまらなく楽しい。 |
| 103 |  | Trios | カーラ・ブレイ | ECM Records | 編成はジャズのピアノトリオ+αで、拍はあるが拍子を取るのは難しく、旋律はあるがメロディを追うのは難しい。現代音楽と現代ジャズの狭間というか、ハイブリッドなのであろう。物凄い低音をしっかりと鳴らしたい。 |
| 104 |  | アマリッリ 麗し | 福井敬 | OMF | 毎年末の第九でもおなじみ、日本を代表するテノールの福井敬が、アントネッロを伴奏に古楽を歌う。どんなことになるのかと思ったら、大変に豊潤で力強く、絢爛たる世界が現出した。名手の新境地に、拍手を贈りたい。 |
| 105 |  | 歌うサクバット ~モンテヴェルディ 愛の歌~ | 宮下宣子 | OMF | サクバットはトロンボーンの素線に当たる楽器で、本作は日本の第一人者、宮下宣子がモンテヴェルディの歌曲を吹く。現代トロンボーンより繊細で温かな音色が耳に染み込むような演奏と録音は、ずっと聴いていたくなる。 |