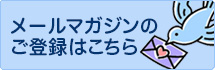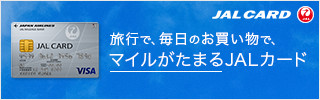友人に誘われてカラオケに行ったとき、ナット・キング・コールのナンバーを歌ったりすることが多い。彼の「モナ・リサ」や「トゥ・ヤング」はふつうの店ならリストに載っているからだ。
それくらい彼の歌はポピュラーなのだが、彼はもともとすぐれたピアニストで、トリオを組んでからは弾き語りで成功し、「スィート・ロレイン」などのヒットを放ったことはよく知られている。
彼の影響力は結構大きくて、レイ・チャールスも最初トリオを組み、弾き語りでナット・キング・コール風に歌っていたし、ギターの弾き語りのジョン・ピザレリも最初はナット・キング・コール・ナンバーを歌って売り出した。カナダの弾き語り歌手だったダイアナ・クラールも最初の頃はよくナット・キング・コールのナンバーを歌っていた。
黒人のジャズ・ポピュラー・シンガーの中で最初にビッグ・スターになったのはナット・キング・コールではなかろうか。彼についでビリー・エクスタインやジョニー・マティスがビッグ・スターになっていったように思う。
ナット・キング・コールの初期のヒット「スィート・ロレイン」や「ストレイト・アップ・アンド・フライ・ライト」は、ちょっとジャイヴ風でユーモアがある。キャブ・キャロウェイに言わせると「俺がナットに白人風にきれいで明快な発音をしろ、と言ってから彼の歌はヒットしたのだ。『モナ・リサ』が大ヒットしたのは、俺の教えを実行したからだ」と記録映画『ミニー・ザ・ムーチャー・アンド・モア』の中で語っている。
ナット・キング・コールの魅力とすごいところはどこにあるのだろうか。彼は1950年代にポップ・ソングを歌い数多くのヒットを放ったが、ジャズ歌手のようにはくずさずに比較的ストレートに歌っている。しかしとても味わいがあり、彼が歌うと、ただのヒット・ソングがスタンダード・ソングとして後世にまで歌い継がれていくようになる。そこが彼のすごさだと思う。「モナ・リサ」「ネイチャー・ボーイ」「トゥ・ヤング」「スマイル」「ラブ」「オレンジ・カラード・スカイ」「ザ・クリスマス・ソング」など、多くのポップ・ヒットが、彼が歌うことによって後世まで歌い継がれるスタンダード・ソングになっている。
少し前に中古レコード店で「COLE&CO.」というナット・キング・コールのデュエット集CDを見つけて買い、「PCMジャズ喫茶」で彼とディーン・マーティンの「ロング・ロング・アゴー」と、夫人のマリア・コールとデュエットした「月光価千金」をかけた。このCDにはナットが歌でデュエットしたものと、ピアニストとして歌手と共演したものが収められている。彼のピアノでアニタ・オディが「エイント・ミスビへイヴン」を歌ったり、メトロノーム・オールスターズやジューン・クリスティと共演したナンバーなども聴ける。
番組でかけた、歌手で夫人のマリア・コールとデュエットした「月光価千金」も聴きもので、この曲はキャピトルのバージョンがよく知られているが、そちらはナット・キング・コールのソロである。このマリアとナットの間に生まれた娘がナタリー・コールというわけだが、歌のうまい両親の子だから当然ナタリーもうまい歌手だ。ただナタリーはナットの娘という目で見られるのが嫌で、30歳を超えるまでは意識して父親のレパートリーには手をつけなかったという。しかし、年と共にそのこだわりは薄れ「アンフォゲッタブル」で父ナットと時を超えるデュエットを行い大ヒットさせた(その年のグラミーも受賞している)。その印税の一部を寄付したのだろうか、NYのハーレムには『ナット・キング・コール通り』が生まれている。
ところで、ナット・キング・コールと夫人マリア・コールの出会いも面白い。彼女はもともとデューク・エリントン楽団の専属歌手で、マリー・エリントンの名前で歌っていた(RCAに録音があるがエリントンの親戚ではない)。エリントンの伝記を読むと、ある時から毎晩のようにナット・キング・コールがエリントン楽団の演奏を聴きに来るようになったので、いつから俺のバンドが好きになったのかと喜んでいたら、ある日突然専属歌手のマリー・エリントンがいなくなり、その日からナットも姿をみせなくなったという。「ナットの関心は俺のバンドではなく彼女だったのかと、なんだかおかしくもあり、ほほえましく思った」とエリントンは回想している。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。現在尚美学園大学、大学院客員教授。