熱海伊豆山で発生した土石流災害 被災者を支えた“被災者支援コーディネーター”とは

2016年、内閣府の政策によって、行政・NPO・災害ボランティアセンターの三者が連携して被災者を支援する体制が構築された。全国各地で取り組みが広がるこの三者連携には、まだまだ課題がある。異なる場所で働く団体が、緊急時に即座に連携を取ることが容易ではないからだ。
実際に災害の現場でその三者を繋ぐという難しい役割を担ったのが、鈴木まり子さん。鈴木さんは、2021年7月に静岡県熱海市で発生した伊豆山の土石流災害で、「被災者支援コーディネーター」として現地の人たちを支えた。
被災者支援コーディネーターという肩書きは、伊豆山の土石流災害の支援から生まれた。三者と関係をつくるうえで鈴木さんの役割を示す呼び名が必要だということになり、静岡県の行政の担当者とともに名前を決めたのだった。
「被災者支援コーディネーターは公的な資格ではありません。そのためまだ広く知られていませんが、地元の人たちが主体的に決めていくことをサポートし、必要なところへ繋げることが役割です」
伊豆山土石流災害での鈴木さんの活動は、テレビや新聞に取り上げられた。それらの取材で鈴木さんは、「災害時だからこそ、話し合いの場が必要です」と語っていた。そこにはどういう意図があるのか? その思いを探るべく、鈴木さんの半生を聞いた。
ボランティア活動に明け暮れる父を見て
1960年に静岡県浜松市で生まれた鈴木さんは、ボランティア活動を行う父の影響を受けて育った。鈴木さんの父は視覚障害者のための点訳奉仕活動を行っていて、小学生の鈴木さんは父と一緒に盲学校に行ったり、目の見えない子どもたちと梨狩りに出かけたりした。
鈴木さんの父は工務店を営んでいたが、仕事以外の時間はほとんどボランティアに費いやしていたという。なぜ、鈴木さんの父は熱心にボランティア活動を行っていたのか。それは、父の地元である春野町で、「お互い様」という文化が根付いていたからだった。
「山深いところって、みんな共助なんです。地域の人同士で助け合うことが当たり前だったので、父はボランティアという感覚ではなかったのかもしれません」
自宅には、いつも人が集まっていた。お腹をすかせた大学生ボランティアたちが居間を囲み、庭では父が監督を務めるバスケットボールチームの小学生が遊んでいた。賑やかな生活のなかで一番印象に残っているのは、父と集まった人たちが「話し合い」をしている姿だった。
「父は、人の輪の中で進行役のようなことをしていました。どんな小さなことでも話し合いをする人でしたね。両親は家族で食事した後、いつも1時間ぐらい話すんですよ。ときどき食い違ったり、ケンカになったりするときもあるんですが、お互い折れずに話し合っていました」
家族や周囲の人たちが集まって会話しているのを見ながら、鈴木さんは「話し合いって面白いな」と思っていた。
小学校を卒業した鈴木さんは、浜松市にある静岡県西遠女子学園に入学した。いわゆるお嬢様学校で、入学は母の願いでもあった。というのも、鈴木さんの母は子どもの頃からこの学校に憧れていたのだが、経済的な理由で入学が叶わなかった。そこで、娘である鈴木さんに思いを託したのだ。
当初、鈴木さんは「女子校なんて絶対行きたくない!」と思っていた。けれど、母に連れられて学校見学に行った時、オーケストラクラブの演奏を聴いてときめいた。そこでオーケストラクラブの先輩方に優しくされ、「入ってもいいかな」と思い直す。
入学後はオーケストラクラブに入部し、クラリネットの練習に没頭。練習が忙しくなり、父のボランティア活動には顔を出さなくなっていた。ただ、話し合いの面白さは心のなかに残っていたようで、ホームルームでは率先して議題を提案したり、教室ではなく、公園で話し合うのはどうかと先生に交渉したりした。「どうしたら意見が言いやすくなるんだろう。話し合いでどんなことが変えられるだろう」と思いを巡らすのが楽しかったという。
大学受験で挫折、和裁とボランティアへ
その後、同じ学園の高校に通い、大学受験では志望する大学の教育学部に落ちてしまい、滑り止めとして受験した短大の家政学部に合格した。鈴木さんが短大に進学しようとすると、それまでまったく進学について興味を示さなかった父から猛反対を受けてしまう。
「父からは、『勉強は学びたい分野があるからするのであって、いろんな学部を受けるなんてありえない。なんで家政学部を受けたんだ』と言われました。担任の先生も父を説得してくれたんですが、『行かせられない』の一点張りで。その後の進路が白紙になってしまったんです」
進学をあきらめた鈴木さん。これからどうしようかと悩んでいると、父から「大学に行く代わりに、和裁を学ばないか?」と提案を受けた。
和裁とは、着物などを仕立てる技術のことである。機械を使わず、人の手先の技術だけで着物や浴衣を作る伝統技芸だ。父方の祖母が和裁士だったので、父はその道を娘に進ませようと思ったようだ。「就職するよりそっちの方がいいかな」と思った鈴木さんは、和裁教室の門を叩いた。
その後、鈴木さんは和裁士検定2級を取得し、自身の成人式の振袖を自分で仕立てるまで技術を磨いた。真剣に取り組んだ理由は、単純に和裁の面白さを感じていたのもあるが、師匠の山田はまのさんの人柄が魅力的で、彼女と話をするのが好きだったから。
「先生はよく、『絶対こうだと思いすぎて自分は失敗しちゃったから、人生はそのときどきで合わせていった方がいいのよ』と話していました。私は18歳で和裁を始めて26歳で和裁と離れてしまうのですが、辞めるときも先生は『無理しちゃダメよ。今は辞める時なの。どこかで針を持ったらまた思い出せるから』と諭すように送り出してくださいました。今思うと、先生の人生観が刷り込まれたように思います」
父の工務店再開に奮闘
和裁を始めた同時期、鈴木さんは本格的にボランティア活動に携わるように。きっかけはやはり、父だった。和裁だけでは同世代の友達ができにくいだろうということで、父に連れられて青少年育成活動に参加した。その後、浜松市が運営している『青少年の家』のボランティアに加わり、子どもたちとキャンプをしたり、親しい友人ができたりするうちに、鈴木さんはボランティア活動にハマっていく。
特に熱心に取り組んだのは、父譲りの「話し合い」だった。ボランティアのチームでは頻繁に会議が開かれる。そこで何を話し合うべきか、性別や年齢に関係なく意見を出してもらうにはどうしたらいいかなど、鈴木さんは準備段階から会議の細部までこだわった。
その後、鈴木さんは24歳で結婚し、和裁とボランティア活動を続ける日々を過ごす。結婚から2年後のある日、当時50代だった父が病に倒れ、後遺症で半身不随の身体になってしまった。そこで鈴木さんは、好きだった和裁を離れて父の介護をすることにした。
父の工務店は、廃業を余儀なくされた。けれど、得意先から注文が切れ目なく入ってきて、父は得意先に職人を紹介するなどして業務を回していた。鈴木さんはそんな父の姿に「廃業したのに続けるなんて……」とやきもきした。
そんな状況が続いたある日、夫から「どうやらお義父さんは、僕に工務店を継いでほしいようだ」と聞く。鈴木さんには兄がひとりいるが、父の仕事を継ぐ気がないことは家族全員知っていた。夫は浜松で会社員をしていて建築のことは素人だったが、父の工務店を継ぐことを決意。夫は建築士になるために修行することになった。
鈴木さんは夫の挑戦を手伝うべく、自らも行動を起こした。まず事務の知識が必要だろうと考え、会計事務所のアルバイトを始める。そこで、簿記2級を取得。会計事務所を辞めたあと、人を雇う知識も必要だと人事コンサルタントの会社でも働いた。そこでどんどん仕事を覚えてゆき、キャリア・コンサルタントの資格を取るまでになった。
1995年12月、鈴木さんの夫が建築士の資格を取得し、工務店を再開。鈴木さんも会社を辞めて、仕事を手伝うつもりだった。けれど、会社の上司に「工務店の経営が軌道にのるまでここで働きなさい。せっかく採用の勉強もしたのだから、誰かを募集・採用する経験をしてみたら?」と言われる。そこで工務店では事務員を雇い、鈴木さんはそのまま人事コンサルタントの会社で働くことになった。
キャリアデザインを極めるため、40半ばで大学生になる
2004年、鈴木さんが44歳になった時、法政大学に日本で初となるキャリアデザイン学部が開講されることを知る。キャリアデザインとは、人生の目標や希望を明確化し、どう生きていきたいかをデザインすることだ。キャリアデザインを極めたいと思っていた鈴木さんは思った。
「父が『学びたいものが見つかったときに大学に行きなさい』と言ったのは、これのことだなって。それで大学を受験しようと思ったんです」
しかし、当時の鈴木さんは人事コンサルタントの会社の支店長の立場にあり、すぐに辞めるわけにはいかなかった。そこで、1年ほど会社に勤めながら翌年の受験を待つことに。
管理職として忙しく過ごしていたある日、会社の後輩からこう言われた。
「まり子さんがしていることってファシリテーションっていうのですが、知ってますか?」
「え、ファシリテーション?」
鈴木さんはこの言葉を知らなかった。
ファシリテーションとは、さまざまな話し合いの場が有意義な場になるようにサポートしていくためのスキルとマインドのことである。その進行役を務める人のことをファシリテーターと呼ぶ。後輩は鈴木さんの話し合いの進行や振る舞いを見て、ファシリテーションをしていると感じたようだ。鈴木さんは後輩の言葉を聞いて、ストンと腑に落ちた。
「私が今までこだわってきたことって、ファシリテーションだったんだ!」

鈴木さんはすぐにファシリテーションについて調べ始めた。『ファシリテーション革命』(岩波文庫)を読み、著者である中野民夫さんの講座に参加するようになる。
そして2005年、会社から理解を得て退社し、法政大学キャリアデザイン学部の社会人枠を受験。社会人枠は倍率が高かったが、無事合格した。その後、東京で下宿をスタート。夫に父の介護をサポートしてもらいながらの進学だった。鈴木さんの同期の学生は企業の管理職や通訳、アナウンサーなどとして社会で活躍している人ばかりで刺激を受けた。
同じ時期、鈴木さんは大学でキャリアデザインを学びながら、中野民夫さんが講師を務める「ビーネイチャースクール」でファシリテーションを学び始めた。そして、大学を卒業した2年後、鈴木さんは、同大学でキャリアデザイン学部「ファシリテーション論」の兼任講師として授業を受け持つようになる。
被災者支援コーディネーターの誕生
2011年、東日本大震災が起こった時、キャリアカウンセラーやファシリテーターとして働いていた鈴木さんは被災地でのボランティアに携わる。きっかけは、鈴木さんが所属していたNPO法人「ファシリテーション協会」の会長・徳田太郎さんが、「災害にファシリテーションは必要だ」と提言し、災害復興のためのファシリテーションを行うチームが立ち上がったこと。
鈴木さんは災害の場でボランティア活動は初めてだったが、甚大な被害を受けた東北の地でファシリテーション役を務めた。
そもそも、なぜ災害時に話し合いの場が必要なのだろうか? 理由は1995年に起きた阪神・淡路大震災に遡る。阪神・淡路の復興が進むなか、倒壊したマンションの入居者と管理会社の間でトラブルが起こり、裁判になるケースも少なくなかった。災害が起きた時こそ問題を後回しにしたり、放置したりせず、話し合いの場を設けることが必要だという判断だった。
「災害時は、ちょっとしたボタンの掛け違いでいろんなことが起きます。ちょっとしたことで夫婦の気持ちのすれ違いが生じるようなものです。夫婦ならどちらかが『このままだとまずいぞ』と気づいて話し合いますが、災害時は気持ちのすれ違いがたくさん起こって、対応しきれていないのです」
東日本大震災での活動を経て、鈴木さんは2016年の熊本地震などさまざまな被災地でファシリテーションを行った。被災地のファシリテーションは一度で終わりではない。被災者の心のケアや復興にむけての対応を継続的に行う必要がある。現地に行けない時、鈴木さんはオンラインで現地の人たちの声に耳を傾けた。
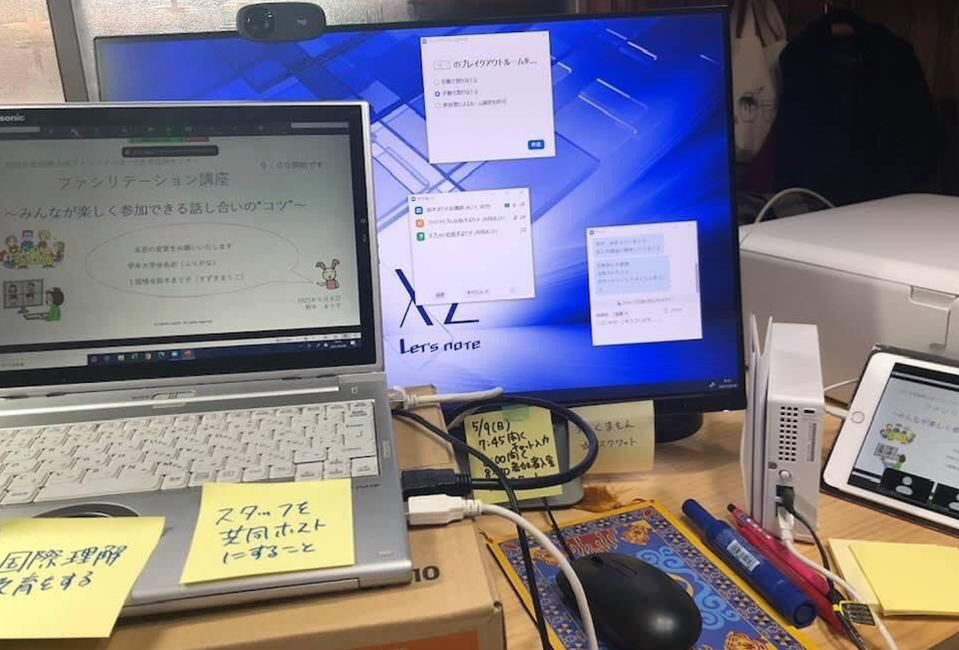
そうしてさまざまな経験を積んできた2021年7月3日、熱海市伊豆山で大規模な土石流災害が発生した。災害発生から3日後、静岡県から「避難所を被災者中心で運営できるように手伝ってほしい」と依頼を受け、鈴木さんは現地に向かった。
土石流で避難した住民は、熱海市のホテルに避難していた。学校の体育館などを避難所にすることが一般的だが、今回はコロナ禍でホテルが一時休業していたことにより、ホテルを避難所として活用することができた。ホテルならそれぞれ部屋を与えられ、被災者のプライバシーが守られる。食事や生活の安全も十分に保たれた。学校や体育館と比べれば良いことばかりだが、その反面、被災者同士が顔を合わせづらくなっており、情報を得ることができずに孤立していく人がでていた。
鈴木さんが現地に到着してすぐに、避難所では町内会の役員同士の話し合いが始まる。鈴木さんがファシリテーターを務め、避難所内での困りごとについて話し合った。このディスカッションを通して解決策が生まれていく。
例えば、ある人はホテルの食堂まで移動が難しい高齢者のために、部屋までお弁当を配りに行った。ある人は運動不足を解消する健康体操の運営などを手伝った。被災者同士で連携しあうようになっていったのだ。
それ以外にも、女性のための支援物資が少ないことに気づいた鈴木さんは、市役所に働きかけ、女性限定の情報交換会や物資配布会を開催。埋もれてしまうかもしれなかった誰かの声を、鈴木さんは見逃さなかった。

伊豆山土石流災害で被害に遭ったエリアは広く、山頂近くから海岸付近の地域にまで被害に見舞われた。写真は伊豆山中腹付近、今も生々しい傷跡を残す(2021.12月 編集部撮影)
鈴木さんの取り組みは、テレビや新聞でも取り上げられた。メディアで紹介されていた鈴木さんの肩書きは、「被災者支援コーディネーター」だ。
冒頭に記したように、鈴木さんはファシリテーターとして被災者の支援を続けてきたが、肩書きはとくに設けていなかった。静岡県の行政から「肩書きがある方が呼びやすい」と言われたことで名乗るようになる。
「被災者支援コーディネーターは、被災者と支援者を繋ぐということがすごく大切です。それも繋ぐだけではなくて、対等に繋ぐ。災害時だからこそ、パートナーとして対等に繋いでく必要があるんです」
色眼鏡をかけていることを理解する
現在、鈴木さんは全国各地でファシリテーションの講演やワークショップを行いながら、被災地への継続的な支援を続けている。ファシリテーターとして、そして被災者支援コーディネーターとして、鈴木さんが最も大切にしていることは「お互いを尊重し合う場づくり」だという。
「会議では、ほとんどの人が色眼鏡をかけて参加しています。そもそも市役所がボランティアの立場に立ったり、ボランティアが市役所の職員の考えを理解したりするというのは簡単ではありません。だから、色眼鏡をかけているっていうことがわかってもらえればいい。少なくとも自分が色眼鏡かけているってことがわかれば、『自分が言っていることが正しい』というような絶対的な主張をしなくなるはずです」
さまざまな思いを抱えた人がひとつの場所に集まる。その人たちを繋ぐことの難しさもあるだろう。「大変ではありませんか?」と聞くと、鈴木さんは少し考え、「そうね。大変です。そうだけれど……」と続けた。
「人の心が自ら変容していく姿を見ると、嬉しくなるんです。例えば、災害が起きた都市で、やる気のない市の職員がいたとします。きっと、『なんでこんな時にこの課になったんだろう』と思うでしょう。けれど、一緒に活動していくうちに被災者の方から感謝されたり、涙を流して喜ばれたりすると、職員の気持ちに変化が起きるんですね。『なんだ? この嬉しさは……』って。そんな瞬間に立ち会って、仲間になれたと思えた時に喜びを感じます」

被災者支援コーディネーターという肩書きは、まだまだ日本に浸透していない。国から費用がでているわけでもなく、鈴木さんは、ほぼボランティアで行っている。しかし、鈴木さんの話を聞いて、災害時におけるコーディネーターの価値がもっと認知されるべきだと感じた。
「全国には、名乗っていないだけで被災者支援のコーディネートをしている人がたくさんいらっしゃると思います。災害時の調整役という存在が、ひとつの仕事として社会で認められになったらと願っています」
写真提供 = 鈴木まり子
取材・文 = 池田アユリ
編集 = 川内イオ















