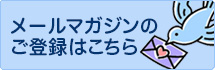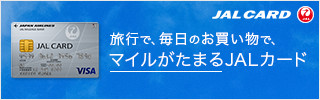2011年7月/第94回(最終回) 危機に立つオーケストラ
2011年7月/第94回(最終回) 危機に立つオーケストラ
東日本大震災のあと、文化や芸術とは何か、ということを考える機会が増えているのではないだろうか。
人間が生存するために、絶対に必要なものというわけではない。人の心を豊かにし、生きる喜びを与えてくれることもあるけれど、全員が同じように感じるわけではない。クラシック音楽も、好きな人もいれば、ほんの少しでも聞かされるのは勘弁、という人もいる。そもそもそれ以前に、多くの人が聴きたがるようなものなら、商売として成り立つはずで、補助金がなければできないのはおかしい、という考えの人もいる。
こうした状況を象徴するようなオーケストラが、いまアメリカと日本にある。一つはフィラデルフィア管弦楽団。4月に破産を申し立て、大きなニュースになった。
完全民営が原則のアメリカでは交響楽団の破産や解散はけっして珍しくないが、フィラデルフィアほどの名門となると、例がない。かれらはストコフスキー、続いてオーマンディに率いられた時代には、アメリカ最高の豊麗な響きで人気をほしいままにした。その歴史を誇る団体にして、この苦境を迎えたことは、アメリカの市民社会におけるオーケストラの存在の難しさを如実に物語っている。
もう一つは、被災地の東北を拠点とする、仙台フィル。被災地においてクラシックを演奏することがどのような意味を持つか、これからその真価を問われることになるだろう。
どちらも、事態は容易ではない。しかし、必ず力強く乗りこえてくれると、信じている。
「CLASSICのススメ」は、今回で最終回です。長らくのご愛読、本当にありがとうございました。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
★「クラシックのススメ」は今回をもって終了となります。ご愛読ありがとうございました。
 2011年6月/第93回 義を見てせざるは~メータの場合
2011年6月/第93回 義を見てせざるは~メータの場合

このたびの東日本大震災では、被災地の一日も早い復興を祈るばかりだが、クラシックの興行界にも大きな影響があった。
海外の演奏家の来日中止も続くが、なかにはそんなときこそと、強い使命感をもって演奏してくれる人々もいる。来られなかった音楽家にもさまざまな事情があるので、あげつらう気はないが、来日した音楽家の勇気とプロ意識の高さには敬服し、大いに励まされたことには、心底から感謝したい。
その一人に、ズービン・メータがいる。
メータが指揮者として来日していたフィレンツェ歌劇場は、震災4日後に公演を中止、帰国した。メータだけは日本に留まって、日本のオーケストラと支援演奏会を開くことを希望したが、電力不足による混乱などのために実現できず、いったん離日した。
しかし4月10日、メータは多忙な日程の合間を縫ってふたたび来日、NHK交響楽団と「第9」を演奏してくれた。この熱意に、私は正直なところ驚いたし、同時に、この指揮者がイスラエル・フィルと、強固な信頼関係を長く築いてきた理由が、初めて本当の意味でわかったような気がした。
イスラエルという国をどう評価するかは、さまざまな意見があるだろう。それはそれとして、イスラエル・フィルが、平和な国では考えられないような、非常に困難な条件のもとで活動してきたオーケストラであることは、たしかである。
メータは1963年以来共演を重ね、いまは終身音楽監督の地位にある。この機会に、このコンビのつくる音楽を、ライヴ録音のボックスに聴いてみることにしたい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2011年5月/第92回 フォルテピアノによるショパン
2011年5月/第92回 フォルテピアノによるショパン

ピリオド楽器がバロックだけなく、モーツァルトやベートーヴェンなど古典派の作品演奏にも広がりはじめた1980年代、その新鮮な響きを面白がりつつも、「これだけは最後まで抵抗が残るかも」と感じたのが、フォルテピアノの、ポコポコとした響きだった。
今にして思えば、演奏側の奏法の未成熟による違和感も大きかったので、たとえばシュタイアーのような優秀な奏者が登場することで、現在ではその独自の美を、かなり自然に楽しめるようになってきた。
近年は、ショパンやシューマンなど19世紀前半の作品でも、同時代のフォルテピアノで演奏することが、かなり普及しつつある。それも、古い鍵盤楽器専門の特殊な奏者たちだけではなく、ふだんはモダン・ピアノを弾いている一流ピアニストが、使い分けてそれを弾くようになってきた。
そうした時代の変化を、CDで一番感じさせてくれたのが、ワルシャワのショパン協会の「ザ・リアル・ショパン」シリーズだ。ショパン演奏の総本山みたいなこの協会が、エラールやプレイエルのフォルテピアノによる全集をつくってしまったのである。
それは同協会のモダン・ピアノによる全集とは違って、けっして「模範演奏」を示すというものではないようだが、ここに新たな地平線がひらけたことは間違いない。
日本の有名ピアニストでも、仲道郁代が1841年のプレイエルで、横山幸雄が1910年のプレイエルでショパンを弾いたりと、自分なりの方法で、新たな道を試みる人が出てきている。どんな果実が生れるか、これからが楽しみだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2011年4月/第91回 ピアノによるバッハ
2011年4月/第91回 ピアノによるバッハ
2月に、東京の紀尾井ホールで、シフがモダン・ピアノで弾く、バッハの平均律クラヴィーア曲集第2巻の全曲を聴いた。
一度の休憩をはさんで24曲を続けて弾くという長大な演奏会で、いつはてるとも知れない、前奏曲とフーガの大迷宮の中にいるような不思議な感覚は、しかしとても心地よい時間だった。それは、シフのつくりだす音楽が味わい深く、遊戯性と真摯な祈りとが共存したものだったからである。ペダルを用いず、タッチの変化だけで生み出される豊かな響きは、ピアノによるバッハ演奏の、一つの頂点と思えるものだった。
いま、バロック、古典派のジャンルでの、モダン楽器(20世紀楽器)による演奏の「揺り戻し」が始まっているようである。といってもそれは硬直化した、保守反動の動きではない。ピリオド楽器の響き、奏法の美点を理解した上で、それをとりいれ、安定性と豊かさに優れた、モダン楽器独自の可能性を示そうという動きだ。
アメリカのピアニスト、ディナースタインによるバッハも、その一つといえる。「いちばん大切なのは音楽に語らせること」という彼女は、ピアノでバッハの音楽の息吹を、豊かな表情をよみがえらせる。自主制作したゴルトベルク変奏曲のCD(発売はテラーク)の大ヒットでその名を知られた彼女は、ソニーと契約して録音を開始した。「奇妙な美」という原題のバッハ・アルバムは、その第一弾である。
教条主義的な演奏は意味がない。どのような方法論であれ、新鮮な音楽を聴かせてくれる演奏家こそが、私たちを感動させてくれる。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2011年3月/第90回 チェコ音楽に捧げた生涯
2011年3月/第90回 チェコ音楽に捧げた生涯

昨年10月に84歳で亡くなったサー・チャールズ・マッケラスは、日本でも多くのファンに愛された名指揮者だった。
録音でふりかえると、その活動には二つの柱があった。一つはモーツァルトであり、もう一つはチェコ音楽である。あえていえば、どちらもプラハに縁が深い。オーストラリアに生れ、イギリスを拠点にした指揮者だが、その愛は何よりも、これらの音楽に注がれていた。
しかしその愛は、同時に、客観的な姿勢と視点を忘れぬものだった。それらの音楽に対して、単純素朴な郷土愛をもちようもないマッケラスは、自らの憧れと愛着が何に由来し、何を対象としているかを、つねに覚めた目で見つめることを忘れなかった。モーツァルト演奏にはその態度が典型的にあらわれていて、生まれついての新即物主義的な様式に、近年のピリオド演奏の音感覚を巧みにとりいれ、厳しさと愉悦性を両立させる音楽をつくってみせた。
そしてその姿勢は、チェコ音楽に対しても変らなかった。とりわけ得意としたヤナーチェクはもちろん、スメタナやドヴォルジャークなど、ともすれば惰性に陥りやすい人気曲でも、背筋を伸ばしたような折り目の正しさが、その演奏にはあらわれた。
チェコ人たちがマッケラスの演奏を高く評価し、愛したのも、たしかな見識に支えられたその響きに、教えられるところが多かったからだろう。チェコを代表するレーベル、スプラフォンはその業績を記念して、四半世紀にわたる録音を2つのボックスにまとめた。今月のニューディスク・ナビでは、そのセットをまとめてご紹介する。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2011年2月/第89回 フィドルの越境者たち
2011年2月/第89回 フィドルの越境者たち
ヴァイオリンを民俗音楽で使う場合に、英語で「フィドル」と呼ぶことがある。
楽器自体や奏法に、大きな変化があるわけではない。どちらかといえば「気分」の問題だ。フィドルの方が、俗っぽい。
近代になって、メロディとリズムの分業が進んでいくうちに、音楽は自由な躍動感を失っていった。整備され、クリーンにはちがいないが、生命力や訴求力の点で、物足りなく感じられるときがある。
かつてはサラサーテやクライスラーなど、たくさんの華やかなスターがいたのに、その後のヴァイオリンは、次第に地味な楽器になっていった。そのことと、分業制の進行とは、けっして無縁ではない気がする。
もともとヴァイオリンは、メロディを歌うだけでなく、リズム楽器でもある。フィドルと呼ぶとき、そこには野性の匂いと敏捷な肉体が、感じられる気がする。
このところ、フランスを中心に、ヴァイオリニストたちがさまざまな越境を試みている。コパチンスカヤは、民俗音楽の演奏者である両親とともに、母国モルドヴァの音楽をひいたアルバム「ラプソディア」をつくり、映画「オーケストラ!」で吹替え演奏をしたサラ・ネムタヌは、「ジプシック」でロマの音楽を奏で、また弦楽四重奏のエベーヌ四重奏団は、映画音楽などを集めて「フィクション」という1枚にまとめ、美声まで披露した。
けっしてお遊びではなく、自分たちのルーツを省察することで、音楽家としての姿勢そのものを提示しようとする覚悟が、それぞれに感じられるのがいい。かれらのこれからが、ますます楽しみに思えてくるのだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2011年1月/第88回 2010年のレコード・アカデミー賞
2011年1月/第88回 2010年のレコード・アカデミー賞
音楽之友社選定の「レコード・アカデミー賞」が、今年も発表された。
大賞は声楽曲部門から、アーノンクール指揮ウィーン・フィルの、ブラームスのドイツ・レクイエム。2010年秋には「最後の来日公演」を行なったこの指揮者は、ブーレーズとともにメジャー・レーベルから話題盤を継続的に発売できる、いまでは希少な老練である。このブラームスといい、歌劇「ポーギーとベス」といい、十八番の再録音に頼らずに新しいレパートリーを開拓する意欲は、レコードという「芸術」の担い手として、まことに頼もしい。
銀賞はオペラ部門から、バルトリが歌う「神へのささげもの」。新譜のごく少ないオペラ部門では、フローレスともに、このバルトリは貴重なスター。単なるアリア名曲集ではない、明快なコンセプトが魅力だ。
大賞も銀賞も声楽関係というのも面白いが、今年の最大の特色は、マイナー・レーベルの躍進である。器楽曲部門のメジューエワ盤を制作した、若林工房のような日本の会社だけでなく、交響曲、管弦楽曲、室内楽曲、音楽史、現代曲の一挙5部門で、輸入盤に日本語解説と帯をつけたスタイルのマイナー盤に賞が与えられた。銅賞も得た室内楽曲部門のアルカント四重奏団の盤を制作したフランス・ハルモニア・ムンディなど、こうなると印象的にはメジャーのように思えてくる。
しかし一方で、ラトル指揮の「くるみ割り人形」とか、小澤征爾指揮の戦争レクイエムなど、「レコード芸術」特選にならなかったために候補から外された話題盤もあり、これらは惜しい気がする。
<大賞 声楽曲部門>
ブラームス:ドイツ・レクイエム
ニコラウス・アーノンクール指揮ウィーン・フィル 他(RCA SICC1369)
<銀賞 オペラ部門>
バルトリ/神へのささげもの
チェチーリア・バルトリ(Ms) (デッカ UCCD9764~5)
<銅賞 室内楽曲部門>
ドビュッシー、デュティユー、ラヴェル/弦楽四重奏曲集
アルカント・カルテット (ハルモニア・ムンディ・フランス KKC5108)
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年12月/第87回 カルロス・クライバー、きらめく残像
2010年12月/第87回 カルロス・クライバー、きらめく残像
今年は、1930年生れのカルロス・クライバーの生誕80周年にあたる。
同い年のマゼールは今も元気に活動中だが、クライバーは2004年に亡くなっている。しかもその5年ほど前から演奏会に登場しなくなっていたし、CDでは現時点で最後の記録となる、ウィーン・フィルとの2回目のニューイヤー・コンサートは、18年前の1992年元旦、つまり平成4年のライヴだから、基本的には「昭和」の時代の指揮者といっていい。
だが、その指揮による演奏は、まったく古びていない。あらためて聴きなおすと、速めのテンポ、跳ねるようなリズムなどには、現代のピリオド様式の演奏スタイルを予告する一面があったことに驚かされる。
重々しい、遅めのテンポが主流だった、同時代の様式を軽々と跳びこえて、閃光のようにその音楽は鳴りひびいたのだ。そうして、一瞬に消え去っていったが、その残像は鮮烈という以外の何物でもなく、いやはや、「天才」という言葉は、こういう人間のためにあるのだ、と、聴く者にため息をつかせるものだった。
今回のウィークエンド・スペシャルでは、クライバーとその遺族が発売を許可した正規の録音の、ほぼすべてを集めてお聴きいただく。現時点で抜けているのは、オルフェオから発売された、フレーニのウィーン国立歌劇場ライヴ録音集に含まれた、1985年の「ボエーム」の第4幕の一場面だけだが、これは15日放送の「ニューディスク・ナビ」で取りあげる。この録音で、すべてが揃ったことになる。ぜひそちらも、あわせてお聴きいただきたい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年11月/第86回 世界のオザワ
2010年11月/第86回 世界のオザワ
小澤征爾が、1973年からアメリカのボストン交響楽団の音楽監督に就任するニュースが流れたときの衝撃と驚きは、現在では想像もつかないほどに、大きいものだったという。
クラシックの演奏では、まだまだ発展途上国と思っていた自分たちの国から、アメリカのメジャー・オーケストラの音楽監督になる人物が出た。カナダのトロント、アメリカのサンフランシスコ、そしてボストンと、精妙華麗な指揮法を武器に、着実にステップアップしてきたオザワの活躍は、北米に進出して地歩を築きつつある自動車や電機メーカーなどの日本企業の姿に重なるものがあった。
その好評によって、ボストンのポストに30年にわたって留まる一方、ヨーロッパでは特にパリで高い人気を獲得し、ベルリン・フィルとも緊密な関係を保って、一時は「帝王」カラヤンから後継者候補に挙げられたという噂が流れるほどだった。1986年には、病気のカラヤンに代って、ベルリン・フィルの来日公演の指揮も担当している。
一方、ウィーン・フィルの定期演奏会にも継続的に招かれるようになり、その演奏はライヴ録音されて広く聴かれた。そして2002年、ウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任。日本人として前人未到の地位を、ついに手にすることになった。その直前のウィーン・フィルとのニューイヤー・コンサートのライヴ盤が、日本で超ベストセラーになったのは、忘れがたい「事件」だった。
今月の「ウィークエンド・スペシャル」では3回にわたって、その世界的な活躍を、録音を通じてふりかえりたいと思う。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年10月/第85回 カラヤン・ライヴ・イン・ジャパン
2010年10月/第85回 カラヤン・ライヴ・イン・ジャパン

1977年11月、「帝王」カラヤンはベルリン・フィルを率いて、7度目の来日公演を行なった。
東京ではベートーヴェンの交響曲全9曲が2曲のピアノ協奏曲(独奏はワイセンベルク)と演奏され、巨大な普門館に鳴り響いた。
その交響曲全集が、FM東京(現TOKYO FM)の録音を元にCD化された。カラヤン&ベルリン・フィルの絶頂期のライヴが如何なるものであったかを知る、最高の実例となるものだ。堂々として力強く、雄大なスケール感をもつベートーヴェンである。
「ニューディスク・ナビ」の10月第3週は、特別編「カラヤン・ライヴ・イン・ジャパン」として、カラヤンの日本でのライヴ、それにザルツブルク音楽祭やウィーンでのライヴを、30時間にわたって特集する。
1日目の11日は、ベートーヴェンの交響曲第1番から第8番までの8曲。FM東京のラジオ番組の収録を、ディレクターとして担当された東条碩夫さんをお招きして、当時の思い出をうかがいながらお送りする。
12日は「第九」とともに、ザルツブルク音楽祭でのブルックナーの交響曲など。
13日は、カラヤン初来日となった1954年のNHK交響楽団との演奏会の「悲愴」など50年代のライヴ、それに1972年ロンドンでのベルリン・フィルとのライヴ。
14日は、ベルリン・フィルだけでなくウィーン楽友協会合唱団、多数のスター歌手まで帯同して盛大に挙行された、1979年普門館での来日公演から。
そして15日は、最後の来日となった1988年サントリーホールと東京文化会館でのライヴを中心に、晩年のライヴを集めて。
昭和後半、戦後日本を彩ったカラヤンのライヴを、たっぷりとお楽しみあれ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年09月/第84回 今年のウィーン・フィル来日公演の指揮者
2010年09月/第84回 今年のウィーン・フィル来日公演の指揮者

11月の「ウィーン・フィルハーモニー・ウィーク・イン・ジャパン」は小澤征爾が指揮するはずだったが、病気療養のために降板し、アンドリス・ネルソンスとエサ=ペッカ・サロネンが担当することになった。
小澤さんの一日も早いご快復を祈る一方で、これはこれで楽しみな来日公演になったと思う。ヴェテランにはヴェテランのよさもあるが、期待の若手と旬の中堅ふたりがウィーン・フィルからどんな響きを引き出してくれるのか、大いに期待できるからである。
ネルソンスは1978年ラトヴィアのリガ生れ、同郷のマリス・ヤンソンスの薫陶を受けた。2008年にイギリスのバーミンガム市交響楽団の首席指揮者兼音楽監督に就任し、国際的な注目を集めた。今年夏にはバイロイトで『ローエングリン』新演出を指揮し、秋にはベルリン・フィルとも共演、さらに来年の「東京・春・音楽祭」でも「ローエングリン」を指揮する予定だが、それより一歩早く日本でも聴けることになった。
サロネンは1958年、フィンランドのヘルシンキ生れ。精巧な表現で定評があったが、1992年から2009年にかけてのロサンジェルス・フィルハーモニックの音楽監督時代にさらに音楽のスケールを増し、現在は2008年からフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者・芸術顧問の地位に就いている。
ウィーン・フィルとの録音はまだないが、ネルソンスはオルフェオからバーンミンガムと、サロネンはシグナムからフィルハーモニアとの録音が継続的にCD化され、好評を得ている。「ウィークエンド・スペシャル」でそれらをまとめてお送りするので、お楽しみに。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年08月/第83回 マーラーの演奏史
2010年08月/第83回 マーラーの演奏史

今年はマーラー生誕150年のアニヴァーサリー。さらに来年は没後100年にあたり、記念年が2年続くことになる。
生前のマーラーは作曲家としてよりも、指揮者としての名声の方が高かった。残念ながらその指揮ぶりをディスクにとどめることはなかったが、しかしピアノ・ロール用に自作をいくつか演奏している。緩急の変化の幅が大きく、一つのフレーズの中で俊敏軽快につけられることに特徴がある。
このスタイルは、弟子のワルターや友人のメンゲルベルクなどに受け継がれ、戦前のSP録音などに記録されることになった。また、同じ弟子でもクレンペラーの場合はその後の新ウィーン楽派などの作曲様式、新即物主義と呼ばれる演奏法をとりいれ、厳しさと激しさを共存させるスタイルで名演を残した。
1960年代になるとステレオ録音が普及し、マーラーへの関心もさらに高まってくる。バーンスタインやバルビローリによる、共感度の高い熱い演奏がこの時代を代表する。さらに70年代には、クーベリック、ショルティ、カラヤン、アバドなどのさまざまなスタイルが録音で残されるようになる。
しかし、本当の意味でマーラー人気が高まったのはバブル景気の前後、80年代と90年代だ。CDというソフトもこの作曲家にぴったりだった。バーンスタイン、ベルティーニ、シノーポリ、テンシュテットの没入的な演奏が登場し、日本でもさかんに演奏された。
そして21世紀。ヴェテランから若手まで、それぞれのアプローチで多様なマーラーが生れている。100年間の演奏史を8回にわけてふりかえる、48時間のマーラー。どうぞお楽しみに。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年07月/第82回 ウィグモア・ホール・ライヴ
2010年07月/第82回 ウィグモア・ホール・ライヴ

ロンドンにウィグモア・ホールという、素晴らしい音響の室内楽用のホールがある。
地下鉄のボンド・ストリート駅の近く、その名もウィグモア・ストリートに面した古風なビルの中にある、座席数約600の演奏会場だ。1901年に開場したときにはベヒシュタイン・ホールと呼ばれていたが、第1次大戦中の1916年に現在の名に改称している。
幸運にも2回の大戦での空襲でも被害をまぬがれ、開場記念演奏会に登場したブゾーニやイザイ以来、110年間の歴史は世界を代表する大演奏家、名歌手、室内楽団によって華やかに彩られてきた。
その魅力は、大理石による格調高い内装と、豊かで美しい響き。室内楽用では世界有数という評価をもつ名ホールである。巨匠や中堅だけでなく、新進の演奏家にも広く門戸が開かれ、毎年400ものリサイタルが行われている。
このホールが自ら「ウィグモア・ホール・ライヴ」と題したレーベルを立ち上げ、ライヴ録音をCDで発売し始めたのは、2005年のこと。現在までに30種強が店頭に並び、このホールでのコンサートの魅力を、日本でも簡単に聴くことができるようになった。
親密な空間が生む、殺風景な巨大ホールでは難しい、聴衆に語りかけるような音楽。最近ではジョナサン・ビスやピノックのリサイタルが印象に残っているが、今月ご紹介するイブラギモヴァとティベルキアン、ペレーニ、そしてエリアスとドーリックの2つの弦楽四重奏団の4種も粒揃いの名演。
普段はオーケストラ中心という方も、ぜひその音楽に接してみてほしい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年06月/第81回 アルミンクの過去、現在、未来
2010年06月/第81回 アルミンクの過去、現在、未来

クリスティアン・アルミンクが新日本フィルの音楽監督に就任したのは、7年前の2003年秋のことである。
ウィーン生れのこの指揮者は当時まだ32歳という若さだったから、この決定には驚かされた。日本のオーケストラのシェフになる外国人は、ヴェテランが多かったからだ。
しかしその起用は、けっしてギャンブルではなかった。ちょうどその頃から、内外のオーケストラで優秀な若手指揮者が何人も活躍しはじめたことを思えば、指揮者の若返りはむしろ世界的な潮流だったのである。
東フィルの常任エッティンガー、都響の首席客演フルシャ、日フィルの首席客演インキネン、新日本フィルなどに客演のハーディング、新国立劇場の常連フリッツァは東京でもおなじみの顔ぶれだし、世界的にもデュダメル、ユロフスキー兄弟、二人ペトレンコ、ソヒエフ、ネルソンス、ヴォルコフ、ネトピル、セガン、ティチアーティ、フランク、オロスコ=エストラーダ等々、70&80年代生れの俊英は、まさしく枚挙に暇がない。
そのなかでアルミンクの魅力は、清新で澄んだ響きと明晰な構成力と、そして意欲的なプログラミング。シーズンのテーマを決め、現代曲や大規模な声楽作品を採用して、大きな成果を残している。契約延長を重ね、13年まで10年間も務めることになったのは、楽団側と指揮者が強い信頼関係に結ばれていることの何よりの証明だ。
昨年ライヴ録音されたフランツ・シュミットの「七つの封印を有する書」は、黙示録の最後の審判を描いた、隠れた傑作オラトリオ。指揮者とオーケストラの過去、現在、未来が、そこに聴けるだろう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年05月/第80回 ハルモニア・ムンディの充実
2010年05月/第80回 ハルモニア・ムンディの充実

特に充実しているのは、ハルモニア・ムンディである。現在では残念ながら、国内盤化されるのはそのごく一部にすぎないのだが、現代の演奏の潮流をしっかりととらえた、すばらしい演奏が次々と出ている。今月の「ニューディスク・ナビ」で紹介するシュタイアーのゴルトベルク変奏曲と、イザベル・ファウストの無伴奏ヴァイオリン曲集という2種のバッハなどは、その代表格である。
前者の豊麗で多彩な、しかし虚飾のない、スケールの大きなチェンバロ演奏はおどろくべきものだ。シュタイアーにはフォルテピアノによるモーツァルトなどで意表をつく仕掛けをする人、というイメージが日本では生れてしまったが、このバッハは創意にあふれつつも正攻法の解釈で、広がりを感じさせてくれる。一方ファウストの演奏は、渋くてコクのある響きでひきつけ、同時に弾力のあるリズムで舞曲としての特性を印象づけてくれる。どちらも呼吸感が豊かで、音楽の大きさを自然に提示している。
これ以外にも新進のフォルテピアノ奏者のベズイデンホウトのモーツァルトのソナタ集、中堅のトリオ・ワンダラーが俊英ヴィオラ奏者のタムスティと共演したフォーレのピアノ四重奏曲など、爽快で新鮮な息吹を感じさせてくれる新譜がならんでいる。
アメリカ風の大量消費社会のシステムで考えると、現代のクラシックは衰退の一方のように思えるかも知れないが、実演と同様CDでも、このハルモニア・ムンディを代表に、すばらしいものは日々生れているのである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年04月/第79回 スイトナーをしのんで
2010年04月/第79回 スイトナーをしのんで

今年の1月8日、指揮者のオトマール・スイトナーが、ベルリンで87年の生涯を終えた。
1970年代と80年代には、名誉指揮者をつとめるNHK交響楽団への客演、音楽監督として君臨したベルリン国立歌劇場のオペラ公演や、そのオーケストラであるシュターツカペレ・ベルリンの演奏会で、ほとんど毎年のように来日して、日本でもおなじみの指揮者だった。海外の一流歌劇場のオペラ公演を日本でこれだけ数多く指揮した指揮者は、ほかには少ないだろう。
1989年に「ベルリンの壁」が崩壊し、東ドイツが西ドイツに吸収される形で統一が実現した頃から、健康を崩してベルリン国立歌劇場音楽監督の座をバレンボイムに譲り、長い隠退生活に入った。それから約20年目にしての訃報である。
コンヴィチュニーが1962年に亡くなった以後は、東ドイツの音楽界を代表する存在と位置づけられたが、生まれはインスブルック、学んだのはザルツブルクと、もとはオーストリアの指揮者であった。細部に拘泥せず、大らかで自然な感興を活かした音楽づくりは、ドイツ語圏でも南方の出身であったことが関係しているのかも知れない。
モーツァルトからR・シュトラウスまで、ドイツ音楽の王道を幅広く演奏したが、今回の特集では名盤として名高いシュターツカペレ・ドレスデンとのモーツァルトの交響曲やオペラ、シュターツカペレ・ベルリンとの、ライヴならではの迫力をもつベートーヴェンやブルックナー、ブラームスなどの交響曲、そして旧東独の名歌手たちとのオペラなど、その演奏にあらためて親しんでいただきたい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年03月/第78回 現在進行形のショパン
2010年03月/第78回 現在進行形のショパン

今年はショパン生誕200年にあたり、また秋には、ワルシャワでショパン国際コンクールが行われる年である。
ゴールデン・ウィークに東京と金沢、そして今年は新潟とびわ湖ホールでも開催される「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」も、主役はショパン。いろいろな形でこの作曲家の音楽に触れる機会が多そうだ。
今月の「ウィークエンド・スペシャル」も、2回にわたってショパンの録音を特集する。先月も「往年の巨匠」「現代の巨匠」と題して、往年のコルトーやルービンシュタインから、ポリーニ、アルゲリッチ、ツィメルマンなど、1975年までのショパン国際コンクール優勝者を中心に紹介したが、今回は1980年のダン・タイ・ソンから2005年のブレハッチまでの優勝者、そして現在活躍中のキーシン、アリス=紗良・オットのような俊英たちのショパン演奏を取りあげる。
現代のショパン弾きの特徴の一つは、アジア各国からの出身者が増えていること。ヴェトナムのダン・タイ・ソン、中国のユンディ・リの2人のショパン国際コンクール優勝者を筆頭に、日本や韓国からも優秀なピアニストが登場して、ポーランドとフランスというショパンゆかりの2国、完成された教育システムをもつ旧ソ連出身などのヨーロッパ勢とともに、高い技術と豊かな個性をもつ演奏を聴かせてくれる。
また近年は、ショパン自身が用いたのと同じ時代(ピリオド)のプレイエル社製のピアノが弾かれることも増え、20世紀型のピアノと使い分けるピアニストも珍しくなくなった。今回はプラネスとダン・タイ・ソンによるピリオド・ピアノの録音で、そうした現代の潮流もご紹介しよう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年02月/第77回 ティーレマンの「指環」
2010年02月/第77回 ティーレマンの「指環」

ティーレマンは2006年からバイロイト音楽祭で「ニーベルングの指環」全曲の指揮を担当しているが、その2008年の上演が14枚組のCDで発売された。
ドイツ指揮者界に久しく途絶えていた、骨太で重厚な音楽を聴かせてくれる指揮者として、ティーレマンへの期待は大きい。そして今回の「指環」全曲盤は、その期待に十二分に応えてくれるものである。
スケールはきわめて雄大で力強く、劇性も叙情性も、それが求められるところでは存分に発揮される。これまではクライマックスのつくり方がうまいとはいえなかったティーレマンだが、この演奏ではその弱点が克服され、解放感と達成感に不足することはない。50歳前後にさしかかったティーレマンは、本当の意味で、ついに巨匠指揮者への道を昇りはじめたといえるだろう。
それから、このCDの大きな魅力は、音質がきわめて優れていることだ。豊かな音場感と、まろやかに溶けあって歌手の声を絶対にかき消さない、バイロイトの祝祭劇場ならではの音響バランスによる、刺激的にならない美しい響き。この音響を聴いているだけで、気持ちよく酔えるほどだ。本来はDVDメーカーであるオパス・アルテが、あえて音だけのCDで発売した理由が、聴けば聴くほどよくわかるのである。
今月の「ニューディスク・ナビ」の第1週は、特別編としてこの「指環」を中心に、ティーレマンのこれまでのCDをまじえてお送りする。その「巨匠への軌跡」をたどっていただければ幸いである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2010年01月/第76回 ザルツブルク音楽祭2009
2010年01月/第76回 ザルツブルク音楽祭2009

今月の「ワールド・ライヴ・セレクション」は、昨年のザルツブルク音楽祭のオーケストラ、歌曲リサイタル、室内楽、オペラを一つずつ、5回にわたってお送りする。
あらためて2009年のザルツブルク音楽祭の全体の演目を見てみると、その多彩さに今さらながら目をみはる。かつては、ウィーン・フィルとザルツブルクのモーツァルテウム管弦楽団で大半のオペラと演奏会を占め、ゲストのオーケストラは数えるほどだったのが、現在はほかにもたくさんのスター・オーケストラが登場するのが当然になった。
今年はドイツ・カンマーフィルがベートーヴェンの交響曲全曲を4回のチクルスで取り上げ、古楽勢ではフライブルク・バロック・オーケストラがオペラ「テオドーラ」、ルーヴル宮音楽隊とガブリエリ・プレイヤーズが演奏会。通常の交響楽団もロンドン響、コンセルトヘボウ、ベルリン・フィル、ウィーン放送響が顔を出し、ウェスト・イースタン・ディヴァン管弦楽団もベートーヴェンの「フィデリオ」を演奏会形式で上演している。
歌曲リサイタルにもコジェナーと内田光子、クヴァストホフとフォークトなど、豪華な顔合わせが多かったが、なかでも今回放送するネトレプコとバレンボイムは、ネトレプコがお国物のロシア歌曲を歌ってくれるだけに期待できる。ヤルヴィもライヴでどんな演奏をするのか、セッション録音のCDとの聴き比べが興味深いし、音楽祭開幕を飾った「テオドーラ」はシェーファーほか、充実した歌唱陣もききものになるだろう。ウェスト・イースタン・ディヴァンのメンバーによる新ウィーン楽派とメンデルスゾーンもどんな響きなのか、楽しみだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年12月/第75回 ミンコフスキの愉悦
2009年12月/第75回 ミンコフスキの愉悦

ほんの数日前に、ミンコフスキとルーヴル宮音楽隊の来日公演を聴いてきたばかりだ。
猛烈に面白く、愉しかった。音楽が、フレーズが、一つ一つの音が、生き生きと鮮やかに躍動した。しかも、同時にフォルムがしっかりしていて、崩れないことに驚かされた。崩れているなら、ただの下品な音楽にすぎない。しかしかれらは、高速で緩急強弱と音色を変化させながら、総体的な響きや基本となるリズムを崩さなかった。
おそろしく高水準な位置で、遊んでいるのである。フレーズを崩さずに、しかも歌うという矛盾をやってのけた人に、大指揮者クレンペラーがいるが、そういった人々を思い浮かべずにはいられなかった。もちろん、ミンコフスキはいかめしく皮肉っぽい表情の代りに、音楽を楽しんでいることを隠さないが。
その弾力と呼吸感。二十世紀後半によく聞かれた、禁欲的で潔癖主義の、しかし単調なハイドンとは、まったく別の痛快で刺激的で、快活なハイドンがここにいる。来日公演の前後には他にも演奏会が続いて、さまざまな時代と様式と規模の音楽を聴いたのだが、ミンコフスキたちの音の鮮やかさと芳醇さは傑出していた。二十世紀風のオーケストラは、もはや「モダン」などと、あぐらをかいていられる状況ではなくなっている。
感心したのは、ミンコフスキが個々の奏者に見せ場を与えるように細かく配慮していたこと。それがハイドンの場合、音楽の中にある合奏協奏曲的な性格を引き出し、響きを多彩にする効果につながっていた。優秀なロンドンのオーケストラを得て、あれこれ工夫するパパ・ハイドンの喜びが、甦ってきたかのようだった。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年11月/第74回 没後20年のホロヴィッツ
2009年11月/第74回 没後20年のホロヴィッツ
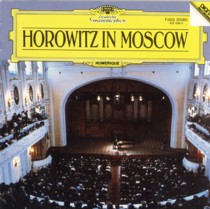
ホロヴィッツは公式には1904年生れとなっていたが、それは徴兵逃れのためのもので、本当は1903年生れ、つまり86歳で亡くなったと現在ではいわれている。
その響きの蠱惑的な魅力、圧巻の技術などピアニストとしての評価は絶対的なものだったが、一方で長期間の引退と劇的な復帰など、センセーショナルな話題も多い人だった。
日本ではとくに1983年の初来日が大きな話題になったし、長く語り種になることになった。専属の料理人を日本のホテルまで帯同するなどの豪華な生活ぶり、当時では異例の高額だったチケット、そして「ひびの入った骨董」という、吉田秀和の有名な言葉。
このとき不調だったことは本人もよく承知していて、3年後に再来日、力みのないすばらしい演奏で汚名をそそいだ。チケット代もぐんと下がって、良心的なものだったという記憶がある。
そのときのライヴ録音はあるのかどうか知らない。が、同じ年に行われたロシアへの61年ぶりの里帰りのさいのモスクワでのライヴ盤は、この年のホロヴィッツがいかに好調であったかを示す、価値あるドキュメントになっている。この一枚だけでなく、前後に録音された数枚は、ピアニスト晩年の境地を音にとどめる、味わいの深いものばかりである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年10月/第73回 ハーンの現在
2009年10月/第73回 ハーンの現在

ヒラリー・ハーンは1979年生れだから、今年ちょうど30歳ということになる。
クラシックの演奏家としては、まだまだ若い。しかし、彼女がバッハの無伴奏ヴァイオリン曲集で鮮烈なCDデビューを飾ったのは97年で、早くも12年前のことになる。以来12年、途中ソニーからグラモフォンへのレコード会社の移籍はあったが、発売されるCDはつねに話題盤となり、レコーディング・アーティストとしては名実ともにもはやヴェテランといっていい。
彼女が録音してきたのは、たんに名曲を並べるのではなく、ひとひねりしていて、しかも一貫性のある構成をもったアルバムである。新譜の「バッハ ヴァイオリン&ヴォイス」もそうで、受難曲やミサ、カンタータなどのバッハの宗教曲のなかから、ヴァイオリンが人間の声とからむ部分を抜き出して1枚にまとめたものだ。
ひょっとするといまの彼女は、自分のヴァイオリンと声との共演に興味を持っているのかもしれない。今年1月の来日でもシンガーソングライターと共演するリサイタルを行なって、クラシック好きを驚かせていた。
そのヴァイオリンに、ケレンは微塵もない。完璧な、陶磁器のようになめらかな響きで演奏すること自体が、それだけで一つの凄味に達する、希有のスタイルである。そこに人間の声や多人数のオーケストラが加わったとき、音楽はどんな表情をみせるのか。それがいまのハーンのテーマなのかも知れない。
前述の新譜と、クライツベルク指揮ウィーン交響楽団と共演した、シベリウスの協奏曲のライヴ。この二つの演奏に、ハーンの現在をお聴きになってみてほしい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年09月/第72回 音が消えた瞬間に
2009年09月/第72回 音が消えた瞬間に

新国立劇場オペラ芸術監督の若杉弘さんが7月21日に亡くなられた。
新国立劇場では昨年6月の「ペレアスとメリザンド」を日程が合わずに聴けなかったので、5月の「軍人たち」と2月の「黒船」が、若杉さんの指揮に接した最後になった。
前者は日本初演、後者も序景(ヴィジブル・オーバーチュア)が舞台版では初上演と、若いときから「初演魔」の異名をとった若杉さんならではの選曲であり、それを本格的な上演で見せてくれた。
特に「黒船」の意義ははかり知れない。オペラとは本来多弁な芸術のはずなのに、山田耕筰がそこに「いわぬが花」の日本的美学を持ち込もうとしたことを、オーケストラのみの黙劇で演奏するヴィジブル・オーバーチュアを象徴として、この上演で私は初めて知ることができた。これを第一歩として、日本オペラの秘められた魅力が明らかにされていく可能性が、ご逝去によって閉じられたのは、残念でならない。
若杉さんの指揮を初めてナマで聴いたのは、1980年10月11日、上野の東京文化会館での、東京都交響楽団とのマーラーの「復活」交響曲だった。高校生にとっては強烈な音体験で、壮大な最後の音響はもとよりだが、それよりも第1楽章クライマックスでの、鮮やかな2発のルフトパウゼが凄かった。足元が一瞬に消え、文化会館の最上階から虚空に放りだされたかのような驚きは、29年後の今でも、ありありと憶えている。
――音楽は、音が消えた瞬間がいちばん恐ろしく、美しい。
そう教えてくれたこの思い出とともに、若杉さんの指揮姿はいまも目の中にある。
若杉さん、ありがとうございました。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年08月/第71回 男は、タフでなければ生きていけない
2009年08月/第71回 男は、タフでなければ生きていけない

「男は、タフでなければ生きていけない」
フィリップ・マーロウだったかのこの言葉を、ゲルギエフとバレンボイムの名を聞くたびに思い出す。
歌劇場の監督というのは雑務も多くて大変なはずだが、さらに他のオーケストラにもどんどん客演し、音楽祭や臨時編成のオーケストラを主宰し、倦むことを知らずに世界を飛び回る。
バレンボイムの場合、ベルリンの歌劇場でオペラだけでなくバレエまで指揮している。ロシアの指揮者ならともかく、ドイツではバレエなど下っぱの楽長が振るもの(指揮者の音楽的主張よりもダンサーの都合が優先されるため)なのに、嬉々としてそれをやる。
かつての本職だったピアノだって、おろそかにはしていない。ソロ・リサイタルやそのライヴ盤が出続けているし、オーケストラと共演して弾き振りすることにも熱心だ。日本でも、弾き振りをたびたび披露している。
今月29日の「ワールド・ライヴ・セレクション」では、ウィーン・フィルを指揮するだけでなく、「スペインの庭の夜」とカーターの「サウンディング」では、独奏ピアノまで担当するバレンボイムを聴ける。
ちょうどその少し後の9月には、ミラノ・スカラ座の来日公演に帯同して、ヴェルディの「アイーダ」を指揮することになっている。ゼッフィレッリ演出の豪華絢爛な舞台に負けない、タフな音楽が響くはずだ。
そのかれとウィーン・フィルの演奏会。どうぞお楽しみに。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年07月/第70回 ウィーンの3つのオーケストラ
2009年07月/第70回 ウィーンの3つのオーケストラ

今月の「ワールド・ライヴ・セレクション」では、ウィーンに本拠を置く3つのオーケストラの演奏会を4回にわたってお送りする。
現在「ウィーン」の名を冠した常設の交響楽団は、ウィーン・フィル、ウィーン交響楽団、ウィーン放送交響楽団の3つ。ほかに日本ではウィーン・トンキュンストラー管弦楽団の名で知られている団体があるが、これは以前の名称で、現在の正式名称はニーダーエスターライヒ・トンキュンストラー管弦楽団(ニーダーエスターライヒとはウィーン市を囲む州の名前)。
今回はその3つが顔を揃える。まず4日は、ドゥ・ビリー指揮のウィーン放送交響楽団。フランス人ながら首席指揮者を務めるドゥ・ビリーが、ウィーン・フィルのフランス人イケメン・ハーピスト、ドゥ・メストレと共演するハイドンのピアノ協奏曲(ハープ版)のライヴがまずききものだ。
続く11日はルイージ指揮ウィーン交響楽団の演奏会。グリモーと共演のブラームスのピアノ協奏曲第1番がある。ルイージは実演で披露するブラームスの交響曲がいつも素晴らしい(ところがなぜかレコーディングしていない)ので、オーケストラ・パートの充実で名高いこの協奏曲も楽しみだ。
18日はそのウィーン交響楽団が関係の深いウィーン楽友協会合唱団と共演して、プリンツ指揮でメンデルスゾーンの大作「エリア」。クヴァストホフなど、豪華な独唱陣が期待をそそる。
そして25日はウィーン・フィル。今年9月の来日で共演するメータの指揮で「浄夜」とブルックナーの第9番。メータらしいマッチョな響きで聴かせてくれるだろう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年06月/第69回 100年目の2人と弟子
2009年06月/第69回 100年目の2人と弟子

現代音楽というのは曲名の命名のセンスで知名度がわかれるような要素が強い。メシアンの「世の終りのための四重奏曲」などは、最大の成功例の一つだろう。
ロマン派時代の曲名が大仰で自己肥大的で、そのぶん壮気にみちているのに較べると、斜に構えたような姿勢で、しかし第2次大戦中に捕虜収容所で、ヨハネ黙示録からの啓示をもとに書いたという事実には充分な真剣さも保証されていて、じつによくできている。「純音楽的に標題性を排して」なんて学者くさい考えは気にせず、曲名が喚起する先入観にどっぷり浸って聴けばいいし、またそれに答えてくれる名曲なのである。
このメシアンに較べると、弟子のブーレーズはあんまり命名センスがよくない。一時メシアンのことを評価しなくなったのも、師の高度な詩的センスに対する嫉妬からだったんじゃないか、という気がしないでもない。
メシアンと同い年で、パリに留学してエコル・ノルマルに学び、さらにナディア・ブーランジェに教わるという、アメリカ人作曲家の王道を歩んだのが、エリオット・カーター。メシアンは92年に死んだが、カーターは驚くべきことに、100歳を超えていまだ現役の作曲家なのである。
この人の命名センスはどうか。どちらかというとブーレーズに近いようだ。我が道を行く傾向の強いメシアンによりも、前衛の王道を歩んで抽象画的な方向に進んできたカーターもまた、詩性に惹かれるところが薄いのかも知れない。
いずれにしても、昨年生誕100年を迎えた2人とブーレーズの音楽。カーターの最近の作品まで含めて、名手エマールのピアノでどうぞ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年05月/第68回 ハイドンと諸国民戦争の時代
2009年05月/第68回 ハイドンと諸国民戦争の時代

後期ロマン派に較べて小編成の曲ばかりだから、切符は売りにくいだろうし、必ず余る楽員も出るし、その他にも難問も多かったろうが、楽団の努力の甲斐あって、会場は4回とも盛況だった。
いちばん会場が沸いたのは、「軍隊」交響曲で打楽器4人が「おもちゃの兵隊」よろしく、ぎこちない動きでオーケストラの前を行進しながら演奏したときである。あざといといえばあざとい演出だが、ハイドンがこれらの交響曲を、限られた貴族階級向けでなく、市民、大衆に向けて、わかりやすく書いたということが目に見える演出だった。
打楽器の響きは力強く、わかりやすい。音楽のありかた、古典派からロマン派への変換が、ここに端的にあらわれている。しかし同時に、それは「軍楽」である。そう、ハイドンの晩年は、フランス革命からナポレオン戦争へ、人間が「国民」となって戦争に動員されていく、諸国民戦争の時代の幕開けであった。勇壮で楽しげな軍楽は、人々を破壊と殺戮の戦場に誘う、死の響きでもあるのだ。
ハイドンが愉快なのは、「軍隊」に続けて「時計」を書いたこと。ブリュッヘンの演奏を聴きながら、映画『第三の男』のオーソン・ウェルズの、あの有名な皮肉を思い出さずにはいられなかった。
「スイス五百年の平和はいったい何を生んだよ? 鳩時計だぜ」
ハイドンはけっして単純ではない。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年04月/第67回 ピアノは甦る
2009年04月/第67回 ピアノは甦る

指揮者もピアニストも、時代は完全に1970年代以降の生れの人たちのものになりつつあるのか、という気がする。
若いからいい、新鮮だからいい、物珍しいからいい、というのではない。若い世代というのはいつの時代にもいるから、別に珍しくはない。そういう年の若さの問題ではなく、20世紀後半風の重苦しい、音をおくような音楽とは異なる、軽快で俊敏に弾むリズムのセンスをもった人々が、1970年を境に、どんどん増えてきているようなのだ。
トッパン・ホールでベートーヴェンのソナタ全曲の連続演奏をおこなっているティル・フェルナーは、1972年生れ。今月の「ニューディスク・ナビ」でモーツァルトとショパンの素晴らしい演奏をご紹介する、オリヴァー・シュニーダーは、1972年生れ。ドイツのバッハ弾きとして注目を集めるマルティン・シュタットフェルトは、1980年生れ。6月に来日して「ハンマークラヴィーア・ソナタ」を弾くことになっているジャン=フレデリック・ヌーブルジェにいたっては、1986年生れで今年まだ23歳である。
外国人だけではない。日本にも、3月にデビュー盤がRCAから出たばかりの、河村尚子(かわむらひさこ)という、1981年生れの女性がいる。しなやかでやわらかいタッチが生む多彩な音色は、これまでの日本人ピアニストには聴いたことのないものである。
それぞれに個性は異なるけれど、共通するのは軽妙なセンス。クラシックが50年間忘れていた音の愉悦と躍動が、かれらとともに甦りつつある。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年03月/第66回 バッハとヨーロッパ
2009年03月/第66回 バッハとヨーロッパ
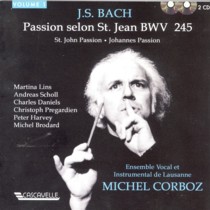
ひとりひとりに、キャッチフレーズがついていた。ベートーヴェンなら「楽聖」、シューベルトは「歌曲王」、J・シュトラウスは「ワルツ王」、といった具合である。
その一覧表の始まりのところにいたのが、バッハ、J・S・バッハだった。そうしてその位置にふさわしく、かれには「音楽の父」という尊称がたてまつられていた。
「音楽の父」とは凄い。始まりの人アダム、あるいは始祖鳥みたいである。小さなリュート曲から巨大な受難曲まで、あらゆる分野を一人で創造し、体系づけていった「巨人」であるかのような印象だった。
しかし、こうした見方は正確ではない、というのが現代の定説である。中世以来、ヨーロッパ各国の音楽は相互に関連をもちながら発展してきた。特にイタリアには優秀な作曲家たちが出現して、北の諸国をリードした。またフランスにもドイツにも先達や同輩がいて、バッハと影響を与えあったのだ。
バッハを孤独な絶対者ではなく、相対的な天才(天才であることは間違いない)としてとらえることで、その作品の演奏スタイルも大きく変ってきた。峻厳なだけではない、慰撫するようなコルボの指揮する受難曲や、アンタイ指揮のル・コンセール・フランセの躍動的な管弦楽組曲などは、その例である。
今月のウィークエンド・スペシャルでは、ラ・フォル・ジュルネ予習編として、さまざまなバッハ像をお聴きいただこうと思う。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年02月/第65回 メンデルスゾーン再発見に向けて
2009年02月/第65回 メンデルスゾーン再発見に向けて

カラヤン生誕100年で沸いた2008年に続き、2009年は作曲家のアニヴァーサリーがいくつかある。ヘンデル(1685~1759)の没後250年、ハイドン(1732~1809)の没後200年、メンデルスゾーン(1809~47)の生誕200年。
ハイドンはゆかりの深いウィーンを中心にさまざまな演奏や行事が行われるし、ヘンデルも、近年のバロック・オペラの隆盛の波もあり、英語歌詞に作曲した貴重な大作曲家ということで、イギリス・アメリカなどで演奏されるはずだ。
しかし私が注目したいのは、メンデルスゾーン。その前期ロマン派らしい軽妙で温雅な作風は、深刻で激情的なものが偏愛された後期ロマン派以降の時代には軽侮される傾向があり、さらに彼がユダヤ人で、ナチス時代に演奏が禁止されたことが尾を引いた歴史的経緯もあって、その全貌に関心を持たれることは多くなかった。
たとえば、賛美歌第98番「あめにはさかえ」の旋律はメンデルスゾーンの曲からとられたことで有名だが、その原曲で男声合唱とオーケストラのために書かれた「グーテンベルク祭のための祝典歌」は、CDもろくにないという現状なのである。
だが、彼の数多い合唱曲にはもっと聴かれてもいい佳品があって、再評価の機会を待っているし、ピアノ三重奏曲や弦楽四重奏曲の濃厚なロマン性は、近年高い人気をあつめるようになっている。
今月のウィークエンド・スペシャルでは3回にわたり、交響曲全集など彼の基本的なレパートリーをお送りする。まずはここから。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2009年01月/第64回 2008年ザルツブルク音楽祭から
2009年01月/第64回 2008年ザルツブルク音楽祭から

ベネズエラの俊英指揮者グスターボ・ドゥダメルとシモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラは旋風を巻き起こしているが、昨年のザルツブルク音楽祭にも登場、アルゲリッチとカプソン兄弟とともにベートーヴェンの三重協奏曲を演奏した。今月3日の放送では、それにくわえて当日のアンコール、彼らの十八番バーンスタインの「マンボ」やラデツキー行進曲などで、熱狂的な演奏ぶりを聴けるのがポイントだ。
翌週10日の放送にも、期待の若手指揮者が登場する。カナダのフランス語圏モントリオールで活躍、ゲルギエフの後任としてロッテルダム・フィルのシェフとなったヤニック・ネゼ=セガンである。ネトレプコの代役に抜擢されたニーノ・マチャイーゼとローランド・ビリャソンを主役コンビとするグノーの歌劇「ロメオとジュリエット」で、どんなフランス音楽を聴かせてくれるか楽しみだ。
一方、中堅では小澤征爾を継いでウィーン国立歌劇場の音楽監督となるウェルザー=メストが、手兵のクリーヴランド管弦楽団をあえてピットに入れて演奏した、ドヴォルジャークの歌劇「ルサルカ」もカミッラ・ニルンドの外題役とあわせ、精妙で透徹した表現で評判になった。
また、近年レパートリーをためらうことなく拡げて、バロック専門から次代の巨匠へと羽ばたきつつあるミンコフスキが、カメラータ・ザルツブルクを指揮したグリーグの劇付随音楽「ペール・ギュント」、そしてドイツのピアニストのフォークトによるモーツァルトの協奏曲集など、世代交代が進むザルツブルク音楽祭の「いま」をお楽しみに。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年12月/第63回 小澤征爾とサイトウ・キネン
2008年12月/第63回 小澤征爾とサイトウ・キネン

長野県松本市は日本アルプスへの入り口で、美しい山並みに囲まれた信州の町。ここにあった旧制松本高校(信州大学の前身)の愉しい伝統は北杜夫の『どくとるマンボウ青春記』に活写され、現在も保存されている校舎と、隣接する旧制高等学校記念館を通じて、そのよすがをしのぶことができる。
長野駅からその旧制松本高校校舎のある「あがたの森公園」を結ぶ直線道路の、ちょうど中間に建つのが、まつもと市民芸術館。
ここはサイトウ・キネン・フェスティヴァルの会場の一つで、今年はヤナーチェクの傑作オペラ「利口な女狐の物語」が上演された。また、長野県松本文化会館ではオーケストラ・コンサートが行なわれ、下野竜也指揮の「わが祖国」や小澤征爾指揮のマーラーの「巨人」ほかという、2つのプログラムが演奏された。さらに毎年恒例の武満徹メモリアル・コンサートや「ふれあいコンサート」などの室内楽演奏会、子供のためのオーケストラ演奏会や青少年のためのオペラなど、さまざまな演奏会が8月中旬から1か月にわたって開かれた。
松本市でこの音楽祭が始まったのは、1992年。毎年オペラや大規模な声楽曲とオーケストラ演奏会を中心として、今年で17回めを数えることになった。松本市民だけでなく日本各地からやってくる聴衆に根づく一方、中継や毎年つくられるCDを通じて、広く親しまれる催しとなっている。
ミュージックバードではその演奏会、さらにはCDも大挙してお送りしているので、どうぞこの機会に。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年11月/第62回 ウィーンのイタリア男
2008年11月/第62回 ウィーンのイタリア男

モーツァルトが生きた時代のウィーンでは、オペラはイタリア語で歌うのが当然だった。音楽とはイタリアから輸入されたものだったから、歌詞もイタリア語ということになっていたのである。
ドイツ語で歌うなんていうのは、たとえていえばパスタを箸で食ったりするような、下品なふるまいとされていたのだ。ときには啓蒙主義の皇帝が「みんながわかる言葉で歌おう」などと言い出して、モーツァルトがドイツ語歌詞で「後宮からの逃走」を作曲する時期もあった。しかし、すぐに宮廷のイタリア人音楽家たちが巻き返して、音楽はやっぱりイタリア語ということになり、「フィガロの結婚」などのダ・ポンテ三部作はイタリア語で書かれた。
もはや歴史の中の話だから、どちらが正しいか間違っているかを論じてみてもはじまらない。ただ、ドイツ語圏のなかでも南のカトリック地域には特に、音楽においてイタリアとの関連が深いという伝統があって、これはいまも脈々と生きている。
ムーティがウィーンで人気が高いのは、まさにそんな伝統に則ったものなのである。彼は今年、日本でもウィーン・フィルとニーノ・ロータを演奏し、国立歌劇場を指揮してはイタリア語の「コジ・ファン・トゥッテ」を上演することになっている。
そして、400年の歴史を持つウィーンの宮廷楽団(ホーフムジークカペレ)を指揮して、ケルビーニとハイドンのカトリック宗教音楽を演奏する。ウィーンのイタリア男の誇りは、いまも生きているのだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年10月/第61回 ゲルギエフ、世界を征く
2008年10月/第61回 ゲルギエフ、世界を征く

ゲルギエフの名が広く知られはじめたのは、1988年に35歳の若さでロシアのマリインスキー劇場(キーロフ劇場)の芸術監督になって以来のことだから、今年でちょうど20年ということになる。
その直後にソビエト連邦が解体され、新体制が始まったが、社会的、経済的混乱を受けてロシア音楽界も激動の時代となった。そのなかでいちはやく基盤を固め、組織を活性化して大躍進したのが、ゲルギエフ率いるマリインスキー劇場であった。
それ以来、ゲルギエフのスタミナは尽きることを知らない。マリインスキーばかりにとどまることなく、その活動範囲は広がるばかりである。オランダのロッテルダム・フィルとの密接な関係も20年に及び、同地では自らの名を冠したフェスティヴァルも開催してきた。
このように日常の演奏に加えて、音楽祭のような集中的活動を好むのはこの指揮者の特徴の一つで、ほかにサンクトペテルブルクの「白夜の星」音楽祭、フィンランドのミッケリ国際音楽祭など数々の音楽祭を創設、取りしきっている。
今年の11月末から12月にかけて、東京のサントリーホールで行なわれる「プロコフィエフ・チクルス」も、そうした音楽祭的活動の一つといえる。演奏するのは、昨年から率いるロンドン交響楽団。
10月の「ウィークエンド・スペシャル」では、ロッテルダム・フィルやロンドン交響楽団とのライヴ録音を中心に、その野性的なカリスマぶりをたっぷりと楽しんでいただこうと思う。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年09月/第60回 ラトルとベルリン・フィルの6年
2008年09月/第60回 ラトルとベルリン・フィルの6年

サイモン・ラトルがベルリン・フィルを初めて指揮したのは1987年のことだから、カラヤン時代の終わりごろである。
まだ32歳の指揮者は、定期演奏会でマーラーの交響曲第6番「悲劇的」を演奏してそのデビューを飾ったのだった。このときの成功ぶりはベルリン・フィルの自主製作盤に聴くことができる。それ以来、客演を重ねるようになり、1999年に行なわれたアバドの後任を決める楽員たちの投票により、2002年からの新しい芸術監督に選ばれたのだった。
芸術監督の就任披露演奏会ではまたしてもマーラーの作品が選ばれ、交響曲第5番が演奏された。ラトルとは長いつきあいのEMIレーベルはこれをライヴ録音して発売し、それから最新録音の幻想交響曲まで、オペラも含めて20点を超すCDが発売されている。
就任直後の一、二年はなぜか新録音が出てこなかったが、その後は堰を切ったように、コンスタントに発売されている。
冥王星が惑星から外されたのとほぼ同時にホルストの「惑星」、それもマシューズ作曲の「冥王星」や小惑星などの新作を加えた盤が出て、ベストセラーになったのは記憶に新しい。ハイドンの交響曲集では、ノリのいい演奏のために思わず聴衆がフライングで拍手してしまった演奏と、それと同じ楽章の拍手なしの演奏との2種類をいれるなど、遊び心の嬉しい工夫も行なわれている。近代と現代の音楽では鋭利に、ロマン派音楽では堂々と、作曲年代でスタイルを鮮やかに変えるのもこのコンビの特長だ。その躍動ぶりを、就任以来の全録音に追ってみよう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年08月/第59回 生誕90周年のバーンスタイン
2008年08月/第59回 生誕90周年のバーンスタイン

1989年11月、ベルリンの壁が崩壊して東西ベルリンの交通が自由になったとき、世界のあちこちで歓喜の声があがったが、そのとき、ヘルベルト・フォン・カラヤンはもうこの世にはいなかった。
4か月前に急逝していたのである。だから、続いて各所で行なわれた祝賀演奏会に加わることはなかった。ベルリン・フィルが急遽開いた演奏会の指揮をしたのはバレンボイムだったし、クリスマスに関係諸国の音楽家を集めて演奏されたベートーヴェンの「合唱」を指揮したのは、バーンスタインだった。
そう、バーンスタインの方はこの世界史的大事件に間に合った。彼もその1年後には亡くなってしまうのだが、カラヤンと違って、どうにか間に合った。
この一事が象徴するように、生誕100年目のカラヤンと90年目のバーンスタインの人生は、時代的には重なりながらも、微妙にズレているのが面白い。第三帝国と、戦後の東西分断の時代のドイツ・オーストリアを拠点として生きたカラヤンと、史上未曾有の繁栄を謳歌した20世紀アメリカに生きたバーンスタイン。前者は指揮に専念したのに、後者は作曲にも大きな足跡を残した。
そのバーンスタインの遺産を聴きながら、彼の生涯をふり返ってみる。そこからは、繁栄の陰にかくれがちな不満、貧困、憎悪、対立といった人間の苦しみにつねに目を向け、しかしニヒリズムに陥ることなく、人間を信じようとする情熱の炎を燃やし続けた音楽家の姿が、かいま見えてくるかもしれない。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年07月/第58回 ネマニャ!
2008年07月/第58回 ネマニャ!

ネマニャ・ラドゥロヴィチ。
1985年セルビア生れの、若い男性ヴァイオリニスト。メジャー・レーベルに録音していないせいか、メディアに大きく取りあげられてはいないのだけれど、ここ1年の間に数回来日して、熱心なファンを獲得している。
日本での始まりは、昨年の「熱狂の日」音楽祭だった。その直前のナントでの元祖「熱狂の日」でラドゥロヴィチなる若者の演奏が大きな話題になったと伝わってきて、その彼が日本にもくるということから、耳ざとい人たちの噂になったのだった。
ふだんは流行遅れなことばかりしている私だが、なぜかこの人は気になった。ひとまずフランスのマイナー・レーベル、トランスアートから1枚だけ出ていた無伴奏リサイタルを聴いて、まだ粗削りだけれど「大化け」を予感させる個性の大きさに惹きつけられた。
そして、ナマを聴いて、大好きになった。チャイコフスキーの協奏曲。まさに躍動するヴァイオリン。歌い、飛び跳ね、踊る。その自由さと活力。
印象的なのは、弾くうちに弓がチーズのようにささくれること。合間合間に「削りカス」をちぎりすてる。右手のバネが強靱で、独特の激しい動きをするために、弓が削れるらしい。しかしこの力強い動きこそが、ダイナミックに瞬動する音楽を生むのである。
彼を聴いて痛感するのは、ヴァイオリンがリズム楽器でもあること。そしてリズムとメロディの、不可分な結合だ。こういう人がいるかぎり、クラシックは活きつづける。
その待望の新譜は、メンデルスゾーンの協奏曲。やっぱり凄い!
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年06月/第57回 フルネとベルティーニのこと
2008年06月/第57回 フルネとベルティーニのこと
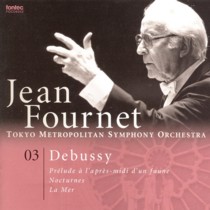
今年は、ジャン・フルネの生誕95周年であるという。
2005年12月、東京都交響楽団を指揮して引退コンサートを行なったフルネが初めて日本にきたのは、1958年のことだった。ドビュッシーの歌劇「ペレアスとメリザンド」の日本初演を指揮するためである。
いまからちょうど50年前のことで、存命の指揮者のなかでは、もっとも早い時期の来日経験をもっている。
興味深いことに、同じく都響に縁が深いベルティーニも、最初の来日は1960年にイスラエル交響楽団とのツアーだった。つまりある時期までの都響には、最古参の来日経験をもつ指揮者二人が、ならんで登場していたのだ。が、2005年3月にベルティーニが急逝、同じ年にフルネも引退して、もはやその指揮姿を実演で見ることはできなくなった。
さいわいどちらもそれなりの量の録音を残しているから、かれらの芸術が虚空に消えてしまったわけではない。二人と都響とのライヴ録音も、フォンテックから発売されている。芳しい叙情性をたたえたフルネ、鋭利な緊張感にみちたベルティーニと、芸風が対象的なのも面白い。
今月の「ニューディスク・ナビ」では、フルネの都響とのライヴ録音、ベルティーニとケルン放送交響楽団とのライヴ録音と、偶然にもここでも二人の名がならぶことになった。日本で長く愛された両者の指揮ぶりを、楽しんでいただければと思う。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年05月/第56回 カラヤンとムター
2008年05月/第56回 カラヤンとムター

ヘルベルト・フォン・カラヤンは、これと見込んだ演奏家を、集中的に協奏曲のソリストとして起用する習慣があった。
ピアノではワイセンベルクがそうで、ベートーヴェン、ラフマニノフ、チャイコフスキーなどの協奏曲を録音しているし、ヴァイオリンではフェラスというフランスの奏者と、ベートーヴェンやブラームスの協奏曲を録音している。それは60年代から70年代にかけてのことだが、彼らがドイツやオーストリアの演奏家でないのは、この時代のドイツ語圏に不作が続き、若手の有望な奏者がなかなか出なかったからである。わずかにエッシェンバッハをソリストにしてベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番を録音しているが、他の曲は録音されず、やがてエッシェンバッハは、指揮者中心の活動に転じてしまった。
その状況を変えたのが、カラヤンより55歳年下のヴァイオリニスト、アンネ・ゾフィー・ムターの出現だった。77年にザルツブルク音楽祭でカラヤンの指揮でモーツァルトの協奏曲を演奏した彼女は、翌78年にそのモーツァルトをカラヤンとともに録音して、14才でレコード・デビューを飾る。そして以後も共演は途絶えることなく、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、ブルッフ、ブラームスの協奏曲、ヴィヴァルディの「四季」、そして1988年、カラヤンが亡くなる前年のチャイコフスキーの協奏曲まで、たくさんの作品が録音されることになった。
それから20年、いまやムターはドイツを代表するヴァイオリニストとして、押すに押されぬ地位にある。カラヤンの慧眼を示す、最良の例となっているのだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年04月/第55回 カラヤンの両輪
2008年04月/第55回 カラヤンの両輪

これは演出家の三谷礼二さんから昔うかがった話だが、朝比奈隆は「コンサートとオペラは指揮者にとって両輪のようなものなので、並行して指揮した方がいい」という意味のことを語っていたそうだ。
その言葉通り、ご両人は関西で協同してオペラ公演を行っていた。そのときのライヴ録音の「蝶々夫人」の一部を三谷さんが聴かせてくださったが、その指揮ぶりは意外にも、じつに堂に入ったものだった。だが「意外」というのは若造の勝手な思い込みで、三谷さんによれば「マタチッチなど、優れたブルックナー指揮者は同時に優れたプッチーニ指揮者であることが少なくない」。朝比奈隆もまた、その一例なのだそうである。
残念ながら朝比奈隆のオペラ指揮は、東京ではあまり聴く機会がなかった。「ニーベルングの指輪」全曲の演奏会形式上演ぐらいなのではないだろうか。しかし、1950年代からヨーロッパ各地のオーケストラに客演し、かの地の音楽活動をその目で眺めてきたこの指揮者は、オペラの重要性を肌で感じ、日本でも実践しようとしていたのだ。
こうした姿勢は、オペラという形式が広範囲に楽しめるようになった現代の日本でこそ、再評価しうることなのではないか。そして、朝比奈と同い年のカラヤンがオペラの上演と録音に心血を注いできたこと、これもまた「カラヤンの両輪」として再考すべき活動なのではないか。
幸いにもカラヤンは、朝比奈とは対照的にたくさんのオペラ全曲盤を遺してくれている。ここであらためて聴きなおしてみたい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年03月/第54回 生誕百年のカイルベルト
2008年03月/第54回 生誕百年のカイルベルト

今年、生誕百年を迎えるアーティストの中で、知名度が飛び抜けているのはもちろんカラヤンだが、指揮者ではほかにカイルベルト、朝比奈隆などもいる。
カラヤンという人は先輩フルトヴェングラーに嫉妬されたとか、年下の指揮者の活動を妨害したとか、同業者との関係にとかくの噂がある(あくまで噂話)のだが、同い年のカイルベルトとは不思議と仲が良く、共存共栄の関係だったという。一九六三年にバイエルン国立歌劇場の本拠地ナツィオナルテアターが再建されたときには、カイルベルトに花を持たせるためにカラヤンがわざわざこの歌劇場に二晩だけ客演し、《フィデリオ》を指揮しているくらいである。
このとき、カラヤンはウィーン国立歌劇場の芸術長、カイルベルトはバイエルン国立歌劇場の音楽監督として、ドイツ語圏のオペラ界をリードする立場にあった。このあたりのことが、それぞれのポストが二人にとってどのような意味を持っていたか、同時代の交響曲偏重の日本の音楽界ではもう一つ理解されていなかったように思う。むしろ、オペラへの偏見が減った現代こそ、かれらとオペラとの関係を、あらためて評価できる時代なのではないか。
というわけで、三月のカイルベルト特集では、一九五五年バイロイト音楽祭の《ニーベルングの指環》など、オペラを中心に構成してみた。さまざまな歌手が出入りし、合唱も加わる大編成の、長大な「綜合芸術」を指揮者カイルベルトがいかにまとめ、花開かせているかを、 確かめていただきたいと思う。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年02月/第53回 思い出のマーラー指揮者
2008年02月/第53回 思い出のマーラー指揮者

今月の「ニューディスク・ナビ」はどちらかというと、ヒストリカル系の新譜に目をひくものが多い。
ロンドン・フィルの75周年記念ボックス、フルトヴェングラーのもう一つの「バイロイトの第9」、ベームの「魔弾の射手」全曲とベートーヴェンの交響曲集。グルダのモーツァルト・ソナタ集や弾き振り。「日本SP名盤復刻選集Ⅲ」所収の、紀元二千六百年奉祝演奏会のための作品群、などなど。
これらのなかでも、ベルティーニの指揮によるマーラーの交響曲集は、個人的な追憶にからんだ、懐かしいアイテムである。
それは1981年のことだ。ベルティーニが東京都交響楽団を指揮して演奏したマーラーの「悲劇的」の、聴くものを曲の内奥に完全に没入させてしまうほどの凄まじさは、はっきりと憶えている。
無我夢中のベルティーニの、足音をまじえての指揮ぶりの激しさ、それは途中まで滑稽なドタバタにさえ見えたが、やがて曲そのものと一体化して感じられるようになった。終了直前に午後9時となり、聴衆の腕時計の時報アラームが各所から鳴り響いたのは幻滅ものだったが、いまとなってはそれすら懐かしい。
この成功がベルティーニの東京での人気を一気に高め、数年後に都響の音楽監督となってマーラーの交響曲を連続的に演奏する、その端緒となったのだ。今回取りあげるCDは、1980年代のマーラー・ブームの一翼を担っていたこの指揮者の、ライヴによる演奏である。どんな演奏が聴けるのか、楽しみだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2008年01月/第52回 2007年のレコード・アカデミー賞
2008年01月/第52回 2007年のレコード・アカデミー賞
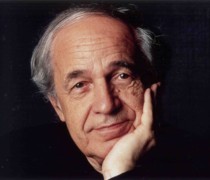
音楽之友社選定の「レコード・アカデミー賞」が今年も発表された。
大賞は交響曲部門からブーレーズ指揮のマーラーの「千人の交響曲」。例年大賞は交響曲、管弦楽曲、オペラ部門から選ばれることが多いから、まずは順当な選択か。この盤は同時に、ブーレーズによるマーラーの交響曲全集という「大パズル」の、最後の一ピースとなるものだ。十三年がかりでオーケストラもバラバラだが、現代のレコード業界の状況において、セッション録音で全集を完成させるというのは、表面的に思う以上の多大の困難を乗り越えてのものであるに違いない。その点でも、この一組は大賞にふさわしい。
協奏曲部門を受賞したプレトニョフは、指揮者としても今年ベートーヴェンの交響曲全集を録音して大きな話題となった。その個性的な解釈への評価は意見の分かれるところだが、それはともかく、指揮者としての活動を重視したいという今のプレトニョフ自身は、むしろピアニストとして評価されたことに、どんな感想を持つのだろうか。
室内楽部門で一九九三年録音のプレヴィン盤が選ばれたのも面白いところ。以前の録音なのに、国内盤がいままで発売されていなかったお陰の受賞である。
現代曲部門賞の「江村哲二作品集 地平線のクオリア」も気になる一枚。独学で作曲を身につけ、武満徹に私淑する作曲家だが、茂木健一郎と対談した新書『音楽を「考える」』が話題になった矢先に訃報が伝わり、読者を驚かせた。その彼の作品を集めたアルバムである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年12月/第51回 1959年組の活躍
2007年12月/第51回 1959年組の活躍

今年は「1959年組」の指揮者たちが次々と来日して、それぞれに素晴らしい演奏を聴かせてくれた。
1959年組とは、シルマー、クライツベルク、パッパーノ、ティーレマン、準メルクル、ルイージ(ほぼ来日順)である。50歳を間近に控えていままさに旬の、心身のバランスのとれた、精力的な活動を欧米各地で繰り広げているが、日本にもかなり頻繁に来てくれることが嬉しい。
みな、相異なる個性と得意分野をもっている点も面白い。歌劇場やオーケストラなどの実演の場に加えて、レコーディングの方でも種々のレーベルに分散して、色々なジャンルの曲を録音してきた。しかし、そろそろ足場が固まってきたというか、特定のポスト、特定のレーベルに腰を落ち着けて、じっくりと成果を挙げるべき時期に入ってきたようである。今年の来日公演やCDには、そうした気配が如実にうかがえるようになってきていて、その意味で今後への期待をいっそう増してくれるものが多かった。
そのなかでも特に、今までよりもう一段上のレベルの仕事をこれからしてくれそうな予感があるのが、準メルクル(写真)だ。2005年にフランス国立リヨン管弦楽団の音楽監督になって以後の充実ぶりが、最近の新譜(アルトゥス、ナクソス)には明確に現れている。すっきりしたフレージングのセンスと適切なテンポ感覚、透明な響きといった魅力が、はっきりと形をとりはじめているのだ。自分に合ったオーケストラ、つまり「よい楽器」を、この指揮者はいま手にしているのではないか。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年11月/第50回 プレトニョフのベートーヴェン
2007年11月/第50回 プレトニョフのベートーヴェン

ピアニストとして超一流の腕を持っていて、指揮者としても大活躍している音楽家はいま、何人もいる。バレンボイム、エッシェンバッハ、チョン・ミョンフン、アシュケナージなどの名前がすぐにあがるだろう。
そしてプレトニョフも、その道を歩もうとしている。1978年のチャイコフスキー・コンクールのピアノ部門(第3位にテレンス・ジャッドという、若くして亡くなったイギリスのピアニストが入っていたことでも名高い)で優勝という輝かしいキャリアを持つ彼はソ連解体のさなかの1990年に私財を投じて、ロシア初の民営オーケストラであるロシア・ナショナル管弦楽団を設立、その音楽監督として本格的な指揮活動を始めた。このオーケストラは録音機会にも恵まれ、1990年代にはプレトニョフの指揮でチャイコフスキーやラフマニノフの交響曲全集を完成した。
その後、1999年からプレトニョフは音楽監督の地位をヴァイオリニスト出身のスピヴァコフに譲って、ピアニストとしての活動や録音を再開していたが、このオーケストラの芸術監督として主導的地位に返り咲くと、ふたたび指揮者に重点を置くことにし、ピアノの方は控えるという。
そしてそのプレトニョフが満を持し、ロシア・ナショナル管弦楽団を指揮してリリースしたのが、ベートーヴェンの交響曲全集なのである。緩急強弱、バランスなどでの独自の解釈とアイディア、そして力強さと活力に満ちたこの演奏を、プレトニョフはピリオド奏法の影響とは無関係につくりあげたそうだ。
彼らの活動からは今後は目が離せない。そう痛感させてくれるベートーヴェンである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろ)う
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年10月/第49回 光は歌劇場より
2007年10月/第49回 光は歌劇場より

9月上旬に行なわれたチューリヒ歌劇場の日本公演は、近年のさまざまな引越し公演の中でも特筆すべき絶賛を得た。
始まる前の人気はけっして高くなかったのだが、特に「ばらの騎士」での、オーケストラの精妙な表現が支えるアンサンブル全体の出来のよさが客席の聴衆を興奮させ、評判が評判を呼び、人気が急激にクレシェンドする形になったのである。
その評価の中心にいたのが、この歌劇場の音楽監督として全公演の指揮にあたったウェルザー=メストである。少し前に2010年から小澤征爾の後を受けてウィーン国立歌劇場の次期音楽監督になることが決定して話題になったものの、これまで日本ではもう一つ評価が定まらない存在だった。それというのも、日本ではどうしても指揮者を交響楽団とのコンサート活動で評価する傾向があるのに、その方面でのウェルザー=メストの動きが、近年あまり伝わっていなかったからだ。
すでに2002年からアメリカの名門クリーヴランド管弦楽団のシェフとして活動し、契約が延長されるほどの成果を残しながら、アメリカのオーケストラのCDがほとんどつくられない、来日公演も少ない時代にあたってしまったため、日本では評価しようがなかったのである。
だがその間に、世界が求める指揮者像は変わりつつあったのだ。交響楽団を中心に華やかに活躍するアメリカ型のスター指揮者よりも、歌劇場に拠点を置いて着実に自らとその音楽を錬磨していくヨーロッパ型の指揮者たちこそが、向後の音楽界を担いつつある。そしてかれらはいま、歌劇場だけでなく交響楽団のシェフとしても、その翼を拡げようとしている。ウェルザー=メスト以外にもファビオ・ルイージ、ウラディーミル・ユロフスキなど、その数は増える一方だ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年09月/第48回 黄金時代の夢
2007年09月/第48回 黄金時代の夢

どうやらまたマーラー・ブームらしい。東京では7月にインバルとフィルハーモニア管弦楽団が四日間のマーラー・チクルスを開催したし、CDも新録音が毎月いろいろと登場している。
ブームの再来を早い段階で意識づけたのは、アバド率いるルツェルン祝祭管弦楽団によるマーラー演奏だろう。アバドという人自身はベルリン・フィルのシェフになる以前もその最中も、マーラーを絶えず指揮し続けている人だが、マーラー・チェンバー・オーケストラを中心にゲスト・メンバーで強化拡大したこのオーケストラを手にしたときから、そのマーラー演奏は新しいエポックを迎えたようである。
そしてそれはそのまま、音楽界全体の潮流の変化をも示していた。マーラー・ブームの再来と、そしてかつてのカラヤン時代の華やかなザルツブルクを想わせるような、「音楽祭の都」としてのルツェルンの浮上。ルツェルン音楽祭も1938年からの長い歴史を持ち、カラヤンはここを重視してベルリン・フィルなどと一緒に必ず演奏会を開いていたほどなのだが、オペラ中心のザルツブルクに較べると、どうしても影に隠れがちだった。
しかし今や、シンフォニーの分野においてはザルツブルクに勝るとも劣らぬ豪華さと話題性を誇っている。その中心にあるのがマーラーの交響曲なのだ。9月最終週の「ユーロ・ライヴ・セレクション」では、ドイツ語圏の超一流交響楽団が顔を揃えた同音楽祭の模様をお送りする。どうぞお楽しみに。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年08月/第47回 ドゥダメルあらわる
2007年08月/第47回 ドゥダメルあらわる

鳴り物入りで登場する新人は少なくない。しかし、何年かクラシック界の動きを追っている人なら、その新人たちが皆そのまますくすくと伸びるとは限らないことは、いやでもわかってくる。
ドゥダメルという指揮者が登場したときにも、「またか」という感想を抱かれた人が少なくなかったに違いない。
かくいう私自身がそうだった。デビュー盤のベートーヴェンの交響曲第5番と第7番の1枚は、正直言ってそれだけではその実力を測れるものではなかった。現代流のピリオド・アプローチではないことだけはわかっても、それがただのアナクロニズムなのか、それとも彼の真の個性の強さによるものなのか、判定するには材料が少なすぎた。それに、彼の率いるシモン・ボリバル・ユース・オーケストラという団体も、その活動は称賛されるべきものであるとはいえ、演奏自体の評価とは無関係な「物語性」が強くて、客観的な判断をしにくくしている。
それやこれやで「もう少し様子を見たい」と思っていたのだが、どうやら音楽界の潮流は恐ろしく速く、東亜の孤島のマニアのことなど待ってくれないようだ。どういうことかというと、今年26歳のドゥダメルは秋からスウェーデンのエーテボリ交響楽団の首席指揮者に就任、さらに2009年からはロスアンジェルス・フィルの音楽監督になるという。ヨーロッパでも各所に顔を出し、あっという間に「EURO LIVE SELECTION」で4晩特集できるほど音源が集まってしまった。
少なくとも、その東奔西走の活躍ぶりが本物であることだけは確かである。では、真価は如何。今月の放送で確かめてみたいと思う。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年07月/第46回 ルイジアナって、どこ?
2007年07月/第46回 ルイジアナって、どこ?

ルイジアナなら、アメリカの州の名前でしょ、とお答えになった方がほとんどではないだろうか。南東部のメキシコ湾沿い、ジャズ発祥の地といわれるニューオリンズがあり、2005年には超大型ハリケーンで大きな災害に見舞われた、あの州だ。
そのルイジアナ、今月11日から14日にかけて放送される「ユーロ・ライヴ・セレクション」では、ルイジアナ現代美術館、なる会場での演奏会が取り上げられている。
4回のうち3回にはエベーヌ弦楽四重奏団、ピアノのエリック・ル・サージュという、東京国際フォーラムでの「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」でおなじみの、将来を嘱望されるアーティストが出演し、残る一回もヴェテランのラレードなど、実力者たちによるトリオ演奏だ。
この番組で取り上げるプログラムを選択していた私たちがこの演奏会シリーズに気がついたとき、アメリカにはこんなセンスのいい催しをやる会場があるのか、などと感心していた。ところがデータをよく見ると「デンマーク放送提供」とある。そう、よく調べたらこれはコペンハーゲンの北35キロ、フムレベックなる町にある美術館のことで、アメリカではなく北欧のものだったのだ。
この美術館のサイトを覗いてみると、毎年面白そうな内容のコンサートをやっている。やっぱり世界は、いやヨーロッパだけでも充分に広い、と教えられた次第。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年06月/第45回 本場ナントのラ・フォル・ジュルネ
2007年06月/第45回 本場ナントのラ・フォル・ジュルネ

今年も5月のゴールデン・ウィークに、東京国際フォーラムで3回目の「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」が開催され、大変な人気を集めた。
日本クラシック界最大の行事ともいえそうなこの催しが、フランス西部の町ナントで毎年行なわれている音楽祭を移植したものだというのは、多くの方がご存じだろう。
1995年に始まったナントの「熱狂の日」は、すでに13回を数える。今年も1月31日から2月4日まで、5日間開催された。テーマは東京と同じ「民族のハーモニー」。曲目も演奏者の顔ぶれも、かなり共通している。
東京都だけで1200万、首都圏で考えれば4200万という人口を持つ「オ・ジャポン」とわずか30万人のナントでは、そもそも周囲の規模が異なるし、ゴールデン・ウィークという特殊な休日の連続も、ナントにはない。ところがそれでも町の人口の半分にあたる15万人を動員するというのだから、さすが「元祖」の熱狂恐るべし、である。
今月のユーロ・ライヴ・セレクションでは、14日から24日にかけ、9回にわたって今年のナントの「熱狂の日」のライヴをお送りする。颯爽たるヴァイオリンで旋風を巻きおこしたネマニャ・ラドゥロヴィチなど日本にも来た音楽家ばかりでなく、コンチェルト・ケルンやケルン室内合唱団のように、来日しなかった人たちの演奏も聴けるという、オマケも付いている。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年05月/第44回 嵐を呼ぶ男
2007年05月/第44回 嵐を呼ぶ男

劇的な人、とでもいうほかない人生を生きる人がいる。
現役の指揮者のなかで、大植英次ほど劇的な生を生きている人は少ないかも知れない。
始まりからしてそうだった。1990年のバーンスタイン最後の来日公演のさい、死を目前にして衰えていたバーンスタインから、演奏会中の一曲の指揮を委ねられる。健康上の理由だけでなく、バーンスタインはかつて自身が副指揮者だったときの経験から、こうした形で若い副指揮者たちに機会を与えることを好んでいたのだが、開演直前になって急にその事実を知らされた聴衆の一部が激昂、主催者に抗議する騒ぎとなった。
大植にとっては最悪の形での「デビュー」だったろうが、しかしむしろこの一件で彼の名が、音楽ファンの印象に残ったことはたしかである。そしてそれから時間をかけて大植は汚名を雪ぎ、知名度をますます高めてきた。1995年にアメリカのミネソタ交響楽団音楽監督へ抜擢されて大成功し、3年後にはハノーファー・北ドイツ放送交響楽団の首席指揮者となって欧州に地歩を築き、2003年には大阪フィルの朝比奈隆の跡を継ぐという難事を引き受けて、成功を収めつつある。
かと思えば、バイロイト音楽祭の指揮者を1年で降板するなど、とにかく話題に事欠かない「嵐を呼ぶ男」大植英次。EURO LIVE SELECTIONでは24日から3日間、彼の指揮を特集する。お楽しみに!
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年04月/第43回 ユーロ・ライヴ、お楽しみに!
2007年04月/第43回 ユーロ・ライヴ、お楽しみに!

EURO LIVE SELECTION(ユーロ・ライヴ・セレクション)が放送回数を増やし、これまでの週2回から、週5回と2倍以上になった。THE CLASSICのライヴ・コンサート番組としては、文字通り看板番組になる。
そこで取りあげるのはEBU、ヨーロッパ放送連合に加盟するヨーロッパ各地の放送局が録音した、クラシックの演奏会やリサイタルだ。ドイツ各地、フランス、スイス、イタリアといった西欧諸国を中心に、北欧、中欧、東欧各国からの音源が次々と登場する。
現時点では毎週水曜日がさまざまなジャンルのリサイタル、木曜日から日曜日までがオーケストラ・コンサートを中心として、オペラも適宜取りあげていくことになっている。
いまのクラシック界には「帝王」のような存在はいない。しかしそれは衰退を意味するのではなく、群雄割拠の黄金時代を意味しているのである。モダン楽器の指揮者、器楽奏者、歌手、そしてピリオド楽器の音楽家たちを含めて、ヨーロッパの音楽界は非常な活況を呈している。その沸きかえる「いま」を、この番組でお伝えできるはずである。インターネット上の同時中継なども増えているが、それらはまだまだ冷凍食品的で、音質的には不満足なものだ。ミュージックバードで、その「熱い」音を確かめてほしい。
不肖私めも、舩木篤也さんともにご案内役として登場する。どうぞお楽しみに!
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年03月/第42回 来日公演は終わったが
2007年03月/第42回 来日公演は終わったが

この「プログラムガイド」を皆さんがお読みの頃には、ふたりの俊英指揮者がオーストリアとフィンランドの放送局のオーケストラを率いて来日、各地での演奏会を終えているはずである。
この稿を書いているのは1月末なので、そのツアーがどのような結果になったかは知る由もないのだが、どうか盛況と喝采のうちに終わっていてほしいと願っている。というのも2人とも、わたしが将来を大いに期待している指揮者たちだからだ。ひとりはウィーン放送交響楽団を指揮したベルトラン・ド・ビリーであり、もうひとりはフィンランド放送交響楽団と来日するサカリ・オラモである。
ふたりとも、純度と澄明度の高い、見通しのよい響きをもち、躍動感にみちたリズムを持っている。21世紀前半の主流となるだろう、俊敏な音楽性をそなえた指揮者たちなのだ。若手をなめてかかる傾向のつよい我が国での人気はまだ限られた範囲の中だけだが、今後はひたすらに増していく一方のはずである。
オラモの方は幸い、今月の「ユーロ・ライヴ・セレクション」にも登場するので、演奏会を聴き損ねた方たちにもその指揮ぶりを聴いていただける。バルトーク、シベリウス、ラヴェルなど、オラモが得意とする近代の作品群だから、きっとその実力を確かめることができるはずだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年02月/第41回 花も実もある女性たち
2007年02月/第41回 花も実もある女性たち

近年の欧米では、若手俊英の女性ヴァイオリニストの活躍が著しい。
ヒラリー・ハーンの登場は衝撃的だったし、一時の話題性に溺れてしまうことなく、その後も充実した活動を実演でも録音でも続けて、そのまま一流音楽家の列に加わってしまった。彼女を代表格に、ジャニーヌ・ヤンセン、ユリア・フィッシャー、バイバ・スクリデ、ニコラ・ベネデッティ、アラベラ・シュタインバッハーなどなど、さまざまなタイプのヴァイオリニストが毎月のように登場しては、音楽界を賑わしている。
どうかすると、CDは出るが演奏会ではその名前を聞かない「有名」ヴァイオリニストというのもいたりするのだが、先に名前を挙げた人たちは実演でも録音でも、花も実もある活動をしているのが重要だ。
今月の「ユーロ・ライヴ・セレクション」には、その中から2人が登場する。まずジャニーヌ・ヤンセンが10日にマスネやサン=サーンスの小品、さらに16日の放送ではモーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲を弾く。ヴィオラは彼女の「四季」のCDでも共演していたジュリアン・ラクリン。続いてユリア・フィッシャーが24日の放送で、ギラードとミュラー=ショットとの共演によるモーツァルト、ラヴェル、シューベルトなどのピアノ・トリオ。
二人とも優れた音楽家たちとの顔合わせで、プリマドンナ気取りではできない、息を合わせた共演を聴かせてくれるはずだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2007年01月/第40回 左手からのピアニスト
2007年01月/第40回 左手からのピアニスト

エレーヌ・グリモーというピアニストが最初のCD、ラフマニノフのピアノ曲集を録音したのは1985年7月、まだ15才のときだった。
このときすでにパリ音楽院のプリミエ・プリ(首席中の首席)を獲得して卒業していたというのだから、まさしく早熟のピアニストだった。だからこのデビュー盤も、単なる「神童」の記録というよりは、世界に向けて活動を開始したプロの音楽家としての第一歩として考えるべきなのだが、どうも発売当時の日本での受けとりかたは、そのような真摯なものではなかったように記憶している。
グリモーが長髪の「美少女」であったことが、この場合はよくなかったような気がする。約十年後のJクラシック・ブームや、また最近は欧米のメジャー・レーベルでも、「実力より容貌」的な美女が玉石混淆に登場してCD界を賑わしているけれど、その先駆けのような印象が、はじめの5年間ほどはつきまとっていたのである。
あるいは、契約していたのが日本のレーベルだったのも、やや安易な欧米志向の強い私たちの目を、いや耳を曇らせていたのかも知れない。しかしグリモーはその後も着実に、その高い知性によってキャリアを築いている。
そのピアノの第一の特徴は、左手の独創的で自在な動きにある。普通なら脇役になりかねない左手が、ときに主役になったりする。けっしてパワフルとはいえない彼女が大曲を見事に弾きこなすのも、この左手のリズムによるところが大きい。この人とノリントンのブラームス、どんな音楽が生まれるのか大いに楽しみである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年12月/第39回 ハーディング30才
2006年12月/第39回 ハーディング30才

クラシック界のあちこちで、当たり前のようにハーディングの名前を見かけるようになった。
この秋にはマーラー・チェンバー・オーケストラと一緒に来日して演奏会を行なったし、レコード店に行くとかれが指揮した《コジ・ファン・トゥッテ》や《ドン・ジョヴァンニ》、《ねじの回転》などのDVDが、新譜として並んでいる。少し前はテレビで、去年のミラノ・スカラ座の《イドメネオ》をやっていた。
この《イドメネオ》は、ミラノ・スカラ座のシーズン開幕公演だった。歌劇場によって差はあるが、スカラ座では以前からシーズン開幕公演が非常に重要視される。それをこの歌劇場にデビューする指揮者が任されたのだから、立派なものである。
現時点の固定したポストはマーラー・チェンバー・オーケストラの音楽監督くらいで、あとはロンドン交響楽団の首席客演指揮者に、2007年からのスウェーデン放送交響楽団の音楽監督の座が決まっている程度だから、楽壇を驚倒させるようなビッグ・ポストをつかんでいるわけではない。でも、あと4、5年もすれば、大変なところにいるかもしれない。
指揮者というのは、意外に大器晩成とは限らない。出るべき人は運も味方につけて、早く世に出る。たとえばトスカニーニがスカラ座の音楽監督的な地位に就いたのは31才、フルトヴェングラーがベルリン・フィルの常任になったのは36才。ハーディングがかれらに比肩できる存在になるかどうかは、この先の数年間の未来が知っているはずだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年11月/第38回 アーノンクールの40年
2006年11月/第38回 アーノンクールの40年

今年秋のクラシックのコンサートで最大の話題は、アーノンクールがウィーン・フィルやウィーン・コンツェントゥス・ムジクスを率いて来日して、演奏会シリーズを行なうことである。
昨年、25年ぶりに日本を訪れたのに続いて、今年はその指揮による演奏会が開かれることになった。カラヤンが生きていたころには、「音楽の都」ウィーンに拠点を置きながら王道を行くことを拒否する異端者として、刺激的かつ挑発的な活動を続けていたアーノンクールも、ここ10年ほどはウィーン・フィルやそのニュー・イヤー・コンサート、さらにベルリン・フィルなどの演奏会も当然のように指揮するようになった。
もちろん、保守的伝統を持つそれらのオーケストラを指揮しても、つねに斬新な視点から作品とその演奏を見つめなおすアーノンクールの姿勢は変わっていない。ウィーン・フィルを指揮してスメタナの交響詩を指揮するときにも、ピリオド楽器の団体を指揮してモンテヴェルディの歌劇を指揮するときと同じく、古びた作品の時代の垢を洗い落とし、新鮮な色彩を甦えらせる手法がとられているのだ。
レコードの上でのその活動は、1960年代初めから数えて、すでに40年を越える長さに及んでいる。11月6日から11日と13日から18日までの日曜日を除く2週間、昼12時からお送りする「スペシャル・セレクション」では、若いときから現在に至るまで、アーノンクールの指揮をたっぷりとお聴きいただこうと思う。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年10月/第37回 アバドの集中
2006年10月/第37回 アバドの集中

オペラを、コンサートの場で演奏することは珍しくない。それも全曲ではなく、単独の幕を取り出すことも多い。
ワーグナーの作品でよくそうしたことが行なわれるのは、彼の巨大な歌劇や楽劇を、十全な形で上演するのが困難なためである。コンサート形式での一幕だけの抜粋上演なら、視覚的要素を捨て、人数をしぼることで限られた資材を集中できる。聴覚的要素、つまり音楽面に限定すれば、指揮者のコントロールが行き届きやすくなるという利点もある。
そうしたことから、《ワルキューレ》の第一幕や第三幕、《トリスタンとイゾルデ》の第二幕などは、よく取りあげられる。これらの幕は、ほとんどの音楽が長大なソロか二重唱だけでできているからだ。
だが、《ローエングリン》第二幕はどうだろう。登場人物はオペラ全幕と同じで、大合唱団も必要という点では、けっして向いていない。だから、一九八三年のエジンバラ音楽祭でアバドがこの幕だけを取りあげて演奏したのは、とても珍しい、異例のことだった。
その主目的は節約ではなく、集中にあったのだろう。幸福に満たされたはずの盃の中に、呪いの一滴が注がれる。そして猜疑心の波が生じ、やがて悲劇が渦まいていくさまを、ソロから大アンサンブルへの拡大の過程で、じっくりと描き出す。アバドは視覚的要素を聴衆の想像力にゆだねて、オラトリオのように音へ集中することで、そのドラマを築こうとしたのである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年09月/第36回 ショスタコーヴィチの時代は来るか?
2006年09月/第36回 ショスタコーヴィチの時代は来るか?

1980年代に、マーラーの交響曲が実演でもCDでも大人気となったときがあった。
そのとき、チラホラとささやかれていたのが、「次はショスタコーヴィチだ」という言葉だった。
マーラーの次はショスタコーヴィチ・ブームが来る、ということである。マーラーの後の時代で、演奏会の中心的レパートリーである交響曲を15曲も書いて、たっぷりと楽しめるようにした大作曲家といえば、ショスタコーヴィチしかいないからだ(数だけでいえばミャスコフスキーとかホヴァネスとかブライアンとかもいるが、彼らはマイナーだ)。
しかし1990年代、ショスタコーヴィチの実演やCDは数を増やしたが、ブームとまではならなかった。代わりに来たのは意外にも、ブルックナーの大ブームだった。
そして、いまはそのブルックナー・ブームも終わって、時代は次にどこへ向うか、気配しか見えないところである。マーラーもリバイバルしつつあるけれど、新鮮味において落ちることはいうまでもない。
ショスタコーヴィチ・ブームは来るか。
数年前、わずか2500円前後で買える交響曲全集が大ヒットして、その音楽への親しみの度合いは大きく増している。それが次の段階へつながるか、どうか。
ともかく、生誕100年の今年に、あらためて彼の音楽をまとめて聴いてみよう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年08月/第35回 帝王のレコード
2006年08月/第35回 帝王のレコード

帝王と呼ばれた男、ヘルベルト・フォン・カラヤン。
しかしかれは、ただの指揮者だった。どんなに豪壮華麗な響きをオーケストラから導き出そうと、それは瞬時に消えていく。永遠に残り、聴きつがれていくような名曲を書き上げる作曲家ではなく、ただの指揮者だった。それでも、カラヤンという名前とその存在は、没後17年を経た現在も色あせることなく、クラシック界を象徴するものとして、光り輝いている。
彼は、指揮者が永遠の名声を博すためにはどうすべきか、自らが不在となっても、この世にあまねく在るためにはどうすべきか、よく知っていた。
レコードである。かれはつねに最新の技術を用いて、永遠に残るレコードに、自らの芸術をとどめていった。SP、LP、CD、さらに映像ソフト。生前のカラヤンが知る由もなかったDVDやインターネットの時代にも、その演奏は記録となって残る。
そのレコードの中に、カラヤンは自らの何を、どのような姿を、とどめようとしたのか。いま、あらためて聴きなおしてみよう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年07月/第34回 人にやさしいメトロポリタン歌劇場
2006年07月/第34回 人にやさしいメトロポリタン歌劇場

今月放送される、メトロポリタン歌劇場の盛大なガラ・コンサートは、ヴォルピー支配人の引退を記念したものである。
ヴォルピーは1964年から、42年間もこの歌劇場に関わってきたそうで、社会人としての人生のほぼすべてを、この歌劇場とともに過ごしたような人だ。ひんぱんな転職やヘッドハンティングが日常的なアメリカでは珍しい生き方で、日本でも最近は珍しくなりつつある終身雇用で頂点へ登りつめた、つとめ人のお手本みたいな存在だ。
そういう人物の引退を、老若の名歌手たちが大挙して舞台につどい、華やかに飾る。
これにはもちろん、完全民営の団体としてのメトロポリタン歌劇場のお家の事情もある。このような機会を華やかに盛り上げることで高額の寄付金を募り、経営の一助や基金の資金源とするのだ。往年の名物支配人ルドルフ・ビングの引退ガラ、開場百周年記念ガラ、レヴァイン二十五周年ガラなど、CDやDVDになったさまざまなガラも、すべてそのような性格をもっている。
そう思うと、一般庶民には遠い場所に思えるけれど、その遠さを憧れと夢に変え、輝く華やかさを維持してきたのが、この歌劇場なのだ。だからその遠さには、同時に温かさがある。それは、名歌手、指揮者、そして支配人を頂点とする裏方たちがこの歌劇場で数十年も活動し、先輩から後輩へと受け継いできた、その人々の温もりが生むのである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年06月/第33回 ゲルギエフの《ボリス》初稿版
2006年06月/第33回 ゲルギエフの《ボリス》初稿版

サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場を率いるゲルギエフは、ムソルグスキーの傑作オペラ《ボリス・ゴドゥノフ》の全曲を、1997年にCDで商業録音している。
2000年度の音楽之友社主催の「レコード・アカデミー賞」を受賞した名盤だが、この盤の特長は、その演奏の素晴らしさだけでなく、1869年版と1872年版という2つのヴァージョンを、ともに収録した点にあった。
大ざっぱに言えば、後者の1872年版というのが、私たちのよく知っている《ボリス》の版である。それに対して1869年版というのは、ムソルグスキーが最初に書き上げた版だが、劇場側から上演を拒否されて、お蔵入りしてしまったものだ。
拒否された理由の一つは、女声がほとんど出てこない男声ばかりの出演で、地味すぎるということだった。そこでムソルグスキーは華麗なポーランドの場面などを書き足し、公女マリーナの役を追加して1872年版とし、ようやく翌73年のサンクトペテルブルクでの初演にこぎつけた。
こうして 1869年版の初稿は忘れられてしまったのだが、近年は主役ボリスのドラマに凝縮されたこの版が、次第に関心を集めるようになっている。その復活の最大の功労者が、CDや各地での上演を指揮したゲルギエフその人なのである。2003年には日本でも上演されたこの初稿版を、2002年プロムスの演奏会形式公演で聴いてみよう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年05月/第32回 《ジュノーム》の意味
2006年05月/第32回 《ジュノーム》の意味

BBC Concertで放送する曲には、ときに未知の現代曲が含まれている。
問題なのは、そうした曲のタイトルをどう日本語にするかである。「交響曲第1番」などなら苦労はないが、凝った標題だったりすると大変だ。ただ直訳すればいいというものではないからである。
二重の意味があったり、北欧の作曲家なのにわざわざドイツ語を使っていたり、単純でないものが多いので難しい。原語をただ機械的にカタカナ表記するのが最近の流行だが、それでいいのかという思いが残る。
この問題はいつの時代も変わらないようで、石井宏さんによると、昭和前半にある高名な評論家がモーツァルトの《ジュノーム》協奏曲を評して「ジュノームとはフランス語で『若い人』の意味で、その名のとおり若々しい音楽です」と書いたそうだ。
しかしこの曲の場合の「ジュノーム」は、ある女性ピアニストの姓にちなんでいる。つまり人名だから訳してはいけないのである。それをわざわざ訳して解説してしまい、後世に失笑を買うことになったわけだ。
とても人ごととは思えない「怪談」だが、今回の《ジュノーム》協奏曲にかぎっては、「若い人」と訳しても間違いでないかも知れない。1970年生れのアンスネスに67年生れのギルバート、オーケストラも若手中心。
特にアンスネスの瑞々しい感性は、まさに「ジュノーム」ならではの音楽である。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年04月/第31回 スペシャリストの枠を超えて
2006年04月/第31回 スペシャリストの枠を超えて

サー・チャールズ・マッケラスという名前を知ったのは、1970年代後半にデッカが次々と録音発売した、ヤナーチェクのオペラ・シリーズの指揮者としてのことである。
チェコ、オーストリアの名歌手たちをあつめ、オーケストラにウィーン・フィルを起用したこのシリーズは、優れたオペラ作曲家としてのヤナーチェクの存在を、国際的に知らしめるものだった。しかし同時に、そのシリーズの柱となっている指揮者がアメリカ生れのオーストラリア人で、東欧の血を引いているわけではないと知ったときには、不思議な思いをした。偏狭な本場主義を信奉しているわけではないが、演奏がいいだけにむしろ、何か落ちつかない気分だった。
それから四半世紀をへた今、1925年生れで80歳を過ぎたマッケラスは、オーストラリア人とか、ヤナーチェクのスペシャリストといった枠を超えた、一人の優れた指揮者として世に隠れもない存在となっている。銘木だけで建てた家を想わせる、華美ではないが艶やかさをもった響きと、ひきしまって無駄のない、厳しい構築感。
その彼がいま意欲を燃やしているのは、ドイツ・オーストリアの古典派音楽、とくにモーツァルトとシューベルトである。今回のBBC Concertでは、その二人の作品が聴ける。ブレンデルとのピアノ協奏曲は、セッション録音で全集が進行中だが、これは同時期のライヴなので、聴き較べも楽しみである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年02月②/第30回 「明けの明星」の人
2006年02月②/第30回 「明けの明星」の人

2月19日のBBC Concertでは、フランツ・ウェルザー=メスト指揮のロンドン・フィルハーモニックによる、1993年プロムスの演奏会を放送する。
現在クリーヴランド管弦楽団の音楽監督をつとめるウェルザー=メストは、1992年から96年までロンドン・フィルの音楽監督だった。この演奏会はちょうどその時期のもので、偶然にもメスト33歳の誕生日にもあたっている。
私がこの指揮者の演奏を初めて聴いたのは、92年に東芝EMIから発売された、ロンドン・フィルとのブルックナーの交響曲第7番(91年プロムスでのライヴ)だった。ウェルザー=メストはその3年ほど前からEMIに録音を始めていたが、このブルックナーはライヴ録音だったので、興味がわいたのだった。
一聴して嬉しかったのは、そのリズムに弾力があっで、音楽に呼吸感があったことである。そうした要素は1970年以降のクラシックの録音には、めっきり耳にできなかったものだった。もうクラシックは、自分の好みとは正反対の方向に進みつつあるのだとあきらめかけていた、そんな時期に1960年生れのウェルザー=メストは颯爽と登場し、音楽に弾力を与えてくれたのだ。
ひょっとしたら、音楽はふたたび甦えりつつあるのかも知れない――そのときは正直な話、そこまでムシのいい予想はできなかったけれど、それから15年近くたった今、音楽は全体の傾向としてどんどん俊敏に、快活になってきている。嬉しい方向へと予想は外れたのだ。
ウェルザー=メストは俊敏なリズム感が復活する、その先駆けとして私たちの前に現れた指揮者だった。喜びをかみしめつつ、「夜明け」の頃の演奏会を聴いてみたい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年02月①/第29回 アバドのライフワーク
2006年02月①/第29回 アバドのライフワーク

2月前半のBBC Concertでは、アバド指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による、マーラーの交響曲を2曲ご紹介する。
すでによく知られていることだが、アバドはマーラーの交響曲の録音に、ひとかたならぬ情熱を注いできた。今回お送りする第4番と第9番の場合、1回目の商業録音はそれぞれ1977年と87年に、ともにウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮して行なっている。
その後、ベルリン・フィルの芸術監督への就任を翌年に控えた1989年からは、このオーケストラによるマーラー作品の録音プロジェクトを開始した。これは監督辞任後の現在も継続中で、第9番が1999年に、そして第4番は昨2005年に録音されて、発売されたばかりである。
さらにこれらのレコード用録音とは別に、映像ソフトでもマーラーの録音録画を開始していて、第9番が2004年のグスタフ・マーラー・ユーゲント管弦楽団(アバドが手塩にかけて育ててきた団体)とのライヴ演奏がDVDになっている。第4番はまだだが、いずれこのオーケストラか、おそらくルツェルン祝祭管弦楽団との演奏が商品化されるに違いない。
アバドによる最初のマーラーの商業録音は1976年の《復活》だから、今年はちょうどそれから30年目ということになる。この間、90年代にはブルックナーの方がマーラーよりも人気を博してもいたが、アバドは目移りせずに、ライフワークのようにマーラーを指揮し続けてきた(ベルリン・フィルのブルックナー演奏は、ヴァントに任せてしまったようだった)。
今回お送りするのは1991年と94年、CD化されたベルリン・フィルとの録音よりも以前の、プロムスでの演奏である。若く熱い5000人の聴衆に囲まれての、ライヴ録音だ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年01月②/第28回 「問題音源!?」ショルティ
2006年01月②/第28回 「問題音源!?」ショルティ

1月22日のBBC Concertでは、ショルティ指揮ロンドン交響楽団による、1968年のコンサートをご紹介する。
1961 年にコヴェント・ガーデンの王室歌劇場の音楽監督となって以降、イギリスとは縁の深かったショルティだけに、さまざまなオーケストラとのライヴ録音が bbcから放送されたのではないかと思う。しかし、現時点でbbcのアーカイヴズが提供しているのは、1963年のワーグナー・コンサート(こちらも以前 BBC Concertで放送した)と、今回の1968年のコンサートとの2種しかない。
大物指揮者だけに権利関係などの問題があるのかも知れず、残念だがこれは今後の進展を待つほかない。というわけで、貴重なアイテムとなった今回のコンサートなのだけれど、実はこれにも2つ問題があった。
ひとつは、後半の《英雄》交響曲のオリジナル音源が行方不明で、LPに転写した33回転盤(トランスクリプション・ディスクという)からの音源しかないこと。もうひとつは、前半の2曲め、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番が、BBCレジェンズですでにCD化されていることである。
難しい問題だが、状態を確認するために音源を取り寄せて聴いてみた結果、放送することを決めた。まず転写盤からの音源にはLP特有のチリチリ・ノイズがあるし、音質もやや甘いが、音源の貴重さをかんがみれば許容範囲にあると判断した。
もうひとつの、すでにCDがあるという問題も、聴き比べてみて解決した。オリジナル音源の生々しさと明快さは、CDをはるかに上回っている。これなら、あえて放送する意義も充分にある。コピー容易なデジタル時代になっても、やはりオリジナルは、オリジナルならではの存在価値を持っているのだ。
みなさんはどう判断されるか。どうぞお楽しみに。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2006年01月①/第27回 「よき後継者」テミルカーノフ
2006年01月①/第27回 「よき後継者」テミルカーノフ

いきなり宣伝めいて恐縮だけれども、半年ほど前に『名指揮者列伝』という本を上梓させていただいた。月刊誌のシリーズ掲載をまとめたものである。そこで、一人ずつ書いていたときには気がつかなかったのだが、本にまとめる段になって、初めて気がついたことがあった。
オーマンディ、バルビローリ、ベイヌムの3人がほぼ同年代(前2人が1899年、ベイヌムが翌1900年)だったことである。この3人、それぞれフィラデルフィア、ニューヨーク、アムステルダムのオーケストラの指揮者を務めていたことがあるのだが、いずれも非常に個性の強い前任者(ストコフスキー、トスカニーニ、メンゲルベルク)の跡を襲うという、困難な役目を負わされていたのだ。
華やかなスター指揮者が嵐のように去って、いわばその「後始末」をするというのは、苦労ばかりで報いられることの少ない仕事である。その難事を引き受けた3人がそろって19世紀末年の生れということに、何か不思議な因縁を感じたのだった。
さて、最近は指揮者とオーケストラの関係が何十年も続く機会が減ったので、こうした苦労を背負う指揮者も少なくなった。その中でユーリ・テミルカーノフは、数少ない例外の一人である。彼が1988年に芸術監督に就任したレニングラード・フィルは、その直前までムラヴィンスキーが、半世紀の長きにわたって君臨していたオーケストラだったのだ。
引き継いでから数年後にソ連が解体、市名の変更に伴ってオーケストラもサンクトペテルブルク・フィルと名を変えた。周囲の状況も激変した。その中でテミルカーノフは、この名門に新しい血を流し込み、すでに15年以上も指揮を続けている。
今回のBBC Concertでは、1991年と2004年の二つのライヴを聴き比べて、両者の関係の「深化」のほどを確かめてみたい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年12月②/第26回 「若すぎた男」キーシン
2005年12月②/第26回 「若すぎた男」キーシン

来年のトリノ五輪で、スケートの浅田真央が年齢制限のために出られないことが話題になっている。生まれたのが三か月だけ遅く、まだ若すぎるということだそうだ。
今から20年前、1985年のショパン・コンクールの頃に、似たような話を聞いたのを思い出した。そのときはソ連(当時)のスタニスラフ・ブーニンが優勝して、日本で一大ブーニン・ブーム――ちょうどヨン様ブームみたいな――が巻き起こり、その初来日は社会的事件といって過言でない大騒動になった。
当時私は、ブーニンを招いた音楽事務所でバイトしていた。連日灰神楽のたつような騒ぎだったが、その陰で、「じつは、ブーニンより凄い才能を持つ少年がモスクワにいる。年齢制限で出られなかったそうだ」という噂が、早くから事務所内に流れていた。それが、この年15歳のキーシンである。
翌年、故郷のモスクワで行なわれたチャイコフスキー・コンクールへも、彼は年齢制限のために参加できなかった。にもかかわらず、そのオープニング・セレモニーで演奏する機会を与えられたのは、「真の勝者は誰か」を示しておきたいと、彼の周囲の人々が望んだ結果だったのだろうか。
そして、それから4年後の1990年は、5年に一度のショパン・コンクールと、4年に一度のチャイコフスキー・コンクールが同じ年に開催される年だった。19 歳になるキーシンにとって、願ってもない巡り合わせのはずだが、彼はどちらにも参加しなかった。すでに諸外国にその名を轟かせ、カラヤンとも共演した経験を持つ人気ピアニストにとって、いまさらのコンクール優勝など、無用のお飾りになっていたのだ。
近年はアンスネスのように、大コンクールをあえて経由せずに世に出る、優秀なピアニストが増えている。「若すぎた男」キーシンは、そうした人々の嚆矢となったのである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年12月①/第25回 偽作が化けて名作に
2005年12月①/第25回 偽作が化けて名作に

偽作とは、誰か別人が作ったのに、偽りの作者(多くは有名人)の名前が表記されている作品のことである。絵画や彫刻など美術品の世界には無数の偽作と贋作があふれていて、真贋の目利きこそが「専門家」の最大の仕事となっている。
それに比べれば、音楽作品の場合は多くない。偽作と認定されているとか、その可能性が高いとかいうのはモーツァルトの世代くらいまでで、それ以降の作曲家の作品で、真贋を疑われているものはまずない。音楽作品というのが絵画や彫刻のような一品物ではなく、写したり印刷したりすることが容易にできる楽譜という形で大量に流通するものなので、専門家の目に触れないまま素人を騙してしまうことが難しいからだろう(作品そのものではなく、その自筆譜のような一品物なら、贋作はきっとたくさんあるに違いない)。
ところがロマン派以降の音楽の世界では、知名度の高い音楽家が自作を他人の作品と偽って発表し、好評を得てしまったというケースがある。有名なのはヴァイオリニストのクライスラーの事件で、擬古典風の自作を「イタリアの修道院に秘蔵されていた過去の作品」として、長いこと演奏会で演奏していた。
今回の「BBC Concert」でお送りする《キリストの幼時》も、もとはクライスラーの場合と同様にベルリオーズが「偽作」した曲である。フランス楽壇の形式主義と権威主義に悩まされ、作品を正当に評価してもらえなかった彼は、自作の合唱曲を17世紀後半のパリの宮廷音楽家の作品と偽って演奏し、見事批評家たちを騙して、からかってみせたのである。
この結果に気をよくしたベルリオーズは、その「偽作」を曲中に含むオラトリオを完成し、今度は自らの作品として初演した。この曲の清冽で静謐な美しい響きは、皮肉な冗談から生まれたものだったのだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年11月③/第24回 「マーラの10年」が煌めいて
2005年11月③/第24回 「マーラの10年」が煌めいて

1990年代のオーケストラ界が「ブルックナーの10年」だったとするなら、80年代はまさしく「マーラーの10年」だった。
猫も杓子もマーラーの長大かつ大編成の交響曲を演奏し、録音していたのである。とくに、LPよりも長時間収録が可能なCDが普及し、買い換え需要でレコード業界が潤い、バブル景気で演奏会のスポンサーも簡単に見つかった80年代後半のマーラー・ブームは、本当に凄いものだった。
何人もの指揮者が全集の完成を目指してレコーディングし、外来のオーケストラもこぞってマーラーを演奏した。
その総仕上げ、頂点ともいうべき事件は、1990年11月の2週間に集中して行なわれたシノーポリ&フィルハーモニア管弦楽団と、同じ月からの1年間で断続的に行なわれた、ベルティーニ&ケルン放送交響楽団とによる、2つのマーラー全曲チクルスだった。外来のオーケストラがこんな手間と金をかけてもおつりが来るくらい、当時のマーラー熱は凄かったのである。
シノーポリとベルティーニ、それに(日本での実演の回数は少なかったが)テンシュテットを加えた3人が、この「マーラーの10年」を象徴する指揮者たちだった。
言ってしまえば、彼らはマーラーを演奏するために指揮者になった人たちであり、そのことを自らの芸術的使命とし、またそうすることを、周囲から望まれた音楽家だった(ちょうど、「ブルックナーの10年」におけるヴァントのように)。
彼らは「マーラーの10年」において、水を得た魚のように躍動し、輝いた。そしてその後は、ただ衰えゆくだけの光を虚しく追うがごとき歳月を生きて、死んでいった。その栄光はひたすらに「マーラーの10年」の日々にのみあった。 1987年、「マーラーの10年」にシノーポリが指揮する、交響曲第6番《悲劇的》。過ぎし日の煌きを、そこに聴こう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年11月②/第23回 「待ち男」シャイー
2005年11月②/第23回 「待ち男」シャイー

リッカルド・シャイー、52歳。
ムーティがミラノ・スカラ座の音楽監督を辞任したとき、いよいよシャイーが迎えられるのではないかという推測がされたが、当面スカラ座は音楽監督、つまり主導的な指揮者をおかない体制でやっていくことになったらしい。 スカラ座にムーティが君臨していた今世紀の初め、シャイーの姿勢には、何か半世紀前のカラヤンを想わせるものがあった。つまり、1950年代のカラヤンがその「最終目標」であるウィーン国立歌劇場に到達する直前、ミラノ・スカラ座でドイツ・オペラを指揮して経験を重ねつつ、ウィーン交響楽団をウィーンにおける「橋頭堡」として、ウィーン国立歌劇場を牽制していたことがある。同じようにシャイーは、アムステルダムのコンセルトヘボウのシェフとしてオペラなどを指揮しつつ、やはりミラノにジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団という「橋頭堡」を持っていて、ミラノの聴衆にその存在を顕示していた。
歌劇場にもう興味はない、とシャイーは何かのインタヴューで口にしていたが、スカラ座だけは特別なのではないか、スカラ座以外の歌劇場にもう興味はない、という意味なのではないか、とその真意を推測する向きがある。 とりあえず、今回シャイーがスカラ座に行くことはなかった。だが、未来はまだわからない。シャイーは心中秘かに、時節の到来を待っているのではないか。
「待ちの男」シャイー。その姿勢は、1988年にアムステルダムのロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の指揮者になったときから、すでに始まっていたように思える。もちろん、今いる場所でベストを尽くさなければ、輝かしい明日は来ない。シャイーのコンセルトヘボウ時代は、まさにそうした研鑽の日々だった。そのころの彼をふり返ってみよう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年11月①/第22回 「音楽の母」って?
2005年11月①/第22回 「音楽の母」って?

むかし、「音楽」の授業が大嫌いだった。
ハーモニカもリコーダーも不得手な私にとって、小学校と中学校の「音楽」の時間は、すべての学校生活の中でいちばん憂鬱な部分だった。高校に入ると多少気楽になり、さらに3年になると受験体制なのか、ついに「音楽」がなくなった。
私がクラシックを猛然と聴き出したのは、その高3のときからである。やらされる、聴かされる「音楽」がなくなって初めて、自由意志で聴きたい、と思ったのだ。気がつけば、クラシックに関連する仕事で生活しているのだから、不思議なものだ。
さて、そんな憂鬱な「音楽」の時間、テスト用に暗記させられた教科書には、古今の大作曲家が年表式に並べられ、それぞれに称号みたいなものがつけられていた。ベートーヴェンは「楽聖」、大バッハは「音楽の父」といった具合である。
その中で異様だったのが、ヘンデルの「音楽の母」だった。長いカツラをかぶっているけれど、女性ではないヘンデルがなぜ「母」なのか。単純にバッハと対にするためにつけられたもので、深い意味などないのだろう。バッハを「音楽の父」として、それ以前のイタリア・フランスのバロック音楽の優れた作曲家たちを無視していることは、以前のドイツ絶対主義的な歴史観によるものだ。そしてヘンデルが並べられたのは、彼が一応ドイツ生れだったから――音楽家人生の大半はイギリスにいたのだが――というだけのことに違いない。
《メサイア》以外には、そんないい加減な印象だったヘンデル。ところが近年、そのオペラやオラトリオへの関心と人気が、日本でも急速に高まってきた。そこで11月6日のBBC Concertでは、現在ミュンヘンやザルツブルクで活躍中のイギリス人ボルトンの指揮で、ヘンデルのオラトリオ《復活》をお送りする。ベテラン、カークビーの存在も魅力的だ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年10月②/第21回 BBCの4番打者
2005年10月②/第21回 BBCの4番打者

BBC Concertで取りあげるプログラムは、2、3か月分をまとめてBBCのアーカイブズに発注して、送ってもらっている。
できるだけ、それまで取りあげていない音楽家や曲目を選びたいが、知名度のないものばかり並べるわけにもいかない。アーカイブズにはたくさんの番組が保存されているけれども、そのすべてが日本の聴取者の嗜好に合うわけではないのだ。バランスを適度にとる必要があるのだが、当然のことながら発注の段階では演奏の出来自体がどうなのか見当がつかないから、多少の「賭け」を交えて数か月の予定を立てることになる。
しかしここで助かるのは、BBCのアーカイブズに「4番打者」がいることだ。
サー・サイモン・ラトルである。
彼が登場するプログラムは、退屈ということがない。そこには何かしら刺激と啓発がある。ほとんどの場合、2時間をたっぷり楽しませてくれる。そして、これが重要なことなのだが、彼が出演した番組は数多い。だから、何度も登場してもらえる。
数か月間の予定の中に「華」が欲しいとき、あるいは「賭け」が続く中で確実な結果の期待できる番組が欲しいとき、私はいつも彼に頼る。すると彼は,必ずこちらの無責任な期待に応えて、目の覚めるようなホームランを放ったり、鋭いライナーで野手の間を抜けるタイムリーを打ったりしてくれる。
まさに4番打者、本物のクリーン・アップ。それが私にとってのラトルなのだ。
10 月後半のBBC Concertは昨年のプロムスから、彼とベルリン・フィルの演奏会(2日続きで行なわれたもの)を2週続きでお送りする。芸術監督就任から2年を経て、彼の新しい「楽器」ベルリン・フィルがいよいよその圧倒的な力量を発揮し始めたことが、これらのライヴで確認できる。お楽しみに。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年10月①/第20回 ピリオド楽器のワーグナー
2005年10月①/第20回 ピリオド楽器のワーグナー

10月のBBC Concertは、ラトル強化月間(?)。11月にベルリン・フィルと来日するサー・サイモン・ラトルのライヴ録音を、4週間にわたってお送りする。
4週のうち、前半はイギリスのバーミンガム市交響楽団とオーケストラ・オブ・ジ・エイジ・オブ・エンライトゥンメント、後半はベルリン・フィルという構成になっている。
オーケストラ・オブ・ジ・エイジ・オブ・エンライトゥンメントというのは、いうまでもなくピリオド楽器の団体で、ノリントンの指揮で録音したcdなどで知られている。面白いことにラトルがこの団体を指揮する機会は、演奏会ではなくオペラ(セミ・ステージ形式の上演も含めて)に限られているようだ。モーツァルトの《コジ・ファン・トゥッテ》はcd化されているし、《フィガロの結婚》も以前に当番組で放送した。
モーツァルトの作品をピリオド楽器で演奏するのは、現代ではむしろ当然のこととなっているから、それでラトルがモーツァルトのオペラのためにこの団体を起用したのだろうとは、容易に想像がつく。ところが今回の放送で取り上げられるのは、ワーグナーなのである。ベートーヴェン以降の音楽では基本的に現代楽器のオーケストラを使っているラトルが、ワーグナーでなぜピリオド楽器なのだろう。
ラトルはワーグナーでも《トリスタンとイゾルデ》や《パルジファル》のような 1850年代末以降の楽劇では、現代楽器のオーケストラ(ロッテルダム・フィルなど)を指揮して上演している。しかし今回の《ラインの黄金》は1853年から翌年に作曲されたもので、書法的にはまだ極端に複雑な音楽ではない。その明快な響きを活かすにはピリオド楽器こそふさわしい、とラトルは考えたのではないだろうか。
さて、その成果は如何。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年09月②/第19回 太平洋沿岸のオランダ人
2005年09月②/第19回 太平洋沿岸のオランダ人
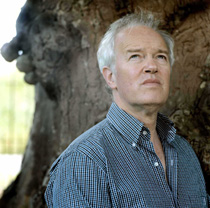
9月後半のBBC Concertでは、2週にわたってエド・デ・ワールト指揮の演奏会を放送する。
エド・デ・ワールト、1941年アムステルダム生まれ、64歳。近頃のこの人の周囲には、「巨匠の予感」が漂いはじめている。
その経歴はとても華やかなものとはいえない。母国第一のオーケストラ、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団では、団員としてオーボエを吹いたことはあるが、指揮者としてポストを得たことはない。
ロッテルダム・フィル、ネーデルランド・オペラ、オランダ放送フィルなど、母国ではつねに「二番目」の団体を指揮して、地道に実績を残してきた。 1990年代前半にオランダ放送フィルと録音したマーラーの交響曲全集は、「今のコンセルトヘボウよりもよほど往年のコンセルトヘボウに近い」などと讃えられた、絹のように美しい響きで一部に熱心なファンを獲得したが、あくまでも局地的なもので、大評判というわけではなかった。
並行して指揮してきた他国のオーケストラも、サンフランシスコ交響楽団、ミネソタ管弦楽団、シドニー交響楽団、そして現在音楽監督をつとめる香港フィルと、やはり派手ではない。
しかしそのケレン味のない、温暖な気候を想わせる、のびやかな響きの音楽は、徐々にファンを増やしはじめている。わが国でもPMFや読売日本交響楽団の指揮者としておなじみになりつつあり、11月にはこのオーケストラを指揮して、二期会の《さまよえるオランダ人》を上演することになっている。
かつて列強に伍して、七つの海で覇を競った国、オランダ。その国に生まれたこの指揮者は、サンフランシスコ、シドニー、香港と、不思議に太平洋沿岸と関係が深い。ということは、あるいはこれからは日本とも縁が強まるかも知れない。いや、どうもそうなる気がしてならないのだが…。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年09月①/第18回 若き日のムーティ
2005年09月①/第18回 若き日のムーティ

リッカルド・ムーティが足かけ19年間も務めたミラノ・スカラ座の音楽監督を辞任したのは、今年の2月のことだ。
就任時45歳だった彼も、今年で64歳になる。色々と無念の思いもあるだろうが、陰謀渦まく歌劇場という伏魔殿に、20年近くも君臨できたことの方が、オペラの歴史の中ではむしろ奇跡に近い(メトロポリタン歌劇場で32年間も君臨するレヴァインは、例外中の例外というべきである)。
ムーティの次の活動がどのようなものになるのか、まだはっきりしないが、不断の緊張から久しぶりに解放されたのだから、しばらくは気楽にやってほしいものだと思う。小澤征爾に声をかけられて東京の「オペラの森」に参加したり、ウィーン・フィルの日本公演に帯同したりなど、日本との関係もさらに強まるかもしれない。
正直いって、ここ10年ほどのムーティの音楽にはあまりに遊びがなく、きつすぎて聴き疲れがした。ミラノ・スカラ座の舞台は緊張感に満ちていなければならないと、ムーティ自身が自分を追いこんでいるような印象があった。スカラ座へ行く前、1970年代にフィレンツェを拠点に指揮していたときの方が、彼の指揮するオペラには自然な活力と熱気が感じられた。
忘れてしまいがちだが、ムーティは生まれも育ちも南国ナポリなのである。しかし19歳でミラノのヴェルディ音楽院に入学して以後は、彼の音楽活動から故郷ナポリは抜け落ち、北イタリアがその舞台となってきた。特にミラノ・スカラ座は、彼の南方性を奪い、北イタリア生まれの人間以上に厳格であることを、彼に求めたように思えてならない。9月4日と11日のBBC Concertでは、スカラ座へ行く前の、1978年と80年のムーティの演奏をお送りする。現在のムーティが取り戻すべき「熱血」が、そこにあるように思う。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年08月②/第17回 301年目のビーバー
2005年08月②/第17回 301年目のビーバー

特に人気が高く、名のあるバロック・ヴァイオリニストたちがこぞって録音しつつあるのが、「ロザリオのソナタ」と通称される、聖母マリアの生涯を描いた連作ヴァイオリン・ソナタ集だ。中でも、無伴奏ヴァイオリンのために書かれた第16番のパッサカリアは、バッハのシャコンヌの先駆けとなる大曲として注目されている。
しかしそれだけでなく、教会音楽の分野でも再評価の気運が高まっているのだ。8月 21日のBBC Concertで放送する「キリストの復活のためのミサ」も、2000年に校訂譜が出版されて300年ぶりに甦った作品だが、輸入盤CDが2種たて続けに発売を予定されるなど、いま話題の作品である。
ここで指揮にあたるアンドルー・マンゼは、バロック・ヴァイオリンの名手として知られる。ビーバーもヴァイオリンを得意としたから、その作品の演奏家としてはうってつけの存在ともいえるだろう。当時の雰囲気を再現するべくビーバーの別の作品を挿入して、それに合わせて合唱団を出入りさせるなど、演出も凝っていて楽しい。4か月後にセッション録音された同作品のcd(ハルモニア・ムンディ)も間もなく発売される予定なので、聴き比べが楽しみである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年08月①/第16回 生と死の束の間に
2005年08月①/第16回 生と死の束の間に

ベンジャミン・ブリテンという人の性格には、多分にアマノジャクなところがあった。
若くしてイギリスを代表する作曲家として認められた彼には、何か国家的な祝い事があるたびに、それを記念するような作品を作曲してほしいという依頼がきた。
それに対してブリテンは、慶事に冷水を浴びせるような作品を書き上げた。たとえば大日本帝国の建国2600年記念にはシンフォニア・ダ・レクイエム、すなわち鎮魂交響曲を書いて「祝賀にレクイエムとは何事か」と演奏を拒否された。また女王エリザベス2世が戴冠した1953年には、年老いたエリザベス1世の心の不毛と荒廃を描いた歌劇《グローリアーナ》を記念公演用に作曲し、客席の着飾った名士貴顕たちを当惑させた。
だから、1940年にドイツ軍の爆撃で破壊されたコヴェントリー大聖堂が22年後に再建された際、その再建記念の音楽をブリテンが引き受けたことには、多くの人が不安に感じた。
彼らの期待を裏切らず(?)、ブリテンが書いたのはまたしてもレクイエム(祝賀の機会なのに)であり、しかもラテン語の典礼文に、第1次世界大戦で出征中に戦死した詩人の詩を挿入し、さらに初演時の歌手には破壊の当事国であるドイツのバリトンが含められていたから、初演の前から激しい非難の声がブリテンに向けられることになった。
だが、そうして誕生した音楽は戦争のもたらす惨禍と人間性の破壊を訴える傑作として、単なる機会音楽の域を超えた高い評価を受け、その後も演奏され続けることになった。
有限の人間にとって、生と死は表裏一体。死あるがゆえに生は輝き、生あるがゆえに死は重い。慶事から弔事への束の間を、人は生きる。生にあって死を忘れず、死にあって生を、慶事には弔事を。ゆえに今こそ、戦争レクイエム。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年07月③/第15回 ワーグナー馬鹿一代
2005年07月③/第15回 ワーグナー馬鹿一代

イギリス人のくせに、ワーグナーの楽劇を指揮することしか眼中になく、それ以外の音楽にはほとんど目もくれなかった。
時は20世紀なかば、イギリスがオペラの大輸入国で、首都ロンドンのコヴェント・ガーデン歌劇場さえ、やっと自前のカンパニー(歌劇団)を常設したばかりの頃である。
ワーグナーのファンはイギリスにもけっして少なくなかったが、上演のさいには、ドイツから大指揮者を招いて指揮してもらうのが当然だった。コヴェント・ガーデンの指揮者陣に加えてもらっていたその男が、どれほど切歯扼腕しても、ワーグナーを指揮する機会は与えられなかった。
好きでもないイタリア・オペラばかり指揮させられた男は、投げやりになった。気難しい上に、独学の指揮はひどくわかりにくかったから、やがて男は指揮棒を取りあげられた。コヴェント・ガーデンの最上階、掃除係と共同の一部屋に押し込められ、歌手のコーチだけがその唯一の仕事となった。
ところが 1968年、63歳になった男が引退を考えはじめたとき、運命が変わった。ロンドンのもうひとつの歌劇団、サドラーズ・ウェルズ・オペラ(現在のイングリッシュ・ナショナル・オペラ)が突然彼のことを思い出し、《ニュルンベルクのマイスタージンガー》の指揮を彼にまかせたのである。
公演は大成功、天井裏から出てきた男は、イギリス最高のワーグナー指揮者として、熱狂的な人気を博することになった。
その名は、レジナルド・グッドオール。
7月31日のBBC Concertでは、彼の《ワルキューレ》第1幕などをお送りする。その「不器用な愛」の深さをお楽しみに。
(彼の生涯にご興味がおありの方は、洋泉社発行の拙著『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』をお読みください)。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年07月②/第14回 ロンドンのハイティンク
2005年07月②/第14回 ロンドンのハイティンク

ベルナルト・ハイティンクが故国オランダのオーケストラを離れてから、はや17年が経とうとしている。
1929年にアムステルダムで生まれたハイティンクは、28歳でオランダ放送フィルの首席指揮者になり、1961年に32歳でコンセルトヘボウ管弦楽団の常任指揮者(64年からは芸術監督)となった。1988年、オーケストラの創立百周年を期に勇退するまで、四半世紀以上も母国の名門を統率していたのである。
いわば名実共に「オランダのシンボル」的な存在だったわけだが、60歳をすぎた1990年代からは、一転して活動の場をオランダの外に移すようになった。そしてその新たな拠点となったのが、イギリスのロンドンである。それ以前にもロンドン・フィルの芸術監督を70年代につとめるなど、早くから関係を強めてきたこの町の、コヴェント・ガーデンの王室歌劇場の音楽監督というのが、彼の新たな主要ポストだった。
その実直で虚飾のない、ていねいで柔和な音楽づくりが、ロンドンの聴衆に愛された一因なのだろう。ハイティンクは2002年まで、15年間もこの歌劇場に留まることになった(陰謀うずまく歌劇場の職務というのは、オーケストラよりもずっと過酷である)。その後は急逝したシノーポリの後を引き受けて、ドイツのドレスデン・シュターツカペレの首席指揮者となっている。
今回のBBC Concertでは、ハイティンクが「第2の故郷」ロンドンに、ボストン交響楽団とドレスデン・シュターツカペレを引き連れて登場した演奏会を、2週続きでお送りする。
アメリカとドイツのこの二つのオーケストラは、それぞれの国において、とりわけ落ちついた、木質の響きを持つことで有名な存在だ。この点でハイティンクの音楽性ともよく似ているだけに、相性はぴったりといえる。それぞれに調和のとれた美しい響きを、ご堪能あれ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年07月①/第13回 スヴェトラーノフの力強い響きを
2005年07月①/第13回 スヴェトラーノフの力強い響きを

なかでも現在CD店の店頭で特に人気が高いのが、エフゲニー・スヴェトラーノフである。ロシア国立交響楽団(旧ソヴィエト国立交響楽団)との来日やnhk交響楽団への度重なる客演で、徐々に熱狂的なファンを増やしていった。2002年5月に73歳で急逝したときの彼らの落胆ぶりはひどいものだった。それから早くも3年が経とうとしているが、しかしその人気は一向に衰える気配さえなく、廃盤の復活や初出音源の登場など、死してなおその話題性の大きさは変わっていない。
彼の魅力は、「ロシアの指揮者」という言葉がもつイメージをそのまま具現化してくれたことにある、といってよいだろう。豪壮雄大、狩野派の絵を想わせる肉太な響き。自国ロシアの音楽だけでなく、フランスやドイツの作品でもその流儀を変えずに貫きとおす、強引ともいえる頑固さ。
ところでロンドンという町は、ロシアの音楽家への熱狂の度合において、東京に優るとも劣らぬところである。たとえばロジェストヴェンスキーの高い人気は、 30年以上にわたって続いている。スヴェトラーノフももちろん例外ではない。ソヴィエト国立交響楽団とのツアーやロンドン交響楽団などへの客演は、むしろ日本よりも早い時期から大喝采を浴びてきた。
今回の「BBC Concert」では、1968年から78年にかけてのスヴェトラーノフのロンドンでのライヴを、2週続きでお送りする。とにかくCDの多い人なので、一部すでにCD化されている曲もあるが、ベートーヴェンの《皇帝》協奏曲やブラームスの交響曲第3番など、なるべく録音の少ない曲目を選んでみた。ファンの方も、これから聴いてみようという方も、お楽しみに。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年06月②/第12回 マリス・ヤンソンス登場
2005年06月②/第12回 マリス・ヤンソンス登場

アムステルダムのコンセルトヘボウ管弦楽団やバイエルン放送交響楽団の指揮者として、いま日本でも高い人気を得ているマリス・ヤンソンス。かれの名前と演奏を初めて知ったのは、1980年頃の「プラハの春」音楽祭のラジオ中継のときだった。
曲目はブラームスの交響曲第2番だったようにも思うが、もはや定かではない。解説の方が「ヤンソンスというからアルヴィドかと思ったら、こんなに立派な息子さんがいたんですねえ」というようなことを話していたのを憶えている。父アルヴィドはたび重なる来日公演で親しまれていたから、「その息子」というのが印象的だったのだろう。 その次にわたしがかれの名前を聞いたのは、1986年秋である。准首席指揮者をつとめていたレニングラード・フィルの来日公演に帯同したのだが、数公演を指揮するはずだったムラヴィンスキーが病気で来られなくなり、その分もヤンソンスが指揮することになったのだ。
そのとき招聘元が「指揮者の変更では払戻しの義務はない」として多くのファンを失望させた(個人的には怒るのが当然だと思う)のだが、当時その事務所で電話番のアルバイトをしていたわたしは、お客さんからの問合せや苦情の電話を社員に取りつぐ日々となった。いったい何度「マリス・ヤンソンス」と口に出したことか。
しかしヤンソンスは健闘して、来日公演を好評のうちに終わらせた。そしてこれがきっかけのように、レニングラード・フィルやオスロ・フィル(79年から首席指揮者)とのCDが発売されるようになり、着実な評価と人気を得はじめたのである。
「BBC Concert」では、80年代後半のオスロ・フィルとのライヴを2週続けてお送りする。しかもその一つは、86年の来日の1か月前の演奏会だ。どんな演奏が聴けるだろうか。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年06月①/第11回 みんなが宇宙に興奮したころ
2005年06月①/第11回 みんなが宇宙に興奮したころ

あれはNASAの壮大なまやかしだったと主張する人さえいる。しかし私は、当時小学1年生だった自分が1969年7月20日のアポロ11号月面着陸の日に味わった、あの興奮が嘘だったとはとても思えない、とだけはいえる。
それは「科学の勝利」だった。その興奮がどれほどのものだったかは、持ち帰られた「月の石」が、翌年の大阪万博のアメリカ館の展示物になって、数時間待ちの行列ができた(ただの小さな石を観るために!)という事実でもわかるだろう。
さて、それから約1か月後のこと。ロンドンでは41歳のコリン・デイヴィスが、ホルストの組曲《惑星》を指揮していた。
この曲は、ホルストが占星術からイメージを得て書いたものだった。しかしこの1970年前後から、宇宙時代(当時はそう信じられた)にふさわしい音楽として、作曲家が予想もしなかったような形での人気を得はじめる。その曲を、ビーチャムやボールトたちの世代以来、イギリスに久々に出現した俊英指揮者が指揮したのだ(彼がこの曲を指揮するのは、このときが生涯初めてだったという)。それは新時代の幕開けにふさわしい、若々しい活力にあふれた演奏だった。
ところが不思議なことに、デイヴィスはこの《惑星》をなかなかレコード録音せず、1988年になってやっと録音した。なぜためらったのか、わからない。私が思うに、《惑星》の本質は宇宙時代にはないと、彼は考えたのかも知れない。その興奮がおさまるまで、待ったのかも知れない。
しかし、若きデイヴィスによる《惑星》は、たとえ「時代の勘違い」が生んだものだったとしても、熱く、とても魅力的である。その火照りを、6月5日の放送でお楽しみあれ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年05月②/第10回 砂を捲いて再び来たる
2005年05月②/第10回 砂を捲いて再び来たる

エッシェンバッハがかつてはピアニストであったことは、多くの方がご存じだろう。いやむしろ、ピアニストが余技で指揮をやっている人という印象を、いまだにお持ちの方も多いかも知れない。
ピアニスト時代の彼は、1960年代以降めっきり減ってしまったドイツ出身の数少ない優秀なピアニストとして、メジャー・レーベルのドイツ・グラモフォン(DGG)に独奏や歌曲伴奏のレコードを数多く録音していた。ところが、1970年代に指揮者に転じ、1981年にチューリヒ・トーンハレ管弦楽団の首席指揮者となってからというもの、エッシェンバッハの録音はそれほど多くないのである。
いや、数の問題よりも、印象の問題かもしれない。指揮者への転向と同時に、dggの専属アーティストでなくなったことが大きいのだろう。華やかなメイン・ステージを離れた男、「都落ち」した音楽家というイメージがつきまとい、日陰者あつかいされていたように思う。
しかしそれからの彼は、チューリヒに続いてヒューストン、ハンブルクと安定したポストを保ち、そして2000年にパリ管弦楽団、2003年からはフィラデルフィア管弦楽団と、着実にステップアップして、ついにメジャー・オーケストラに地位を得るまでになった。いつのまにか、指揮者としての経験も30年を超え、プロとしてのキャリアはピアニストとしてよりも長くなっている。そしていよいよ日本にも、フィラデルフィア管弦楽団の指揮者として、間もなくお目見えする。
忘れられた男エッシェンバッハは、指揮者として捲土重来を成し遂げたのか。まずは「BBC Concert」でご確認あれ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年05月①/第09回 時間旅行はBBCで
2005年05月①/第09回 時間旅行はBBCで

皆様のご支持により2年目に入ったBBC Concertと、新番組として始まったばかりのBBC Recital。この2つの番組は、イギリスのBBC放送のアーカイヴズから音源の提供を受けている。
このアーカイヴズというのが凄い。1950年代以降のさまざまな録音がストックされていて、当方で検索して注文すると、あっという間に録音がCDやCD-R に収められて送られてくる。アーティストによっては、往時の活躍に比べてあまりストックされていない人もいるから、アーカイヴズ全体としてはまだ構築途上なのかもしれない。しかし、それでもすでに膨大な量があり、しかもきちんと管理されている。
このあたりはさすがに国営放送という印象で、民放ではなかなか真似ができないことだろう。
録音というものの面白さの一つは、さまざまな時代を一瞬に駆けめぐれることだと思う。われわれはどうあがいても、今この時を離れることはできない。しかし録音は、さまざまな過去を甦らせることができる。そうして現在と過去との関係を考えていると、未来の姿がおぼろげながら見えてくることがある。脳内時間旅行の醍醐味は、まさにその瞬間にある。
さて、5月1日と8日のBBC Concertでは、フィンランドの指揮者エサ=ペッカ・サロネンのコンサートをお送りする。1日は当時まだ27歳のサロネンが、最初の手兵となったスウェーデン放送交響楽団を指揮した1985年のライヴ。8日はそれから17年後、現在も音楽監督をつとめるロスアンジェルス・フィルハーモニックを指揮した、2002年のライヴ録音だ。
指揮者サロネンは、17年の歳月をどのように過ごしたか。それが聴きものだ。BBCのアーカイヴズだからこそ可能な時間旅行を、お楽しみに(今後放送ご希望のアーティストなど、ぜひリクエストをお寄せください。探してみます)
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年04月②/第08回 ヤルヴィ家の父子鷹
2005年04月②/第08回 ヤルヴィ家の父子鷹

巨大組織の世襲は、簡単なようでとても難しい。安定成長期ならいいが、混乱期になると無理と矛盾ばかりが露呈する。
では、芸能や芸術の世界はどうだろう。歌舞伎や落語の世界では、今まさに盛大な襲名披露興行が行なわれている。伝統ある名前に新たな花を添えるか、それともその重さに負けてしまうかは、彼ら自身の今後の精進にゆだねられている。何事も、結局は芸次第というわけだ。
クラシックの世界も同様である。「組織とその権力」を単純に相続するよりもずっと、個人の資質がむき出しに問われる。エーリヒ・クライバーの息子カルロス、アルヴィート・ヤンソンスの息子マリス、あるいは母方の姓を名乗った、アノーソフの息子ロジェストヴェンスキー、マルケヴィッチの息子カエターニなど、息子たちはみな自身の実力で地位を得ている。
エストニア出身の指揮者ネーメ・ヤルヴィの二人の息子たち、パーヴォとクリスチャンも、やはり自らの音楽性を頼りに活動の場を拡げつつある。ただ、ヤルヴィ家が他の「父子鷹」指揮者たちとちょっと違うのは、父も現役で、息子たちに負けじとばかりの健在を示していることだ。こういうケースは珍しく、また微笑ましい。それぞれのさらなる活躍を祈ろう。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年04月①/第07回 プレヴィンを指揮者にしたオーケストラ
2005年04月①/第07回 プレヴィンを指揮者にしたオーケストラ

指揮者アンドレ・プレヴィンとロンドンとの関係は、レコードで始まった。
1960年代の初めまで、プレヴィンはハリウッドのミュージカル映画や、ジャズ・ピアニストとしての活動をメインにしていた。クラシックの分野にも本格的に参入したいと思っていたけれど、アメリカのクラシック界というのは、こういう「闖入者」に対して意外なほどに頭が固い。なまじプレヴィンの名前が売れているだけに、活動の場は限られていた。
それにアメリカのオーケストラは、ドルが強い(まだ1ドルが360円に固定されていた時代だ)せいもあって、レコーディングに起用するとやたらに金がかかる。そこでマネージャーとレコード会社が考えだしたのが、イギリスのオーケストラ(ドルが強いから割安で雇える)を使ってプレヴィンのレコードをつくり、それを「既成事実」にして、指揮者プレヴィンを認めさせてしまおう、という戦法だった。
というわけでプレヴィンは1965年にロンドン交響楽団(LSO)を指揮して、レコードを何枚か録音した。ところが思わぬ副産物があった。LSO自体がプレヴィンの力量と魅力にほれ込んでしまい、なんと首席指揮者に招いたのである。録音から3年後の1968年のことで、まさに「瓢箪から駒」が出て、プレヴィンは長い歴史を誇るオーケストラのシェフになったのだ。
ちょうど不倫騒動(妻がいたのに女優のミア・ファローと懇ろになった)でアメリカにいづらくなったプレヴィンはイギリスに移住、LSOとの活動に全力を傾注することになる。 そして聴衆から熱狂的な人気を獲得、1979年までその地位に留まり、以後もLSOから桂冠指揮者(名誉指揮者)の称号を与えられて、密接な関係を保っている。LSOは、プレヴィンを「クラシックの指揮者」にしたオーケストラなのである。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年03月②/第06回 聖週間に《パルジファル》を
2005年03月②/第06回 聖週間に《パルジファル》を

しかしよく知られているように年末の「第9」というのは、欧米では旧東独などに例があるくらいで、ほぼ日本独自の習慣である。では、ヨーロッパで特定の時期に結びついた作品は何か。バッハなどの教会音楽(特定の祭日のための作品が多いのだから当然だ)とともにあげられるのが、春の聖週間(復活祭前の1週間)の前後に上演される《パルジファル》だ。
これは作曲者ワーグナーが意図したことではないが(彼はこの作品の上演を夏のバイロイト音楽祭だけに限定するように遺言していたから、春には上演できない)、作品中に聖金曜日(キリスト受難の日)が出てくるため、作曲者の著作権が切れた1914年以降は、各地の歌劇場が聖週間に上演するようになった。
今年の復活祭は3月27日、聖週間はその前の20日からということで、「BBC Concert」でも20日と27日の2週間にわけて、《パルジファル》をお送りする。指揮はラトルで、2000年のプロムスでの演奏会形式のライヴ録音だ。
オーケストラはロッテルダム・フィルだ。これは「?」と思われる方もおられるだろう。実は彼らはアムステルダムのネーデルランズ・オペラの歌劇場オーケストラとしても活動しており、この《パルジファル》も、元はそこでラトルの指揮によって上演したプロダクションなのである。2001年には《トリスタンとイゾルデ》もラトルは指揮している。つまり、オペラのオーケストラとして、ラトルが最も信頼する楽団の一つなのだ。
なおラトルは、今年1月にウィーン国立歌劇場へこの作品でデビューを飾って大評判となったばかり。その原型とも言うべき5年前のこの公演では、どんな清新な演奏を聞かせてくれるのか。乞ご期待。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年03月①/第05回 40年目のリンパニー
2005年03月①/第05回 40年目のリンパニー

ロンドンのプロムスが始められたのは1895年、今からちょうど110年前のことである。その初めの50年間は、創始者のヘンリー・ウッドが指揮をしていた。
ウッドが1944年に亡くなった後、その「跡目」を誰が継ぐべきかで数年間混乱が続いたが、1950年、マルコム・サージェントがプロムスの常任指揮者になったことで、ウッドの後継者をめぐる騒動は片がついたのである。サージェントは以後1967年に亡くなるまでプロムスの主柱として活躍した。プロムスで演奏した作品は延べ2402曲、これはウッドに次ぐ第2位の曲数だそうで、まさにプロムスの「第2の顔」というにふさわしい。
3月6日と13日の「BBC Concert 」では、このサージェントによる演奏会と、彼を記念する演奏会とを続けて放送する。6日は1954年、つまり第60回目の年にサージェントが指揮した「ラスト・ナイト」。例年のお祭り騒ぎが楽しい「ラスト・ナイト」だが、そのスタイルは半世紀前にはすでに確立されていたことが、この貴重な録音でわかる。
13日の方はそれから40年後、第100回の記念年に開催された「サージェントに捧げる」演奏会。サージェントゆかりの作品が演奏されるが、面白いのは、40年後のこの演奏会にも1954年と同じソリストが参加していることだ。
そのソリストとはモーラ・リンパニー。1916年生まれで、イギリスを代表するラフマニノフ弾きとして有名なこの女性ピアニストは、ウッド時代の 1938年にプロムスへデビューしたという。1994年の演奏会は、彼女のちょうど60回目のプロムス出演にもあたっていたという。
40年の歳月を隔てて、同じピアニストの演奏を2週続けて聴けるなんて、まさに録音文化の醍醐味であろう。bbcのアーカイヴズの底深さは、ほんとうに素晴らしい。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年02月②/第04回 ロジェストヴェンスキー、バレエのように
2005年02月②/第04回 ロジェストヴェンスキー、バレエのように

ロジェストヴェンスキーは、指揮者として早熟の人である。デビューは1951年、ボリショイ劇場での《くるみ割り人形》のバレエ公演を指揮してのことで、この年の彼は20歳、まだモスクワ音楽院在学中の学生だった。1955年の音楽院卒業試験でも、プロコフィエフのバレエ《シンデレラ》をボリショイ劇場で指揮して教授陣を驚倒させ、その翌年に早くも同劇場の正指揮者の一員に迎えられたという。そして1957年には日本を初めて訪れたボリショイ・バレエ団に指揮者として帯同しているから、来日経験はすでに半世紀に及ぼうとしているわけだ。
1961年にモスクワ放送交響楽団の首席指揮者に就任してからは、コンサートとオペラを中心に活躍してきたが(欧米で「バレエ専門の指揮者」というのは、あまり尊敬されない存在なのだ)、その演奏の根本にあるのはやはり、バレエすなわち舞踏音楽の持つ躍動感である。実際、彼のコンサートの曲目にはバレエの全曲や組曲がしばしば含められている。バレエ音楽がけっして踊りの添え物ではなく、独立して楽しめるものであることを聴衆に伝えたい、と彼は思っているのではないだろうか。
確かに、20世紀音楽の歴史、特にその前半の歴史を考えるとき、バレエ音楽がはたした役割は大きい。ストラヴィンスキーの《春の祭典》他の作品やラヴェルの《ダフニスとクロエ》など、興行師ディアギレフがパリで上演させたバレエ音楽は、その後の時代に甚大な影響を与えた。それはドイツ流の交響曲中心主義とは別の、力強く活気にあふれたムーヴメントだった。オーケストラには、交響曲で発揮されるものとは異なる魅力、つまりもっと肉感的な運動性や色彩感が潜んでいることが、バレエ音楽をとおして提示されたのである。
ロジェストヴェンスキーは、オーケストラという「楽器」の、そのようなバレエ的な肉体性を聞かせてくれる指揮者なのだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年02月①/第03回 ノリントン、ライヴで聴かなきゃ意味が無い
2005年02月①/第03回 ノリントン、ライヴで聴かなきゃ意味が無い

レコード業界の人から、「ノリントンが売れなくて困る」という話を聞いたのは、今から10年くらい前のことだ。
当時は、アーノンクールにガーディナー、ブリュッヘンなどの「古楽器指揮者」たちが一躍脚光を浴び、ポスト・カラヤン時代のメジャー・レーベルの新たな金看板として次々とCDを発売、話題の中心にあった。ノリントンもその一人として、ヴァージンやデッカに録音していた。
それなのに、ノリントンだけはライバルたちに比べて、さっぱり売れなかったという。ただし、これは日本だけの現象で、本国イギリスはもちろん、ヨーロッパ諸国やアメリカでは逆に大人気だったのだそうだ。「なぜ日本だけ?」と欧米でも日本でも、首をひねっていたという。
ところが今、ノリントンは日本でも大きな話題を集める存在になった。2003年度のレコード・アカデミー賞の大賞をとったベートーヴェンの《合唱》交響曲を筆頭に、彼の指揮するCDはことごとく高い評価を受け、そしてとてもよく売れている。
人気急上昇のきっかけになったのは、2001年のシュトゥットガルト放送交響楽団との初来日公演だった。スタジオ録音ではわからなかった、彼の音楽の跳ねまわるような活力や、英国の指揮者の伝統ともいうべきユーモアのセンスが、実演でようやく日本の聴衆にも伝わったのである。ノリントンの魅力は、ライヴかライヴ録音でなければ、わからなかったのだ。
今回の放送では1992年と93年の、日本ではまださっぱりだった時期のライヴ録音をご紹介する。ピリオド楽器のロンドン・クラシカル・プレイヤーズと、20世紀楽器のロンドン・フィル、それぞれでどんな「活気とユーモア」を聴かせてくれるのか。さらに前者の演奏会には、ベートーヴェン自身の所有という1817年製のフォルテピアノも登場する。これも楽しみだ。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年01月②/第02回 1955年生まれのふたり、ヨーヨー・マとラトル
2005年01月②/第02回 1955年生まれのふたり、ヨーヨー・マとラトル
ヨーヨー・マが今年で50歳になると聞いて、「そんな年になったのか」と驚いた。
ばかな話で、こちらも同じぶんだけ年を取っているのだから、不思議でも何でもない。
「まだ20代半ばの、すごいチェリストが出てきた」と話に聞いたのは1980年頃で、それから四半世紀の歳月がすぎている。その時期に生まれた子供が当時のヨーヨー・マと同年齢になろうとしているのだから、かれが50歳になるのは当然のことだ。
しかし四半世紀たっても、ヨーヨー・マは変わることなく、世界のトップ・チェリストであり続けている。所属のレコード会社も変わらない。
一方、クラシックの世界は大きく様変わりした。かれを引き立て、レコード・デビューのチャンスを与えてくれたカラヤン(1979年録音のベートーヴェンの三重協奏曲で、ヴァイオリンは当時16歳のムターだった)も、もういない。
カラヤンが君臨したベルリン・フィルのシェフの座は、アバドを経てラトルに移っている。そのラトルは1955年生まれ、ヨーヨー・マと同い年だ。ラトルも、最初の大きなポストであるバーミンガム市交響楽団の首席指揮者になったのが1979年だから、ヨーヨー・マが華々しく活躍し始めたのと、ほぼ同時期ということになる。
スターであり続け、レコード会社が一貫して変わらない点も同じ。さらに言えば、1990年代からピリオド楽器の動向に関心を寄せ、自らの音楽に貪欲に取り入れ始めている点も、やはり一緒である。
こんなに共通点があるのに、どちらも所属のレーベル(ソニーとemi)が手放さないためか、レコード上で共演したことはない。しかし今回の「BBCコンサート」では、ライヴならではの両者の共演が楽しめる。
1984年、ともに次代を担う俊英音楽家として、期待をあつめた時期の録音である。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2005年01月①/第01回 プロムスのはじまり、オーケストラのはじまり
2005年01月①/第01回 プロムスのはじまり、オーケストラのはじまり
ニワトリとタマゴ、どちらが先か。これはむずかしい。
ではシンフォニー・オーケストラとオーケストラ・コンサートなら、どちらが先か。これは、答えがある。
オーケストラ・コンサートが先だ。楽器をもった連中が100人ばかり、目的もなくただ集まったとしても、どうしようもない。演奏会場と日時と演奏曲目が定められたもの、すなわちオーケストラ・コンサートで、楽器をひくために集められた連中が、やがてシンフォニー・オーケストラになるのだ。
イギリス史上初の常設のオーケストラも、そうして生まれた。 それまでは、コンサートがあるたびに集められ、終わればちりぢりになるだけだった烏合の衆が、初めて有機的な集団として、長期的に活動するようになった。それは、ロバート・ニューマンなる興行師が、ヘンリー・ウッドという指揮者と組んで、ロンドンのクイーンズ・ホールで、夏に大衆向けの廉価なコンサートをシリーズで開こうと考えたのが、はじまりだった。
安くするために平土間は席を取り払って、立見席だけにする。これはフランスで「プロムナード・コンサート」と呼ばれる方法だった。集められた音楽家たちは、会場の名前をとって「クイーンズ・ホール・オーケストラ」と呼ぶことにした。このシリーズが大成功して長期化したため、コンサートは「プロムス」と愛称がついて定着し、オーケストラの方も、イギリス初の常設オーケストラに発展することになるのである。
第1回の日付は、1895年8月10日。それからちょうど100年後の1995年8月10日、その第1回演奏会の模様が再現された。クイーンズ・ホールは第2次大戦で破壊されたためにロイヤル・アルバート・ホールに変わったが、往時を記念してニュー・クイーンズ・ホール・オーケストラと名乗った団体は、楽器を19世紀末のスタイルでそろえる徹底ぶりで聴かせてくれる。
山崎浩太郎(やまざきこうたろう)
1963年東京生まれ。早稲田大学法学部卒。演奏家たちの活動とその録音を、その生涯や同時代の社会状況において捉えなおし、歴史物語として説く「演奏史譚」を専門とする。著書に『クラシック・ヒストリカル108』『名指揮者列伝』(以上アルファベータ)、『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』(キングインターナショナル)、訳書にジョン・カルショー著『ニーベルングの指環』『レコードはまっすぐに』(以上学習研究社)などがある。
山崎浩太郎のはんぶるオンライン
 2011年7月/第90回(最終回) ナット・キング・コールの魅力
2011年7月/第90回(最終回) ナット・キング・コールの魅力
友人に誘われてカラオケに行ったとき、ナット・キング・コールのナンバーを歌ったりすることが多い。彼の「モナ・リサ」や「トゥ・ヤング」はふつうの店ならリストに載っているからだ。
それくらい彼の歌はポピュラーなのだが、彼はもともとすぐれたピアニストで、トリオを組んでからは弾き語りで成功し、「スィート・ロレイン」などのヒットを放ったことはよく知られている。
彼の影響力は結構大きくて、レイ・チャールスも最初トリオを組み、弾き語りでナット・キング・コール風に歌っていたし、ギターの弾き語りのジョン・ピザレリも最初はナット・キング・コール・ナンバーを歌って売り出した。カナダの弾き語り歌手だったダイアナ・クラールも最初の頃はよくナット・キング・コールのナンバーを歌っていた。
黒人のジャズ・ポピュラー・シンガーの中で最初にビッグ・スターになったのはナット・キング・コールではなかろうか。彼についでビリー・エクスタインやジョニー・マティスがビッグ・スターになっていったように思う。
ナット・キング・コールの初期のヒット「スィート・ロレイン」や「ストレイト・アップ・アンド・フライ・ライト」は、ちょっとジャイヴ風でユーモアがある。キャブ・キャロウェイに言わせると「俺がナットに白人風にきれいで明快な発音をしろ、と言ってから彼の歌はヒットしたのだ。『モナ・リサ』が大ヒットしたのは、俺の教えを実行したからだ」と記録映画『ミニー・ザ・ムーチャー・アンド・モア』の中で語っている。
ナット・キング・コールの魅力とすごいところはどこにあるのだろうか。彼は1950年代にポップ・ソングを歌い数多くのヒットを放ったが、ジャズ歌手のようにはくずさずに比較的ストレートに歌っている。しかしとても味わいがあり、彼が歌うと、ただのヒット・ソングがスタンダード・ソングとして後世にまで歌い継がれていくようになる。そこが彼のすごさだと思う。「モナ・リサ」「ネイチャー・ボーイ」「トゥ・ヤング」「スマイル」「ラブ」「オレンジ・カラード・スカイ」「ザ・クリスマス・ソング」など、多くのポップ・ヒットが、彼が歌うことによって後世まで歌い継がれるスタンダード・ソングになっている。
少し前に中古レコード店で「COLE&CO.」というナット・キング・コールのデュエット集CDを見つけて買い、「PCMジャズ喫茶」で彼とディーン・マーティンの「ロング・ロング・アゴー」と、夫人のマリア・コールとデュエットした「月光価千金」をかけた。このCDにはナットが歌でデュエットしたものと、ピアニストとして歌手と共演したものが収められている。彼のピアノでアニタ・オディが「エイント・ミスビへイヴン」を歌ったり、メトロノーム・オールスターズやジューン・クリスティと共演したナンバーなども聴ける。
番組でかけた、歌手で夫人のマリア・コールとデュエットした「月光価千金」も聴きもので、この曲はキャピトルのバージョンがよく知られているが、そちらはナット・キング・コールのソロである。このマリアとナットの間に生まれた娘がナタリー・コールというわけだが、歌のうまい両親の子だから当然ナタリーもうまい歌手だ。ただナタリーはナットの娘という目で見られるのが嫌で、30歳を超えるまでは意識して父親のレパートリーには手をつけなかったという。しかし、年と共にそのこだわりは薄れ「アンフォゲッタブル」で父ナットと時を超えるデュエットを行い大ヒットさせた(その年のグラミーも受賞している)。その印税の一部を寄付したのだろうか、NYのハーレムには『ナット・キング・コール通り』が生まれている。
ところで、ナット・キング・コールと夫人マリア・コールの出会いも面白い。彼女はもともとデューク・エリントン楽団の専属歌手で、マリー・エリントンの名前で歌っていた(RCAに録音があるがエリントンの親戚ではない)。エリントンの伝記を読むと、ある時から毎晩のようにナット・キング・コールがエリントン楽団の演奏を聴きに来るようになったので、いつから俺のバンドが好きになったのかと喜んでいたら、ある日突然専属歌手のマリー・エリントンがいなくなり、その日からナットも姿をみせなくなったという。「ナットの関心は俺のバンドではなく彼女だったのかと、なんだかおかしくもあり、ほほえましく思った」とエリントンは回想している。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2011年6月/第89回 目の上のタンコブ
2011年6月/第89回 目の上のタンコブ

このところ本欄にミュージックバードのディレクター、太田氏の登場が多くなった。
別に私と親密感が最近いよいよ高まったとかそういうことではなく、彼、62才にして諸楽器の中でも最難関といわれるトロンボーンを始めたからである。
少し前のこのページでもそのことはお伝えしたが、大抵の楽器志望者は、最初の勢いはどこへやら、途中で、いやほとんどの人が始めるやいなや、すぐに挫折して果てる。
これは決定的な事実で99%の人が楽器とバイバイしてしまう。100人に一人、いや1000人に一人というがんばり屋が実に太田さんなのである。これが書かずにいられるか、てなものである。
太田さんはなぜがんばるのか。大概の男性楽器志望者は、よこしまな、いや本能に従った立派な理由、つまり女にもてたいという切なる希望で血を吐くような練習にはげむが、太田さんはこれとは少し違う。
彼にはライバルがいるのである。そのライバルとは、この人も以前このコラムに登場し、「PCMジャズ喫茶」にも度々ゲスト出演している『ジャズ・キャブ』の藤田さんである。
ことのついでに藤田さんを紹介しておこう。東京には聞くところによるとジャズを流すタクシー、要するに移動ジャズ喫茶みたいなタクシーが3台ほど走っているらしい。四六時中ジャズを流して、時にはお客のリクエストにも応じるというが、当然ひまな時間もあるわけで、その時間を有効に使って藤田さんは車中でトロンボーンの練習に熱中する。ぴったり窓を閉めれば、これほど音が外に漏れない格好のサイレント・ルームはなく、かんじんの走行業務より楽しいものだからついつい練習に身が入り、結果、上達の塩梅も著しいというわけだ。
一方の太田さんは自宅で練習する。こちらも防音には気を使う。なにしろトロンボーンは音が大きい。昼間から雨戸を閉め立てるが、どうがんばってもタクシーのように完全密閉というわけにはゆかず音の漏れが気になってしまう。楽器の上達は練習あるのみなのに、思いどおりに事は運ばず切歯扼腕の態なのだ。
二人は美人トロンボーン奏者、志賀聡美の門下生である。前にもお伝えした通り月一回開かれるメグの『トロンボーンを楽しむ初心者の会』で顔を合わせる。席は決まって向かい合わせに座る。トロンボーンという楽器は、トランペットと同様にベルが前方を向いていて、吹いている本人の音よりも目の前の人の音の方がよくわかる。
目の前にいる“目の上のタンコブ”が吹き出す美麗な音に、毎回太田さんは悔し涙にくれていた。
そんな悲しみの日々が半年も続いたろうか。とある日の『トロンボーンを楽しむ会』。私は久しぶりに太田さんのソロを聞いた。始めて半年だから曲といえば「カエルの唄」がせいぜいだろうとふんだが、彼はなんとチャップリンの「スマイル」を吹き出したのである。さすがにまだ流暢というわけにはゆかないが堂々たる吹きっぷりで、わずか半年でこれだけ腕前を上げるとはどれだけ艱難辛苦の日々が続いたのだろう。
歓声を上げつつ打ち鳴らす藤田さんの拍手が優しかった。
さらなる進歩を願って、私から曲のプレゼントをしよう。J.J.ジョンソンを“目の上のタンコブ”として励み、スウェーデン、いや北欧、いや世界のトロンボーン名人の一人になったオキ・ペルソンの「ベサメ・ムーチョ」だ。
(ディレクター記)また自分がネタにされてしまいました。ほとんど“ほめ殺し”状態ですね。でも寺島さん、私にも“よこしまな”気持ちも充分ありますよ、隠してるだけで。それから、お願いですからソロをリクエストするときは私が“しらふ”の時にして下さい。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2011年5月/第88回 フランク・シナトラのそっくりさんたち
2011年5月/第88回 フランク・シナトラのそっくりさんたち
フランク・シナトラは一世紀に一人しか現れない大歌手と言われたりする。いやそれどころか、彼に匹敵するシンガーなど絶対に現れないだろうと僕は思う。
歌がうまいのはもちろんだが、人間としての存在感がほかの歌手とまったく違う。背おって歩いてきた人生の重みが違うのだ。真のスターでありエンターテイナーである。
だからスキャンダルで何度か危機を迎えたが、それを乗り越え、決して消されることはなかった。スキャンダルによって消されないのが本当のスターなのだ。
彼はマフィアとの繋がりがスキャンダルのネタにされたこともあった。少々意地の悪い伝記作家キティ・ケリーが、シナトラの伝記を書くと発表しただけでこの作家を名誉毀損で訴えたが、まだ発表されていないという理由でシナトラ側の敗訴となった。この本は日本でも出版されたが、たしかに彼の私生活をあばき立てていた。
ところで先日イギリスの歌手による『シナトラを歌う!ゲイリー・ウイリアムズ』(SSJ)というCDがでたので、この中の「アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン」をPCMジャズ喫茶でかけた。
声はシナトラよりやや細い、明るくクリアーだがバックのオーケストラのアレンジもネルソン・リドルそっくりなので一層シナトラ風に聴こえるのである。ゲイリーはイギリスでは著名で、この『シナトラを歌う!』が10枚目のアルバムというから、彼は決してシナトラのそっくりさんで商売しているわけではない。シナトラが好きなのでシナトラの愛唱歌集を吹き込んだのだろう。
だからそっくりさんを目指すいやらしさはない。すっきりした嫌味のない歌い方だ。好感はもてるがシナトラと比較してはかわいそうだ。シナトラは女性遍歴も多彩だったし、人生の酸いも甘いも味わい尽くし、重い荷物を背おって歩いてきた人生がその歌に反映されている。深い表現には他の歌手は太刀打ちできないのだ。
うまい歌手には、シナトラが最初目標にしたビング・クロスビーもいたし、同じか少し遅れて現れた人気歌手にはペリー・コモもいた。しかし、シナトラに関する本は何十冊も出版されているが、ビング・クロスビーの本は数冊しかなく、ペリー・コモにいたっては1~2冊しか僕は知らない。二人は真面目人間で、大きなスキャンダルもなく、話題にする話がないからだろう。
僕がニューヨークにいる時、フランク・シナトラが亡くなった。すると一週間後くらいから、ゴシップ誌、ライフ、音楽誌、新聞が一斉にシナトラを特集したので、それを全部買って日本に持って帰った。その中で一番面白かったのが「シナトラが愛した12人の女と憎んだ20人の女」というゴシップ誌の記事だった。シナトラの面目躍如である。
さて、次の週のPCMジャズ喫茶ではもう一人のシナトラそっくりさんのスティーヴ・ローレンス『Steve Lawrence Sings Sinatra』(GL Music)を持ってきて、この中の同じ曲「アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン」をかけた。スティーヴのほうがゲイリーよりもっとシナトラに似ている。声も男性的で力強く、シナトラに間違えかねないほどよく似ている。
寺島靖国氏もスティーヴは好きだという。スティーヴのシナトラ好きはシナトラ公認であり、このCDのジャケにもシナトラと並んで笑っている写真が掲載されている。編曲もまたネルソン・リドル風だ。スタジオでの写真にはスティーヴの夫人のイーディー・ゴーメの姿も写っている。この夫妻はデュエットのレコードも沢山作っており仲の良さでも有名だ。
スティーヴの方も愛するシナトラに敬意を表するために作ったCDであって、そっくりさんで商売しようとしているわけではないので好感がもてる。
7~8年前頃だろうか、N.Y.のブロードウェイでミュージカル・ショウ「Dear Sinatra」が上演されていた。シンコッティはこのショウに出ていた一人なので、そっくりさんとはいえないが、シナトラのレパートリーを歌ってきた歌手の一人だ。またハリー・コニックJr.はピアノの弾き語りだが、シナトラがレパートリーにしてきた古いスタンダードが得意だし、シナトラにあこがれ、シナトラのように映画でも成功したいと考え、何本かの映画に出演してきた。うまい歌手だが日本ではあまり人気がないのか、500円以下といった中古CDコーナーに沢山彼のCDが残っている。
これからもシナトラをめざす歌手は何人か現れるだろう。それを聴くのもひとつの楽しみだ。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2011年4月/第87回 ジョニ・ジェイムスにキスした(された?)男
2011年4月/第87回 ジョニ・ジェイムスにキスした(された?)男

思い出せば約20年前、熱烈な恋をした。
片時もそいつのことを忘れたことはなく、歌をうたうやつだったので、夜中になるとよく一緒にデュエットした。
一番頻繁に歌ったのはホーギー・カーマイケルの作った『The Nearness Of You』で、すっかり歌詞を憶えてしまい、今歌ってみろといわれれば「ほいきた!」とリクエストに応じることが出来る。
そういえば先日の新聞で、女優の山口智子さんがインタビューを受けていた。「一番好きなことは何ですか?」と訊かれて、「好きな人のそばにいること」と答えていた。あっ、『The Nearness Of You』だと即座に笑ってしまった。昔から知的なムードを漂わせた頭のいい女性で、彼女を恋人にしたかったが他の男に持っていかれた。
山口智子の話しではなかった。
熱烈な恋の相手というのはジョニ・ジェイムスである。
シュテファン・ツヴァイクの書いた短編集に『アモク』というのがあるが、これは熱帯性気候の地域に発生する特殊な熱病で、これにかかると24時間密林の中を走り続け、2日目にばったり倒れて死に至るという恐ろしい病気だ。私のジョニ・ジェイムスに対する愛はまさに『アモク直前』、よくぞ倒れて死ななかったものだ。
1950年代にアメリカに出現した美人歌手で、最初ダンサーになるつもりだったが、運悪く(私には運良くだが)足をくじいて歌手に転向した。そして幸運が訪れ“アメリカの恋人”といわれるようになった。MGMからレコードを40枚出しているが、私はそのすべてを買い集めた。コンプリート・コレクションは後にも先にもジョニ・ジェイムス一人である。
どこにそんなに惚れたのかって?あんたねぇ、野暮な質問はしっこなしにしようよ。惚れたから惚れたんで、どこになどという解析はまったく不毛なのだ。
しいていえば、声。彼女の声を聞けば、他のどんなボーカリストの声も蛙声にしか聞こえない。
それから目。彼女の目を見れば、他の女の目はすべてトカゲ目だ。
私は彼女の声を聴いてボーカルに開眼した。それまではボーカルは女子供のなぐさみ物と思っていた。ボーカルを聴く奴の顔を恥ずかしくって見られなかった。昔から今に至るまで原稿を書くことほど嫌いなことはないが、彼女のことだったら幾らでも書ける。惚れた当時、書きまくった。それらを見て岩浪洋三さんが言ったものである。
「彼女のことなんかとっくに知っていて僕なんかよく聴いているよ。」
なら書けばいいのに書かない。私ほど情熱がなかったのと、当時は白人女性歌手など毛ほどの価値もなく、もっぱらエラ・サラ・カーメン全盛時代。
ジョニ・ジェイムスのことなどを吹聴すれば、ボーカルのわからないエロじじい扱いされるのが関の山だった。私はそんなの平気だった。悪態つきたい奴はつけ。惚れてしまったらこっちの勝ちよ。
そういうジョニ・ジェイムスにキスした男がいるのである。アメリカ人ならまだしも日本人である。しかも私の知り合いだ。
ディスク・ユニオンの菊田有一氏がその極悪犯だ。
八つ裂きにしてもあき足りないその菊田有一が、今回PCMジャズ喫茶に出演した(3月5日放送)。当然その話題が出たが、マイクの前なので公式的な発言しかしない。DIWとの契約でシカゴまで彼女に会いにいき、帰り際に握手をして別れたという。
何が握手だ!
番組の録音の帰り、四谷に出て、酒をのみ、自由になると、どうだ。
「帰り際に彼女は自分にキスしてきた」と言うのである。
それほどの男には見えないがねぇ。ジョニ・ジェイムスもカンが狂ったのだろう。長い女の一生、そういう日もあるということだろう。後で彼女、一生の不覚と思ったに違いない。「私としたことがどうしたことだろう。わけのわからない東洋人の男と、何ということをしでかしてしまったのだろう・・」洗面所に行き、オキシドールを探し、脱脂綿にひたして唇をなんどもぬぐった。しかし何度ぬぐっても肉体的なけがれはともかく、精神的なけがれは落ちない。よって1980年某月某日は彼女にとって最悪な人生の一日になったはずである。
ああ、少しすっきりした。
(ディレクター記)
菊田氏は「あのキスはあくまで交通事故みたいなもの」と録音後の飲み会でしきりに弁解していましたが、その現場の様子を実にリアルに描写したのが、寺島氏の怒りの炎にさらなる油を注いだようです。写真のツー・ショットは事前のものか事後のものかは不明です。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2011年3月/第86回 イタリア系テナー、ジョー・ロヴァーノの魅力
2011年3月/第86回 イタリア系テナー、ジョー・ロヴァーノの魅力
ミュージックバードの番組出演を、体調を崩して休み、関係者や出演者に多大の迷惑をかけたが、1月16日に2ヶ月ぶりに退院し、1月31日にやっと復帰出演した(2月19日放送)。寺島靖国氏やAさん、それにゲストでドラマーの諸田富男氏の元気な姿に接し、なにか自分にも生気が戻ってきたようだ。
ただ復帰出演といっても古いCDや日本盤だけ持っていっての出演ではいささか無責任である。
それで2ヶ月ぶりに吉祥寺の輸入レコード店に足を運び、輸入CDを数枚買った。家で試聴すると、それほど当て外れのものはなく、早速録音日に持っていき、2枚ほどかけた。
その中の一枚がテナー・サックス奏者のジョー・ロヴァーノの『バード・ソングス』である。ロヴァーノは名前で分かるようにイタリア系の白人テナーで、もっぱらニューヨークで活躍している。
ただ、日本では不思議とあまり人気がない。彼の最高傑作『ジョー・ロヴァーノ・プレイズ・カルーソー』(Capitol)が日本で発売されていないからだろうか。 日本で白人のテナー奏者といえば、エリック・アレキサンダーやグラント・スチュアートの方が人気が高い。レコード会社の売り出し方がうまいからかもしれないが、アメリカではジョー・ロヴァーノの方がずっと人気がある。イタリア系ミュージシャンは人なつっこいところもあり、ライヴのやり方がうまいからかもしれない。また彼のよく歌うスケールの大きなテナーは、一度ライヴを聞くとファンになってしまうところがあるが、彼は意外と来日が少ないので、日本では人気が上がらないのか もしれない。
僕はロヴァーノが好きで新譜が出ると買うことにしている。今回の新譜『バード・ソングス』では、チャーリー・パーカーのオリジナルや愛奏曲を集めて演奏している。パーカーはアルト・サックスでロヴァーノはテナー。ちょっと違和感を持つ人がいるかもしれないが、昔ソニー・ロリンズに『プレイズ・バード』(Prestige)というアルバムもあったし、少し前に日本のテナー奏者川島哲郎もパーカー愛奏曲集を吹き込んでいた。要は演奏次第ということになる。
今回のロヴァーノはちょっとひねった演奏もみせるが、よく歌っているのと、ユーモアのセンスが生きているのがいい。
僕は『バード・ソングス』の中からパーカーのオリジナル・ブルース「バルバドス」を選んでかけた。パーカーはこの曲をサヴォイに録音しているが、西インド諸島のバルバドス島をテーマにした曲である。ラテンの国ということで、この曲はラテン・リズムを用いて演奏されることが多い。パーカーの演奏もそうだったし、今度のロヴァーノもラテン・リズムを用いて演奏しており、ドラマーのほかにパーカッションも参加、メンバー・クレジットにはラテン系の名前のメンバーも見られて、エキサイティングな本場のラテン・リズムのよさに感心した。ロヴァーノ嫌いの寺島氏も珍しくこの盤のロヴァーノは気に入ったようだった。
パーカーのオリジナルとパーカーの存在は不滅だ。
今回の入院中、僕がよく聴いたのがチャーリー・パーカー、デューク・エリントン、ルイ・アームストロングのCDだった。この3人の演奏はいくら聴いてもあきがこないのだ。
パーカーのアルトはシンプルで、暖かく、音の魅力も大きい。パーカー以前のアルトはジョニー・ホッジス、ウイリー・スミス、ベニー・カーターと、比較的線の細い、女性的な音の人が多かったが、パーカーはアルトを力強く、男性的に吹いた最初の人ではなかろうか。
さて、この録音日の寺島さんは風邪をひいていて、自身で「日頃の美声がそこなわれて」などとのたまっていたが、むしろ低音の魅力が出ていたように僕は思ったのだが......。
なお、この日の夜は高田馬場の「コットンクラブ」でジャズ界の新年会があるというので、寺島氏、Aさん、それに迎えにきてくれた越谷政義氏とパーティーに出かけた。ディレクターの太田氏も後からかけつけた。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2011年2月/第85回 こんなアルバムがあってもいい
2011年2月/第85回 こんなアルバムがあってもいい
病を得た岩浪洋三さんが元気になられ、一時退院された。目出度いことなどまるでなかった私の今年の正月だが、このことが唯一お目出度いことだった。
退院祝いはぜひ当店でと申し出た飲食店があるというから、いやすばしこいというか、商魂たくましいというか。広い店を持っていたら私も商戦に加わっていただろう。
その岩浪さんから以前聞いた話だが、オーディオ評論家は大抵の人が私のことを嫌っているらしい。
なぜだろう。思い当たることは、私がことあるごとにオーディオとはもっと楽しいものだ。そんな大それたホビーではないんだ。楽に気軽に音を聴こう。など広言しているからだ。
オーディオ界の先生方にしてみれば、もっとシリアスにオーディオを扱ってゆきたいところだろう。私と違って『その道』を極めた方たちだから、そんなに簡単なものに思われては困ると。
わかります。
すみません。
そうしたオーディオ評論家の中で、ほとんど唯一私と口をきいて下さる方が林正儀さんである。林さんを「PCMジャズ喫茶」にお招き出来たのはうれしいことだった。
もうおひと方は誰にお願いするか。当番組のヘビー・リスナーであり、胸に一物、手に二物(?)ある横須賀のあの方、といえばもうどなたも先刻承知の三上剛志さんである。久しぶりにオーディオ話が激して私は興奮した。
おのずと3人の話が長くなり、ディレクターの太田さんによると番組の冒頭から50数分間曲がかからなかった。これは故安原顕さん時代の48分という従来の記録を破る新記録だとのこと。
ジャズ・ファンの方、申しわけなしである。
まあ実際の激論(?)ぶりはオン・エア(1月8日)の通りだが、今思い出してよかったなと思うのは、私がお二人に質問した「いい音とは?」である。
林さんは実際のオーディオ運用面からいろいろ発言して下さった。三上さんはたしかご自分の人生におけるオーディオの音とは、みたいなお話だったと思う。
言い足りないことがあったらしく、ご自分のホームページで詳しく開陳されているという。これらも要参照である。(私はパソコンの類を一切やらないのでわからないのである。)
結局その日は私も10枚ほど選んでいったが、1枚かそこいらしかご紹介出来なかった。
番組収録後、すぐに林さんと三上さんから「言い足りないことが多かったし、もっと曲をかけたかったので、リターンマッチをやらないか?」とのお誘いがあり、勿論二つ返事でOK。
で、1月22日の放送はお二人の再登場になった。
今回登場のアルバムは必ずしも適切であるとは思えないが、いや申しわけないという選曲なのである。
どうも本日は謝ってばかりいるが、それというのも私がかかわっている「寺島レコード」の4月新譜なのだからいささか身の縮む思いなのだ。
ただ、言いたいことは一言、ミュージシャン凄し、なのである。
『オール・アバウト・ベサメ・ムーチョ』という一枚を企画した。全曲「ベサメ・ムーチョ」である。
ミュージシャンは11人。一人一人彼らの都合に合わせて録音していたら莫大なお金がかかるので、「今までのアルバムの各録音の度に、番外でこの曲を追加演奏してくれ」と頼んだのである。
凄いのは、OKとばかり、パッとその場でプレイしてしまうことである。
まあこの曲を知らないミュージシャンはいないから当然だろうという声も聞こえるが、その場で瞬間的に自分の「ベサメ・ムーチョ」にしてしまうのがさすがプロの音楽家。というわけで別種、別雰囲気の11通りの『ベサメ・ムーチョ』が出来上がった。
あらかじめ企画の趣旨を話し、アレンジなど考えていたら、こういう自然発生的なプレイは生まれなかったろう。自然発生がジャズという音楽の一番あらま欲しきことなのである。
今回番組では、内田光昭さんのトロンボーン演奏で皆さんのご機嫌を伺った。
(ディレクター記)
アルバム・ジャケットはまだできてませんが、かなり“官能的”なものになるという噂が....。だって「ベサメ・ムーチョ~たくさんキスして」ですからねー。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2011年1月/第84回 岩浪洋三の強さ
2011年1月/第84回 岩浪洋三の強さ
岩浪洋三さんはジャズ界でいちばん偉い人だが、岩浪さんの凄いのは絶対に威張ったり自慢したりしないことだ。自慢など聞いたことがない。
人間は、特に男は60才を過ぎたら自慢したくて仕方がない生き物に生まれ変わるのである。なぜなら未来は少なく過去だけは豊富にあり、その中で特に大きく記憶に残っているのが栄光の時代だからである。
我々には努力しなければいけないことがたくさんある。その中でも特に大事なのは、自慢しないことなのだがこの抑制がむずかしい。出すまいと思っても酒などを飲むとつい気持ちよくふっと出てしまうのが自慢なのだ。自分は気付かず他人が気付くのが自慢なのだから始末が悪い。
ちょっと講釈が長くなったが要するに自慢とは無縁の人が岩浪洋三さんということを言いたかった。
そういう岩浪さんだが、たまにふと自慢めいたことを口にすることがある。
「いやあ、昨夜はライヴハウスを3軒はしごしたよ。六本木へ行ってそのあと目黒へ行って、最後は吉祥寺でしめたんだ。酒、しこたま飲んでね。きつかったけど楽しかったよ。」
「北海道へ行ってね。向こうの連中と一気飲みをやったんだ。雰囲気出ちゃってスキャット歌って、翌日朝一番の飛行機で東京に戻ってその足でPCMジャズ喫茶出演なんてちょろいもんだよ。」
これ、自慢というより、言ってみれば健康の押し売りである。岩浪さんの誇りは健康第一にあるのである。普通の人は健康第一なら節制するだろう。しかし岩浪さんは健康を維持、そして倍増するために頑張って無理を重ねてしまったのである。
その結果が入院となった。
少し前に練馬にある大学付属病院に入院中の岩浪さんをお訪ねした。岩浪さんは何をしていたとお思いだろうか。
原稿を書いていたのである。
こういってはなんだが原稿書きというのは健常者にとっても大変にきつい作業である。それを平気な顔をして書いておられたから、これは当然元気に決まっている。同行の太田ディレクターと顔を見合わせ、これはひとまず安心だわい、と。
ネマキ姿の岩浪さんは初めてだが、ネマキを着ていてもやっぱり岩浪さんは威厳を失わない。凄いことだと思った。少し面やつれしていた。それは仕方がないだろう。岩浪さんの普段の食事は肉である。三食肉だらけといってもいいほどの肉食獣、いや肉好きである。それが一挙にカロリーゼロに近い病院食。ちなみに病院食は治療食などと称して、費用をけちり病気の直りを遅くしている傾向がなきにしもあらずだ。
「今ね、肺に水がたまってドレーンに抜いているんだ。」
岩浪さんの脇腹のところからビニールの細い管が出ている。時々黄色い液体がツツーとしたたり落ちる。
「ひょっとしたらリンパのガンかもしれないって医者は言うんだけどね、だけどこんだけの歳だろう。進行が遅々としてはかどらないんだよ。そこがめっけものだよね。」
そんな深刻な話をしながら岩浪さんは口許にエミを浮かべている。
「そうですよ岩浪さん、世の中には45才でガンにかかって今だに生き延びてのさばっているやつがいますからね。私ですけど。」
そういえば私、ガンを宣告された時、ジャズなど聴く気になれなかった。うずくまってひたすら我が身の不幸を嘆いていた。
しかし岩浪さんは変わらず耳傾けているというのである。CDを病院に送らせているらしい。精神力の弱い私でさえガンから生還したのだから、精神力の強い岩浪さんが勝たないわけはないのだ。
さらにこの一発。ポリー・ギボンズの強力肉食的発声ボーカル『マイ・フェバリット・シングス』を岩浪さんに贈りたいと思う。まだガンと決まったわけではないが、この一曲を毎朝起きがけに聴いたら病気などたちまちどこかへすっ飛んでしまう。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2010年12月/第83回 歌はストレートに歌うにかぎる
2010年12月/第83回 歌はストレートに歌うにかぎる

日本の歌手の中には、無理にくずして歌って個性を出そうとする人も多いが、人間の声は千差万別であり、ストレートに歌っても、自然と個性はにじみ出すものである。無理なくずし方をして個性を出そうとする必要などないのである。
ストレートに歌って、すてきな個性を発揮した歌手は1950年代に多かった。ドリス・デイ、ジョー・スタッフォード、ローズマリー・クルーニー、ダイナ・ショア、ジョニ・ジェイムス、フランク・シナトラ、ディック・ヘイムズらがその代表。マーガレット・ホワイティングもその一人だった。
マーガレットは一度も来日公演を行ったことはないが、以前、日本のラジオ局の朝の番組で、彼女の歌う「グッド・モーニング・ミスター・エコー」が長くテーマ音楽に使われていたことがあり、それなりにその名は通っていたのではないかと思う。
ただ、僕が50年代に聴いた彼女の歌で最初に惚れ込んだのは「ア・トゥリー・イン・ザ・メドゥ」で、日本でもこのキャピトル盤はキングからSP盤で発売され、買って聴いた記憶がある。
その後もずっと彼女に関心を寄せ、LPを買っては聴き、いつも素直にストレートに歌っていてる様子が気に入った。中でも好きな一曲が、チェット・ベイカーも歌っている映画「虹の女王」の主題歌「ルック・フォー・ザ・シルバー・ライニング」だった。
一度彼女の生のステージを聴きたいと思っていたところ、偶然そのチャンスが巡ってきた。
1970年代の中頃だっただろうか、ニューヨーク五番街近くの52丁目の銀行前の舗道で、昼休み時間に、彼女の無料ライヴがあるという情報を得てかけつけた。
一時間ほど、うっとりと彼女の歌に聞き惚れたあと、ステージを降りてきた彼女に話しかけると、いやな顔もせず10分ばかり立ち話に応じてくれた。
日本には一度行って赤坂のクラブで歌ったことがあるという。また「私は歌手になるつもりはなかったのに、作詞家の父のところに作詞家で歌手のジョニー・マーサーがよく遊びにきていて、こんどキャピトル・レコードという会社を立ち上げるのだけど、歌手が足りないのでお前歌手になれ、と強引に歌手にされてしまったの」とデビューの裏話を聞かせてくれた。
彼女の歌はキャピトルで何曲かヒットし、スター歌手に育っていくことになる。
その後もマーガレット・ホワイティングとはニューヨークで二度ほど会ったり、歌を聴いたりしたことがある。一度はキャバレーに出演していた時。とても温かい和やかなステージだった。スタンダード・ナンバーにおしゃべりを交えながら淡々と歌っていた。終わってから挨拶にうかがったら、以前銀行前のライヴの時会ったのを思い出してくれた。記憶力もいいようだ。
アメリカでは歌手が年輪を重ねると、ローズマリー・クルーニーやバーバラ・リーのようにキャバレーに出演する機会が多くなる(もっとも、バーバラ・リーは根っからのキャバレー歌手だが)。キャバレーといっても日本のようにホステスのいるクラブではなく、エンターテインメントのある大人の酒場のことである。
また、1980年代にニューヨークのダニー・ケイ・ホールで行われた「トリビュート・トゥ・リー・ワイリー」というコンサートで、ロビーでばったりマーガレット・ホワイティングに会ったこともあった。聞けば、バーバラ・リーとは仲のいい友だちだという。
「PCMジャズ喫茶」ではマーガレットとジョニー・マーサーのデュエット・ナンバー「ベイビー・イッツ・コールド・アウトサイド」をかけた。幸い寺島氏は気に入ったようだった。やはりストレートに歌った歌はいつ聴いてもいいものだ。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
1現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2010年11月/第82回 生真面目な生徒
2010年11月/第82回 生真面目な生徒
「PCMジャズ喫茶」の担当ディレクターである太田さんがトロンボーンを始めるという話を前に書いた。
その後、その件が立ち消えになった。よくある話である。人間は一時的な高揚、衝動で物ごとを決めたりするが、それが収まるときれいさっぱり忘れてしまうものだ。
太田さんも、その手だなと思っていた。だから薦めた張本人である私もせっついたり強要したりはしなかった。大体人に言われて不承ぶしょうやるようなことにいい結果が生まれたためしはない。
ところが先日、急に始めると言い出したから驚いた。率先楽器を買いに赴き、ヤマハのかなり高額な一品を手に入れたという。
こいつは本物だなと思った。
そうしてジャズ喫茶「メグ」で行われている『トロンボーンを楽しむ会』に入会したのである。楽しむ会は練習が終わった後の“反省会”という名目の宴会が楽しい。50~60代のおっさんたちが大部分であるから金を持っており、ビールも一本ではなく5本単位で注文する。店にとっては神さまのような人たちである。
酔いがまわると遠慮がなくなるから、会の運営について言いたい放題が始まる。
先生は志賀聡美さんといって、美形だがまだ30代の前半なのでおっさんたちにとっては娘のような存在であり、それでつい放言が度を超してしまうのだ。
「あのさあ、オレ、オタマジャクシなんて読めなくていいんだよ。アローン・トゥゲザーとビューティフル・ラブの二曲さえ吹ければあとはどうでもいいんだよ。」
という人がいる。個人タクシーの運転手で、始めて間もない人だが近頃めきめき腕を上げているおっさん中のおっさんだ。それに賛同する人が何人もいる。私もその口であり、なにしろ老い先短いのだ。
先生は困った顔をする。彼女が卒業した芸大ではそういう教え方はなかった。
そこで断固一説述べたのが太田さんだった。
「そういう話もわからなくはないが楽器の練習はやっぱり基本でしょう。私は譜面も憶えたい。ロングトーンをみっちりやって、音が満足に出るようになってしかる後の曲の演奏でしょう。先生、今のままの練習スタイルでお願いします。」
先生にホッと安堵の表情が浮かぶ。さすが私が『ミスター正論』と呼んでいるだけあって立派な発言である。生徒からこのように言われて可愛く思わない先生がいるだろうか。段々オボエがめでたくなっていくような塩梅である。
ドリス・デイの昔の歌に「ティーチャーズ・ペット」というのがあったが、そっちの世界にめざましく発展してゆきそうだ。
そのうち、太田さんがうまくなってリチャード・ロジャースの作曲した「ピープル・ウィル・セイ・ウィー・アー・イン・ラブ」などをデュエットで演奏し始めるんじゃないか。
邦題が「粋な噂を立てられて」。
春が来たようであり、光る未来が見えてきて、思わず「がんばれ60の手習い!」と言いたくなった。
番組でもとりあげたトロンボーン奏者の片岡雄三さんは、すでにそのことを実践されている方である。奥さんはベース・トロンボーン奏者の山城純子さん。このCD(片岡雄三QUARTET)のラスト・トラックでなんと微笑ましくも奥さんとデュエットで演奏を行っている。あんまり面白くなくて、この曲だけは聴きたくないのである。
(ディレクター記) 寺島さーん、妄想いいかげんにして下さいな(笑)
寺島靖国(てらしまやすくに)
938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2010年10月/第81回 いまイタリアのジャズが熱い!
2010年10月/第81回 いまイタリアのジャズが熱い!
最近ヨーロッパのジャズが人気を博しているようだが、僕はイタリアのジャズにいちばん魅せられている。
イタリアのジャズが素敵なのは今に始まったことではない。もともとアメリカのジャズ界で活躍してきた白人ミュージシャンで、数の上でも実績の上でも一番際立っていたのはユダヤ系とイタリア系のミュージシャンである。ヴィド・ムッソ、チャーリー・マリアーノ、アート・ペッパー、バディ・デフランコ、トニー・スコット、フランク・ロソリーノ、パット・マルティーノ、ジョー・ロヴァーノなど、いくらでもイタリア系の名前が思い浮かぶ。歌手ともなれば、イタリアは歌の国だから、フランク・シナトラ、トニー・ベネット、ペリー・コモ、ヴィック・ダモーン、ディーン・マーティン、コニー・フランシス、ジョニー・ジェイムス、ロバータ、ガンバリーニと数えきれない。
ところが、このところイタリア本国でもジャズメンの活躍が目立ってきたのだ。ポニー・キャニオンなどはイタリアのレーベルと契約して次々にイタリアン・ジャズを発売している。もともとイタリアはクラッシックにおいても傑出した音楽家をたくさん輩出しており、音楽的水準の非常に高い国なのだ。ジャズのレベルが高いのも当然だと思う。
最近のイタリア・ジャズでいちばん感心したのは、2年前に出たハイ・ファイヴの「ファイヴ・フォー・ファン」だった。ホーン入りのクィンテットというのも嬉しかったし、メンバーの中ではなんといってもトランペットのファブリッツィオ・ボッソが凄い。いまアメリカのトランぺッターたちを抜いて世界一のトランぺッターと言っても過言ではない。グループのサウンドは「ネオ・ハードバップ」といえばいいだろうか。ハード・バップ期や新主流派時代のナンバーに新しい生命を吹き込み、さらに自分たちのオリジナルも演奏するというグループなのだ。
そして、今度このグループの新作「スプリット・キック/ハイ・ファイヴ」が出た。これがまた前作を上回るスマートで、しかも熱い演奏なのだ。なんとハードバップを最初に推進したホレス・シルバーのオリジナルを3曲も取り上げている点に感心した。特に僕はアルバム・タイトル曲「スプリット・キック」に心が躍った。
僕にとってこの曲には忘れられない思い出がある。この曲はアート・ブレイキー・クィンテットの有名なアルバム「ナイト・アット・バードランド」で演奏されているナンバーだが、僕はこの曲の演奏をほぼリアル・タイムで聴いている。まだ四国の松山にいた頃、多分55年頃だろう、南海放送が試験電波を出しはじめていて、友人のいる局の資料室を訪ねたところ、ブルーノートの25センチ盤が何枚かあり、セロニアス・モンクやミルト・ジャクソンとともに、このブレイキーの「スプリット・キック」を聴いたとき、従来のビバップとは違う、何か新しいサウンドの誕生を感じ胸がときめいたのだ。従来のバップと違って、とてもメロディックな曲のテーマにも驚かされた。今振り返ると、この曲の演奏こそがバップとハードバップの境界線上にあった曲であり、演奏であることを知るのであった。
ハイ・ファイヴが今改めてこの曲を取り上げたのは、このグループがメロディックな演奏をめざすことを宣言したとも言えるわけで、その行き方に僕は共感したのだ。
さっそく番組に持ち込み、かけようとしたが、寺島氏はオリジナルの「サッド・デイ」をかけることを主張した。だが僕は「スプリット・キック」に固執し、この曲をかけた。
それでよかったのだ。この曲こそ今回のこのグループの主張だと思うからだ。ボッソのトランペットも凄いし、いまジャズ界でいちばん魅力のあるコンボはこの「ハイ・ファイヴ」なのだから。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2010年09月/第80回 新ジャズ誌への期待
2010年09月/第80回 新ジャズ誌への期待

新しいジャズ雑誌が創刊されるという。
『ジャズ・ジャパン』。
案内状によると「ジャズ・ドキュメント」誌をコンセプトに、ジャズ・ファンありき、音楽ファンありきの初心に立ち戻って出発するとのこと。
いい話である。つい先日「スィング・ジャーナル」誌が休刊となり、くさっていたところへのビッグニュース、新雑誌のスタートを歓迎したい。
この際、ジャズの雑誌とは何かについて考えてみようじゃないか。ちょっと突飛な発想かもしれないがジャズの雑誌は「雑誌のためのジャズ」を作っているのである。私は嫌味な人間だが、嫌味で言ってるんじゃない。要するに雑誌が存続してゆくためには買ってもらうことが前提になる。買ってもらうためにはどうしたらいいか。教科書化することである。読者は生徒なのだ。ジャズの聴き方の法則を作って生徒に教え込む。
法則といえば、むかし私は『ジャズの聴き方に法則はない』という文庫本を出した。ぜんぜん売れず、すぐに絶版になった。聴き方に法則あり、としなければいけなかったのだ。
特に新しいジャズ・ファンは法則を求めて雑誌を買う。ビ・バップ、ハード・バップ、新主流派などという演奏スタイルの呼称があるが、この呼称に添って雑誌のCD評は成立してきた。「スィング・ジャーナル」のレコード・レビューアーはこの法則にのっとり、そこから一歩も抜け出せなかった。
ところがである、初めのうちこそ読者は法則に従って聞いているが、当然そういう聴き方をしていてジャズが面白いわけが無い。もっと根本的に聞くべき要素があるだろう、と。スイングであり、メロディーであり、からみ合い、睦み合い、そして楽器のサウンドである。大体5年くらいといわれているが、読者が「雑誌の聴かせ方」と「自分の聴き方」のへだたりに気付いた時、別れが待っているといえるのだ。
かと言ってである。「法則」を無視して雑誌は成立しない。雑誌も大変である。
『ジャズ・ジャパン』の社長兼編集長はスィング・ジャーナル誌の編集長を務めた三森隆文氏。どのような辣腕をふるうのか。これ、ワクワクせずにおられるか、といったところだ。
そんな風雲急を告げるジャズ・シーンに、これはまたのんびりとお出ましなのがバリー・ハリス。スィング・ジャーナル流に言えば「ビ・バップ流派の引き継ぎピアニスト」ということになるが、そんな法則は頭の片隅に追いやってひたすら1曲目の「She」を聴いて欲しい。ジョージ・シアリングの作曲で、さてどんな『She』がきみの頭に浮かぶのか。
私の場合はジーナ・ロロブリジーダだった。
きみ知るか、この往年の豊満イタリア女優。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2010年08月/第79回 順子 対 順子
2010年08月/第79回 順子 対 順子

前号で寺島靖国氏もふれていたが、64年の歴史を持ったジャズ専門誌「スィング・ジャーナル」が6月発売号で休刊してしまった。ジャズ界の大きな柱がなくなって、とまどい困っている。ジャズ界の話題を提供してくれる点でも便利だったのだが・・・。
しかたなく自分で話題を探すことにした。
いま注目しているプレイヤーの一人にアルトサックス奏者の寺久保エレナがいる。ミュージックバードのぼくたちの番組でも先日紹介して好評だった。口の悪い寺島氏もほめていたが、彼女はまだ現役の高校三年生で、いまも札幌の高校に通っている。6月に「NORTH BIRD」(キング)でデビューしたばかりだが、たぶん“北国のチャーリー・パーカー”という意味で「NORTH BIRD」のタイトルをつけたのだろう。別にパーカー・スタイル一辺倒というわけではなく、今日の新しい奏法も取り入れている。渡辺貞夫、山下洋輔、日野皓正らも絶賛しており、早い曲もバラードもうまいし、高校生としては出来過ぎと言いたいほどしっかりとした演奏で、なにもかもが整っている。早くも9月上旬の「東京JAZZ 2010」への出演も決まり、これからの活動にも注目したい。
頭角を現すジャズ・ミュージシャンの年齢はどんどん下がってきている。なんでも小学生のブラスバンドがチック・コリアの「スペイン」を演奏する時代なのだから。
もっとも、話題にしたいのは新人だけではない。中堅やベテランにも見逃せない人がいる。それは二人の『順子』だ。ピアノの大西順子と歌の秋元順子だ。
大西順子は昨年EMIミュージックから久々にトリオのアルバムを出して、あざやかに復活を果たし、ベスト・セラーを記録した。その大西順子が早くもユニバーサル・ミュージックに移籍し新作「バロック」(ヴァーヴ)をニューヨークで録音した。やはり注目しないわけにはいかない。ニコラス・ペイトン(Tp)、ジェームス・カーター(Ts, Bcl, Fl)、ワイクリフ・ゴードン(Tb)、レジナルド・ヴィール、ロドニー・ウィテカー(B)、ハーリン・ライリー(Ds)らN.Y.の精鋭たちと共演している。
大西順子は日本でも6重奏などで演奏しているのを聴いたことがあるので、彼女が試みたかった編成なのだろう。この6重奏で自作3曲と、ミンガス、パーカー、モンクのナンバー、それにスタンダードの「フラミンゴ」、ほかにもピアノソロで「スターダスト」「メモリーズ・オブ・ユー」を演奏している。ピアノ・ソロはアート・テイタムを思わせるオーソドックスなプレイで、彼女の成長と円熟を感じさせ、共感を覚えた。6重奏団のものは、ワイルドで奔放で、ガッツを前面に押し出している。現代的集合即興演奏で、チャーリー・ミンガスの精神を感じた。
番組では寺島氏のリクエストで「フラミンゴ」をかけたが、これがまずかった。バラードで、幻想的なアンサンブルとエリントン的なミュートを用いたりしているのだが、聴き方によっては欲求不満になる演奏である。ハードな演奏の連続の後でこの演奏を聴くとホットするのだが、この曲を最初に聴くと「なんだ!これは?」といいたくなるだろう。案の定、この日の出演者みんなから悪評ふんぷんだった。寺島氏の誘導にのってこの曲をかけたのが間違いだった。
家に帰って一連の流れの中で聞き返すと、大西順子のピアノ・ソロの部分などは美しかったし、全体の演奏も悪くなかった。ただ演奏すべてに全面的に共感というわけではないが。
大西順子の後に、もう一人の順子こと、秋元順子の「テネシー・ワルツ」を口直しにといってかけた。寺島氏は下手だといったが、素直でハートを感じる歌手だ。新作「スィンギン/原信夫とシャープス&フラッツ・ウィズ秋元順子」(キング)の中で4曲歌っている中の一曲である。彼女は歌謡界でも人気者だが、もともとジャズも歌っていた人で、ぼくは感じのいい歌と聴いた。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2010年07月/第78回 脱"定番”の時代
2010年07月/第78回 脱"定番”の時代

「スイング・ジャーナル」が休刊になった。
私のような老ジャズ・ファンにとっては大変な衝撃である。高校生の頃ジャズが好きになり「スイング・ジャーナル」に育てられ、 まさに我が青春のスイング・ジャーナルだったのだ。編集部員が神々しく見え、まして編集長ともなれば雲の上の人で口などきけたものではなかった。
そういえば岩浪洋三さんが編集長の頃のことだった。この話はどこかに書いたが、えーい、かまうものか。どうせ原稿料は安いのだ。二重書きくらいしないと元のとれるものではない。ホレス・シルバーのブルーノート盤「ザ・スタイリングス・オブ・シルバー」のオリジナル盤を買ったがいまいち面白くない。それで売ることに決めてSJ誌の「売りたし欄」に応募したら、岩浪さん本人が買いたいと言ってきた。
さあ大変だ。会わなければいけない。渋谷の「デュエット」でお目にかかったが、まともに顔も見られない。うつむいてモジモジしていた。
なのに今はどうだ。「PCMジャズ喫茶」でいくら私が店主とはいえ、「岩浪さん、そんなのも知らないの?」などと言いたい放題。どうもすみません。
というのはどうでもいい話で、SJ誌がなぜ休刊という事態に落ち入ったのか。
レコード会社その他の広告が激減した。それもあるだろう。しかしもっと大きな原因は「大物ミュージシャン至上主義」を40年も50年もくり返してきたことにありそうだ。マイルス、コルトレーン、エバンス、キース、などなど、毎号同じような記事扱いで、さすがに読者はあきた。60代、70代の読者が多い。よくぞ、何十年も読み続けてきたものである。大物ミュージシャンを論じておけば間違いない。そう、安易にSJ誌はふんでいた形跡があった。
しかし再刊の話もある。ぜひもう一度立ち上がって欲しいものである。 やっぱりスイング・ジャーナル誌がなくしては困るのだ。
さて、長いマクラだったが今回は日本人歌手をご紹介しよう。先日さるジャズ・クラブで「クライ・ミー・ア・リバー」の聴き比べをやった。ジャズのビギナーが望むのは聴き比べである。まず曲を憶えられるというメリットがある。ついでにミュージシャンの個性を知ることが出来る。
「クライ・ミー・ア・リバー」といえばジュリー・ロンドン。このトップの位置はゆるがない。彼女の同曲を聴いたらあとは誰を聴いてもくい足りないという人もいる。
比較の相手に先頃発売されたシャンティをえらんだ。2曲終わったあと、どちらが好きかを訊いてみた。ビギナーとはいえ、さすがにジュリーの名前を大部分の人が知っている。ジュリーに軍配が上がると思ったら五分と五分のいい勝負となった。驚いた。
シャンティ派の人に理由を尋ねると、ジュリーはうま過ぎていやだ。色気が遠い。体が大理石で出来ているんじゃないか。それに比べシャンティはうまいとは言い難い。しかし人肌を感じる。色気が近い。そばに寄っていって肩を抱きたくなる。
ノリのいい会場であった。しかしそれにしてもジュリー・ロンドンかたなしである。
いつまでも大物に頼ってはいられない。新しい歌手を次々と発掘、光を当てていかなくては女性ボーカル界、先がないと感じた。
寺島靖国(てらしまやすくに)
938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2010年06月/第77回 ミュージカルとジャズ
2010年06月/第77回 ミュージカルとジャズ

ニューヨークに行くと、いつもブロードウェイ・ミュージカルを3、4本は観たものだ。ジャズも好きだが、ミュージカルも好きだからだ。近年のブロードウェイにはロンドン製が多く進出してきたが、どちらかと問われれば、僕はアメリカ製のミュージカルが好みである。大ざっぱにいうと、アメリカのミュージカルの方がジャズの要素が多く、ロンドン製はジャズ・サウンドがやや希薄である。
このアメリカ製ミュージカルで近年観たものの中で、ジャズ色にあふれていて楽しかったのが、初演の「スィング!」だった。スィング・ナンバーが次々に歌われ、演奏され、ラストは「シング・シング・シング」で大いに盛り上がるのである。音楽も聞き慣れたスイング曲が多くて満足したが、なによりも主演して歌いまくったアン・ハンプトン・キャラウェイの歌がすばらしかった。ミュージカル・スターであると同時に優れたジャズ・シンガーぶりを発揮していた。あまりに感動したので、帰りにレコード店によって彼女のCDを買ってしまった。
このミュージカル「スィング!」は2度ほどアメリカのキャストで日本でも上演されたが、主役がアン・ハンプトン・キャラウェイではなかったのには失望した。このミュージカルは主役の歌唱力に成否がかかっているわけで、ちょっとアン・ハンプトン・キャラウェイを超えるスターは現れそうにない。
彼女はこのミュージカルをきっかけに、人気ジャズ・シンガーになり、TELARCから次々にアルバムが発売されており、僕も出る度に買っているが、一度も失望したことがない。彼女は白人で、美人で、しかもジャズ歌手として、いまや最高の一人だと思う。近頃のダイアナ・クラールやジェーン・モーンハイトよりも、僕はアン・ハンプトン・キャラウェイの方を高く評価する。
最新作「At Last」が発売されたので早速買って、「PCMジャズ喫茶」のスタジオに持ち込み、寺島氏の好きな曲「Comes Love」をかけた。寺島氏は、セリフをしゃべっているような、ドラマティックな歌い方が嫌いだという。その気持ちもわからないではないが、ぼくはミュージカル好きだからドラマティックな歌い方も嫌いじゃない。
僕はこのアルバムの中の歌、「アット・ラスト」「スペイン」「レイジー・アフタヌーン」「オーバー・ザ・レインボウ」などみんな好きだ。もっとも、ぼくの場合、ブロードウェイで観た「スィング!」の印象があまりに強烈だったので彼女の歌への思い入れが人一倍強いのかもしれない....。
僕がはじめてニューヨークを訪れたのが1972年、その後30数年間毎年訪れているが、年々ニューヨークの芸能やエンターテインメントのレベルが下がっていくのを肌で感じている。それは一時ニューヨークが破産しかけて、「アイ・ラブ・ニューヨーク・キャンペーン」を打ち出し、観光客を大量に呼び寄せた結果だと思う。観光客好みのものが多くなりニューヨーカーの街だったのが普通の観光都市に変貌していったからであろう。
秋吉敏子にいわせると、70年代どころか、50年代がジャズ・シーンのベストで、56年に渡米した彼女は「私はジャズの黄金時代のしっぽをかろうじて摑むことができた」と言ったことがある。
50年代の中頃までは、ジャズ・クラブも午前2時半から3時頃まではライヴをやっていたという。秋吉敏子はクリフォード・ブラウン・マックス・ローチ・クィンテットに飛び入りしてピアノを弾くという幸運に恵まれ、午前2時に出演が終わった後、午前3時までやっているデューク・エリントン楽団の演奏を聴くこともできたという。
僕も70年代にはブロードウェイ近辺で、シャーリー・マクレーン、ハロルド・ニコラス、アーニー・ロス、マーガレット・ホワイティング、ヘレン・フォレスト、リナ・ホーンらのトップ・エンターテイナーのショウをいくらでも観ることができた。70年代に一時期流行った黒人ジャズ・ミュージカル「バスリン・ブラウン・シュガー」「ユービー」「ソフィスティケイテッド・レディーズ」「タップ・ダンス・キッド」「ブラック&ブルー」などは本当に楽しかった。
そう言った意味で、数年前の作品ではあるが「スィング!」は久しぶりにニューヨーク・ブロードウェイらしいミュージカルだった。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2010年05月/第76回 ネイロで聴くジャズ
2010年05月/第76回 ネイロで聴くジャズ

「人間50歳を過ぎたら、ちったあジャズの聴き方変えてみないか」というのが今日のテーマだ。
これまでのジャズの聴き方というとハンで押したように、まずジャズ・ジャイアント主義。
マイルスがいて、コルトレーンがいて、ビル・エバンスがどうたらこうたら。
あんたら歴史学者か。
そう言う聴き方、まあ、初心者はよしとしよう。右も左もわからないビギナーがとりあえずスタンダードで教科書的な聴き方を求める。これはこれで理にかなったジャズの攻略法というものだ。
だけどねえ、20年も30年もジャズと過ごして相変わらずマイルスやコルトレーンの演奏スタイルや、変化がどうしたこうしたじゃ情けない。
実は私の店『メグ』で少し前からトロンボーン教室というのを始めた。毎月第一日曜日の午后、メグの周辺はトロンボーンのケースをかついだ老若男女で溢れるというのは嘘だが、大体10人から15人の主として中高年男性が集まってくる。先生は若い女性だ。当たり前だろう。オッサンがオッサンに習ってなにになる。
遠方からはるばるやってくるこの番組のヘビー・リスナー、児玉さんもその一人。茨城だか群馬だか、そういう遠隔地だ。月一回上京し、美しい先生に習い、あまつさえレッスンが終わった後の反省会という名の宴会に参加、これが楽しくてたまらないと。
それはともかく、児玉さんのジャズの聴き方は変わった。以前はおきまりの名盤主義、ジャズ・ジャイアント主義。トロンボーンを始めて、J.J.ジョンソンとカーティス・フラーしか知らなかった児玉さんは次々いろいろなトロンボーン奏者のCDに手を出し、この頃行き当たったのがアービー・グリーンだ。
児玉さんはたまげたのである。なんという微妙に美しい音色なのだろう。いやこれは『オンショク』ではない。あくまで敢然と『ネイロ』と言うべきである、と。
トロンボーンを自分でくわえて初めて『ネイロ』という問題につき当ったのである。それまではJ.J.ジョンソンのモダン・トロンボーンにおける革命的奏法なんていうことしか考えなかったのが、“音で聴くジャズ”の聴き方という考えてみればいちばん根元的、かつまっとうなリスニング法に目覚めたのだ。
なんとかしてアービー・グリーンみたいな絹ずれ音色を出したい。そういう欲求を抱いてアンブシャーに精を出す児玉さんだが、いろいろ漁ってみると、いるわいるわ、アービー・グリーン的スィート・サウンドのトロンボーン奏者が。
古くはトミー・ドーシーから始まり、ジャック・ティーガーデン、ルー・マクガリティにマレー・マッカカーン。こういうひとつの勢力がトロンボーン界にあったのか。知らなんだあ、と。
先日お会いしたらこういうことを言っておられた。「トロンボーンだけでなく、いろんな楽器を音で聴くようになりました。一つまた聴き方の世界が開けたんです。いや実に嬉しいことです。」
考えてみれば、あらゆる楽器奏者、まずいかに最初にいい音を出すか。そのことに腐心するというではないか。楽器は音色だ、と言ってはばからないミュージシャンもいる。おお、そうかい。それならおまえさんの音を心ゆくまで聴いてやろうじゃないか。
そう考えるジャズ・ファンがいたって絶対におかしくない。いや、本来的にそうあるべきなのだ。
(P.S.) 「PCMジャズ喫茶」のディレクター、太田俊さんが来月からメグのトロンボーン教室に参加することになった。いいジャズ人生が広がりそう。あなたもトロンボーンをお買いになったら?
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2010年04月/第75回 和ジャズのススメ
2010年04月/第75回 和ジャズのススメ

最近、日本人による「50~60年代」のジャズがたくさんCDで復刻発売されている。そのきっかけを作ったのは先日この「PCMジャズ喫茶」にゲスト出演したディスク・ユニオンの塙耕記氏の企画で、日本のジャズの再発は『和ジャズ』と呼ばれてきた。この番組の相棒・寺島靖国氏は、『和ジャズ』という呼び方に抵抗を感じるらしい。
僕自身もこの呼び方は好きではないが、『日本のジャズ』『日本人のジャズ』『和製ジャズ』といろいろ呼び名を変えてみてもしっくりこない。コロンビア・ミュージックは「昭和アーカイブス」とよんで再発売している。原盤を持っていないディスク・ユニオンの場合は、キング、ビクター、コロンビアあたりから原盤を借りてきて発表してきたわけだが、売れ行きがなかなかいいので、こんどは貸す側が、他社に儲けさせるのはもったいないとばかり、貸し渋りをはじめたという。それもあってコロンビアも古い日本のジャズを初CD化し始めたのだ。
その1枚に「モダン・ジャズ・スクリーン・ムード/モダン・ジャズ・プレイボーイズ」というのがあり、この中のなつかしい映画のテーマ「褐色のブルース」をかけた。1960年の録音で、ピアノとアレンジが三保敬太郎で、林鉄雄(Tp)・渡辺貞夫(As Fl)・宮沢昭(Ts)・金井英人(B)・猪俣猛(Ds)というオールスターなのだ。いま振り返って思うのだが、1950年代の後半から60年代の中頃にかけては、日本のジャズが大変なブームで、コンサートも盛んに開かれ、人気プレイヤーが続出した。また、フランスのヌーベルバーグ・シネマにモダンジャズが多用された影響もあって「死刑台のエレベーター」「大運河」「危険な関係」などのジャズ・テーマが日本でも大ヒット。おかげでジャズの需要が飛躍的に高まり、日本のレコード会社は、日本のジャズメンを起用して、先を争ってジャズ・アルバムを制作した。それが今掘り起こされているのだが、1950年代の中期以降の日本のジャズメンはレベルもアップしているし、個性豊かだし、いま聴いても充分に楽しめる。もっとも60年代の後期以降は外タレの来日ブームがきて、日本のジャズメンは逆に70年代にかけてはアメリカへの留学(流出)の時代と変化していくのは皮肉である。
別に日本のジャズ史を書くつもりはなかったのだが、番組で「褐色のブルース」をかけたところ、なんとこの曲をテーマにした映画「墓に唾をかけろ」の原作を書いたボリス・ヴィアンの『ジャズ入門』(シンコーミュージック)という本が最近翻訳されて出ていたのだ。
ボリス・ヴィアンは1959年に39歳で亡くなっているが、フランスの大変な才人で、トランペッター、小説家、音楽評論家、歌手、俳優、詩人として活躍し、サンジェルマン・デュプレに入り浸っていた芸術家の一人だった。この本は「入門書」などとは書いてあるが内容はきわめてハイブローで、初心者の手に負えるものではない。古いジャズ、ルイ・アームストロング、デューク・エリントンに関する評論や、シャルル・アズナブール、ジジ・ジャンメールなどに関するエッセイや翻訳などがおさめられていて、ヴィアンの多才を知ることの出来る一冊だ。彼のジャズ本が日本で出るのは、多分今年がヴィアンの生誕90年にあたるからだろう。
ともあれ、和ジャズの再発で「褐色のブルース」が聴けたのがうれしいのだが、最近のCDで多いのがコンピレーションだ。その中に『居酒屋ジャズ』というのがあって驚いたが、これはかなり売れたらしい。そういえば僕が住んでいる大泉学園の居酒屋チェーンも呼び込み用にジャズを使っている。この頃はラーメン店でもジャズが流れている。
最近ついにユニバーサルから「泣きJAZZ /V.A.」と題するコンピレーションCDが出た。不景気で泣いてくれというのか、それともレコード会社の社員の心情を表現したのだろうか。「クライ・ミー・ア・リバー」「煙が目にしみる」なんてのが入っていたな。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2010年03月/第74回 パッチンスキーのシンバル
2010年03月/第74回 パッチンスキーのシンバル
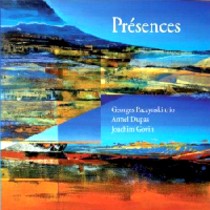
やっぱり人間、ほめられれば嬉しく、けなされれば悲しい。70歳を過ぎたら恐いものなしなどといかにも大物そうに日頃ホザいているが、それはウソ。歳をとれば剛胆になり、キモっ玉がすわるというものではない。ますます周囲の目を気にするようになる。気にしなくなったらそれはボケた時。
そういえばこの間ちょっとくやしい思いをした。ピアニストの山中千尋にホンワリ一発アッパーカットをくらったのだ。彼女、このところ「スイングジャーナル」誌上でエッセイの連載原稿を書きはじめた。これがひときわ異彩を放っている。
本が来ると私は真っ先にそのエッセイを読み出すのだ。どこが面白いか。ケンカを売っているのである。文章が。文章っていうのはこうじゃなくっちゃいけねえよな、とひそかにエールを送っていたのだがついに先月号、私に矛先が向いてしまったのだ。
他人のCDについてはいつも言いたい放題なのに、自分のかかわった「寺島レコード」について少しでも否定的なことを書かれると、烈火のごとく怒る。なんと心のせまい御仁なのか。とまあこんな趣旨のことが書かれていた。
ギャフンときたねえ。クソっと思ったが考えてみるとその通りだ。返す言葉もないし文句のもってゆきどころもない。
もうひとつ。医師であり、ジャズ・オーディオ・マニアであり、重度の当番組リスナーである横須賀の三上さんが自分のホームページで松尾明クィンテットの音がひどいと書いたらしい。本人が私を目の前にして言うんだから間違いない。
グワッーときましたね。医者にもガンを告知する人と、しない人がいるらしいが、この人は勇躍敢然と告知する人だろうなと思った。
「CDの音が悪いんじゃなくてお宅の装置がよくないんでしょう。 自分の装置の音の悪さに気付かずにCDのせいにする。よくあるケースですよ。オーディオ・マニア誰しも自分の装置が可愛い。最高優秀な音を出すと思い込んでいますからね。」
こう言ってやろうと思ったが言えなかった。余計ウラミが残ったのである。
さあ、ここでようやく本日の課題に入ることになる。CDというのはどこのお宅でも同じように鳴るわけではない。相性があり鳴り方はまちまちである。凶と出たり吉と出たりする。それが録音の面白さでありオーディオの楽しみなのだが、ここに一枚、どこへ行っても大体優秀な音で鳴るCDというのがあるのだ。本日ご紹介の『パッチンスキー盤』である。ドラマーのパッチンスキーはフランス人だが、昨年「ジャズ批評」誌で彼の前作「セネレイション」が最優秀録音賞を取った。その次作にあたるのがこの「プレザンス」。ライヴ盤なので若干前作に音的には劣るのは致しかたない。しかしリーダー、パッチンスキーのシンバルの切れ味のすさまじさ、これは恐ろしいくらいに継承されている。
しかしこの世の中、シンバルの切れ味の鋭さを求めて音を聴く秘密結社的、歓楽的オーディオ・マニアが30人ほどいるらしい。私もその一人なのだがこのCDを聴きつつ、シンバルの切れ味に酔いつつ、酒をくみかわせたらどんなに幸せだろう。そうなったら人に何を言われようと平気の平左だろうと思った。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2010年02月/第73回 カウント・ベイシーのこと
2010年02月/第73回 カウント・ベイシーのこと
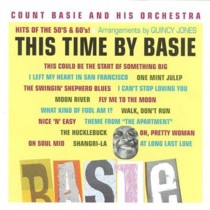
2月にカウント・ベイシー・オーケストラが来日する。昨年はデューク・エリントン・オーケストラが来日しているし、この黒人2大ビッグ・バンドはリーダーが変わっても健在だ。しかしカウント・ベイシーとデューク・エリントンがあまりにも大きな存在だったので、二人に勝るリーダーが現れることはまずないであろう。
ところで、カウント・ベイシーには、以前来日したときに会って話をしたことがあるが、ユーモアのセンスに富んだ、とぼけて面白い男だった。ベイシーは一度ビッグ・バンドを解散してコンボで演奏していたことがあるが、すぐまたビッグ・バンドにもどした。その理由を聞くと、
「きみ、コンボだとずっとピアノを弾いていなくてはならないんで、忙しくて大変なんでやめたんだよ。ビッグ・バンドだと、ちょっとだけ弾けばいいからね。」
さぼるのが好きだといわんばかりなのだ。
「ところで、あなたのバンドで、いちばん凄いと思った時期はいつですか?」
と聞くと、
「50年代のはじめから中頃かな。サド・ジョーンズ、ジョー・ニューマン、ベニー・パウエル、マーシャル・ロイヤル、フランク・フォスター、フランク・ウェスら、スターぞろいでね。自分のバンドなのに、あまりにリッチなサウンドで鳥肌が立ったよ。」
その頃録音した曲には「トゥ・フォー・ザ・ブルース」「トゥ・フランシス」「シャイニー・ストッキングス」などがあった。
カウント・ベイシーといえばカンザス・シティ・ジャズの中心人物のようにいう人もいるが、彼は例外的に東部から来た男であり、人気が出ると、カンザス・シティから離れてしまった。彼の演奏に「マン・フロム・レッド・バンク」という曲があるが、彼はニュージャージー州レッド・バンクの出身である。ぼくは一度この街に立ち寄ったことがあるが、バスを降りると、そばにスーパーがあるくらいの小さな町だった。
なぜ立ち寄ったかといえば、このすぐそばに日野皓正が住んでいて、彼に会うためだった。日野皓正に「ここはカウント・ベイシーが生まれた町だよ」というと、「え!知らなかった」と驚いていた。
ベイシーは若い頃、かなり変な男で、親しい友人が映画館で働いていたので、毎日昼間この映画館に行って映画を見つづけ、夜も家に帰らずに、映画館のソファで寝ていた。あまり毎日ベイシーが同じ映画を観ているので、館主が、「きみ、ピアノが弾けるんだろ?じゃ映画の伴奏をやってくれよ」 といい、ベイシーは無声映画の伴奏をはじめたのだった。
その後、ヴォードビルの一座に加わり、巡業の途中、カンザス・シティに寄ったら、あまりにジャズが盛んなので、この街でジャズ・ピアノの仕事をはじめたのだった。そしてベニー・モーテン楽団のピアニストになったのだが、リーダーのベニー・モーテンが手術の失敗で急死し、メンバーの推薦でベイシーがリーダーになったのだった。
ニューヨークの”ローズランド・ボウル・ルーム”に37年頃に出演したところ、ラジオの電波にも乗り、人気は急上昇、デッカにも録音し、全米的人気バンドになった。ベイシーは実力も勿論あったのだが、幸運にも恵まれていた。
70年代の終わり頃だったか、この”ローズランド・ボウル・ルーム”でベイシー楽団を聴いたことがある。評論家の野口久光氏と一緒だったが、氏は宝塚の女優を同伴してきていた。氏に、彼女と一緒に踊れといわれ、ベイシー楽団の伴奏で踊ったが、こんなに踊りやすいバンドははじめてだった。
この時、ベイシー楽団の秘密に気がついた。ベイシー楽団はいつも強力なリズム・セクションがフォー・ビートを打ち出しているので、その上にどんなホットなソロを乗せてもちゃんと踊れるのである。ベイシー楽団の長寿の秘密のひとつは、この踊りやすさにあったのかもしれない。
ベイシーは編曲が得意ではなかったので、いつもニール・ヘフティ、チコ・オファリルなどの優秀なアレンジャーを起用したが、ぼくはクィンシー・ジョーンズの軽やかでファンキーで、ユーモアたっぷりの編曲が好きだ。「ジス・タイム・バイ・ベイシー」 (リプリーズ)は最高傑作だと思う。
この中のモー・コフマン作曲の「スウィンギン・シェパード・ブルース」はフランク・ウェス、エリック・ディクソンのフルートをフューチャーした大好きな演奏なので番組でかけた。幸い好評で安心した。僕はこの曲を若いフルート奏者の西仲美咲に紹介したら、気に入り、今では彼女の主要レパートリーのひとつとなっている。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2010年01月/第72回 集中と拡散
2010年01月/第72回 集中と拡散
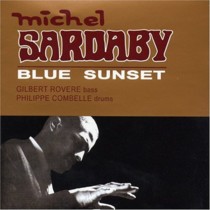
ジャズ・ファンを乱暴に分けると二つのタイプに分類される。一極集中型と拡散型。
横浜に柴田浩一さんという方がおられる。「横浜ジャズ・プロムナード」の立ち上げに参加し、現在はFM放送などに出演、ジャズの布教につとめている生粋の浜っ子三代目だ。この方なんかは集中型の大御所で主として40~50年代のデューク・エリントンくらいしか聴かない。エリントンやその一派についてはめったやたらに詳しいけれど、現代のピアノ・トリオなどについてはからきし駄目。ちんぷんかんぷん。
この間柴田さんが冗談半分にこういう主旨のことを言った。
「あんたたちなんかは、わけのわからない新しいピアノ・トリオを紹介して、俺ってこんなのを知ってるんだぞと威張っているけど、そういう自慢もいい加減にせいよ。」
「違いますよ、柴田さん。私、いろんなジャズ聴くんですよ。エリントンだって時々聴くし、たまたま今はピアノ・トリオが多いだけなんですよ。」
私は「拡散型」である。しかしどうやら柴田さん、私に対して腹にイチモツあり、そういう気配だった。
いろいろ手を出さずに一人か二人のミュージシャンとその周辺をじっくり攻めろよ。それが正しいジャズ・ファンの生きる道だよ。そう言いたかったのかもしれない。
よくわかる。私もそういう生き方にあこがれたこともある。カウント・ベイシー一筋、ジョン・コルトレーン一筋でアメリカの田舎まで墓参りに行ってしまう人も知っている。偉いなあ、凄いなあ、と心底思う。俺には出来ないなと、中途半端な自分を情けなく思うこともある。
しかし一方で、彼らの知らない新しいピアノ・トリオに接して「うーん、いいなあ」と彼らの味わえない幸せを味わったりもする。
まあ、ジャズ・ファンそれぞれ。両者共存。そういう結論なのだが、ちょっと待ってくれ。私にも「この一人」というミュージシャンがいたぞ。
ミッシェル・サルダビーである。エリントンやベイシーに比べ少々の、いや圧倒的な小粒感は否めない。しかし山椒は小粒でもなんとやら。このピアニスト、ぴりっと辛いのである。辛いけど甘い。甘いけど辛い。そのへんの演奏ニュアンスのブレンドぶりが抜群で思わず私、全サルダビー盤を集めてしまった。全部と言っても10枚かそこいら。枚数が少ないから大きな顔が出来ないのがつらい。
そこへゆくとエリントンは何百枚である。おかげで柴田浩一さんは「デューク・エリントン」 という分厚い単行本を書き上げた(2008年、愛育社判)。渾身の一冊だ。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2009年12月/第71回 チェット・ベイカーの思い出
2009年12月/第71回 チェット・ベイカーの思い出

チェット・ベイカーのライヴは何度か聴いたが、いちばん強く印象に残っているのは、ニューヨークでのライヴだ。
1973年のことだったか、52丁目あたりに再開店した“HALF NOTE“にチェット・ベイカーが出演するというニュースを知り、二日間通って聴いた。ニューヨークのクラブにチェットが出演したのは、長いブランクの後なので、毎日満員の盛況だった。ただ本人は毎回くたびれた茶色の同じジャケットを着ていて、あまりお金のある感じではなかった。クラブの席の前5列目あたりまではほとんどが女性客で、女性にもてるチェットは昔から変わりのないことがわかった。
チェットはおなじみのスタンダードを歌ったが、初日になんと「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」の歌詞を途中で忘れ、頭をかいて、最初から歌い直したのには驚いた。よほど長期にわたってライヴを行っていなかったのだろうか。それでも晩年に来日して行った日本でのライヴよりは若々しく、精気にも溢れていた。
この“HALF NOTE“にはジャッキー&ロイなども出演し、いいジャズ・クラブの復活だと喜んでいたら、2年後にはストリップ小屋に変わっていて、がっかりしたのを思い出す。
ところで、昨年だったか、日本でも発売されたチェット・ベイカーの伝記を読むと、あの美人歌手のルース・ヤングがチェットと出会って二人が恋に落ちたのが、この73年の”HALF NOTE“でのライヴだったことを知った。ルース・ヤングという歌手はちょっとファラ・フォーセット似で、大きな映画会社の社長の養女にもなった金持ちの女性で、チェットには相当貢いだのではないかと思う。
チェットの晩年に作られたドキュメンタリー・フィルム『レット・ゲット・ロスト』を見ると、ルースがコメントでチェットの悪口を言うシーンも見られるが、二人がデュエットで歌う「枯葉」の短いシーンがとても印象に残った。この二人のデュエットによる「枯葉」はCD「JAZZ CAFE/The Essential Classic Jazz Voices」にも収録されていて、好きで時々取り出して聴いているが、季節も秋になったので、先日ミュージックバードの録音に持っていってかけたところ、なかなか好評だった。
この頃のチェット・ベイカーとルース・ヤングは仲の良い時期だったのか、呼吸もぴったり合っているし、愛の交換がため息風の歌から伝わってきて、そのなまめかしさが素敵なのだ。
ルース・ヤングはチェットの死後、愛したチェットに捧げたアルバム「This Is Always」を録音し、チェットの愛唱歌を集めて歌っているが、このCDを聴くかぎり、あまりうまい歌手とはいえない。しかしこのチェットとのデュエットの「枯葉」だけは絶妙の出来なのだ。チェットのささやくような歌とルースのセクシーな声がぴったり合っている。
チェットのボーカルにはいつ聴いても魅せられるが、かねてから彼のソフトで素朴なささやきに近い歌い方はボサノバに影響を与えているに違いないと思っていた。アントニオ・カルロス・ジョビンの伝記を書いたジョビンの妹の本によると、彼女ははっきりとボサノバの歌唱法はチェットの影響を受けているというのを読んで納得した。
ところで、僕はチェットとルースの出会いとなった“HALF NOTE“に何日も通いつめながら、二人の決定的な出会いの場面を見逃し、写真も撮らなかったというのはなんとうかつで間抜けだったことだろう。チェット・ベイカー亡き今となってはつくづく残念だと思う。
渋谷の『パルコ劇場』で聴いた晩年のチェットは少しくたびれてはいたが、やはり彼の個性だけは輝いていた。ロビーで会った女優の木の実ナナさんは「私はトランペットより歌の方が好きなのよ」と言っていたが、彼の歌は確かに一級品だった。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2009年11月/第70回 いたずら好きなゲスト
2009年11月/第70回 いたずら好きなゲスト

「PCMジャズ喫茶」はゲストに頼っているところがある。私と岩浪洋三さんだけではお手上げである。長いお付き合いなのでお互い一言発すれば次の展開が分かってしまい、そうなると次に陥るのはいつもの恐るべきマンネリズムで、にっちもさっちもいかなくなってしまう。
アルトサックスのジャッキー・マクリーンやピアノのバリー・ハリスが紡ぎだすあのマンネリ・フレーズは「あっ、また出た」と言って嬉しく手を叩けるような芸の域に達したもので、これはこれで賞すべきだが、我々二人のフレージングは当然そうはゆかない。
そこで苦しい時の神頼み、ゲストの登場になるが今回の茂串さんは面白かった。茂串さんはご存知のようにジャズ喫茶「イントロ」他数店の経営者である一方、ジャズの論客、文章家としてもよく知られている。茂串さんは数枚のCDを用意してきた。その中にウィントン・ケリーの、よく我々が『ハシゴのケリー』と呼んでいたリバーサイド盤があった。
ウィントン・ケリーも、そういえば臆面もなく発する数々のマンネリ・フレーズを芸術の域に昇華した人である。それは別にして茂串さんは「このリバーサイド盤に興味深い別テイクが一曲見つかった」と言った。よくある話であり、だから最近再発のCDはうっかり出来ないのである。
実はこのCDにはドラム入りとドラムレスの曲が混在している。ドラマーはフィリー・ジョー・ジョーンズである。昔のジャズ・ミュージシャンは概してちゃらんぽらんだから、その性格がうまく演奏に加味された時に名演が生まれるが、この一作もその伝で、名作なのだがちゃらんぽらんの名手フィリー・ジョーが録音スタジオに遅れてきたかどうかして、とにかく何曲かには彼が参加していない。
茂串さんが言うには、今回発見された別テイクにはフィリー・ジョーが加わっている。しかしどうも聴くところ、若干フィリー・ジョーの匂いが薄い。皆さんの耳のいいところでそこいらあたりを判別してくれ、と言うのである。
よっしゃ、まかせてくれ!こちとら50年以上もジャズを聴いているんだ。まして私は以前から大のフィリー・ジョー・ファンである。聴いてみると、たしかにフィリー・ジョーにしては納豆が糸を引くような粘りが希薄である。グルーヴ感もいささか後退している。音にも1950年代から60年代の古めかしさがない。しかし最新24ビットの近代的マシーンを通した再発CDの音というのは驚くほど新鮮だ。
岩浪さんはどうもフィリー・ジョーらしくないと言う。フィリーにしてはあっさりしすぎていると。しかし私はフィリー・ジョーと確信した。フィリーだって元気のない時もあるさ。だからお蔵入りになって今頃現れてきたんだ。
演奏が終わり、茂串さんが笑い出した。
「これ、オレなんだよね。オレが叩いているんだよ」
一計を案じたのである。
ドラムレスのトラックに自分で叩いたドラムをかぶせたのである。
これはしくじった。完ぺきに一杯くわされた。なんという口惜しさだ。私は、茂串さんが10年以上もドラムを練習し近頃は玄人はだしの腕前になっているのをすっかり忘れていたのである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2009年10月/第69回 新進ピアニスト”ジェラルド・クレイトンの魅力
2009年10月/第69回 新進ピアニスト”ジェラルド・クレイトンの魅力

最近単独グループやソロ・アーティストのジャズ・コンサートがめっきり少なくなった。ジャズ人口が減ったわけではないだろうが、ジャズの聴き方が変わったのだろう。
1961年正月にジャズ・メッセンジャーズが初来日した時は、東京大手町のサンケイホールで7日間も行われ、マチネーを入れると10公演、いずれも満員の盛況だったことを思い出すと、その変化に驚くばかりだ。最近の日本のジャズ界もアメリカ風になり、ライヴ・ハウスでお酒を飲みながらジャズを聴くというパターンが一般化したといえるのではなかろうか。
東京を例にとれば、「東京ブルーノート」「コットンクラブ」「ビルボード」といったライヴ・ハウスに毎晩外国からのアーティストが出演しており、カップルやグループで、ジャズやポップス、ソウル、ロックまで楽しむ層がふえてきている。音楽が生活の一部に融け込んできたのであり、それはいいことだと思う。
僕も時々、「東京ブルーノート」「コットンクラブ」に出かけているが、日本のジャズも好きなので、日本のジャズメンや歌手の聴けるジャズ・クラブに出かけることも多い。この前一度、月に何回クラブ通いをしているのかを数えてみたら、平均9回強。かなり通っている方だと自負している。
ただ、一晩にハシゴができるのはせいぜい2軒が限度なので、いろんなアーティストをまとめて聴くことはできない。だから様々なアーティストをまとめて聴ける様な企画のコンサートはありがたいと思う。先日五反田の「ゆうぽーと」で『100ゴールド・フィンガーズ~ピアノ・プレイハウス・パート2』を聴きにいった。10人のピアニストが技と音楽を競う楽しいコンサートで、新旧10人のピアニストを一度に聴けるというありがたさを味わった。ただ、一人のピアニストが2~3曲なのでわずかな曲数でいかに自分のプレイを頂点にもっていくかが大変だと思うし、聴く方も、プレイヤーによってはもっと聴きたいと思うのに、全員一律で切られてしまうことに不満を 感じることもあるわけで、なかなか聴衆全員を満足させるわけにはいかない。
今年のピアノ・プレイハウスでは最年長がジュニア・マンス、最年少がジェラルド・クレイトンだった。また成熟の頂点を示したケニー・バロンもいれば、唯一の日本人、山中千尋もいた。
その中でとくに耳をそばだたせてくれたのが、最年少のジェラルド・クレイトンで、1984年5月11日生まれだから25才という若さ。有名なベーシストのジョン・クレイトンの息子で、サックスのジェフ・クレイトンを叔父に持つという、音楽的には申し分ない環境に育っている。またマンハッタン・スクール・オブ・ミュージックでピアノと作曲を専攻。プレイに力強さとグルーヴ感を持ちつつ、センスがある。音が立っているのもいい。ビル・エバンスやキース・ジャレット、ブラッド・メルドーのような神経質なところがなく、ダイナミックで奔放で遊びの精神に満ちているのがいい。エネルギーにあふれた若者の登場はたのもしい。
早速彼の新作『トゥ・シェイド』(Emercy)を聴いてみたが期待に違わずいい。ジョー・サンダース(B)、ジャスティン・ブラウン(Ds)のトリオだが、ちょっとロックよりのビートを使った『ブーガ・ブルース』の若者らしいのびのびとしたプレイが面白かったので「PCMジャズ喫茶」に持ち込んだ。寺島氏を含めて悪くいう人はいなかった。あの渡辺貞夫も彼のプレイを気に入っていて新作『イントゥ・トゥモロー』(Victor)で起用している。今みんなが彼のピアノに注目しはじめているが、確かに今後の新しいジャズ・ピアノ界を担っていく一人になりそうだ。
成熟したベテランのプレイも勿論必要だが、昔からジャズ界を活性化してきたのは才能ある若者たちだった。最近来日した女性サックス、クラリネット奏者のアナ・コーエンといい、N.Y.の若者に元気が出てきたようである。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2009年09月/第68回 ニシオギとJAZZ
2009年09月/第68回 ニシオギとJAZZ
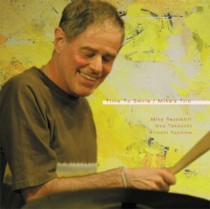
吉祥寺に住んでいるが隣町の西荻窪が好きでよく出掛けてゆく。雑踏の吉祥寺から電車で2分離れるとそこはもう都会の田舎町といった風情でいささかのわびしさがあり、そこが気に入っているのだ。ぶらぶら歩いて古本屋をひやかし、昔からあるダンテの珈琲をのみ、仕上げは丸福の中華ソバとガシッと冷えたビールの中ビン一本という小幸福のパターンをここ10年ほど繰り返している。西荻窪は普通「ニシオギ」と呼ばれていて、そうなると一層わびしさが募ってくるが、そういう西荻窪にこれほどふさわしい店はあるまいというのが「アケタの店」だ。
もっとも私も人さまのことを言えた義理ではない。私の店「メグ」がライブハウス化して久しいが、その汚さ、わびしさゆえにライブハウスの名をけがしているんじゃないのか。吉祥寺には「サムタイム」や「ストリングス」といったライブの名店舗があり、実にゴメンナサイといった塩梅なのだ。私も小綺麗な店が欲しい。
「アケタの店」というと有名な伝説がある。ああ、あれかと察した人は読まなくてもいいが、ある人が「アケタの店」を訪れると、お客が3人いた。演奏時間になるとその3人が舞台に上がって結局ラストまでお客はその人だけ。途中帰るに帰れず、苦悶の数時間を過ごしたという話。
まったく涙を誘う話ではあるが、私の店だってその強力伝聞に負けないぞ。と、威張れた話ではないがミュージシャン5人に客が3人などというシチュエイションがしょっ中だ。さて支払いをどうする。ミュージック・チャージが3人で7,500円。一人の受け取り分1,500円。ベーシストなど駐車場代にもならない。リーダーは本日は持ち出しライヴですなどとアナウンスして笑っているが、いや、店側だって大赤字。売り上げが4,000円に届かず人件費も出ない有様だ。
まあ、月に何回か席の埋まる日があってそれで首を吊らずに済んでいるが、ライブハウスはいずこも同病相哀れむといった現状なのだ。頼む。せいぜい通ってくれや。
さて、「アケタの店」が経営発売する『アケタズ・ディスク』からマイク・レズニコフの「タイム・トゥ・スマイル」が近頃の新譜として発表された。マイク・レズニコフのドラムに竹内直のテナーとクラリネット、吉野弘志のベースというピアノレス・トリオだがピアノレス・トリオという形式がどうのという問題ではない。そんなのは目的に対する手段で目的は「ロンサム」「アイ・サレンダー・ディア」「ハート・オブ・マイ・ハート」といった微光というか寂光というか、鈍い光りを放つ珠玉のB級、いや、C級D級曲群のまさに胸に迫り来る『ニシオギ・ジャズ』的うらぶれ感にある。うらぶれてはいるけれど、卑しくない。うらぶれが胸を張っている。そこが賞すべき決定的に大事なところである。私はドンと一発後頭部をはたかれた思いがした。
『アケタズ・ディスク』のこれまでの作品すべてが好きなわけではない。否、むしろ少なからず異和感があった。しかしこの一作を耳にして私は過去の作品を洗い出してみたくなったのである。そのくらいの静かなハイ・パワー、静かなハイ・テンションを持っていた。概して見かけ倒し、うそっぱちのテンションなどで固めたピカピカのニューヨーク・ジャズやマンハッタン・ジャズ。恐れ入ってこうべを垂れてこれを聴け!
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2009年08月/第67回 ニューオーリンズのパワー
2009年08月/第67回 ニューオーリンズのパワー
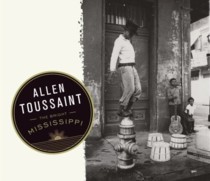
アメリカの南部ニューオーリンズは特別な都市だ。北東部のニューヨークから南部に行くと景色も一変する。「風と共に去りぬ」などに出てくる南部特有の樹も南部の風景を彩る。ジャズの歴史が進んでも、ニューオーリンズは依然として『ジャズ・シティ』だ。ハリケーン・カトリーナに襲われた後はまだ行っていないが、その少し前に行ったときは、ビアホールで昼間からデキシーランド・ジャズが聴けたし、テーブルには灰皿がごろごろころがっていた。ジャズのライブ・ハウスもいくつかあり、観光名所の『プリザベーション・ホール』はいつも満員の盛況だったし、ジャズ・クラブにはマルサリス兄弟の父親エリス・マルサリスが出演していたし、朝方まで騒がしいサンバ・クラブもあった。ニューオーリンズ・ジャズ博物館は先人たちが使った楽器や貴重な資料がいっぱい展示されていて多いに楽しめた。昼間街を歩けば、あちこちでストリート・ミュージシャンの演奏を楽しむこともできた。黒人の親子の演奏もあれば白人の美女トランぺッターがショート・パンツ姿で演奏していてしばらく見とれていたものだった。とにかく活気とエネルギーを感じさせる街だった。
こんなニューオーリンズの風景を思い出したのは、最近『アラン・トゥーサン/ザ・ブライト・ミシシッピ』(Non Such)を聴いたからだ。近頃聴いたジャズ・アルバムの中でも、もっとも感銘を受けた一枚だった。早速『PCMジャズ喫茶』に持っていってかけた。曲は「セント・ジェイムス病院」を選んだのだが、口の悪い寺島靖国氏も「これはいい」とほめた。実は僕はこれまでアラン・トゥーサンのことはよく知らなかった。それで、レナード・フェザーが編集した1999年版『ジャズ人名事典』を調べてみたが、彼の名はなかった。かれはソウルやロック、ファンクのアーティストというのだろうか。しかしこの『ザ・ブライト・ミシシッピ』はどう聴いても創造的ですぐれたジャズであり、南部やニューオーリンズ・ジャズのスケールの大きさをみせつけたもので、昨今のひ弱なモダン・ジャズなどを圧倒してしまうものがある。
アラン・トゥーサンはニューオーリンズの黒人ピアニスト、歌手、作編曲家、プロデューサーである。ハリケーン・カトリーナに襲われた後、一時ニューオーリンズを離れざるを得なくなっていたが、最近はもどり、故郷とニューヨークを行き来して仕事をしているが、先日来日してライヴ・ハウスにも出演した。彼の演奏を聴くと、ニューオーリンズの復活と『ニューオーリンズは死なず』を実感することができる。今回の『ザ・ブライト・ミシシッピ』は黒人霊歌からトラッド、キング・オリバーやジェリーロール・モートン、シドニー・ベシェからジャンゴ・ラインハルト、デューク・エリントン、セロニアス・モンクにいたるまで、まるでジャズの歴史をカバーするような選曲をおこなっており、それをすべて南部やニューオーリンズに集約するような形で演奏し、表現している点に驚嘆し、圧倒される。
また、集められたドン・バイロン(cl)、ニコラス・ペイトン(tp)、ブラッド・メルドー(p)、ジョシュア・レッドマン(ts)といったモダン派といわれる人たちが、すっかりアラン・トゥーサンの音楽に融け込んでいるのにも驚かされるが、ジャズをスタイルで分類することの無意味さを教えてくれる、皮肉で、批評家精神にあふれたアルバムではなかろうか。
上記「セント・ジェイムス病院」もいいが、アルバム・タイトルにもなっているセロニアス・モンクの『ブライト・ミシシッピ』がとても面白い。モンクの音楽からユーモアの精神を引き出しているのも正解だが、ドン・バイロンのクラリネットをフィーチャーしてロック・ビートのブラス・バンド風の演奏を展開してみせる独創的なアイデアには感心してしまった。
また、デューク・エリントンの作品を2曲『デイ・ドリーム』と『ソリチュード』を演奏しているのにも注目した。エリントンはニューオーリンズ出身ではなくワシントンD.C.生まれだが、ぼくは日頃「エリントンの音楽にはジャズのすべてがある」と言っているだけに興味深く聴いた。『ソリチュード』はトゥーサンのグルーヴィーでどこかファンキーなピアノとマーク・リビットのアコースティック・ギターだけで演奏されるが、『エリントンも黒人であり、彼の音楽ルーツのひとつがニューオーリンズにあるといえるのではないか』と主張しているようにも聴こえてきて感心した。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2009年07月/第66回 長澤祥という人
2009年07月/第66回 長澤祥という人

220歳トリオの一角が崩れた。長澤祥さんが「PCMジャズ喫茶」をおやめになったのである。
長澤さんは以前から隠遁生活に憧れていた。家に閉じこもり、気が向けば(ほとんど毎日気が向いていたのだが)昼間から酒を飲み、電気を暗くしてジャズを低く聴く長澤さんだからすでに充分隠遁生活者なのだが口を開けば「田舎に行きたい」を繰り返していた。しばらく前にも何ヶ月か奈良のほうの山奥に籠り、とても商品になりそうにない(失礼!)丸いエントツのような形をしたスピーカーを設計、製作に励んでいた。隠遁のきざしはすでにしてあったのである。
しかし今回はどうも本物のようだ。決心は固い。74才。決断の歳かもしれない。
実は私は長澤さんのジャズの聴き方に敬意を払っていた。ご自分の『聴き方』を持っている。そのことを大したものだと思っていた。しかもそれがいささかもぶれない。聴き方が大地に根を張って微動だにしないのだ。私など今だにふらっとくることがあり、いい歳をして不甲斐ないなと思ったりしているのにである。
長澤さんのジャズの聴き方は徹底した自分主義である。この方くらい気分よく個人主義を楽しんでいる人はいない。人の言に左右されない。一部のジャズ・ファンのように観念的にジャズを聴くことをしない。頭の中でジャズを鳴らすのではなく、あたかも手を延ばして音楽に触れるような聴き方だ。触ってみてうまく自分に反応しなければ蹴っ飛ばす潔さを持つ。だから長澤さんは音楽に聴かされない。常に自分が上位にいる。ジャズ・ファンでこういう人は案外少ない。幾山も越えた人が出来ることである。
長澤さんはまた、音でジャズを聴く人である。音楽と音を同時に両方楽しんでしまうのであるから得な人である。普通の人は片方しか聴かないから損をしているのである。ベースが特に好きで、ベースの音はとにかく弦の感じがはっきり出た「ブルン」という音が聴こえないと承知しない。そのことを放送で何百回繰り返したことだろう。耳にタコが出来て、今では私のまわりにベースはブルンでなければ駄目な人が何人もいる。
こういう美しく格好よく偏った聴き方を麗々しく説く評論家はいない。バランスという言葉しか発しないのが本邦のオーディオ評論家である。音がどこかで一カ所突起して面白くなるのがジャズという音楽なのである。ベースとかシンバルとか。もっと長澤さんのような音楽と音の両方をよく分かった人を日本のオーディオ界は活用しなければ駄目だ。
とまあ、ずいぶん長澤さんを持ち上げてしまったが、長澤さんが一風変わった人であるのは間違いなく皆さんご承知の通りである。約束しても来なかったり、約束してないのに来たり、今では我々はぜんぜん彼の奇行に驚かない。田舎に雲隠れしてもすぐに戻ってきてもまったく不思議はないのであり、その時は大歓迎である。
一応、田舎でのんびりラテン・ピアノでも聴いてもらおうと思って写真のCDを捧げてみたが無駄になるのを祈っている。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2009年06月/第65回 ビッグ・バンドの楽しさ
2009年06月/第65回 ビッグ・バンドの楽しさ
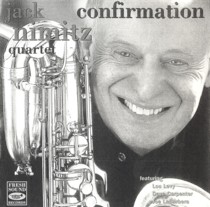
日本人はジャズではピアノ・トリオが好きなようだが僕はビッグ・バンドが大好きだ。アレンジメント、アンサンブル、ソロと楽しみが多いからでもある。日本でも最近、守屋純子、野口久和、三木俊雄がときどきビッグ・バンドの演奏を聴かせてくれるし、レギュラーのビッグ・バンドもいくつかあるが、シャープス&フラッツが今年で姿を消し、ニューハードなくなったのは淋しい。そして、日本のビッグ・バンドも少し行儀がよすぎる気がする。
かつてトランぺッターの大野俊三は、ギル・エバンスのビッグ・バンドにいて、毎週月曜日に”ヴィレッジ・ヴァンガード”や”スィート・ベイジル”に出演していたのを聞いたことがあるが、ギルは彼にいつも、譜面どおり吹かなくてもいい、自分が飛び出したいと思ったらそこでソロを取れ、と言っていたそうである。ギルのバンドのエキサ イティングな演奏は、そういったバンドのあり方から生まれたのだと思う。
また黒人のクリフォード・ジョーダンのビッグ・バンドを何度かニューヨークで聴いたが、昔のハーレム・バンド風で楽しかった。セカンド・ステージが始まっても、何人かのミュージシャンが外出したまま戻っておらず、歯抜けなのだがリーダーは平然と演奏をはじめ、抜けていたメンバーもそのうち一人、二人と戻ってくるのだが、悪びれずに演奏をはじめ、リーダーもとがめないのだ。そののんびりとした風景にぼくは、これがジャズというものなんだ、と感じた。
僕はニューヨーク在住のピアニスト・なら春子と一緒に聴きにいっていたのだが、リーダーのジョーダンは、よく知っている彼女を客席に見つけるとステージに呼び上げ、あまり編曲のいらないブルースを一緒に演奏した。また別の日にはサックスのジョージ・ブレイスやトランペットのデイジー・リースが遊びに来たのだが、すぐにステージに呼び上げ一緒に演奏した。たとえビッグ・バンドでもこれが本当のジャズのあり方なのだ。日本のビッグ・バンドもこのようなルーズさを取り入れて欲しいものだ。
ところで西海岸にいくと、ウエスト・コーストならではの面白さがある。ハリウッドは映画の都なのでスタジオ・ミュージシャンが多く、ビッグ・バンドもたくさんあるが、故ベイリー・ジェラルド・ウィルソン、フランク・キャップらのビッグ・バンドをよく聴きに行ったが、どのバンドにも何人か同じミュージシャンが座って演奏しているのを見かけた。バリトン・サックスの座には複数のバンドでジャック・ニミッツを見かけた。彼は西海岸一のビッグ・バンド・バリトン奏者なので引く手あまたなのだろう。一時西海岸にいた秋吉敏子の話だと、西海岸ではアレンジャーやビッグ・バンド・リーダーには自ずとランクがあり、先に契約していても、ランクナンバ-1のクィンシー・ジョーンズから声がかかると、メンバーをクィンシーに取られてしまうケースがあるのだとか。ジャック・ニミッツは、ウディ・ハーマン、スタン・ケントン、ジェラルド・ウイルソン、ビル・ベリー、ルイ・ベルソン、ドン・メンザなどの有名ビッグ・バンドを渡り歩いてきた名手であり、スーパー・サックスでも演奏した。
その彼の珍しいコンボ演奏の『コンファメーション』(フレッシュ・サウンド)を中古CDの箱で見つけたので、すぐに買って早速『PCMジャズ喫茶』で紹介したら幸い好評だった。「センチになって」や「ハロー・ヤング・ラバーズ」といったスタンダードのほか、スーパー・サックスやチャーリー・パーカーのアドリブを軽々と吹いてみせてびっくりさせた「コンファメーション」や「ブルー・モンク」「ブルー・ボッサ」といったジャズ曲も演奏している。西海岸では、ビッグ・バンドで演奏した後の彼に何度も会ったが、いつも笑顔をたやさない礼儀正しい紳士という印象を受けた。
なお、上記のアルバムは、ルー・レヴィ(P)、ジョー・ラバーバラ(Ds)らと共演したカルテット、95年、彼が65歳の時の演奏である。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2009年05月/第64回 遠くて近いジャズとオーディオの仲間
2009年05月/第64回 遠くて近いジャズとオーディオの仲間

私の部屋には地方からもジャズファンが時々やってきます。
岐阜の20代の女性・Kさんが突然やって来ました。「PCMジャズ喫茶」を聴いているうちに好奇心が湧いてきたというのです。寺島さんや岩浪さんは恐れ多いので流石に訪問は出来ないという言い訳でした。放送で声だけ聴いているうちに我々がどんな風体なのか検証したいということで、新幹線でやって来たのです。
2時間ほどオーディオルームでジャズを聴いていましたが、無口な彼女からの会話は無く、私からの質問ばかりでした。彼女はハイとかイイエとか答えるばかりで、家出の女性と会話しているような雰囲気がしばらく続いたのを憶えています。
名古屋市内のジャズ喫茶には時々通っているという話が糸口でした。ジャズと読書が余暇の楽しみですという彼女は、小柄ながら凛とした顔立ちで、次第にジャズの好き嫌いを話し出しました。帰る途中ジャズカフェ「メグ」に寄りたいというので地図を書いて別れました。その数か月後に彼女から宅配便で柿が届きました。
九十九里浜の近くに住む初老のオーディオファンMさんが2時間かけて車で遊びに来たことがあります。はがきで連絡があり約束をしていました。10数枚のCDとお土産などを袋にどっさり詰めて汗をかきかき部屋に入ってくるなり、私の装置をこまごまと尋ね始めて立ちつくしています。それからオーディオ人生を延々と話し始めたのです。自慢話ではなく苦労話です。ストーリーの多くはスピーカーシステムやアンプの自作と音にこだわったジャズアルバムのコレクションであったと思う。収入の大半を道楽に費やしてカミさんと喧嘩が絶えないという話にもなりました。
オーディオ自慢で有名な方の自宅を数件訪問したという話になり、本当か嘘かも定かでありません。訪問した先々で必ず試聴したというCDがこれですと言う。ディブ・ブルーベック・カルテットの「GONE WITH THEWIND」(Sony Records SRCS9362)、1959年ロス録音です。確かに音は素晴らしい。特にポール・デスモンドのアルトサックスの音色には聴き惚れてしまいます。私が気に入った様子をみたのかCDをしばらく預けるので、後で返して欲しいということになりました。それならと私も好意を受けて借りることになったのです。このアルバムを何十回聴いただろう。今も手許に残っています。というのは約束通りCDを返送したのですが、受取人不明で戻ってきてしまいました。
ディブ・ブルーベックを初めて聴いたのは昭和28年高校生の頃で深夜VOA(Voice Of America)放送でした。当時短波放送で野球の中継を聴いていましたがVOAを受信してジャズを聴くことも出来たのです。マイルスのレコードも連夜流れていました。その後、日本でもブルーベックのシングル盤が発売となり直ちに買ったのを憶えています。「ブルーベックのピアノはスィングしない」などとジャズ雑誌で書かれていましたが、ポール・デスモンドのアルトサックスを聴いているだけで満足です。ピアノはおまけで聴いていたように思います。
アルトサックス吹きを3人挙げろと言われれば文句なしにアート・ペッパー、バド・シャンクとポール・デスモンドではないでしょうか。ピアノトリオは飽きたのでワンホーン・カルテットを聴こうという掛声が出ていますが、残念ながら現役プレーヤーでこれら3人を超える者はおりません。テナーサックスを含めて今は管楽器プレーヤーにスター不在の時代となってしまったのです。
話は脱線しますが女性はアルトサックスを好み、男性はテナーサックスに惚れるというのは本当でしょうか。
アルバム「風と共に去りぬ」はアメリカの民謡ばかり集めた構成で「スワニー・リヴァー」「ロンサム・ロード」「草競馬」「ベィズン・ストリート・ブルース」「オール・マン・リヴァー」と「ゴーン・ウィズ・ザ ・ウインド」など9曲が収録されています。ほかメンバーはジーン・ライト(b)ジョー・モレロ(dms)でピアノやアルトサックスに負けないくらい鮮やかな音の輪郭で鳴るのです。ブルーベック数多いアルバムの中でこれは最高傑作です。新素材をベースにした再発CDが各社からリリースされていますがこれはぜひ新技術で復刻して欲しい1枚です。
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年生まれ。オーデイオメーカー数社を経て、日本オーデイオ協会事務局長を15年務める。
 2009年04月/第63回 お酒とマイナー・レーベル
2009年04月/第63回 お酒とマイナー・レーベル

今は夜中の2時半だが重い腰を上げてこの文章を書きはじめた。
文章を書くにはある種の度胸が要る。自分をいつもより強くもっていかなくしてはいけない。亡くなったジャズ・ファンの鍵谷幸信さんは「物を書く人間は自分を天才と思わなければ、いいものは書けないよ」と言ったがそれは無理だ。天才と思うには余りにも自分を知りすぎている。
それで酒に頼ることになる。うまい具合に最近ウィスキーのお湯割りに凝っている。「ウィスキーはロックだろう。氷がグラスの中でカキンと音を立てる。そいつを聞きながら一杯やるのが粋なんだよ。」そう言われても当方、もう格好つける歳でもない。年寄りにはじわりと体があたたまるお湯割りが一番だ。熱湯をそそいだ時の鼻をつく強いウィスキーの香り。これはちょっとしたものである。ニュー・センセーションである。新しい恋の芽ばえである。やがて時間が経つとお湯がさめてくる。すると香りがだらしなくなってくる。恋の終わりである。
それはどうでもいいが、書けないとつい頻繁にグラスに手が延びる。当然酔っぱらってくる。すると本当に書けなくなってしまう。酔っぱらっているような、いないようなその微妙な中間地点の維持がむずかしい。なぜ今回酒の話から始めたかというと、ガッツ・プロダクションの笠井青年。この人が無類の酒好きなのだ。この人もけっこう中間地点の維持がむずかしい。大抵いつもセイフティ・ポイントを突破して宇宙の彼方で彷徨することになる。酒を飲んで地球にとどまっていても仕方ないだろうという広大な精神が天晴れである。愛すべきジャズ一筋の好青年。このCDがよく売れない時代に、ガッツ・プロのCDは出足がいい。迅速とはいかぬまでも快速である。
そういえばもう一社、俊足テンポを保持しているマイナー・レーベルがある。澤野商会である。この会社とガッツ・プロを比較するとその好業績の秘密が見えてくる仕掛けになっている。
澤野商会はジャズをとことん骨のズイまでわかった上で、あのような聴きやすい、しかし充分マニアの鑑賞に堪える新譜名盤を出してくる。ビギナー向けにしてマニア向けという絶好の境地。 一方のガッツ・プロはジャズの詳細には不案内だけれど「自分の耳に気持ちよく響いたもの」を主に選んで発売している。ジャズの知識背景にこり固まったマニアックな耳ではない。普通の好センスの耳。そういう耳が世に問うCDだからこそ誰が聴いても平易で楽しく心に残る。
特に昨今の輸入CDは気張ったものが多い。ピアノ・トリオにしろ『俺トリオ』みたいにいきがった作品が多く、買って失敗し蹴飛ばしたくなるが、澤野商会とガッツ・プロダクションなら安心というものだ。両社にはマイナー・レーベルの雄として末永く頑張って欲しいものである。
ウィスキーのお湯割りのせいで例の『微妙な中間地点』をこえてしまったようなのでこの辺で失礼。
■ガッツ・プロダクション http://www.gatspro.com/
■澤野工房 http://www.jazz-sawano.com/
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2009年03月/第62回 コンボの出現はジャズを活性化するか?
2009年03月/第62回 コンボの出現はジャズを活性化するか?

ジャズのCDは毎年沢山発売されているのに、最近は何か核になる演奏がないなあ、と感じていた。ところが、昨年末あたりから少し様子が変わってきたように思える。
そのきっかけになったのが、イタリアのグループ、「ハイ・ファイヴ」の登場で、その第一作「ファイヴ・フォー・ファン」(EMI)を聴いたとき、心のどこかで、待っていた演奏はこれだ、と確信した。リーダー格のトランぺッター、ファブリッツィオ・ボッソの輝かしいプレイもさることながら、クィンテットの力感あふれるプレイにも圧倒された。シダー・ウォルトンやジョー・ヘンダーソンら60年代の新主流派の曲も取り上げているので、全体的にはニュー・ハード・バップと呼びたい演奏なのだが、アドリブはどこまでもメロディックで、ドラミングが昔の演奏と違って多彩なので新鮮に感じるのだろう。ボッソは昨年の「銀座ジャズ祭」にはラテン・バンドをひきいて来日したがこちらもエキサイティングで悪くなかった。
これらの演奏を聴いているうちに、やっぱり最近はイタリアやヨーロッパのジャズの方がアメリカよりも元気がいいのかなあ、と思ったものだった。
ところが、ニューヨークのジャズも黙ってはいなかった。「ブルーノート・セブン/セレブレーション」(Bluenote)がそれで、これはハイ・ファイヴに充分対抗できる演奏だった。N.Y.の精鋭で結成されたグループで、ニコラス・ペイトン(tp)、ラヴィ・コルトレーン(ts)、スティーヴ・ウィルソン(as,fl)、ピーター・バーンスタイン(g)、ビル・チャーラップ(p)、ルイス・ナッシュ(ds)、ピーター・ワシントン(b)という7人編成。これは最強の顔ぶれだ。悪かろうはずがなく、しかもイタリアの連中と同じように、ジョー・ヘンダーソン、ハービー・ハンコックら新主流派らによる曲を取り上げているのだ。まるで申し合わせたように。したがって演奏もニュー・ハード・バップ的なのだ。海をへだてた国で同じようなフレッシュ・サウンドが生まれ、これは面白いことになりそうだが、共にレギュラー・グループ化するというのが嬉しい。ブルーノート・セブンはなんでも今年全米45ケ所のツアーを行うという。
とにかく、ジャズの活性化はレギュラー・グループの出現によって行われるだろうというのが僕の見方である。思い返せば1950年代から60年代の中頃にかけては、モダン・ジャズの黄金時代と呼ばれたが、この時期には、実に沢山のレギュラー・コンボが活躍していた。枚挙するときりがないほどだが、マイルス・デイビス・クィンテットを筆頭に、ジャズ・メッセンジャーズ、ホレス・シルバー・クィンテット、ローチ・ブラウン・クィンテット、キャノンボール・アダレイ・クィンテット、ジョン・コルトレーン・カルテット、ジャズテットなどが人気を競い、ジャズ・シーンを活気あるものにしていたと思う。
レギュラー・グループの魅力と良さは、トータルな表現や主張が長く一貫して行える点にあると言えるだろう。それが、一回だけのセッションだとなかなかそうはいかないし、一過性で終わってしまうことが多いと思う。レギュラー・グループを待望してきたのはそのためだが、まだハイ・ファイヴとブルーノート・セブンの2つだけでは満足できない。そう思っていたところへ、こんどはアメリカ西海岸のコンコード・レコードから「ベニー・ゴルソン/ニュー・ジャズテット」が発売された。あの懐かしい三本管編成によるジャズテットの再編である。しかし、昔のままのグループ再結成ではノスタルジーだけで終わってしまう。しかし今回のニュー・ジャズテットは、リーダーと作、編曲こそ大ベテラン・テナー、ベニー・ゴルソンだが、メンバーの顔ぶれはがらりと変わっているし、ゴルソン自身のテナーがこれまでのプレイと違って、サウンドも吹き方も少し新しくなろうと務めており、変身しているのがいい。メンバーはエディ・ヘンダーソン(tp)、スティーヴ・デイビス(tb)、マイク・ルドン(p)、バスター・ウィリアムス(b)、カール・アレン(ds)で、ベテランもいるが、旧ジャズテットよりもガッツがあり、感覚的にも新しい。感心したので早速グルーヴィーでファンキーな「グローヴス・グルーヴ」をPCMジャズ喫茶でかけた。すると、日頃口の悪い寺島靖国、長澤祥の両氏も気に入ったようで文句は出なかった。まだこのグループの行く末はわからないが、僕はぜひレギュラー・グループ化し、ジャズ活性化の一翼を担って欲しいと願っている。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2009年02月/第61回 So What(だからどうなの?)
2009年02月/第61回 So What(だからどうなの?)
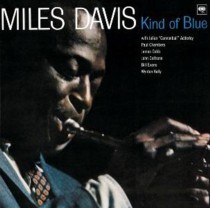
新譜CDの数を越えて名盤の復刻盤が続々と発売になっています。単なる復刻ではなく最新の製盤技術が駆使されたという宣伝文句がジャズとオーデイオ・ファンの心を刺激するのは当然でしょう。24ビットといった従来の電気的改善も行きわたった現在レコード各社が注目しているのは製盤の素材です。ガラス盤の導入などの実例もありました。従来から使用されてきたポリカーボネィトを更に改良した素材の応用と製造工程のノイズ低減です。すでに新素材によるHQCDやSHMCDも発売となっています。
そこで「PCMジャズ喫茶」の録音スタジオで音質の比較試聴を行いました。先入観を排除したブラインドテストです。2枚のCDを聴き終わってからどちらが新旧かの意見も述べました。リスナーの皆さんにも放送で判定してもらう企画です。音の良し悪し以外に好き嫌いもあるので判定が間違ったとしてもいいのです。
ソニーミュージックからも「Blu-spec CD」の発表があり、六本木のスタジオで聴くことが出来ました。その特徴は資料と解説によれば「正確なピット成型によりジッターの発生を極限まで排除したマスターテープクオリティCD誕生」とありました。具体的には「ブルーレザー・ダイオードを使ったカッティングによる極微細加工と空冷フアンによる振動を除去した製盤行程」さらに「新開発の素材である高分子ポリカーボネィトの採用」です。
数人ずつ6回に分けて試聴会が行われるというので、指定された時間に合わせて六本木駅にたどりつくと、ジャズオーデイオ評論家のKさんとばったり会いました。何年間かジャズ専門誌「スイング・ジャーナル」で録音評を担当してきた間柄です。
ソニーのスタジオでは試聴の音源としてクラシックやポップスをはじめとした、各音楽ジャンルの曲が紹介されました。ジャズはマイルスのヒットアルバム「Kind of Blue」から、『So What』を従来盤とブルースペック盤との聴き比べです。楽器の輪郭はより鮮やかになり、全体的にノイズ感が無くなったのは確かです。ジャズファンのKさんと私もそこは納得したのです。『So What』はアナログLPや最初のCDで、音は耳の奥まで記憶されていました。
問題はここからです。比較試聴の結果を例えれば、薄ものを着ていた美人が素裸になって現われたような印象です。もしマイルスが再再発の復刻CDを聴いたら、口癖の『So What』と云うかもしれません。
吉祥寺のジャズカフェ「メグ」でビールを飲みながらこの話を聞いていたS君は、「CDが再発されるたびに買ってしまうから、同じアルバムが何枚も溜まってしまう。だから古いのは友達にあげることにしています。」と云うのです。再発CDは誰が買うのだろうと疑問を持っていた私への回答にもなっていました。
ジャズレコードをそのまま聴かないで自分の好みの音に再調整して聴くのがジャズオーデイオの極意ではないかと思っている私には、オリジナル音源再生への願望はありません。オーデイオ純粋主義者からみれば異端児なのです。
にもかかわらずアナログLPを探してレコード中古店をうろついているには理由があります。アナログLPでしか味わえないジャケットの存在感(大きさや色など)という誘惑には負けてしまうのです。レコードを買うというよりは、絵画を買うという感覚かもしれません。
そのS君がなんとイラストで描かれたオリジナル・ジャケットだけを集めた写真集を出すというので、原稿を見せてもらう機会がありました。仲間うちで囁かれている幻の名盤も数多く入っています。出版されれば直ちに購入すると約束したのでした。
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年生まれ。オーデイオメーカー数社を経て、日本オーデイオ協会事務局長を15年務める。
 2009年01月/第60回 個性を隠す個性
2009年01月/第60回 個性を隠す個性

今日はジャズ・ミュージシャンの個性というものについて書きたいです。
個性ほど大切なものはないと言われています。どうしてかというとジャズは伝承の音楽、ありていに言うとコピーの音楽ですから個性が大切ということにしておかないと皆、先輩と同じになってしまうのですから個性、個性とうるさいのです。
個性自体は悪いことではありません。大いに結構。ソニー・ロリンズやジョン・コルトレーン。立派な個性です。しかしいくら立派と言われても、あなた、あなたですよ。
もし好きになれなかったらどうします?
私、毎度申し上げているように駄目なんですね。御両人とも。強過ぎて。吹き方の個性が。一曲二曲なら「おお、いいなあ」と思います。けれど、2~3曲続くともうげんなり。個性というのは『自分の好きな個性』に限るんですね。
さて、そこで私の好きな個性というのを申し上げましょう。テナー・サックスで言うなら自分を殺して好きな曲の旋律を目いっぱい満開にして吹いてくれる人。そういう個性を持つ人を私は求めています。
いませんね、そういう人。最近。どこぞにいないかそういうテナーマン。いたら一作CDを作りたい。
ドラムの松尾明さんが紹介してくれました。高橋康廣さんです。
「むずかしいなあ」。開口一番高橋さんはそう言いました。「あなたが言うように、テーマを崩さずにメロディーをろうろうと歌い上げるってのが一番大変なんですよ」。
だからミュージシャンってみんなして曲を崩して、変なくせで吹いてそれを個性と称している。個性をかくれみのにしている。
さすがに高橋さんはそこまではおっしゃらなかったが、性格の悪い私はそんなふうに邪推したわけです。
「例えばどんな曲ですか?」高橋さんは聞いてきました。
「『リンゴの木の下で』なんかどうでしょう。」
「どんな曲でしたっけ?」
私歌いましたよ。黙っているわけにはゆかない。ミュージシャンの前で曲を口ずさむって大変なんですけどね。『冷や汗三斗』というやつです。
「うーむ。」
再び高橋さんは考え込みます。
さてレコーディングの当日、一曲目に『リンゴの木の下で』がスタジオから聞こえてきました。
実は高橋さんは52歳の大ベテランです。吹こうと思えばコルトレーン風だろうがロリンズ風だろうがスタンリー・タレンタインだろうが自由自在のテナーマンだそうです。
しかしスタジオから聴こえてきた『リンゴの木の下で』はもちろんそのどれでもない『個性を殺した』高橋さんのテナーでした。『リンゴの木の下で』をともかく高橋さんはストレートに真っすぐに歌い上げています。一節たりとも崩していない。崩そうとしない。自分を押し出すのではなしに『曲を吹く』ミュージシャンという境地に自分を持っていっています。
ジャズのミュージシャンにとって曲は演奏のための素材といわれています。しかし、高橋さんはあえて曲の『しもべ』になったのです。曲に勝ちを譲ったのです。
これが、しかし、結果的に強い個性となりました。そんなふうに演奏するミュージシャンなんてどこにもいませんからね。シンプル・イズ・ビューティフル。美旋律が身ぐるみはがされてもだえている。うそだと思ったら聴いてみて下さい。
自分のプロデュースしたCDをこのページで書くのは本意ではありませんでしたが、ご勘弁願います。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2008年12月/第59回 ブラウン/ローチ・クィンテットを聴き直す
2008年12月/第59回 ブラウン/ローチ・クィンテットを聴き直す

ここのところ「ファイブ・フォー・ファン」のファン・ファイズや「ブルーノート・セブン」といったグループ名のつくアルバムが発売されたが、活気があり、これからのジャズを示唆するようなすてきな演奏だった。グループの演奏だと、ワン・タイム・セッションにはない、グループとしての主張と個性が見られるからだ。これらのグループの出現には今後のジャズの活性化を予感させられる。
振り返ってみると、50年代の中頃からの10年間くらいは、人気グループがあり、ジャズはまれにみる活況を呈していた。ジャズ・メッセンジャーズ、マイルス・デイビス・クィンテット、ブラウン・ローチ・クィンテット、ホレス・シルバー・クィンテット、キャノンボール・アダレイ・クィンテット、ジョン・コルトレーン・カルテット、チコ・ハミルトン・クィンテット、デイヴ・ブルーベック・カルテットなどが人気を競い合っていた。
その中でもブラウン・ローチ・クィンテットは最強のコンボの一つだったと思う。リーダーを務めた二人、マックス・ローチとクリフォード・ブラウンは旗揚げする前にロスアンゼルスでアパートを借りて共同生活をしながら周到にプランを練り、選曲し、アレンジも行った。
ただテナー・サックス奏者だけがなかなか安定しなかった。最初のテナーはソニー・スティットだったが、すぐにやめた。スティットが来日した時、話を聞くと、そうだと言う。「ライヴでは何度か演奏したし、その録音テープは俺が持っているよ」と言ったが、彼が亡くなったのでそのテープの行方はわからない。このあとテナーはテディ・エドワーズ、ハロルド・ランド、ソニー・ロリンズと変わっていく。
ところで、『PCMジャズ喫茶』ではここ何回か過去の名盤を聴き直して検証するという企画をやっていて、順番が回って来た時、僕はブラウン・ローチ・クィンテットの中でも、いちばん好きで、最高の演奏だと思う「ジョイ・スプリング」をかけた。
僕がまだ四国の松山にいた1955年から56年ごろ、毎週日曜日の午後3時から30分間、岩国のFENの番組「ベイズン・ストリート」でこのグループのライブを放送していて、この時間だけは外出もせず、ラジオにかじりついて聴いていた。中でも「ジョイ・スプリング」に惚れ込んだが、この曲については思い出がある。
毎年ロスアンゼルスのホテルでは北村英治オールスターズも加わって日米合同のインターナショナル・ジャズ祭が開催されていたが、1996年はクリフォード・ブラウンの没後40年ということで、コンサートがブラウンに捧げられた。ブラウン夫人も招待されていて、僕はたまたま同じテーブルになったのだが、「アイ・リメンバー・クリフォード」が演奏されると、夫人は夫の思い出がよみがえって来たのだろう、目頭をおさえていた。この席で彼女に、僕がいちばん好きなのは「ジョイ・スプリング」だと言うと、彼女もそうだと言い、この曲のエピソードを話してくれた。
「クリフォードとはロスの空港でマックス・ローチに紹介されて会ったんです。お互いに一目惚れで、すぐに付き合いはじめました。ある日ブラウン・ローチ・クィンテットの演奏を聴きにいくと、いつもMCはローチなのに、その日はクリフォードがマイクの前に立ち、僕はまもなく、今このクラブに来ているラルーという女性と結婚します。今から彼女に捧げて書いた曲を演奏します。と言ったんです。そして、その曲が「ジョイ・スプリング」だったんです。だから今もこの曲がいちばん好きなんです。」
そして、ラルー夫人は赤ワインを2杯もごちそうしてくれた。「ジョイ・スプリング」は曲名通り、喜びにあふれた春のように、温かくて美しいメロディーをもった光り輝くような曲であり、歌いたくなるほどだ。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2008年11月/第58回 色気とは何ですか
2008年11月/第58回 色気とは何ですか

裸の放浪画家と云われた山下清は素朴な質問を連発したことでもあ知られています。「色気とは何ですか」は、その代表的な質問ではないでしょうか。
PCMジャズ喫茶では店主の寺島靖国さんの独断でゲストをスタジオに呼ぶことになりました。ゲストの1人、山中千尋さんが2度目に現れた時、寺島さんが最初に突然質問したのは「男の色気って何ですか」どうやら70歳に突入した寺島さんが男の色気を気にする事件があったらしい。あたまの回転が速い彼女は「状況によってちがいます」と答えをはぐらかしたのです。この辺のやりとりは放送で聴いて下さい。
色気を広辞苑で引いてみると「色情」「愛嬌」「性的魅力」「欲求」とありました。女性が感じる男の色気と男性がひかれる男の色気は違うかもしれません。男の嗅覚からすれば映画の「高倉健」野球の「イチロー」将棋の「羽生善治」などにセクシーな雰囲気がうかがえます。落語の世界で男の色気は「眼病男」と「風邪ひき男」です。ついでに「色香」は「女のあでやかな容色」で男には使えない言葉であることも分かりました。竹久夢二の絵に描かれた女性からは「色香」が漂ってくるではありませんか。
幻想の色香ではなく本当の色香といえば体臭です。動物的には異性を惹きつけるために体臭は存在するらしい。人の場合それを隠すために香水が発明されたといわれています。しかし安物の香水でそれを誤魔化すというのは男にとって寂しいかぎりです。男をその気にさせるのも女性の体臭でその代用品とも呼ばれているのに「じゃ香」があります。ジャコウ鹿の嚢から製した香料で油性の固形で売られています。これぞ媚薬中の媚薬です。
さて今回の放送の前に寺島さんが考えたのはミュージシァンいじめの試聴です。山中千尋さんにブラインドで数枚のピアノトリオのCDを聴かせてから彼女の感想を聞くという試みでした。彼女を磔にして楽しもうという寺島流の仕掛けです。その顛末も彼女の笑いとともに期待して下さい。
ジャズヴォーカルの評価の一つが色気であることは放送でもよく話に出ました。ヴォーカルに限らず楽器それぞれにも色気を感じることを発見したのです。楽器の音色に色気が有るか無いか。実はこれが特定の楽器の音に虜となる理由の一つかもしれません。楽器で多彩な色気を発散するのはピアノでしょう。クロード ウイリアムソンがそうです。実はベースやドラムスも色気を放って
います。例えばベースではスコット ラファロ、ドラムスならジェフ ハミルトンにそんなオーラを感じます。
ジェフ ハミルトンはウエストコーストの代表的なドラマーで、今これほどスィンギーなスティックさばきができる人は他にいないと山中千尋さんが断言しました。ダイアナクラールの「ライヴ イン パリ」DVDの映像では彼の素晴らしいブラシワークが見られます。
ブラインドの試聴も最後となりジェフ ハミルトントリオのアルバム「the best things happen...」Azica Recordsから曲「POINCIANA」を彼女に聴いてもらいました。これにすっかり感激した彼女はこのCDを探して買いたいというのでした。
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年生まれ。オーデイオメーカー数社を経て、日本オーデイオ協会事務局長を15年務める。
 2008年10月/第57回 長生きの素
2008年10月/第57回 長生きの素

今回は、「ジャズはクインテットだ」、という話です。
クインテットとは何でしょう。言うまでもなく“五重奏団”です。では五重奏団は何かと言うと、トランペットとテナー・サックス(あるいはアルト・サックス)にプラス、ピアノ・ベース・ドラムスのいわゆるリズム・セクションを加えたジャズ演奏の形式です。
例えば、有名なところでブルーノートではソニー・クラークの「クール・ストラッティン」、プレスティッジはマイルス・デイヴィスの「クッキン」「リラクシン」など一連のマラソン・セッションは全てクインテット形式で演奏され好評を拍しました。
時代の寵児的役割りを果たしたんですね。
と言うと、では、マイルスの「カインド・オブ・ブルー」の「セクステット」はどうなんだ。あれだって同じようにジャズの黄金期を築いた立派な要因的形式だろう。そう喰ってかかってくる人もいるかも知れません。
違います。「セクステット」はクインテットを根にして発生した一つの派生的ジャンルに過ぎないのです。もう一度言うと、あくまでプラス・アルファー。
クインテットは一世を風靡しました。私のジャズ喫茶など、来る日も来る日もクインテット物のリクエストが殺到して仕舞いにはもう、うんざり。
ジャズ喫茶はジャズ界の縮図ですから、ジャズ喫茶でうんざりなら、ジャズの世の中も同様で、急速にクインテットは飽きられていったのです。
それから何十年。クインテットは存在はしましたが、それは気の抜けた老人性のクインテットだったり、妙に観念的なものだったり。
ところが、2000年代もここに来て、活きのいいクインテットが出現し始めたじゃないですか!
本日ご紹介の「Five For Fun/High Five」もその1枚なのですが、彼らはクインテットを以前とは別物として捉えて演奏しているんですね。それは一口で言えば、“クインテットは格好いい”。格好良さをリスナーに見せたくて俺たちは演奏していいんだ。格好良さを存分に聴いてくれ。・・・彼らの主義主張はその一言に尽きるのです。
以前のように長々延々とソロをとったりはいたしません。そんなのは格好悪いのです。ダサイのです。ソロは短めにとり、トランペットとテナー・サックスの2人による主題の合奏。そこに意を注ぐことを至上命令といたしました。もちろん格好いい曲を書くことを忘れてはおりません。そして、リズム・セクションには本能のおもむくまま、弾けるような演奏を施すよう指示したのです。
ビシバシとしたクインテット。私など古臭さの象徴のように従来のクインテットを捉えていましたが、考え方を変えるとこんな風にまったく別種のもののように聴こえてくるんですね。
大手レコード店でこのクインテット盤が入口一杯に飾ってありました。店の人に訊いてみると、20代・30代の若い人に聴いてもらいたいんだと。むしろ昔のジャズを知らない人々がターゲットになるんだと。50代・60代の旧人はピアノ・トリオに淫していればいいんだと。
おいおい、冗談も休み休み言ってくれ。こちとらロートルを下に見てもらっては困る。ロートルだって活きのいいものは分かる。ロートルだからこそ活きの良さがはっきりと感じられるのだ。これまで何十年間、干物みたいなクインテットばっかりだったから聴かなかっただけの話ではないか。いや、実にいいのが出て来た。
このクインテットの音楽にストローを突っ込んでエキスを吸って吸血鬼のように生き長らえて行きたいものである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2008年09月/第56回 ジャズとユダヤ人の関係
2008年09月/第56回 ジャズとユダヤ人の関係

アメリカで活躍してきた白人系ジャズメンでは、ユダヤ系とイタリア系が多いのに気がつく。とりわけユダヤ系のミュージシャンはジャズの発展にも多いに寄与していたように思える。そんなこともあって、僕はユダヤ系のジャズメンに大きな関心を寄せてきた。レコード屋でもユダヤ系ジャズメンのCDがあるとつい手が伸びてしまう。
先日も輸入レコード屋の店頭に並んでいた新譜に「アヴィシャイ・コーエン・トリオ/ジェントリー・ディスターブド」(RZDAZRD4607)があったので買ってしまった。最近では名前を見ただけでユダヤ人かそうでないかの区別がつくようになった。
コーエンというのはユダヤ系にかなり多い名前である。映画「ノー・カントリー」で今年のアカデミー賞を取ったのがコーエン兄弟なのはご存知の方も多いだろう。ジャズではないが、レナード・コーエンというカナダの吟遊詩人、シンガーソングライターも有名である。ヴァイヴ奏者テディ・チャールズも最初の頃はテディ・コーエンと名乗っていた。
さて、買ったアヴィシャイ・コーエン・トリオの演奏を聴いてみると、これが悪くないのだ。全11曲中2曲はコーエンとメンバーの合作だったが、いちばん心にのこったのは2曲のユダヤ民謡だった。特に「LO BAION VELO BALY LA」の哀愁をおびたメロディに魅せられた。
早速「PCMジャズ喫茶」のスタジオに持っていってこの曲をかけたが、たまたまこの時だけスタジオのモニター・スピーカーの調子が悪く、ベースの音があまり聞こえなかったため、寺島氏と長澤氏の感想も「まあまあだね」で終わってしまったが、自分がいいと思えばそれでいいので、あまり気にならない。
ところで、コーエンというミュージシャンは他にもいる。手元にも「Avishai Cohen/The Trumpet Player」(Freshsound)や「Anat Cohen / Place & Time」(ANZIC)がある。同姓同名のジャズメンでトランぺッターがいるというのも紛らわしいが、彼はイスラエル生まれの正統派のユダヤ人である。
このコーエンは3兄弟で、妹のアナ・コーエンはテナー・サックス、クラリネット奏者として今最も注目株の新進プレイヤーであり、特に女性テナー奏者としてはナンバー・ワンだと私は思っている。彼女はシェリー・マリクルの「The Diva Big Band & Combo」でも活動していて、2年前にコンボの方で来日しているが、その時演奏後に少し立ち話をしたが、笑顔のとてもかわいい女性だった。
演奏が終わってステージで写真を撮っていた時のこと。彼女がユダヤ人の好きなクラリネットでユダヤ的旋律を吹き始めると、メンバーのみんながジューイッシュ・メロディを演奏し和気あいあいの雰囲気が楽しかった。
ユダヤ的なジャズを前面に出している人には、「マサダ・シリーズ」のジョン・ゾーンやトランぺッターのデイヴ・ダグラスもいる。ダグラスもユダヤ系アメリカ人に多い名前で、有名なところでは俳優のカーク・ダグラス、息子のマイケル・ダグラスなどが知られている。
僕がユダヤ系のジャズメンに注目し関心を持つのは、個性的かつ創造的な人たちが多いからだ。
ユダヤ系の人がポピュラーやジャズの世界でまず頭角を現してきたのはティンパンアレーの作曲家・作詞家たちで、ガーシュイン、アーヴィング・バーリン、リチャード・ロジャース、等々みんなユダヤ系である。 例外はコール・ポーターやホギー・カーマイケルなどそんなに多くはない。
そして30年代以降はベニー・グッドマンが「すてきなあなた」「そして天使は歌う」などのユダヤ系の歌をヒットさせ、ハリー・ジェイムス、ジギー・エルマン、スタン・ゲッツなどのユダヤ系の人たちをメンバーに加えた。50年代からは「オー・マイ・パパ」「チェナ・チェナ」「ハイ・ヌーン」「蜜の味」「エクソダス」「アニバーサリー・ソング」などのユダヤ・メロディがヒットし、僕もいつの間にかユダヤ的旋律の虜になってしまっていったようだ。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2008年08月/第55回 「アメリカかぶれ」が治らない
2008年08月/第55回 「アメリカかぶれ」が治らない

「ジャズを聴き始めたのは」「オーデイオ道楽にはまったのは」と何回も尋ねられる。
番組で話したり雑誌にも書いたが、答えが同じであったことはない。というのも、その場の雰囲気で返答しているから。正直なところ気がついたらジャズとオーデイオの虜になっていたというわけで「その切っ掛け」など「ある日突然」来るわけがない。
漠然と覚えているのは、中学生から高校生時代にかけて「アメリカかぶれ」が始まったらしい。その後遺症が60年も続いて「ジャズとオーデイオ」に残ってしまった。
アメリカからプロ野球のチーム「シールス」がコカコーラとともに日本に上陸したのは1949年、当時ジャズ演奏は進駐軍キャンプ内に留まっていた。ただひとつFEN放送でダンス音楽が鳴っていたのを覚えている。毎週日曜日の昼12時から始まる番組「Twelve O'clock Noon」はレス・ブラウンのバンド・オブ・リナウンの軽快なテーマ曲「Leap Frog」が幕開けであった。
中学校へは中央線国分寺駅から徒歩で30分ほどかかったが、府中街道に出ると直ぐに道は切通しになっている。そこにぽつんと古本屋が建っていた。朝はガラス戸が閉まっているが学校からの帰りには必ず寄った。店先のりんご箱にアメリカの古雑誌が詰められて置いてある。近くの府中や横田の米軍基地からごみとして放出されたものであった。手当たり次第に雑誌をめくって1時間ばかり道草する。クルマや食品、台所用品から下着など目をみはる鮮やかなカラー広告ページに見とれているうちにレコードや映画の紹介コラムに気がついた。ジェリー・マリガンの名前を初めて
知って何故か記憶に残り、やがてキャピトルのSP盤「Walking Shoes」を初めて買うことになる。「アメリカかぶれ」の発端でもあった。
当時レコードプレーヤー単体の完成品は販売されていないので自作するしかなかった。それを5球スーパー真空管のラジオにつないでSP盤を鳴らす。スピーカーだけをラジオから外して大型の木箱にマウントするなど工夫を凝らす。こうしてジャズとオーデイオの面白さにとりつかれた。
ジャージーなビッグバンドを気持ち良く鳴らすのがオーデイオの極意で、その理由はセンスよく編曲されたパワフルな集合サウンドとその間にキラリと輝く短めのソロの対比を再生することだと思う。そこでレス・ブラウンはじめクロード・ソーンヒル、ハーブ・ポメロイそれにマーティ・ぺーチのスタジオバンドを聴くことが多い。
1944年、レス・ブラウンと無名のバンド歌手ドリス・ディは一夜にして有名になった。海外のアメリカ兵隊向けに放送された「Sentimental Journey」が望郷の夢とともに士気を鼓舞したという。この録音テープは近年CDに復刻されてthe swing factoryレーベルで発売となった。今もアメリカではレス・ブラウンの人気は続いているのかCD時代になり次々と復刻されている。最新デジタル技術、24ビット・リマスタリングされた「BEST OF CAPITOL YEARS」など音質と選曲が素晴らしい。ヒット曲になった「I've Get My Love To Keep Me Warm」をはじめ「Leap Frog」など25曲が全盛期のノリで収録されている。もう1枚は「THE COMPLETE SONG BOOK」ここではフランク・ロッソリーノ、ズート・シムス、バディ・デ・フランコ、テリー・ギブスのアドリブも随所に聴ける。
ジャズはリラックスして聴くに限るのでテネシー生まれのウイスキー「ジャック・ダニエル」は欠かせない。これで「アメリカかぶれ」は今夜も目出度く総仕上となる。
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年生まれ。オーデイオメーカー数社を経て、日本オーデイオ協会事務局長を15年務める。
 2008年07月/第54回 男は黙ってゴリソリ・テナー
2008年07月/第54回 男は黙ってゴリソリ・テナー

ジョン・コルトレーンが苦手である。
コルトレーンはジャズの偉人中の偉人であり、私はこういう人をキライだと言える自分を大したものだと思う。蛮勇をふるえる自分が嬉しい。
苦手な理由を言わなくてはいけない。
私は音楽というのは、本来歌い上げるものだと思っている。しかし、この人は「歌い下げる」のである。下げるから、自然と聴いている自分の心も下がってゆく。私は気持ちを下げるために音楽を聴いているのではない。
それから音である。この人のテナー・サックスは、テナー・サックスらしい音がしない。テナーより一音域上のアルトのような音がする。妙に甲高くて聴いていてイライラする。テナーでアルトのような音を出す。彼はこのことを『ジャズの改革』と勘違いしているのだ。改革は悪いことではないが、その結果が問題で聴き手に心地よい感情を与えて、初めて改革は成功なのである。それにジャズのミュージシャンは本来改革者ではない。演奏者である。
もう一つ。ソロが長い。20分も30分も延々ソロを吹き続けて床がツバでベトベトになったらしい。ライヴでは面白いかもしれないけど、普通の人はそんなに長く神経を集中して聴けるものではない。本当に集中して聴けるのは、せいぜい3分か4分ぐらいなものである。
さて、このようにして私はコルトレーンが苦手なのだが、先日、秋葉原の高級オーディオ・ショップ「レフィーノ・アンド・アネーロ」で行われた「PCMジャズ喫茶」公開録音で、1人の男性の方がコルトレーンの『バラード』を持ってこられた。
私は、参ったなと思ったが、ちょうど手許に同じテナー・サックスのハリー・アレンのCDがあった。
よし、比較してみよう。頭の中のゴー・サイン・ランプが点滅したのである。
コルトレーンとハリー・アレンを同じ土俵にのせる。同等に扱う。あまつさえハリー・アレンを上に見た言い方をする。
これ、蛮勇である。天にツバする行為である。岩浪洋三さんなど呆れてものが言えないといった風情。口をあんぐり開けている。
かけた曲は上に出ているジャケットの中の「マイ・フーリッシュ・ハート」である。
こうした腹の底から歌い上げて聴き手を感動させる曲を、コルトレーンは絶対取り上げない。歌い上げられないからである。
さて、会場のアバンギャルドのスピーカーで2曲かかって、私は見物にいらした会場の老若男女の皆さんに訊いてみた。
「どちらがお好きですか?」
挙手していただいた。驚いたことに3割、いや、私には5割くらいに見えたが、そのくらいの人たちがハリー・アレンに手を挙げたのである。
音である。音。
ハリー・アレンのテナーの音色。いやまあよくもここまでテナー・サックスらしい音が出現したものだ。よくぞここまでテナーの音をえぐり、精分を抽出拡大して録音できたものだ。最高だ。
会場の方はジャズ・ファンというよりオーディオ・ファンの方が多かった。だからこそ白い耳で両者を比較できたのである。先入観なしの胸のすくような快挙。
スピリチュアルならコルトレーンだろう。
しかし、音なら文句なし、男は黙って低音声帯、ゴリッ、ゾリッのハリー・アレンなのである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2008年06月/第53回 ジャズメンとカラオケ
2008年06月/第53回 ジャズメンとカラオケ
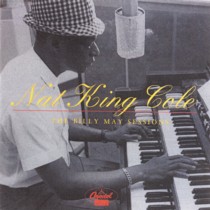
この間、CDの中古店に言ったらナット・キング・コールの二枚組があったので買ってきた。彼のCDなど珍しくもなんともないが、「Nat "King" Cole / The Billy May Sessions」(Capitol Jazz)との題名にひかれて買ったのである。ビリー・メイはかつてグレン・ミラー楽団のトランぺッターとして活躍し、キャピトルにあっては、自楽団の演奏とアレンジャー、歌伴として魅力的な仕事をしてきた男であり、彼が伴奏したセッションならジャジーに違いないと思って買ったのである。
じっさいにそうで、中にはキング・コールがオルガンを弾いたのもあり、未発表曲も4曲程あった。「ウォーキン・マイ・ベイビー・バック・ホーム」「コールド・コールド・ハート」というポップ曲も楽しかったが、番組で「ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス」をかけたところ、寺島氏、長澤氏といった男性陣からはあまり反応がなく、人妻Aさんは「私はもっと晩年の声の方が好きなんです」と言われてしまった。
たしかにこれは1961年頃のもので、晩年の渋い味わいはない。僕はナット・キング・コールものならみんな好きだ。友人にカラオケに誘われると、たいていキング・コールの「モナリザ」や「イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン」を歌う。
カラオケは自分から進んでいく方ではないが、誘われて行って、午前3時頃まで歌ったことが何回かある。昔、高木東六という作曲家が「カラオケ亡国論」を新聞に書いていたことがあるが、いまやカラオケと寿司は世界に広まっていてとどまることを知らない。何年か前にニューヨークのハーレムの街角を歩いていたら、ジャズ・クラブのウインドウに”ライブのない日はカラオケ”と書いてあった。カラオケがハーレムにまで進出しているのには驚いた。もちろん、ニューヨークのミッド・タウンやダウン・タウンにもあり、一度友人と入ったことがあるが、ちょうど「ニューヨーク・ニューヨーク」が歌われていたが、日本のように一人が立って歌うのではなく、みんなで合唱していた。ちょうど日本の一昔前の「歌声喫茶」のようであった。
僕は日本のジャズメンともカラオケに行ったことがあり、じつはベースの鈴木良雄、ピアノのアキコ・グレース、ドラムスのヒロ近藤らと一緒に行ったのだが、3人はジャズメンなのにジャズは決して歌わないのである。鈴木良雄は「僕は大学の時からこの歌が得意なんだよ」といって、みごとに舟木一夫の「高校三年生」を歌ってみせた。アキコ・グレースはJ-POPをさかんに歌っていたし、ヒロ近藤は演歌好きだった。彼らジャズ・ミュージシャンがカラオケでジャズ・ソングを歌わないのは、オフタイムくらいは、ジャズから離れてリラックスしたいと思うからに違いない。
ところが僕みたいに、歌の素人でちゃんとジャズ・ソングが歌えない人間にかぎってカラオケでジャズ・ソングを歌いたがるのだろう。
カラオケでジャズを歌って、うまいなあと感心したのは、日本在住のベーシスト、スタン・ギルバートである。一度赤坂の「KAY」に行ったとき、ライヴの終わったアフター・アワーズにカラオケの「ナット・キング・コール愛唱歌集」に合わせて二人で遊びながら歌ったことがあるのだが、彼の渋い声はまるでキング・コールのようであり、見事な歌いっぷりだった。彼なら歌のアルバムを出してもおかしくないとおもった。
最近は一人カラオケも流行っていて、一人でカラオケ・ルームを借り切って歌うらしいが、カラオケって多少は他人に聴いてもらいたい気持ちで歌うものではないのだろうか?もっともミュージシャンの中には一人でルームを借りて楽器の練習をしている人もいるとか。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2008年05月/第52回 マスター・テープへのこだわり
2008年05月/第52回 マスター・テープへのこだわり

私のような根っからジャズオーディオ人間は飽きもせずジャズの音源捜しに熱中しています。
今はデジタルオーデイオ時代ですが、ひと昔まえはアナログオーデイオ全盛でした。当時のオーデイオ・ファンにとって是非聴きたい音源のひとつはレコード会社に保管されているマスターテープであったでしょう。アナログレコードは勿論ですが現在復刻されている数々の名アルバムのCDもマスターテープから編集加工されているのです。
マスターテープを聴くことは録音時のナマ音を聴くことに近いわけで、酒なら原酒を味わうのと同じスリルが体験できるのです。あるメジャーのレコード会社に友人が在籍している時、秘かにジャズのマスターテープを数本コピーしてもらったことがありました。アルバム名を明かせば誰でも知っている名盤中の名盤です。それを自宅で聴くのは禁断の果物の汁を吸う興奮に似ていました。
アナログ・マスターテープは10インチのリールに巻かれており2トラック、速度38cm/sec、録音時間は30分です。テープは巻き取られたまま保管され、これはマスター巻きと呼ばれます。このマスターテープのジャズ音源を10インチリールにコピーして販売を決意した人がある時現れました。ヴィーナスレコードの原さんです。テープ1本に4曲が入って2本セット価格は25,000円でした。私が直ぐ注文したのは言うまでもありません。
リチャード・ワィアンズ・ピアノトリオ「ラヴェンダー・ミストの女」とアーチー・シェップ・カルテット「トゥルー・バラード」でした。アナログ・マスターテープの音はナマの楽器のカタチを彷彿とさせるだけでなく、楽器本来のエネルギーが部屋の空気を圧縮するほどの凄さです。それに比べればCDの音など私にとってはミニチュアみたいなものでした。
ヴィーナスのジャズサウンドの真髄をマスターテープから聴いてから、以来すっかりヴィーナスレコードの虜になったのです。門外不出と言われるレコード会社のマスターテープを例えコピーといえども惜しげなく販売を始めた原さんに興味を惹かれて広尾の事務所までインタヴューに行ったこともありました。
そんなわけでマスターテープのコレクションも秘かに始まりました。アン・バートンが日本公演を行った時、日程の合間ある夜、レストランでプライヴェートのコンサートが企画されました。彼女の希望もありマスターテープに録音して、そのコピーを帰国のさいに持って帰ったのです。それを頼まれた私がもう1本自分用にコピーしたことを白状してもよいくらい時は過ぎ去りました。
ジャズオーデイオに不可欠な音力が溢れていることでヴィーナス・サウンドを有名にしたCDアルバムはビル・チャーラップ・トリオの「ス・ワンダフル」とデニー・ザィトリン・トリオの「音楽がある限り」でした。アナログレコードも同時発売となり30cmサイズジャケットの存在感同様に音のスケールもマスターテープをイメージさせる出来栄えです。
ヴィーナスレコードの看板男はエディ・ヒギンズですがビル・チャーラップもそれに負けない看板男と言ってよいでしょう。クリスクロス、EMIや東芝からも彼のアルバムはリリースされていますが、ジェイ・レオンハート(b)ビル・スチュアート(drs)と組んだ彼のニューヨーク・トリオのアルバムはヴィーナスからすでに5タイトルがリリースされました。今度のニューアルバム「オールウェイズ」はアービング・バーリンの名曲を集めたものです。どの演奏も実にいい雰囲気で彼の個性が良く出ているのです。私が好きなピアニストでもあるディヴィッド・ヘィゼルタィンを剛とすればビル・チャーラップは柔と言えるかもしれません。
タイトル曲「オールウェイズ」のトップから最後まで音よし、演奏よしで久しぶりに全曲を通して聴いたアルバムでした。
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年生まれ。オーディオメーカー数社在籍。日本オーディオ協会前事務局長。
 2008年04月/第51回 (続)素人衆の底力
2008年04月/第51回 (続)素人衆の底力

前回の「素人衆の底力」。その続きのような形になる。
実は私、読んですぐに捨てられる小冊子のような雑誌が好きなのだが、それはそこで頭の中に侵入した知識なり情報をすぐにうっちゃれるからだ。いつまでもつまらんことを頭に係留するのを好まぬ。しかし今月読んだ「青春と読書」の花村萬月の一文は頭にとまった。骨っぽい文体を操るこのぴかぴか頭作家はそこである音楽好きの作家をくさしている。引用すると長くなるのではしょるが、彼、その作家先生と論争のあげくに「論理的に論破できるのだがそういうことに淫していると、この人と同じように音楽を耳でなく知識で語るという無ざまなことになりかねないので俺はリタイヤした。」
当然のごとく私が痛快さを感じたのは『音楽を耳ではなく知識で・・・』のくだりである。無ざま、ねえ。無ざまとは凄いねえ。こてんぱんではないか。完ぷなきまでに、とはこのことだ。
話は突然変わって、さるジャズ・クラブでの出来ごと。
中年の女性が多く在席する。ビギナーの方がほとんど。そこで私は2枚のCDをかけたのである。
曲は「ルビーとパール」。ビギナーのかたは比聴をとくに好む。曲を憶えられるし雰囲気がすぐに伝わるからである。2曲をかけ終え、さて、どちらがお好きですか、と。
これほど差が開くとは思わなかった。
大抵の比聴は半々くらいに別れるものだ。この場合はウェイン・ショーターが圧倒的だった。ほとんど全員という感じだった。ウェインといってもウェインなど彼女らは知らぬ。ウェインといえばジョン・ウェインなのである。
一方のブルーノート盤。こちらに挙手した3人程の男性はけっこうなジャズ・マニアだった。私の察するところブルーノート盤というご威光に負けたらしい。ウェインはウェインでもビー・ジェイ盤だし、初期もいいとこ、オカルトのウェインになる前の並のウェインじゃあ大したことなかろう。このように踏んだに違いないのだ。
私はといえばもちろん、ウェインに圧倒的な勝利の一票を入れる者である。
このJ・リビングストンという人の書いた「ルビーとパール」。
目に入れても痛くない曲でジューイッシュの哀しい旋律が胸に突きささって痛いけれども痛さがたまらなく快感なのである。その痛さとか快感、もっと言うと喜怒哀楽の感情をこれでもかと表現したのがウェイン・ショーターのテナー・サックスだった。
それにご婦人方は深く共鳴したのである。耳、つまり、心。
ワン・ホーンは心で2管は機械、は言い過ぎだがジャズは心が感じられるジャズが1位で2位、3位はない。
さて、私は論旨を鮮明にするためにややオーバーな書き方をした。
しかし昨今、私など井戸からはい上がって周囲を見まわすとジャズ知識派の人々のなんと絶望的に少なくなったことよ。変わって耳で聴く人たちのなんとたくさん増えたことよ。
そのことに驚くのである。知識階級の没落と感覚派の台頭。
今後両者のへだたりは間違いなくもっと大きくなってゆくだろう。
その推移、ことの顛末をしっかり見届けるため私はあと10年石にかじりついても生きてゆきたいと思っているのだ。見ものである。いや、絶景かな、である。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2008年03月/第50回 最近惚れ込んでいる歌
2008年03月/第50回 最近惚れ込んでいる歌

「PCMジャズ喫茶」ではいろいろなテーマをもうけて放送しているが、店主の寺島靖国氏はときどき難題を吹っかけてくる。先日は「最近もっとも惚れ込んでいる曲か歌を一曲」というリクエストがあったが、これはうれしかった。いま夢中になっている歌があったからだ。
それは「センド・イン・ザ・クラウンズ」で、ミュージカル「リトル・ナイト・ミュージック」の挿入歌。作詞作曲はスティーヴン・ソンドハイム。1973年作だから古くもなく、そんなに新しくない歌である。ぼくは以前から聴いていたが、長くそのほんとうの魅力を知らないでいた。
最近その歌の詞に当たってみて、強く心を惹かれるようになった。
これはサーカスのコンビが恋人同士なのだが、男の気持ちが少し女性から離れていき、それを感じた女性が集中心を欠いて演技を失敗し地上に落下する。”みっともないから、舞台に道化師を入れて”(Send In The Crowns)という歌なのだが、ぼくには一行目からぴったりとした訳がつけられないのである。
一行目はこうで、下手な訳をつけてみた。
Isn't It Rich? Are We A Pair?
『ご立派じゃない? 私たちが名コンビだなんて』
この一行には自虐的な表現がこめられているのだが、どうもうまく訳せない。
翻訳といえば、村上春樹がこのところさかんに小説を訳している。フィッツジェラルドが書いた「グレイト・ギャツビー」(中央公論社)を買って読んだが、彼ほどの英語力があっても、いやあるからこそなのか、訳しきれない言葉があるらしい。主人公のギャツビーが友人を含めて男性に会うと、相手をOld Sportと呼ぶのだが、この言葉の的確な訳がみつからないと彼はあと書きでいっていて、訳さないで『オールド・スポート』のままにしている。ここでの「Sport」は運動のスポーツではなく、友人の意味なのだが、ギャツビーはイギリスのオックスフォード大学の卒業という設定になっているので、ちょっとキザで大げさないい方を好み、Old Sportを連発する。だから強いて訳せば『おお我が友よ』といったところだろうが、村上春樹はわざと『オールド・スポート』のままにしたのだろう。
しかし、歌の歌詞の場合は訳さなければならないからむずかしい。
ところで「センド・イン・ザ・クラウンズ」はサラ・ボーンが得意だったし、ぼくも好きだが、82年にカーネギー・ホールで行われた「ソンドハイムの夕べ」のビデオをニューヨークで買ってきて見たら、なんと映画「危険な情事」の女優グレン・クローズが歌っていて、これが最高だった。
寺島靖国氏はあくの強い黒人の歌が嫌いなので、サラ・ボーンのアルバムははずして、しっとりと歌うアン・バートンのCD「雨の日と月曜日」(TDK)をもっていってかけた。まあまあとの反応だったが、この歌がきっかけで、三人とも「最近あまり昔のようないいスタンダードが生まれないね」という話をはじめたが、ロックなどが台頭して、音楽事情が変わってきたからであろう。現代にあまりいいスタンダードがないので、最近バート・バカラックの曲がリバイバルしているのかもしれない。また最近ジャズメンはスティービー・ワンダーの曲やロックを素材にするケースもおおくなってきている。
ぼくも、「センド・イン・ザ・クラウンズ」の魅力を再発見し、「ジャズは曲で聴くべし」という寺島氏の主張がわかるようになってきている。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2008年02月/第49回 えっ もう10年!
2008年02月/第49回 えっ もう10年!

店主寺島靖国さんのびっくり声でした。
「PCMジャズ喫茶」は「激辛トークセッション」という番組から生まれ変わって1998年4月11日からスタートしました。それ以前1992年8月3日にPCM放送(今のMUSIC BIRD)は始まっており、オーディオ熱中人である私が当時いち早くアンテナをベランダに設置して電波がやってくる空中を凝視していたのは言うまではありません。今年で開局15年目となりました。
CDの性能を超えた音質の電波が飛んでくるというのでFMエアーチェックからPCMエアーチェックが出来るという革命的なことでありました。自宅で聴くCDよりPCM放送で聴くアルバムの方が音がいい不思議を体験しながら「なぜ」という自問自答が続いたのです。その頃まだ日本オーディオ協会に在籍していたのでメーカー各社のトップ・エンジニアと会う機会も多く、私の体験を話したところ一笑されました。彼らはPCM放送を実際に聴かず理論で判断したのでしょう。やがてリスナー数人と話すたびに彼らも私と同じ経験を持ったことを知り、それが空耳でなかったことを確信したのです。
リスナーであった私はやがて寺島さんに誘われて「PCMジャズ喫茶」のゲストになりました。スタジオ録音の現場に通ううちに疑問は解決されましたが、そこで手品の種明かしを知りました。
さてスタートした「激辛トークセッション」は回を重ねるうち寺島靖国さんと中山康樹さん決闘まがいの雰囲気に包まれていきました。1回目の放送から聴いていた私はある結末を想像していたのです。例えば2つの磁石がプラスとプラスで向き合って次第に反発が強まっていくと、やがて最後はお互いに磁場から跳ね飛ばされるという場面です。しかし寺島磁石だけは残りました。その顛末あまりの面白さに私はそれを録音し、コピーしたテープをジャズオーディオ数人の友人に配ったほどです。
「PCMジャズ喫茶」の看板を掲げてから最初のゲスト山本隆さんが1ケ月ほど寺島さんの相手を務めていました。ところが突然「おしかけ」自称永世ゲストの安原顕さんがスタジオ破りで登場してきたのです。「オレにやらせろ」と言ったとか。2002年12月14日まで約4年半の放送を聴いて「安原症候群」に罹ったリスナーもいるらしく未だ後遺症から回復できないと聞きました。現在ゲスト出演中の岩浪洋三さんに言わせれば寺島磁石は安原異次元磁場に吸い寄せられる寸前であった。安原磁場の消滅で寺島磁石が生き残ったというのです。真偽のほどは定かではありません。
12月28日放送から山本博道・田中伊佐資コンビが賑やかに参加し2003年夏から私も加わりました。岩浪洋三さんとの3人組となったのは10月4日放送番組が最初です。
昨年ついに念願の「寺島レコード」が発売となりました。「執筆者」と「レコード・プロデューサー」という2枚看板を掲げることになったのです。寺島レコード第1作は「alone together」、第2作は「Jazz Bar 2007」いずれもジャズオーディオの伝道師が企画制作するに相応しい出来栄えです。本年70歳となる寺島さんですが、少し血走った眼が何時もの睡眠不足を現わしているにせよ磁場は相変わらず強力です。そこにはコンパスを置けば矢印が微動もせず正確に一定方向を指しているのを見ることができるに間違いありません。
その10年、録音現場で奮闘された太田俊デイレクターからの資料提供に感謝いたします。
「寺島靖国プレゼンツ JAZZ BAR 2007」 好評発売中!
TYR-1002(CD/税込2,730円) TYLP-1002(限定LP/税込5,250円)
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年生まれ。オーディオメーカー数社在籍。日本オーディオ協会前事務局長。
 2008年01月/第48回 素人衆の底力
2008年01月/第48回 素人衆の底力

この頃「ジャズ批評」という雑誌が面白くなってきた。
一時期は低迷していて、何とかジャズ最前線などとかけ声ばかり勇ましく、その割に内容はCDやLPを見さかいなく並べたてただけのもので、決して読み心をそそられるものではなかった。
最近は違う。この頃の傾向としては、「素人衆」が執筆者として大挙現れているのである。素人と言ったって、読めば分かるが、その道の権威といわれる人たちよりよっぽどたくさん「聴いて」いる人たちだ。
音楽の評価力は聴く時間の長さによる、というのが私の考えである。ごく一部の大天才を除いて本も楽器も何も皆同じ。仕事を放り出してヒアリングに熱を入れている人の声ほど確かなものはない。権威の人たちが論を立てて解説するのとはぜんぜん異なるリアリティがあって私は大いに好きなのだ。
この方たちの文章の中には大抵たくまざる一行というのが散見される。その人でなければ言えない言葉というのがある。
そういえばさる偉い人が、文章というのはからりと明快に晴れていて、さらにその人しか語れないものだったらそれが最高だと。
いつもそういうわけにはいかないんだけどね。素人の方たちはたまに登場するからそれが可能なのである。毎回苦しんでムリにひねり出す通例執筆者とはそこが違うところだ。
なにより、このミュージシャンが、CDが、レーベルが、音が、こんなふうにとにかく好きなんだと静かに絶叫しているのがいい。通例者が毎回絶叫していたらバカだと思われてしまう。
プロとアマの違いといえば作家の遠藤周作がこういうことを言っている。
「アマの作品を読むと、申しわけないがやはり息を切らしている。何となく余裕がない。文章にも余裕がないし、内容にも余裕がない。また文章に抑えがなくて大声や金切り声をあげている。率直に言うとやはり野球や角力の世界とおなじ差をその時に感じてしまう。」
なるほどね、その通りだと思った。なんだか自分のことを言われているようで急に世の中が面白くなくなったけど。
しかし遠藤周作が言うのは高度の文学の世界のことだろう。私らのやっているのはたかだかジャズという一人よがりの個人主義の発達した趣味の世界。多少暴走したところでそれがどうしたというのだ。
けんかごしのほうが面白い時だってある。第一ジャズは冷静に抑えて聴く音楽ではない。自分で興奮をかき立てていって武者ぶりつくように聴いて初めて向こうが応えてくれる側面もある音楽である。
それから、あと、ユーモアね。ユーモア精神がないとジャズは苦しくなって長続きしない。笑ってジャズを聴く。これがいいのである。嘘だと思ったらやってごらん。楽しいジャズになるから。しかつめらしく聴けばジャズはしかつめらしい音楽になるのである。短い人生、どうせなら楽しく聴かにゃあ損する。
2007年9月号の「ジャズ・ボーカル特集」をパラパラやっていたら岩浪洋三さんと三具保夫さん、志保沢留里子さん、高田敬三さんが座談会をやっていた。
冒頭から面白いのである。
岩浪「ボーカルというのは斜かいに聴くのがいいんで、人の声だからはっきり好みが出る」
高田「人それぞれいろんな好みがありますから」
岩浪「女性から見たら男性ヴォーカリストには色気とかセクシー度とか大切なんでしょう?」
高田「それは違うんじゃないですか」
志保沢「そんな聴き方してませんよ」(笑)
ユーモアが全然通じていないのである。岩浪さん、しまったと思ったんじゃないだろうか。言う相手を間違えたなあ、と。ここはPCMジャズ喫茶じゃなかったんだ、と。
いつものPCMの気分でいってピシャリとやられてしまったのである。
「寺島靖国プレゼンツ JAZZ BAR 2007」 好評発売中!
TYR-1002(CD/税込2,730円) TYLP-1002(限定LP/税込5,250円)
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2007年12月/第47回 ムーン・リバーと私
2007年12月/第47回 ムーン・リバーと私

10月初旬、吉祥寺の「MEG」でヴォーカル・コレクターでミュージックバードにも出演している武田清一氏のヴォーカルLPコンサートを聴きに行ったところ、途中、ゲストとしてウィリアム浩子さんが、ピアノを弾きながら「ムーン・リバー」を歌った。プロ歌手なのだが、まだ憶えたばかりとかで、ちょっと素人っぽく、ささやくように素朴に歌ったのだが、それがとても印象的で、いつまでも頭から離れなかった。
そういえば、映画「ティファニーで朝食を」でのオードリー・ヘップバーンも、外の階段に腰を降ろし、ギターを弾きながら、可愛い声で、やはりちょっとささやくようにさりげなく歌ったが、それがこの「ムーン・リバー」をとても魅力的な歌にしていた。オードリーは歌えない女優ではなく、「パリの恋人」では「ハウ・ロング・ハズ・ジス・ビーン・ゴーイング・オン」を歌っていたし、映画「マイ・フェア・レディ」も最初オードリー自身の歌でも撮影していたくらいだが、結局映画ではマーニ・ニクソンの吹き替え版で封切られた。歌手としてはそれほど上手いとは言えないのだ。
僕の想像だが、ヘンリー・マンシーニは「ティファニーで朝食を」の監督から、オードリーに映画で一曲歌ってもらいたいので、彼女に合った歌を書いてくれないかと頼まれ、彼女の歌唱力に合った、素人っぽく歌うと生きる歌「ムーン・リバー」を作曲したのではなかろうか。
だから、この歌はあまり声を張って朗々とオペラ歌手の様に歌うと、かえって味わいがなくなってしまうのではなかろうか。
こんなふうに思ったのは、実は理由があって、ミュージカル「マイ・フェア・レディ」の作詞、作曲家コンビ、アラン・ジェイ・ラーナーとフレデリック・ロウの回想録を読んだとき、このミュージカルの作曲で一番苦労したのは、ヒギンス教授を演じたレックス・ハリスンが歌う歌を書くことだったという一節を読んだからだった。
レックス・ハリスンは名優だが、正直言って歌は下手だ。僕は彼のLPを一枚持っているが、歌っているんだか、語っているんだかわからないようなアルバムなのだ。レックス・ハリスンが「マイ・フェア・レディ」の中で歌う「レイン・イン・スペイン」という曲など語るがごとく歌う曲であり、作詞作曲者のラーナー=ロウの苦労がよくわかるのだ。
僕は、これとオードリーの歌う「ムーン・リバー」は同じ理由で生まれた歌ではないかとふと思ったのだ。僕はウィリアム浩子の「ムーン・リバー」が頭にこびりついていたので、ミュージックバードの「PCMジャズ喫茶」でこの曲をかけたいと思っていたところキアラ・シヴェロ(ユニバーサルUCCM1131)に出会ったのだった。キアラはローマ出身のシンガー・ソングライターなので、「ムーン・リバー」を僕の理想とするこの曲向きの素朴なフォーク調で歌っていて、大いに気に入った。
そこでこの「ムーン・リバー」を「PCMジャズ喫茶」のスタジオに持ち込んでかけたのだが、いつも口の悪い二人、寺島氏と長澤氏が「まあまあだね」と言ったので一安心。
ところでオードリーが歌った「ムーン・リバー」入りのCDはないものかと探していたら「Music From The Picture Of Audey Hepburn」というアルバムに入っていた。
しかし彼女の歌はこれ一曲。たしかにうまいとはいえないが、可愛くて、とても魅力的に歌っている。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2007年11月/第46回 ジャズ録音に真空管のマイクロホンを使う、そのこだわりとは
2007年11月/第46回 ジャズ録音に真空管のマイクロホンを使う、そのこだわりとは
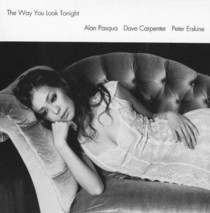
20世紀最大の発明はトランジスタの開発である。現在生活空間にあるあらゆる通信機器や家庭電化製品はトランジスタの集積回路で構成されている。一方オーディオなどの音響機器に真空管システムが生き残っているのは何故か。
半導体では実現できない真空管の特性がある。音楽再生の条件である楽器や声、空間の「潤い」「ひびき」「強弱感」などで真空管システム独自の音響世界が広がる。真空管マイクロホンによるレコーディングは少なかったが真空管式編集機器を活用したCD造りが今も行われているのはそんな理由である。同じオリジナル・マスターテープから編集された数種のCDに音の違いが聴ける例がある。
ソニー・ロリンズ「WAY OUT WEST」は1957年コンテンポラリー・レコードの倉庫を使って録音エンジニアのロイ・デュナンが録音した。当時はまだステレオの録音機がなく真空管式モノラル録音機を使った。そのためテナーサックスは左にベースとドラムが右に位置しており真中に合成音はない。このLPをやがて各社がCDに復刻した。
オリジナルテープから直接復刻されたCDはmobile fidelity sound lab(MFCD801)ビクター輸入盤xrcd(VICJ-60088) Analogue Productions(CAPJG008)・(CAPJS008)そしてFantasy限定盤(4CCCD-4441/2)に限られている。マスタリング・エンジニアのセンスやシステムの違いから音はどれも微妙に異なる。このなかでも楽器の自然感に溢れているのはダグ・サックスが真空管システムを使って仕上げたCD(CAPJS008)であった。
50年代の録音が音質的に自然であると言う人は多い。耳は当時の真空管録音による自然な音を聴いている。現在のマルチ・マイクによる多チャンネル録音やデジタル編集による音の不自然さは聴いていて疲れることが多い。昔オーディオに熱中した科学者が本音を漏らしたことがある。「不純物(半導体)を通った信号より真空を飛んだ信号のほうが音はいい」なにか本当らしく聞こえる。
イントロが長すぎるようだ。真空管マイクロホンを使って録音されたCDを紹介したい。「The Way You Look Tonight」(Field Work Music FW001) Alan Pasqua(p) Dave Carpenter(b) Peter Erskine(drs)TrioでKMFオーディオ・ステレオ・真空管マイクロホン・マークⅡが活用されている。3つの楽器がそれぞれ滑らかな音で鳴るとともに孤立することなく空間にブレンドされてステージ感を伴って響く。録音にはマルチマイクではなく2本のステレオマイクを立てている。KMFというのは真空管マイク開発エンジニアの名前K..M.Fuquaの略である。演奏曲は全部がスタンダードで音の快さに10曲では物足りないという出来栄えであった。現地発売のアルバム・タイトルは「Standards」でジャケットはイラスト風であったが日本発売ではタイトルを変更しCDカヴァーも色香漂う女性となった。こちらのほうが断然いい。
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年生まれ。オーディオメーカー数社在籍。日本オーディオ協会前事務局長。
 2007年10月/第45回 好き嫌い
2007年10月/第45回 好き嫌い

世の中には好き嫌いでしか判断できない作品というのがある。
この「日野=菊地クィンテット」などはまさにその典型であり、私は大嫌いである。
しかしなんですな、嫌いと言い放ったあとの爽快感。言ってやったぜ、という達成感。なんともたまらないものがある。バカな私にしか出来ないことである。
このクィンテット、まず第一になにが言いたいのか、そこらあたりがまったくわからない。
どんな作品にも言いたいことがある。そんな高尚なことでなくてもいい。
しばらく前に向井滋春が4トロンボーンのCDを出したが、その時向井さんは、楽しければそれでいいと言った。「楽しさ」が言いたいことなのである。日野、菊地に楽しさがあろうはずがない。
我田引水で申し訳ないが松尾明トリオの近作で言いたかったことは、シンプルな分かり易さを聴いてくれ、であろう。では日野、菊地は、複雑な分かり難さを聴いてくれ、か。
べらぼうめ。いまどき、そんな酔狂な人などいるものか。
まあいい。今日はそのことを言いたいのではない。
好き嫌いで物を言っていい、ということを申し述べたいのである。
大体、「日野=菊地クィンテット」の演奏は一般大衆には判断できないように作られているのであり、そうであるならば、好き嫌いでもって判断するしかすべがないのである。
先日亡くなった富樫雅彦。彼の往年の名作に「スピリチュアル・ネイチャー」がある。あれが出た時、世の中は大変に混乱した。
誰が聴いても分からない。
好き嫌いで言うしかないのによしあしで判断しようとしたから、さあ大変。あんなにも評論家を苦しめた作品はこれまでなかった。
評論家と言えば、私は評論家ではなく好事家だからひとごとのように言えるのであるが、「日野=菊地クィンテット」をどのように評論するのであろうか。
それを思うと気の毒で自分のことでもないのに胃が痛くなってくる。
やっぱり「宇宙」とか「壮大」とか「パノラマ」とかそんな言葉を散りばめるのだろうか。
皆さんに言っておくが、ジャズ評論で宇宙が出てきたら完璧にまゆつばであるから笑ったほうがいい。
どうということはないのである。好き嫌いで評すればいいだけの話である。それでは沽券にかかわると思うから肩に力が入ってどんどん迷走してゆくのである。
好き嫌いで書くメリットは読者が大変に安心できることである。
「よしあし論」でほめちぎられれば、特にビギナーは、聴いておかなければならないのではないか。おいてきぼりをくうのではないか。
そういう不安にかられるのである。
その点、「好き嫌い論」は大いに安心。
ちょっと暴走して評論家の皆さんに一言。
もうそろそろ好き嫌いを表に出してもいい時期にきているのではありませんか。
ほんとうは各人それぞれ当然好き嫌いを胸の内に持っているのである。
それを隠して書いている。私は彼らの胸の内を知りたいのである。
胸の内が面白いのであり、それが本音の文章になって現れて私はそういう記事をこそ読みたい。
今のままでは、ちょっと。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2007年09月/第44回 女性シンガーを探して
2007年09月/第44回 女性シンガーを探して
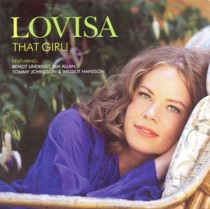
戦後すぐにラジオで聴いて好きになったのが、ダイナ・ショア、ジョー・スタッフォード、ドリス・デイ、ローズマリー・クルーニー、ビング・クロスビー、フランク・シナトラといったシンガーたちのポピュラー・ヒット・ソングだったので、その後もヴォーカル好きは治らない。レコード店をのぞき、ちょっと美人で、面白そうな女性ヴォーカルのアルバムがあるとすぐに買ってしまう。
先日も吉祥寺のレコード店で、小野リサの新譜「小野リサ ソウル&ボッサ」を買ってきて聴いた。今回東芝EMIからエイベックスに移ったので、少しサウンドが変わった。ヴォーカルをリアルに録っている。これまでの彼女のCDを聞き込んできた僕などは、新しいヴォーカル・サウンドが耳になじむまでに少し時間がかかるかもしれない。
それにしても、小野リサの軽やかな歌い方はボサノヴァそのものであり、日本でこんなにボサノヴァをボサノヴァらしく歌える歌手はほかにいない。しかもスタンダード・ナンバーやポップス曲も途中にはさんで歌ってくれるから、なおうれしくなる。今回は「ジョージァ・オン・マイ・マインド」や「愛さずにはいられない」、「フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ」といったナンバーもボッサ調で新鮮に歌っている。
ところで新人ではスゥエーデンの歌姫「ロヴィーサ/ザット・ガール」(SPICE OF LIFE)が気に入り、何度も繰り返し聴いた。好きなスタンダード、「アイ・フォール・イン・ラブ・トゥー・イージリー」「スカイラーク」「ルック・オブ・ラブ」「ホエン・アイ・フォール・ イン・ラブ」などを歌っているからでもあった。
それで早速「PCMジャズ喫茶」に持っていって「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ」をかけたのだが、寺島氏、長澤氏、Aさんの評判はよくない。寺島氏にいたっては「なんじゃ、これは!」である。
僕も自分の家のオーディオで聴いたときは、素直で可愛い歌いっぷりが素敵だと思ったのだが、Aさん宅の立派なオーディオ装置で聴くと、素人っぽくて、まるで歌の先生に言われる通りに、緊張して四角張って歌っていて、リラックスした楽しさがまるで消えてしまっているのだ。ものによってはリアルな音で聴いてはいけないのだろうか。よく映画女優など、小じわや毛穴なまで映さないため、「ソフト・フォーカス」を要求する例もあるが、歌の場合もあまりにもリアルに再現してはまずい場合もあるのだろうか。次回の録音の時に、オーディオに詳しい寺島・長澤両氏に聞いてみよう。
さて「PCMジャズ喫茶」、8月から一時間番組になったわけだが、二時間番組だったときと違って4人で喋って曲を聴いていると、下手をすると自分の分が一曲しかかけられないこともある。
先日もそんな目に会った。僕自身が選曲、監修した女性歌手のCDをかけようと思ったが、時間がなく、封も切らずに持ち帰ってきた。自信作?だったので残念なことをしたが、2枚組で40曲入りで30数人の女性歌手を収めていて、僕はヘレン・オコーネルの「アマ・ポーラ」か女優モーリン・オハラの「ニアネス・オブ・ユー」をかけようと思っていたのだが・・・・。
上記のふたりはアイルランド系であり、僕はこのところアイルランド系の歌手に興味を持ち、カーメル・クインのレコードや「ダニー・ボーイ」の入ったCDなどを探す毎日なのだ。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2007年08月/第43回 昔はピアノトリオ、今やザ・トリオ
2007年08月/第43回 昔はピアノトリオ、今やザ・トリオ

独自のジャズオーディオ・ライフに徹している寺島靖国さんは、以前からジャズレコーディングにも強い関心を持っていた。録音後に行なわれるプロのマスタリングのスタジオにも何回か呼ばれて音造りに立ち会った。楽器から発散する「音力」をCDに注入して、それを再生して聴くというのが寺島流ジャズオーディオの極意ではないだろうか。
寺島靖国さんが自らプロデュースする「寺島レコード」のCDが発売となる。寺島さんと言えばピアノトリオレコードの伝道師であるから、第1作は勿論ピアノトリオに決まっている。「MATSUO AKIRA TRIO」がアルバムタイトルだがサブタイトルはalone together、寺島さんが惚れている名曲である。すでにCDジャケットのデザインも完成しており、これが実にすばらしい。
ピアノトリオの録音については「PCMジャズ喫茶」でかけるCDを片っ端から袈裟懸けにして血祭りにしている寺島さんだから、自分が造るCDも返り討ちにあうという覚悟は決めているようだ。仲間うちとはいえ岩浪洋三さんから闇討ちもされかねない。
先日の「PCMジャズ喫茶」の録音はスタジオから離れて久々の出前録音となった。東京小金井市の小部屋に4人が集まった。寺島さんが例によって当日の明け方5時頃にFAXを寄こした。「1人特集をやりたい。曲<タブー>を数枚持っていくので、そちらも何かを考えろ」言うのだ。
岩浪さんは女性ヴォーカルを揃えてやって来た。突然なので、こちらも女性ヴォーカルとなった。
番組が進行するなか、いよいよ寺島さんが<タブー>の決定盤をかけようとした瞬間に事件が起きた。ケースを開いたが中にCDがない。「また、やっちゃった」と寺島さん。「これで7回目ですよ」と太田ディレクターの冷たい声がする。
話題が「寺島レコード」制作の中プロデユーサーの苦労に移った。ピアノトリオがどうして駄作に終わるのかという話がCDを聴きながら始まりプロデユーサーのセンスにまで及んだ。
ピアノトリオといってもピアノ弾きが主役ではない。むしろ演奏に音の強弱感をつけるのはドラムであり、陰陽感を与えるのはベースではないだろうか。3者が対等に絡みあうのだから正確には「ザ・トリオ」と呼ぶのが相応しい。
そんな意味もあって「ザ・トリオ」最新例のアルバムとして「UNICITY」CAM JAZZ 5019を紹介することにした。ベースは魔法の手と呼ばれるJOHN PATITUCCI、ドラムスは異色のリズム感溢れるBRIAN BLADE、そしてピアノはEDWARDS SIMON。録音エンジニアは数々の名録音を残している達人James Faber、NYのSear Sound Studio、2006年2月録音。
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年東京生まれ。ジャズオーディオ・プロモーター。「PCMジャズ喫茶」常連客。
 2007年07月/第42回 ヘルゲ・リエンは哀愁てんこ盛り
2007年07月/第42回 ヘルゲ・リエンは哀愁てんこ盛り
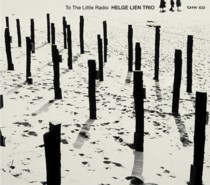
ジャズとは一体いかなる音楽か。
たまには、こういう難問に挑戦してみてもいいんじゃないか。
私に言わせれば、ジャズは「哀愁」と「ガッツ」の音楽である。
また始まったと言われそうだが個人の強い主張は何回繰り返してもいいのである。そうすることによって個人は浮かび上がることが出来るのである。浮かび上がるには強い主張。これ、絶対に必須のものである。
哀愁とガッツの音楽、ジャズ。
この際、ガッツはさておこう。哀愁一本槍でゆくことにしよう。
ジャズは哀愁の音楽ということになれば日本人はアメリカ人に勝てるのである。第二次大戦では敗北したが、ジャズの日米戦争では勝利をおさめることができるのである。
例えば有名なところでソニー・クラークの「クール・ストラッティン」。これがアメリカ人には分からない。日本人には分かり過ぎるほど分かる。アメリカで発売された時、売れずにすぐに廃盤になった。日本では延々と売れ続け、今や通算何十万枚というところであろう。
バド・パウエルの「クレオパトラの夢」も日本人の特権である。ジャッキー・マクリーンの「レフト・アローン」などアメリカ人にはまるきし分かりゃしないのだ。マル・ウォルドロンがリーダーのこのベツレヘム盤も発売されるとあっという間に廃盤になった。私がジャズ喫茶を始めた1970年、この盤が手に入らず、お客のリクエストに応えられず往生したものである。
『神様盤』だったのだ。
デクスター・ゴードンの「チーズケーキ」もカーティス・フラー~べニー・ゴルソンの「ファイブ・スポット・アフター・ダーク」も日本人のために作曲されたような曲なのだ。
どうも我々日本人はジャズではアメリカ人にかなわないと思っている節がある。アメリカで出来たものだしな、黒人のビートにはおよびもつかないしな、やっぱり日本人のジャズは箱庭なのよ。
しかし、である。いったん哀愁曲の鑑賞力ということになったらこのようにアメリカ人など目ではないのである。
大いにここのところを誇ろうではないか、と諸君を鼓舞したところで本日のCD盤紹介にとりかかりたいと思う。
なにはさておき、この紹介盤に網羅された曲目のラインナップに注目していただきたい。これぞ我々日本人が大変に好む哀愁曲のオン・パレードなのである。
しかも、である。オン・パレードとは言いながら先程何曲か挙げたヒット性の哀愁曲ではなく、その奥深いところで今や遅しと光を当てられるのを待っていたB級、いやC、D級のいぶし銀曲のオン・パレードなのだから。いや、私は強力に驚いた。やられたな、とがく然としたのだ。
一曲目の「グランド・ファーザー・ワルツ」など、昔ヴァーヴ盤でスタン・ゲッツとビル・エバンスが共演した超レア曲、しかし聴けば折目正しい日本人のジャズ・ファンなら落涙せずにはいられない、そんな哀愁曲なのだ。私はジャズ喫茶時代、これぞという時にかける必殺曲として隠し持っていた。我が国に「ソノーラ党」なる会派まで存在するという噂のあるハンプトン・ホーズの作った「ソノーラ」。これでリッチー・バイラークの「リービング」が入れば完璧すぎて恐くなる。
「アイダ・ルピノ」、一部に熱狂的なファンを持つ曲、ドラムのトニー・ウィリアムスが作曲した「ラブ・ソング」などまさに日本人にしか、そのまさの分などないアメリカ人などに分かってたまるかという哀愁名曲揃いなのだ。
さあ、諸君、手を延ばしてくれ。
諸君に哀愁を感じ取ることができるか。
出来るさ、日本人だもの。
よくぞ、日本に生まれけり、である。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2007年06月/第41回 テナー・マン、ズート・シムズは変わり者か
2007年06月/第41回 テナー・マン、ズート・シムズは変わり者か

家でCDやLPを聴いたりすると同じくらいライヴ・ハウスの来日ジャズ・メンや日本のプレイヤーを聴きに行く。ライヴ・ハウスだと目の前で聴ける上に、時々ミュージシャンと接する機会も持てるからである。
すると、CDやLPを聴いているだけでは分からない、生身の人間に触れたり、意外な面を発見出来る楽しみがある。最近の若手ジャズメンは内外ともに、「三ナイ主義者?」が多く、酒を飲まない、遊ばない(ステージが終わって女の子たちとも遊ばずにホテルに真っすぐ帰る)、ジャムらない(ステージ後、別のクラブに行ってジャムったりしない)ので楽しくないが、かつてのジャズマンたちはよく飲み、よく遊び、よくジャムったものだった。
ただ、アート・ペッパーには初来日の時、夜のジャズ・クラブに誘ったら、夫人のローリーに、「お酒のある店はダメ」といわれてしまった。彼女はアートを管理することで麻薬から救い出し、酒も飲ませないようにしていた。しかし夫人が来ないとわかっている日のライヴ・ハウスでは、この時とばかりに酒を飲みまくっていた。ところが演奏は全く乱れないのにはびっくりした。
大酒飲みといえば、ズート・シムズもひけをとらなかった。5回目で最後の来日になった83年の10月に、吉祥寺のライヴ・ハウスに彼を聴きに行ったら、演奏の始まる前から飲みはじめた彼は、休息時間も飲み続けるので、演奏は大丈夫か、とハラハラしたが、プレイにはまったく乱れがなく感心したものだった。ズートのテナーは本道をゆく、オーソドックスで、スムースで温かく、穏やかで温厚な人間性を感じさせるが、実像とかなり開きがあるようだ。実際は底なしの酒豪で、2テナーで全国をツアーして廻った西條孝之助も彼の飲みっぷりには驚いたようだ。一日にウイスキーのボトル2本はかるく空け、のどが乾いたといってはビールを飲んでいたが、飲むほどにプレイがよくなっていくのには二度びっくりしたという。
ズートといえば、アメリカで酔っぱらってホテルのドアを壊し、弁償させられたことがあるが、チェック・アウトの時、「弁償したのだからこのドアは俺のものだ」と言って、大きくて重いドアを抱えてホテルを出て行った、というのは有名な話である。彼は実は大変な「奇人」であったのである。
ところで、番組に持参したズートのCDは「ズート・シムズ/クッキン!」(フォンタナ盤)で、61年にロンドンの「ロニー・スコット・クラブ」でライヴ録音されたものである。付き合っているのは、このクラブのオーナー、ロニー・スコット(TS) らイギリス勢だが、これがなかなかの名演集なのだ。
この日は長澤氏の好きな曲特集なので「ゴーン・ウィズ・ザ・ウィンド」をかけるつもりで持ってきたのだが、みんな(といっても寺島氏と長澤氏の二人)が「枯葉」を聴きたいというのでその「枯葉」に。豊かに歌っていて、僕は久しぶりにズートのテナーを堪能した。このオリジナルLPは「幻の名盤」とされていて高値をよんでいたが、CDが出たので、僕は「MEG」のオークションでオリジナルLPを売った事がある。たしか1万円くらいで売れたと記憶しているが、そんなお金はすぐに飲み代で消えてしまった。レコードは売ったり買ったりするから面白いのであって、それでいいと思っている。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2007年05月/第40回 「香り」 と 「匂い」 そして 「気配」
2007年05月/第40回 「香り」 と 「匂い」 そして 「気配」

「香り」の代表的なものはお線香で植物性である。
いっぽう「匂い」は動物的で例えば麝香(じゃこう)ではないだろうか。お線香の最高峰は純粋な伽羅から作られる。京都「松栄堂」のお線香「正覚」はその香りを漂わせる。
「匂い」で最もセクシーな妖しい雰囲気をつくるのが麝香でジャコウ鹿の嚢から抽出された香料である。「TABU」はびんの蓋を開けただけで淫乱な香りがたちこめる。
ジャズ演奏を言葉で表現する難しさ。総合的な表現やワンポイント的表現に限らず「香り」と「匂い」はよく引用されている。
ジャズの美しいメロディから「香り」に敏感なのは寺島靖国さん、ファンキーなリズムから「匂い」に固着するのは岩浪洋三さんである。具体的に言えば寺島さんはピアノトリオに「香り」を求めるが、岩浪さんはホーンカルテットの「匂い」を楽しんでいる。
そういうお前はどうなんだ。ジャズオーディオ熱中症に長く罹っている私は「香り」や「匂い」よりもミュジシァンの「気配」を音で聴こうとする。楽器のイメージまで部屋に再現しようと欲張っている。
前回は寺島靖国さんの選曲を3人でアルバム紹介を行なった。今回は岩浪洋三さんのMy Best 3 Songsで「The Way You Look Tonight」「Willow Weep For Me」「My One And Only Love」を3人でアルバム選びをやろうということになった。
私はジャズオーディオ人間であるから当然高音質の最新録音CDを持参した。「My One And Only Love」はディヴィト・フリーゼン・トリオのアルバムから選曲した。David Friesen(b) Randy Porter(p) AlanJones(ds) による2枚組みのアルバムでタイトルは「THE NAME OF A WOMAN」(MTCJ-6508/09)。
弾けるような弦をベースから聴きたいのでオーディオ装置にこだわってきた。どうしてもリアルなベースの音を求めてCDを探す。大型スピーカーで鳴るベースはたまらない。サブ・ウーハーと呼ばれる超低音再生専用のスピーカーを備えているので床を這う低音に加えブルンと部屋の空気が圧縮される。D・フリーゼンのベースからそれが聴こえる。
CDには記録されていない音の超高音域20KHzから120KHzの空気感を演出するためにスーパーツィーターを左右4セット備えた。FIDELIX社開発のアコースティック・ハーモネィターAH-120Kはミュージシァンの「気配」を空気振動で伝えてくれる。
ピアニストのR・ポーターは自分でも録音スタジオを持っており録音エンジニアもやりながら自主制作の高音質CDを「HEAVYWOOD」レーベルで数枚リリースしている。これらも録音現場の気配が聴こえるアルバムなので手許から離せない。
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年東京生まれ。ジャズオーディオ・プロモーター。「PCMジャズ喫茶」常連客。
 2007年04月/第39回 冷血女ホリー・コールに何が起こったか!?
2007年04月/第39回 冷血女ホリー・コールに何が起こったか!?

やあ、諸君、元気かね。
しかしこの文章の出だし、いかにも軽い。私はわざとやっている。
最初に軽い一行をもってこないと肩に力が入って結局、悲惨な目を見ることが多いのである。
私の場合。肩に力を入れない。
これが私の至上命令になっている。
文章てのは、売文だろう。人を喜ばせるものである。笑わせてなんぼのものであろう。私なんか人に笑われたら嬉しい。笑っているのを見てこっちも笑っているわけだから。
さて、ホリー・コール。
しばらく前にテレビに出ていた。インタビューの番組で、ずいぶん肩の力の入った物言いをしていた。いわく、『スタンダードは昔の人の様に歌うものではない。新しい歌手は新しい歌い方を見つけて歌わなくては新しい歌手の意味がない。現代には現代向きの歌の新しい解釈がある。』大体がそんな主旨だった。
それにしてもホリー・コール。見るからに冷たい女である。黒い制服を着てイギリスの大邸宅に勤めるマユひとつ動かさない女執事。そんなよくないイメージがたちまち想起されてくる。そういう冷たい女が人に規則正しいことを言うのだからたまったものではない。
私はすぐさま、この女が嫌になった。あんたはボーカル学者か。そんなことは一部のややこしい評論家、好事家にまかせておけばいいんだ。歌手は『歌のしもべ』だろう。
ホリー・コールは私の脳裏から消えた。
と、そこへ今回の新譜である。私はどんなに興味のない盤でもとりあえず曲面だけは眺める。すると、けっこう大変だ。大好きな曲のオン・パレードである。
まず、『シャレード』。私はこの曲に目がない。たとえサッチモだろうがビリー・ホリデイだろうがこの曲なら聴いてしまう。「イッツ・オールライト・ウィズ・ミー」「ユー・アー・マイ・スリル」「シェルブールの雨傘」。このように良曲の目白押しで来たら耳をかさないわけにはゆかない。私は聞く耳を持ったのである。
ホリー・コール。あんたはいつから冷たい女からあったかい女に変わったのか。そりゃ、確かに声帯は柔らかくふくよかというわけにはゆかない。幾分摩耗もしていてところどころに生活臭がにじんでいる。
しかし以前のように肩に力が入っていない。スタンダードを新しく歌ってやろう、聴かせてやろう。新機軸のジャンヌ・ダルクになってやろう。そういう力のこもった嫌みが感じられない。なにかとても塩梅のいい歌の境地にいるわけである。自然な歌い方にほんの少し工夫をこらしている。以前のような文化的な大幅な工夫がないから私はよっしゃと思ったのである。
一曲目の「ザ・ハウス・イズ・ホーンテッド」。工夫をつければいくらでもつけられそうな歌である。嫌な予感がしたがしかし、これがどうだ。まったくこの人らしくなく、人臭くて、けだるく、土の香りがする。継続的にずっとけだるい歌手できたんじゃないのか。ふとそんなあり得ないことを考えた。なにか転機になるようなことがあったとしか思えないのである。それとも以前の誇大表現発言は若気の至りだったのか。反省したのか。
まあ、いいんだ、いいんだ。俺なんかしょっちゅう反省の連続の人生よ。カメレオン呼ばわりされる俺さまだ。いちばんよくないのは間違っていると分かっても自説にこだわり、しがみつくことなのだ。
とまあエラそうなことをほざいたがしかし、ホリー・コール。
要するに人を楽しませる、エンターテインメントの世界に突入したのである。
ボーカルはこうでなくちゃあ。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2007年03月/第38回 謎の人妻A特別寄稿/赤い糸
2007年03月/第38回 謎の人妻A特別寄稿/赤い糸

人と人との出会いに運命的な何かを感じることがある。65億人もの人が住むこの地球上でたまたま「PCMジャズ喫茶」を聞いてファンになった私が、たまたま寺島さんに出会い、こうして「謎の人妻A」として「210歳トリオ」の皆さんと一緒に番組に出演させていただいているのも、何か「赤い糸」で結ばれているとしか思えない。
音楽にも同じような事を感じることがある。私の大好きな曲に「リバーマン」というのがある。この曲をブラッド・メルドーの演奏で聴いて「一目惚れ」して作曲者のニック・ドレイクと出会った。しかし彼はすでにこの世の人ではなかった。残された数枚のCDと「ニック・ドレイク悲しみのバイオグラフィー」という一冊の本が私をいっぺんに「本気」にさせた。「リバーマン」が入ってるだけでそのCDを聴いてみたくなる。
昨年発売されたドイツのトランぺッター、ティル・ブレナーの「オセアーナ」にもこの曲が入っていた。ティルの甘い歌声と情感溢れるミュート・トランペットで、曲の持つ美しさ、もの悲しさがじんわりとしみて来て益々好きになった。ティル・ブレナーを初めて知ったのが、ジャズ・アルバムのジャケットで有名な写真家ウイリアム・クラクストンの映画「JAZZシーン」を見てから。音楽監督を務めている彼の音楽が映像と素晴らしくマッチしていた。
赤い糸は伸びて今回番組で紹介する「マデリン・ペルー」に繋がる。「オセアーナ」の中、ハンク・ウイリアムスの曲「泣きたいほどの寂しさだ」で彼女はティル・ブレナーと共演している。ゆったりと肩の力を抜いて歌うこの曲を聴くと、タイトルのような深い淋しさも少しづつ薄まっていく。
マデリン・ペルーの新作「ハーフ・ザ・パーフェクト」の中にもティル・ブレナーと共演した曲が2曲入っている。「スマイル」を選んだ。あたたかい気持ちにさせてくれる彼女の歌を聴くと、まるで「淋しさもスマイルも同じことなんだよ」と思えてくる。そんな気にさせてくれるところに彼女の素晴らしさを感じる。
この先も「赤い糸」はまだまだ繋がっていきそうだ。
重藤敬子(しげとう・けいこ)
「PCMジャズ喫茶」レギュラー・ゲスト。
 2007年02月/第37回 新人歌手 ロバータ・ガンバリーニ讃
2007年02月/第37回 新人歌手 ロバータ・ガンバリーニ讃

去年の11月23日にアニタ・オディが心不全で亡くなった。86歳だったが、最後まで現役で歌っていた。昔の江戸っ子のように、宵越しの金を持たないような生き方が好きだった。カーメン・マクレエはお金が出来ると、ベバリーヒルズにお手伝いさんをやとって生活していたが、アニタはアパートで一人暮らしだった。晩年のインタビューで、アニタは「たとえすっても競馬が大好き。結婚したこともあるが、それももう終わった。結婚はキライ。ジャズとは何かって?それは私の人生」と答えていた。
アニタが亡くなったのは淋しいが、その代わりともいうべき生きのいい新進ジャズ歌手が現れた。それがイタリア系のロバータ・ガンバリーニだ。昨年2度来日し、‘コットン・クラブ’とコンコード・ジャズ祭で聴いたが、抜群の歌唱力で、スキャットもうまいが、バラードの情緒たっぷりの歌い方など、ベテランもびっくりの表現力をみせてくれる。ただ者ではない歌手だ。ベテランがいなくなれば、必ず新人が出てくる。これは何の世界でも同じではなかろうか。野球の松坂大輔が何十億だかで大リーグ入りし、このところの相次ぐ大リーグ入りで日本のプロ野球を心配する向きもあるようだが、そんなことはないとおもう。ビッグな大リーグ入りをみて野球を目指す子供はふえるだろうし、むしろ野球の人気は高まるだろう。日本のプロ野球もケチなことはいわず、もっと全盛期の選手が早く大リーグに行ける道をつけた方がいいとおもう。上がいなくなれば、新人も早くスターになれるだろう。
ジャズ界でも1970年代に日本のジャズメンのニューヨーク行きが流行ったことがある。しかし海外生活は嫌いという人もいて、みんな実力者が海外へ流出するわけではないし、何年か経つと大半のジャズメンは日本へもどってきた。海外での活動がそんなに甘いものでないことは野球もジャズも同じである。
ところで、先日番組‘PCMジャズ喫茶’で、ぼくはロバータ・ガンバリーニの「ディープ・パープル」をかけた。ぼく、寺島靖国氏や長澤祥氏ら古手は「ディープ・パープル」といえば、すぐに昔ヘレン・フォレストが歌った「ディープ・パープル」を思い出してしまう。ところがゲスト出演の若き人妻Aさんは「あら。こんな歌はじめて聴いたけど、とてもすてきね」といった。白紙で聴けるAさんはすてきだ。われわれ3人、‘知り過ぎていた男たち’はどうしても過去のヘレンと比べてしまう。不幸なのだ。次回にはヘレン・フォレストの「ディープ・パープル」をかけて人妻Aさんの感想を聞いてみたい。
ところでロバータ・ガンバリーニの「ディープ・パープル」は昨年末に発売された彼女の第二作「ラッシュ・ライフ/ロバータ・ガンバリーニ&ハンク・ジョーンズ」(55RECORDS)に収められている。今回はバラードをたっぷり歌っているが、そのうまさに舌を巻いた。
ロバータの歌は、じつは4年ほど前ニューヨークでライブを聴いたことがあった。N.Y.の歌手で親しくしている歌手カーラ・ブレイに誘われて‘ジャズ・ギャラリー’で聴いたのだが、その時はエラ・フィッツジェラルドのような歌い方で、スキャットもうまいが、まずまずの新人という印象だった。ところが来日時には見違えるような、個性たっぷりの歌手に変身していて、心底びっくりしてしまった。来年も日本でツアーの予定ありと聞いているので、今から楽しみだ。
岩浪洋三(いわなみようぞう)
1933年愛媛県松山市生まれ。スイング・ジャーナル編集長を経て、1965年よりジャズ評論家に。
現在尚美学園大学、大学院客員教授。
 2007年01月/第36回 不治の病「熱中症」
2007年01月/第36回 不治の病「熱中症」
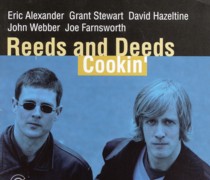
私を含めて趣味の「熱中症」にかかっている人に同情すると同時に自分自身も生涯不治の病と覚悟することにした。熱中症は年齢に関係なく突然やってくる。熱中症には短期で終わるものと長期に続くものがある。私の場合を白状すると「ジャズレコード」「オーディオ」「酒と珍味」は長期熱中症で50年位不治の病となってしまった。いっぽう短期熱中症は「写真撮影」「推理小説」「ストリップ劇場通い」「アブサン」「将棋」「クルマ」「テナーサックス」流石に「骨董品」は銭がかかり過ぎるので諦めた。
短期熱中症候群はバッファリンを飲んで直ぐ効くみたいに治まってしまう。一過性の熱中症で「多趣味症候群」とも呼ばれている。ところが長期熱中症候群は治らない。ジャズレコード人間の私であるから特定ミュージシァンに熱中すると集中的にレコードを買い漁り聴きまくる。
1950年頃からジャズを聴き始めたが直ぐにウエストコースト・ジャズにはまってしまい「コンテンポラリー」や「パシフィック」レーベル熱中症にかかった。後遺症は今も続いている。
1995年頃だったと思う。エリック・アレキサンダーのデビューアルバム「UP, OVER & OUT」に出会って驚いた。なんと新鮮なテナーサックスの音か。エリックのテナーサックスを聴く熱中症にかかってしまった。以来エリックのアルバムは全て買って聴いている。 熱中症候群の危険性は浮気の虫が何時も侵入してくるので危ない。浮気の虫が本気の虫となる。いま私の中に住みついた虫の名前はグラント・スチュアート。クリスクロスレーベルのデビューアルバムから最新アルバムまで集めてしまった。完成されたようなエリック・アレキサンダーとは違って成長期のグラント・スチュアートには発芽期のモヤシのような生命力を演奏に感じる。新作「ESTATE」と「WAILIN’」には芽生えるエネルギーが溢れている。今回放送では「COOKIN’」から曲「TROUBLE IS A MAN」を選んだ。テナーサックスの音に痺れるのはホーンから吹き出る低音のひびきではないだろうか。デクスター・ゴードンにせよソニー・ロリンズにせよ中低音の魔力が耳をひきつける。映画「お熱いのがお好き」でマリリン・モンローが呟いた。「私テナーサックスに弱いの。あの音聴くと骨抜きになっちゃう。甘いメロディーをテナーサックスで8小節吹かれると私メロメロになっちゃう」。グラント・スチュアートはその「メロメロ」の音を聴かせてくれる。「グラント・スチュアート熱中症候群」に感染してしまった現在だが「ジャズオーディオ中毒症」にも50年ほどかかっている。こちらは副作用が激しく金銭感覚が麻痺してしまう。1m15万円のケーブルを平気で買ってしまう友人さえいる。
中毒といえば究極の珍味と魯山人が絶賛した能登半島の「くちこ」と「このわた」の味を覚えてから禁断症状が始まった。羽田からひたすら能登空港に向かう。「珍味と旅する男」はカード払い不感症も併発してしまった。
長澤 祥(ながさわ しょう)
1936年東京生まれ。オーデイオメーカー数社在籍後、前日本オーディオ協会事務局長。現在「PCMジャズ喫茶」出演。
 2006年12月/第35回 藤岡琢也さんとビック・ディキンソン
2006年12月/第35回 藤岡琢也さんとビック・ディキンソン
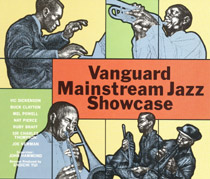
「昔、スイングジャーナル誌に連載していた『ジャズ・ファン訪問』取材のため、藤岡琢也さんを訪問したのは、1962年6月のことであった。NHKの連続ドラマ『横堀川』で演技賞を得たばかりのこの新人俳優は、その頃青山一丁目の都営アパートに住んでいた。」
これ、どなたの文章かお分かりになるだろうか。声を聞けばすぐにわかるが文章は難しい。
油井正一さんである。
このCDのライナーノートに付いていた。私はこれまでジャズ評論家の文章を自分の文に取り入れたことは一度もない。今回が初めてである。
なぜ引用したかというと実にタイムリーだからである。
タイムリーとはこれまた実に不謹慎な言い方で身の細る思いだが、藤岡琢也さん、つい最近お亡くなりになったのをご存知だろう。
その藤岡さんが、油井さんの取材の際に私の一番好きなレコードです、と言って差し出したのが、このビック・ディキンソン盤だったというのだ。
これは転載しないわけにはいかない。
ビック・ディキンソンは主に1940~70年代に活躍した黒人のトロンボーン奏者。人間の声によく似ていると言われるトロンボーンだが、
なかでもディキンソンの演奏ほどそれに酷似したものはない。人間臭いトロンボーンを吹かせたらディキンソンの右に出る人はいないのである。
少ししゃがれた声で関西弁みたいに聴こえたりする。藤岡琢也さんみたいではないか。
藤岡さんのトロンボーン好きは一部の人の間で有名だ。ジャズ・ファンには不人気楽器ながら世の中には信じ難いほどのトロンボーン好きというのがいて、
私もその一人だが、藤岡さんはその第一人者である。
「もし胸の病気をやらなかったらビッグ・バンドのトロンボーン奏者になろうと思うてましてん。」
藤岡さんは油井さんにこのように語ったという。
油井さんはそれについてこう言われている。
「それもいいが、きっと神様が『俳優になれ』と思し召して彼に病気を授けたのだろう。」
なるほど。でも私は反対である。異議申し立てをしたいと思う。
藤岡さんが一念発起し、きびしい練習の果てトロンボーン奏者になっていたら、きっと谷啓をしのぐ名手が誕生したのではないか。好きこそものの上手なれ、である。
さて、少しCDの紹介をしておこう。
とにかく一曲目の「ラッシャン・ララバイ」。これに尽きる。これ一曲でいい。
この一曲を知るかどうかで君のジャズ人生が変わること間違いなし。
元祖「ラッシャン・ララバイ」なのだ。作曲したのは「ホワイト・クリスマス」のアービング・バーリン。ロシアの移民の子で彼以外にこんな「ロシアの子守唄」は作れない。
よくジャズの世の中で「名演」という言葉が遣われる。では名演とは何か、と問われたらどんなジャズ評論家も一瞬目を白黒させるだろう。一言で答えられる人など誰もいないはずだ。
では、ふつつかながら、私がお答えしよう。
この「ロシアの子守唄」のように、である。絶世の旋律と絶世の楽器の音が一体となったもの。琴瑟相和したもの。それを名演という。
出てくるクラリネット、ピアノ、トランペット、いわんや、トロンボーン。
これらの全ての楽器がこの曲を演奏するために製造された。そう思えてくるほどなのである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2006年11月/第34回 息なCD
2006年11月/第34回 息なCD

今、この世で一番つらく厳しい仕事は何か、ご存知か。
息である。息の検査。そう、交通検問所に居並ぶ警察官の方たち。
いや、ご苦労様。大変です。察するに余りある。
息を吸わされたるだけでも嫌なのに、お願いして息を吹きかけてもらわなくてはならない。
一台や二台ならともかく、見渡せば果てしなく列を作って検問を待つ車、また車。
ため息の一つや二つ当然出るが、しかし嫌な顔は見せられない。
笑顔を作ってドライバーの口に顔を近付けなければならないつらさ。
電車の中で隣りのバカ親父にアクビの息を吸わされその日一日不愉快な私などとてもじゃないが勤まる仕事ではない。
いや、本当に。頭が下がります。
一方、楽ではないのはドライバーのほうも同じである。
喜んで吹きかける人など倒錯者以外いないだろう。
急に思い出したりする。
今朝、オレ何食ったっけ?あっ、いけねぇ。納豆だ。薬味ネギをどっさり入れたよなぁ。
うら若い女性だっているだろう。中にはハンサムな警官だっているだろう。
どう考えても恋が芽生えるというシチュエーションではない。
女性はリステリンを用意するだろう。
リステリンが車の必需品になる昨今である。
これは何もかも、ごく一部の飲酒運転常習者のせいである。
憎むべきそうした輩。
さて、息を吸いたい女性がいる。本日のボーカリスト、ジューン・モンハイトである。
私はジューン・モンハイトの歌う「ベサメ・ムーチョ」を聴いてボーカルの奥義がわかった。
究極、そして最高のボーカルとは聴いていて、ああこの人の息を目一杯嗅ぎたい、吸いたい。そう願わせるボーカリストである。
これまで私はいろいろな女性のボーカルを聴いてきた。しかし、本日この人ほど息について思考愚考したことはなかった。
ジューン・モンハイト。若く美しいボーカリスト。まことに活きのいい、そして息のいいボーカリストである。
このCDについて説明しよう。ジューン・モンハイトをたっぷり吸えると思ったら大間違い。たったの一曲だけ。それが「ベサメ・ムーチョ」なのだが、唯一の一曲というのが泣かせる。まさしく一曲入魂を地で行っているのだ。
リーダーはギターのフランク・ビノーラ。コリーダーにドラムのジョー・アショーネ。このドラマーは近頃ヴィーナス・レーベルから頻発されているピアニスト、エディ・ヒギンズのリズムの根底を支えている人。
そのギター・カルテットに何人かのゲストが参加している。なんと、ドクター・ジョンやマントラのジャニス・シゲール、それに本日のヒロイン、ジューン・モンハイトというわけだ。
そして、それぞれ各人が一曲づつ歌っているという珠玉の一曲。
私はこういう贅沢な作りのCDを歓迎する。ギター・カルテットだけで10何曲もやられたら、さすがにうっとおしい。
一曲に福がある。
実に息な、いや、粋なはからいのCDである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2006年10月/第33回 クレオパトラの夢
2006年10月/第33回 クレオパトラの夢

やぁ諸君、元気かね。今日は秋吉敏子さんの話から始めていこう。
昔、秋吉さんがコンサートを行った時のことである。『クレオパトラの夢』を演ることになった。秋吉さんはいつもの少し口ごもるような感じでこうアナウンスしたという。
「日本の皆さんはバド・パウエルの作った『クレオパトラの夢』が大変お好みらしいが私はあんなの好きではありません。でも皆さんがお好みなので演ります。」
演奏の出来がどうだったかは聞きもらしたが、先日こんなエピソードを岩浪洋三さんが苦笑まじりに語ってくれた。
『クレオパトラの夢』は日本のジャズ・ファンの国民的愛唱歌と言っていい。ジャズ・ファンにとって難物に見えるバド・パウエルが親愛の情をもって迎えられたのはひとえに彼が作曲発表した同曲によって、である。
ジャズ・ファンにとってのバイブルは1947年の『バド・パウエルの芸術』ではなく、1960年作の同曲が入った『シーン・チェンジス』に間違いない。この一曲によって「むずかしいパウエル」は「優しいパウエル」に変わったのである。
秋吉敏子さんの場合はどうか。秋吉さんは、なるほど、皆さんご存知のように立派な方で尊敬を集めているが、しかし親しまれているとは決して言えない。私なんぞははっきり言って敬遠しているくらいである。彼女の昔作った『ミナマタ』など、大変つらい。ジャズのミュージシャンにとって作る曲がいかに重要か、ということだ。
若いミュージシャンに言いたいが細かいテクニックなどを磨く暇があったら大きく優美なメロディーの曲を作曲考案したらどうか。そのほうがよほど大きくジャズ界に貢献することになると思うが。
今、『クレオパトラの夢』級のオリジナルが50曲、いや30曲出現したらジャズ界は大きくいい方向に変わるだろう。
さて、こうした名曲はいろいろなミュージシャンによって引き継がれていく。『クレオパトラの夢』を引き継いだ一人が女流ピアニストの川上さとみさんである。これを聴いて私のいつものいたずら心がむくむく頭をもたげたのであった。
例の善男善女が集まるジャズ・クラブへ本家本元のバド・パウエルと川上さとみさんの『クレオパトラの夢』を持ってゆき、どちらがどちらと言わずにかけてみたのである。そして、さて、皆さんはどちらの演奏がお好きですか?挙手でお願いします。
7対3の割合で川上さとみさんが勝利を収めたのである。もちろん、理由を訊くのを忘れてはいない。川上さんのピアノがきびきびはつらつとしていて気持ちがいいという人が多かった。近代録音による音の良さ、という点もあるだろう。女の情念のようなものがピアノの音の中に巧みに混入されていて圧倒されたという若い女性がいた。バド・パウエルはモゾモゾ地面を這っているようでうざったいと。これはビギナーの若い女性。パウエルに票を入れた人はベテランのファンに多く、これはパウエルの名前の威光から抜けられないのだろう。
いや、まったくお気の毒。パウエルまるでかた無し、面目丸つぶれ、である。
名演、名盤も時とともに変わっていくのだな、と思った。名盤も老いる。識者やファンが気付かないだけかもしれない。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2006年09月/第32回 女性のジャズ
2006年09月/第32回 女性のジャズ

二人の23才が活躍している。共に女性である。
ところで今、ジャズは決定的に女性のものになった感がある。男はからきし元気がない。なぜジャズが女性に適しているのか。女性は男より「大人」だからである。ジャズは「大人の音楽」なのだ。男はいくつになっても子供。だから相変わらずいつも青臭いジャズを演って聴く人をげんなりさせている。いまジャズ界に必要なのは青臭いジャズではない。お尻に青いハンテンのついたベイビー・ジャズではない。小難しいジャズではない。必要なのは大人のジャズ。大人のジャズとは、では、どういうジャズか。先日私はあるジャズの会合に出席した。そこで23才の女性盤をかけたのである。大好評であった。拍手をもって迎い入れられた。
その会合に出席していた大部分の人はこれからジャズを聴いてゆこうという人たちである。「超ジャズ入門講座」という臭いタイトルに引かれて集まった善男善女。ジャズ・ファンの金の卵。
そういう知識ゼロ、ジャズ聴取体験皆無の人たちが二人の23歳を絶賛したのである。ジャズ・ファンではない人たちからほめられるジャズを私は「大人のジャズ」と呼んではばからない。ジャズファンではない人が案外ジャズという音楽を見極めたりする。ジャズの渦中に毎日いると固定観念にはまって意外に本質を見抜きそこなうのである。
何十年もジャズを聴いてきた人の勧めるものなどロクなものはないから気を付け給え。あっ、いけない。こういう言い方は自分の首を絞めてしまうな。
さて23才の一人はソフィー・ミルマンである。ロシア生まれの大学生。声を聞いて45才ではないかと言った人がいた。そのくらい歌が深いのである。人生を感じさせてやまないのである。
と言って、安易にビリー・ホリディーの方向へはゆかない。そこが凄い。歌で相当難しいことをやってのけている。大人の23才。
さて本日のスター。ロシアが歌なら我が日本はトランペットである。市原ひかり、その人である。
この人のトランペットのいいところは一聴、あっ、これならオレにも吹けそうだ、と思わせるところである。
村上春樹や川上弘美の文章がそうなんだ。オレにも書けそうだ。私にできそうだ。でも書けない。
市原ひかりのトランペットは平易で深い。ソフィーミルマン同様、すでに長い人生を過ごしてきたようなミュージシャンである。
思わず「臈長けた」などといういにしえの言葉を思い出してしまった。経験を積み重ねて立派になると辞書に出ている。もう一つの意味として女性が美しくて気品がある。
やぁ、まさに市原ひかりさん、その人のことではないか。少しほめ過ぎかな。いや、新人はほめ過ぎがいいのだ。マイルスやコルトレーンをいつまで絶賛していても仕方がない。低音、つや消し奏法ながら特にマイルスの方向にゆかないのがいい。誰の方向でもない。市原ひかりの方向だ。そのうちもっと市原ひかりらしくなるだろう。ただしオリジナル曲にはちょっと力が入った感じがなきにしもあらず。可愛いが。
すでに萌芽は見えている。きざしが感じられるのだ。歌である。歌。彼女のトランペットのベストの個所は歌なのだ。歌うトランペッター。フレーズが口ずさめるトランペッター。こういう人は今、非常に少ない。しかし、大多数の心あるジャズ・ファンが求めているのがそれ、なのである。きらびやかな派手なうまさはこの次でいいのだ。
需要と供給のバランスの崩れたトランペッター界に現れた貴重な人材だ。そしてさらに上手い下手など関係ない「ジャズの雰囲気」「大人のジャズ」「歌うトランペッター」。この三要素を合わせ持つ、いや、実に鬼に金棒。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2006年08月/第31回 ジャズの聴き方
2006年08月/第31回 ジャズの聴き方

やぁ諸君、元気かね。私は元気がない。それで原稿が書けない。仕方がないからテレビをつけたら「突撃」をやっている。カーク・ダグラス主演の第一次世界大戦を扱ったモノクロ映画。二度目だがこれは観るしかないと腰を据えた。またあの鉛の棒を飲むような気分になるのかと思ったらその通りだった。
敵前逃亡の罪で3人が銃殺されることになる。例え、最後の一人になっても後退は許されない。前進あるのみ。それが軍隊だ。各国共通。後退を許したら全員が後退する。そしたら戦争にならない。
見せしめのための処刑だ。一人は傷を負っている。意識もうろう。タンカを立てての銃殺だ。スタンリー・キュブリックの大反戦映画。すごい。一般社会でも見せしめはある。戦争はその究極のかたちだ。
深夜映画で探してみてくれ。人間社会の不条理に腹が立つ。いきり立って元気のなさなど吹き飛ぶ。
さぁ、書いてゆくぞ。
私はいま、いろんな人とジャズの聴き方について争っている。映画を観てますます争おうという気分になった。
ジャズの聴き方には色々ある。私なりにこれまで自分の聴き方をこしらえたつもりだ。しかし、一つじゃない。どうも、そこが不安なのだ。
某日、私は中尾洋一さんをお訪ねした。中尾さんに聴き方を尋ねてみた。
中尾さんはジャズのプロデューサーで何年か前に日本ジャズ維新シリーズを立ち上げた人。今日本人ジャズ・ミュージシャン・ブームの創始者の一人だ。「音ですよ、音」と中尾さんは言うのである。音とは?オーディオですか。それなら私もやっているのですが。違う。楽器の音だとおっしゃるのである。例えばギターだが、最初の一音でぐっときたら、もうそのギタリストは大好き!となると言う。
音のほかにもいくつかある。フレーズで聴いたり、スタイルで聴いたり。しかし、そういうのはニの次、三の次だ。
頭脳のほうが幾らか発達した人なら歴史観的に聴いたりもする。
インプロバイズを極める人もいるだろう。しかし中尾氏は音。完全に見事に楽器の音を聴く。そういうジャズ人生を長年送ってきてそういう生涯をとげるのだとおっしゃる。
分かりやすいではないか。潔いではないか。
音をターゲットにミュージシャンを探し、惚れ込み、レコーディングを行ってきた。そういう人なのだ。本来なら、中尾さんの作ったCDを紹介するところだろう。
しかし、なかなか人生うまくゆかないのよ。
それで今日は音で聴いて最高のトロンボーン盤を俎上に乗せることにした。
片岡雄三さんだ。なんと。初リーダー作だというのである。いかにトロンボーンという楽器が恵まれていない楽器かが分かるではないか。どんどん私はトロンボーン盤を紹介してゆくぞ。
お父さんが有名なトロンボーン奏者である。小学校の時ピアノを習った。中学校に入りブラスバンドに応募すると何か楽器を持ってこいと、家にころがっていたトロンボーンを持っていった。
その頃見た映画が「グレン・ミラー物語」。トロンボーンってこんなに格好いいのか。お父さん、かたなしである。
いや私だって高校生の頃見て始めたいと思ったのよ。しかし家にトロンボーンがなかった。それで片岡雄三さんと差がついたのである。中学校から始めていたら今頃は私だって。いや、よそう。
なんたって美しく格好いいのが「ラブ・レター」である。いやはやこの音の品のいい格好よさはどうだろう。
思わず片岡雄三さんのトロンボーンを検査したくなるのである。ひょっとして管のなかにビロードの布が貼ってあるじゃないか。でなければ、こんななめらかな音が出るわけがない。
なめくじでも住んでいるんじゃないか。でなけりゃこんなぬめりが出るはずがない。 もちろんテクニカルな面も凄い。「マイ・フーリッシュ・ハート」の超絶高音にはただひたすらため息のみ。
しかし、コーヒー・ブレイクに演奏したという「ラブ・レター」の情緒、歌心、なめらかな音が彼のテクニックを感じさせないテクニックだ。ミュージシャンのコーヒー・ブレイク、はし休めがわれわれリスナーのメイン・ディッシュになることが多い。そういう逆転現象もジャズの聴き方の一つである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2006年07月/第30回 ロソリーノと野球
2006年07月/第30回 ロソリーノと野球

私は文化人であるからジャズは聴くが野球は観ない。そういう主義を通してきた。しかしイチローが現れて私は趣旨変えをしたのである。イチローには普通の野球選手にはない知性がある。
私はいっぺんでイチローに惚れこんで彼の出演するマリナーズ戦を好んで観るようになった。
大リーグを観るようになってから気がついたのだが、向こうの野球は日本と違うところがある。観客である。どう観てもアメリカの観客は日本人と違う。何というか、大人しいのである。殺気立っていない。もちろん勝敗にこだわるんだろうが、試合そのものを楽しんでいる風が大きくある。子供連れが多い。
画面を観ているとスタンドの観客のありさまが頻繁に写る。もちろんプレイする選手が主役に決まっているが観客も脇役としてきちんと遇されているのがわかる。ホームランの球がスタンドに叩き込まれる。カメラは球の行方を追ってゆく。首尾よく誰かがその球を手にしたりするといかにも嬉しそうなその人を画面できっちりとらえてあげるのだからアメリカは偉い。
それにしてもアメリカの客はよく球を欲しがるものだ。イチローが、飛んできた球をしっかり補球し、それをいかにも自然にさりげなくスタンドに投げ入れアメリカ人が喜ぶとなんだかこっちもじんわりと幸せな気分になってくる。あれくらい日米親善に役立つものはない。
何回目かの交替の時に観客が一勢に立ち上がってなにやら歌い出すのだから慣れない日本人は驚いてしまう。
アメリカ人は3人集まるとコーラスをはもり出す人種と聞いたことがあるが、野球場であの大勢が口を揃えて歌いだすとは知らなかった。
阪神ファンが黄色い大旗振って大騒ぎしているのに海の向こうでは静かに声を揃えての合唱野球はアメリカが勝ち。さっそくの合唱曲が「Take me out to the Ballgame」である。
いつの間にか憶えてしまい、いい歌だなと思っていたら、おっと、こんなCDの中に入っていたとは。しかも私の好きなトロンボーン演奏ときたもんだ。いや、長生きするものである。
余程のトロンボーン・ファンでなければ目を付けないだろう。レーベルは「ショボイ」いや、失礼、「サボイ」。ブルーノートやプレステージに比べ断然しょぼさで勝るサボイ。
しかしこんな上玉が潜んでいたのだなぁ。あなどれないぞ、サボイは。
特にこうしたオムニバスはさらに深く探ってみる必要がありそうだ。
J・Jジョンソン、カーティス・フラーといった一流名前がジャケットに見える。「Take me out to the Ballgame」を演っているのはフランク・ロソリーノだ。
イタリア系のロソリーノはテクニシャンとして通っているJ・J・ジョンソンよりもテクニカルに聴こえるといってもいい。同じテクニシャンながらロソリーノとJ・Jが明らかに違うところ。それは選曲である。ロソリーノはJ・Jが間違いなく絶対演らない曲を選ぶ。
それが「Besame Mucho」だったり「Linda」だったり「座って自分に宛てて手紙を書こう」だったりするが「Take me out to the Ballgame」もそうしたいかにもユーモリストのロソリーノにふさわしい一曲なのだ。
スタン・ケントン楽団に50年代に在団した。楽団は楽旅が多い。バスの中でロソリーノはマウスピースをピューピュー吹いていつもまわりを笑わせていた。クレイジーだと言われもした。
ハイスピードテンポの実にテクニカルな演奏ながらどことなくユーモアを感じさせるロソリーノのプレイ。屈託のないほのぼのとしたプレイはどこかアメリカの野球場に通ずるものがある。
[P.S.] ロソリーノの「Take me out to the Ballgame」が入ったCDが9月20日、日本コロムビアから発売されます。オムニバス4枚組で岩浪洋三さんと私がコロンビアの持つさまざまな音源から25曲づつ、計50曲を力一杯選曲「岩浪VS寺島」の対立構造でリリースされることになりました。「Take me out to the Ballgame」を発見してしまった私はサボイ音源をさらに深く静かに探ってゆきたい。4枚組で3000円というのですから安い。なんと1枚750円、 1曲60円のお買い得。なんだか岩浪さんと私が低く見られているような気もしますが、そこは会社の太っ腹、といい風に善意に解釈しておきましょう。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2006年06月/第29回 オムニバスのすすめ
2006年06月/第29回 オムニバスのすすめ

オムニバス盤が好きである。思わぬ拾い物があるからだ。
そういえば、10年も昔のこと。とある日本のレコード会社がジャズ・ジャイアンツ10人のオムニバス盤を作ったことがあった。ソニー・ロリンズやジョン・コルトレーン、レッド・ガーランドにビル・エバンスなど。それぞれを得意とする評論家が一人ずつを担当して編集したのだが、いや、そのつまらなさといったらなかった。
拾い物という精神が欠如していたからだ。評論家の特性を活かしていわゆるこれが名演だ、名曲だの方向に走った。ソニー・ロリンズなら「モリタート」に「セント・トーマス」、ビル・エヴァンスなら「ワルツ・フォー・デビー」に「枯葉」。
私はレッド・ガーランドを請け負ったが、ここ一発とばかりに、彼不得意のスロー・バラードを全部採り上げ、おかげで偉い評論家の方からガーランドはチョコマカとスイングする速い曲が名演だろう。あんた間違っていると諭された。やっぱりオムニバス盤というのは、ビギナーを取り込むというより、そんな珍しい曲があったのか、ではそれが入った元のCDを買いましょうという気持ちを購買者に起こさせてしかるべきものだろうという気がする。
そこへゆくと、SONYから出た須永辰緒の「夜ジャズ」は立派である。私がオムニバス盤に絶対必要と考える「何?この曲、誰?この人」というのがこのCDには満載だ。ロニー・ロスの「ブルユワーズ・キャッスル」なんて、あなた、ご存知ですか。私は知らなかった。実に口惜しいのである。俺の知らないものなど駄演、駄曲の類に決まっているだろう。でも、聴いてみるとこれが龍宮城へ案内されたような名品、珍品、酒池肉林の大宴会大会であった。「Brewers Castle」の曲名もいい。「酒池肉林城」。あわててオリジナルのCDを探し出す私であった。
中にはマイルスの「マイルストーンズ」などというお馴染みの曲もあるけれど、その種類はほんの僅かで、ザ・ミラーズの「プリティ」やザ・ペドラーズの「エブ・タイド」などまぁ知らないのは私だけかもしれないが、しかし私にとっては、大変結構な見つけ物。ジャズ・ファンというのはそのようにして「新品」をみつけてゆくのが正しいのである。さて、今月ご紹介のCDはもうお気付きのようにオムニバスの一枚だ。このところ日本で人気、実力ともにほとんどナンバー・ワンの地位にのし上がったオーストラリアの品格正しい名花、ジャネット・サイデル。そのサイデル嬢のこれまで日本版で発売されていなかった6枚のCDから一挙に一枚に収束した、これぞジャネット・サイデルの龍宮城という贅沢盤。
さて、そこでひとつ困った問題が持ち上がったと思ってくれ給えジャネット・サイデルに駄曲、駄唱なし、なのである。全て平均点以上にすばらしい。そういう人なのである。そういう歌い手なのである。選曲者としてはそこで大変に苦労するわけである。
えーい、ここはもうひたすら自分の好きな歌唱の曲を選ぶしかないな。名唱だとか、歌唱力だとか、そんな立派なことを考えていたら10年かかっても完成を見ることはないな。私はそう開き直ってようやく初めて気分がさわやかになったのである。苦痛から解き放たれて、空の彼方に虹を見たのである。
全16 曲、私は柄にもなくストーリーを考え、一曲目に生きることの嬉しさや楽しさが弾けるような「ザ・ベスト・シング・フォー・ユー」を持ってきた。中間の数曲は彼女のトレイド・マークである心に太陽が溢れた何曲かを選曲した。そして、ラストの一曲「ウィンター・ムーン」。ここで彼女はマルチ楽器奏者のトム・ベイカーと共演している。彼女の恋人である。このトム・ベイカーが急死したのだ。まるでそれを暗示するかのような悲痛な一曲。ちょっと涙が出てくるのである。
(P.S.)このCDに入った、思わぬ拾い物を一曲お教えしましょう。よほどのジャネット・サイデル・ファンも多分ご存じないだろう。「黒いオルフェ」である。サイデルの歌う「黒いオルフェ」?といぶかる方が多いんじゃないだろうか。選曲者のほくそ笑む瞬間である。これがまた、とにかくいいんだ。気持ちを込めるような、はぐらかすような、一寸声を高いほうに持っていって、いつものジャネットじゃないみたいで、しかし思わず知らず抱き寄せて果敢に激しくキッスの一つも奪いたくなるような可愛らしさ。いや この一曲は絶品、絶品なのであった。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2006年05月/第28回 スウィングの王様
2006年05月/第28回 スウィングの王様

やぁ、諸君。元気かね、我輩も元気だ。せっかくだから元気の秘密を明かすことにしよう。桔梗21年根エキスという韓国産の薬草を飲んでいるのだ。
色といやぁ、黒茶色の不吉な色をしているし、味ときたら汚濁したドブ水のごとし。しかし、これが効くんだな。
放送のときなど、これをその前にグビリとやるとたちまちハイテンションになって、自分でも歯止めが利かない。
物を書くとき、いつもは第一人称は私だが薬草の効果で自分でもあっと驚く、我輩などとなるから恐れ入る。げに恐るべき桔梗21年根である。
さて、そんなテンパった状態で我輩は「コットン・クラブ」へ行ってきた。
「コットン・クラブ」へ行かずにジャズ・ファンと言えるか、都会人と言えるか。そんな気持ちもあったな。晴れて我輩は都会の人となったのである。
出し物はステイシーケントと旦那のジム・トムリンソンのおしどりコンボであった。
私はステイシーケントを10年ほど前にエジンバラのジャズ・フェスで観ている。
そのときの芸人度の高さとスタイリングの高級さにガーンと一発打ちのめされたが、
さて、10年後の彼女はいかに?
ああ、よかった。美人度のほまれ高さもスタイルの抜群度も健在であった。さらに良かったのはエジンバラの時よりトークや物腰が打ち解けていることであった。
なんとピアノの脇に紅茶セットが用意されている。歌い終わると早速ポットから真っ白のカップにお茶を注ぐ。
その注ぎ方、喫し方、カップの置き方、一切の仕草が可愛い。色気がある。我輩はひたすら、もううっとり眺めるしか方法がなかった。
よし、帰ったら今日は紅茶だ。
旦那のテナーサックスがソロを開始する。イエイなどと合いの手を入れるのである。
小柄な身体でステージ狭しと歩き回り、まるで妖精か踊る人形かと言った塩梅だ。
我輩は物の見事に乗せられていた。首は左右に動き、足はバタバタ、自分でもあっけにとられるほどのビッグスウィング。
我輩は客席、外周のカウンターにいた。真ん中の客席を一望できる。
なんと、我輩ほど大きな動きを示している人は誰もいない。
我輩は客席におけるスウィングの王様になったのである。
しかし、これを喜んでばかりいられるか。ステージのハイ・テンションと客席のローテンション。そのあまりの隔たりの大きさに愕然としたのであった。
真剣に効く、それよりも気さくに楽しむ。こういう方向に日本の聴衆は徐々に確実に持ってゆかないとまずいんじゃないか。
聴くのはCDだ。ライブはビジュアルで楽しむものだ。そういう切り替えが必要な時期が来たのである。
なるべく沢山ライブに通う。少しずつ身体を動かしてゆく。時には思い切ってイエイの一語を放ってみる。
いつか必ず慣れる。ビートに乗せて身体を揺らせる日がくる。
恥ずかしくて、照れくさくて、銅像のように動かなかった我輩が、どうだい!今はライブにおけるスウィングの王様になったのだ。
諸君の健闘を祈るや、切である。
ご紹介のCDにはその時の楽しさがいっぱい詰まっている。ハイテンションの私は楽屋に押しかけ、
サインをせがみ、首尾よく入手したのであった。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2006年04月/第27回 ジャズは乱れてこそ
2006年04月/第27回 ジャズは乱れてこそ

やあ諸君、元気かね。
しばらくご無沙汰していたが縁あって、またお目にかかることになった。よろしく頼む。
早速だが、いまだにPCM番組で重要人物であり続ける安原顯さんが、ついこの間新聞に出た。亡くなって3年になるのに新聞種になる、やっぱり凄い人だ。
朝日と毎日でご覧になった方もいるだろう。村上春樹さんの生原稿を安原さんが古書店に流したとかで、当の村上さんから、それはないよ、みたいな非難の声が上がったのだ。もともと、安原さんは村上さんと仲が良く、中央公論社で担当編集者だった。
ところが、何かのきっかけでこの二人の間に亀裂が入った。音信不通になる。よくあることだ。その間のいきさつが今月号の「文芸春秋」に村上さんの手で詳しく書かれている。
「一種の盗み」だというのである。
この件で、村上さんは安原さんから多くのことを学んだり恩恵を受けた。しかし、それとこの「盗み」は断然別物だろうと。
うーん、それは分かるが、しかし安原さんが意志的に原稿を流出させたというのはどうだろう。もう二人の仲は終わったんだ、こんなものは持っていてもしょうがない。本と一緒に処分してしまおう。・・・・この程度の意志ではなかったのか?安原さんはその時、ガンを宣言されていた。人の原稿のことなどどうでもよかったのではないか?
村上さんには迷惑がかかったが、仕方ないことだったのだ。安原さんが反論できないのが気の毒である。墓の中で歯ぎしりするしかない。そこがいちばんかわいそうである。
もう一度繰り返そう。亡くなってからもなお、今、ノーベル賞候補とも言われる人からモンクを言われた。大した人だ。
さて、今日は、異色のピアノ・ジャズをご紹介しよう。嶋津建一トリオの最新作だ。
嶋津建一はちょと前に「オール・カインズ・オブ・バラッズ」という一作を世に問うている。これが優れていた。バラード集だから心が静かになると思って聴いたのに逆に心が騒がしくなった。
ピアノ・トリオのバラッド集というのは世の中にごまんとある。しかし、この一作は何かが違う。どこかが異なる。シンプルで大人しい形をした人心攪拌器だ。心が美しく乱される。怪しく乱される。
嶋津建一は、この一作でこれまでにない「何か」を掴んだ。
「してやったり」。彼がほくそ笑む感触が伝わってくる。
そして今回の矢継ぎ早の第二弾の発売となった。
殿、ご乱心である。嶋津建一は島津の殿様にそっくりの風貌であるが、ついに乱心した。一作目で人を惑わしたが、今度は自分が乱れてしまった。ジャズは乱れてこそのジャズである。
・・・・・・今は正気のジャズが多くてつまらない。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年12月②/第26回 正しいジャズ、正しくないジャズ
2005年12月②/第26回 正しいジャズ、正しくないジャズ

この間のことである。北千住のあるライブハウスへお話を伺いに行った。
吉祥寺などという、古いんだか新しいんだかわからない、植民地みたいなところに住んでいると、千住という言葉の響きは実に懐かしい。
人情細やかな温かい土地柄という感じがする。
ライブハウスのご主人も人情に厚そうな人柄の方であった。
しかし、「あなた方がジャズをいたずらにむずかしい物にしてしまったんですよ」といきなり話を向けてきた。口許はほころんでいるが目は笑っていない。
あなた方というのはジャズ喫茶のことを言っている。
ジャズ喫茶の親父たちが、やれコルトレーンだ、モンクだ、ミンガスだとやたらジャズを高いところへ持っていった。
ジャズはむずかしくてこそジャズである、などと鼻をうごめかす店主もいた。
私などもその口で、自分の店を「ジャズ道場」などと称していばっていた時期があった。
ジャズは修行して身につけるもの、なんてね。ライブハウス?あんなものは目はあっても、耳のない人が行くところさ、なんてね。
いや、知らなかった。ライブハウスの方たちが我々を苦々しく思っていたのだ。
ひた謝りに謝って逃げるように帰ってきた。北千住は懐かしいところではなかった。怖いところだった。
そうなのである。ご主人の怒りはもっともなのである。
むずかしいジャズを俺たちは分かっているんだぞ、それを言いたくて仕方なかった。
チャーリー・パーカー、セロニアス・モンク、ビル・エヴァンス、バド・パウエルなどが正しいジャズであった。
正しいジャズを更に正しくするために正しくないジャズを槍玉に挙げた。
マンハッタン・ジャズ・クィンテットがその筆頭であった。
「あんなものは分かり易いだけのトーシロ相手のジャズ、我々ベテランの聴くものではない。
あんな犬でもわかるフレーズ、アドリブなどと口が裂けても言えるものではない。おお、恥ずかしい」。
まぁ、こんな塩梅だったのである。正しくないジャズが20年も30年も続くものか。
正しいジャズ喫茶は今、壊滅状態だ。
正しいジャズ喫茶が生き永らえていたら、本日ご紹介のヨーロピアン・ジャズ・トリオなどボロクソ言われたことだろう。
いや、正直言おう。私はヨーロピアン・ジャズ・トリオをいまだに「ニセモノ」と思っているのである。
ところがつい先日このCDを聴いて少し考えを改めた。ヨーロピアン・ジャズ・トリオを聴くからいけないのだ。
ヨーロピアン・ジャズ・トリオという概念はひとまず措いてヨーロピアン・ジャズ・トリオの演っている曲を聴いてみたらどうか。
セロニアス・モンクという概念ではなく、モンクの作った「ラウンド・ミッドナイト」を聴いてみる。
それと同じことをやってみたのである。
すると、どうだ。彼らの演る「夜のタンゴ」が俄然、滅茶苦茶いいのである。
一日に3回くらい頭の中にメロディーが浮かんでくるのである。男と女が足をからませて踊るあのタンゴ状態に気分はなってゆくのである。
「夜のタンゴ」はコンチネンタル・タンゴだ。コンチネンタルとは大陸のことで、この場合はヨーロッパ大陸、つまりヨーロッパ・タンゴ。
発祥の地であるアルゼンチン・タンゴとは別種のものだ。
コンチネンタル・タンゴの代表曲は、アルフレッド・ハウゼの作ったドイツ・タンゴの「蒼空」ということになっている。
これは人の心の奥底に潜むほんの僅かの哀情をも根底から抉り出す、とんでもない名曲だが、この「夜のタンゴ」も負けず劣らずの哀情抉り出し曲なのだ。
第一「夜のタンゴ」というタイトルが示唆的で実にいいではないか。エロチシズムはやはり暗示的でなくてはいけないと思う。
さて、さて、私は皆さんが羨ましくて仕方がない。特に若いあなたに嫉妬を覚える。
なぜならこのヨーロピアン・ジャズ・トリオの「夜のタンゴ」をなんの偏見もなしに聴くことが出来るからだ。私には偏見がへばりついている。払っても払っても落ちない。
だから折角の「夜のタンゴ」が半分くらいしかよく聴こえないのだ。
諸君、私の代わりに聴いてくれ。2倍よく聴いてくれ。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年12月①/第25回 目で聴くディスク
2005年12月①/第25回 目で聴くディスク

やあ諸君、またお会いしたね。
本日のこのCD、私は聴くたびに不思議な体験をする。
普通のCDは聴くためにある。しかしこのCDは「見る」ためにあるのだ。
見えるんだよ。スピーカーとスピーカーの間にピアノとベースとドラムが。
そりゃ見ようと思えば見えるだろう。想像力を働かせれば誰だって目の前に楽器を像として画き出すことはできるだろう。
諸君はそう考えるに違いない。
しかしこのディスクに限ってはだね、そういう「努力」なしに目前に鮮やかに三つの楽器が浮かび上がってくるのだ。そそり立つと言ってもいい。
「目で聴く」ディスクなんだよ。
風景の中にピアノとベースとドラムが点在している。一個一個が離れてはっきり見えて、それはそれは気持ちがいい。
多分そのように音が出るように意識して録音したのだろう。
そうしてそれが達成された時、制作者は嬉しくて思わず『スリー・ワイルド』という大仰なタイトルを付けてしまったに違いない。
しかし、この喜びの三つの世界、ちょっと油断するとすぐに一つの世界になってしまうのだ。
一つ一つ離れていたのがくっついてしまう。ピアノ、ベース、ドラムスがひとかたまりになって聴こえてくる。
するとどうなるか。つまり、一個一個が動かないのだ。壁一面で押し寄せる感じで全体が一つとして動く。
するとどうなるか。演奏が躍動しないから実につまらなく聴こえてしまう。
私はこれまで文中にオーディオという言葉を遣わないできた。
オーディオというとすぐ逃げ出すからね、皆さんは。それによくないイメージもある、オーディオには。
金持ちオヤジが金に飽かせて道楽三昧みたいな。
そういう面も確かにあるがしかし、演奏が躍動せずつまらないとなると諸君も少し考えてしまうだろう。
なんてたってジャズは躍動の音楽なのだから。躍動せずになんのジャズなのだ。
私のオーディオ・システムもちょっと間違えるとたちまち「動かなく」なってしまう。
たとえばケーブルを一本変えようとする。プリアンプとCDプレーヤーの間のケーブルをちょっと気分を変えて他のを使ってみるか。
そんな浮気心を起こして別のをつなぐとさあ大変。ピタッと動きをやめてしまうのだ。
シューンと煙のように上空に延びていたシンバルがいきなり下降を始める。ピアニストがやーめたとばかり寝転んでしまう。ベースもハイさようなら。
結果、ドンヨリとした演奏になって「なにこのピアノ・トリオ、サイテー。もう聴きたくない」。ジャズ・ファンとして最悪の状態になり果てるのだ。
このようにオーディオとは意外や意外、諸君が考える以上にけっこう大事なものなのだ。音楽と密接に結びついている。
金持ちオヤジのホビーにとどまらないジャズ・ファンのための生活オーディオというのがあっていい。否、これがないと損をする。
せっかくの『スリー・ワールド』が『ワン・ワールド』では泣くに泣けない。
さて、先日このディスクを音楽之友社発行の「ステレオ」誌に紹介した。何人かの人が興味を持ってCDを探した。見つからない。ひょっとして廃盤かも。
私はぜひとも皆さんに聴いて頂きたい。
そこで私はこのCDから一曲「ミスター・ボージャングルス」を抜き出して『Jazz Bar2005』に挿入した。
うむ、『Jazz Bar2005』の巧妙な宣伝だな。あなたの推理は正しい。しかし50%の正しさだ。いや70%。30%は本当にほんと聴いて頂きたいという気持ち。それを察して頂きたい。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年11月③/第24回 クリスタルな「ホクホク盤」
2005年11月③/第24回 クリスタルな「ホクホク盤」

そう言えば最近「ホクホク盤」がなくなった。
いきなりで何のことやら、お解りにならないだろう。
ジャズ喫茶の話である。これさえかけていればお客が来る。そういう盤のことを言っているのだ。
1950~70年頃のジャズ喫茶には「ホクホク盤」がごろごろしていた。
ソニー・クラークのブルーノート盤『クール・ストラッティン』。これなんかはその筆頭代表選手だった。但し、A面のみ。たまにヘソ曲がりの客がいて、
B面をリクエストしようものなら他のお客から総すかんを食ったものだ。
あと、60年代の代表で言うと、同じくブルーノートのハンク・モブレー『ディッピン』。
A面2曲目に入っている『リカード・ボサノバ』を聴きたくてジャズ喫茶に通ったのだ。
早く終われよな。面白くない1曲目を目の敵にして待っていた。
70年代に入ると、チック・コリアの『リターン・トゥ・フォーエバー』が毎日5~6回は必ずかかった。リクエストが殺到して断るのに苦労した。
5~6回といっても当時のジャズ喫茶では一日LP片面約36枚かかるから大変に頻度が高い。
そんなの何もジャズ喫茶へ行かなくたって家で聴けばいいじゃないか、とお思いだろう。
それが素人の浅読みというのだ。
1970年代はともかく、50~60年代の日本の学生やサラリーマンは、みんなして貧乏そのもの。
私なんかも1958年頃は学生だったが、大学生協でタバコを5本下さいとか言って買っていたものだ。バラ売りしていたのである。
とにかくジャズ・ファンはジャズ喫茶へ行くしかない。
先の『クール・ストラッティン』でいうと1958年頃は日本盤が出ていなくて輸入盤しか入手できなかった。
しかしこれが3000円。ラーメン150円の時代にである。初任給だってどこも1万円かそこいらだった。
そういうわけでジャズ喫茶の「ホクホク盤」が大活躍した。そうした時代だったのだ。
そうそう、もう一枚、異色の「ホクホク盤」があった。
それを紹介しよう。
異色つまりヨーロッパの盤ということで珍しかった。
当時のジャズはほとんどがアメリカ産。ジャズはブルーノート、プレステージ、リバーサイドに決まっているだろう。バカヤローってなものである。
そういうアメリカ国枠主義真唯中のジャズ界に入ってきたのがフランスのFuturaというレーベルだった。
生ちょろいフランス白人プロデューサーにジャズが作れるのかよ。まあ全体そんな雰囲気だった。
ところが『Under Paris Skies』にはフレディ・レッドが入っていた。
ブルーノートでどす黒い盤を出しているピアニストだ。どす黒いジャッキー・マクリーンにどす黒いアルトを吹かせ、
麻薬をメインテーマにした『ザ・コネクション』がそれだ。
しかしどうだ。この『パリの空の下』。フレディ・レッドをくるりとひっくり返して白ペンキでも塗ったように、真っ白でさわやか。
半信半疑だったが聴き込むうちにこれは大変な傑作だということがわかったジャズ喫茶族。
リクエストが続出したのは言うまでもない。
あっちのジャズ喫茶もホクホク顔、こっちの店主もエビス顔。
『パリの空の下』に足を向けて寝られない。
ジャズ喫茶店主たちを喜ばせたもう一つの理由。
それは音、である。
目覚ましく優れて音質が良かった。
「おたく、なにか装置変えました?」
お客によく訊かれたものである。
それほどシンバルがツキーンと延び、ベースがドーンと下に下がった。ピアノなんかもう、クリスタルそのもの。
田中康夫の「なんとなくクリスタル」はフレディ・レッドのピアノから来たと言うのは真っ赤な嘘、ではなくてリトル・ホワイト・ライズだが。
このリトル・ホワイト・ライズ。そういう曲があって、他愛のないウソという意味らしい。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年11月②/第23回 居眠りをするシンガー
2005年11月②/第23回 居眠りをするシンガー

よう、諸君、元気かね。
私は今、4キロのダンベルを100回持ち上げ、さらにその後、下手くそなトロンボーンで「ビューティフル・ラブ」をひとくさりやらかした。
2つの相反する世界を行き来するとけっこうハイテンションになる。
「ビューティフル・ラブ」といえば、若い頃、あるライヴ・ハウスでの出来事を思い出した。
その店ではボーカル・セッションみたいなことをやっていた。何人もの歌手が一曲づつ歌う。
一種のオーディションだ。
私の歌を認めて下さい。
慣れきった普通のライヴ公演にはない切実な思いがあって、このボーカル・セッション、歌手以上に聴いているほうが緊張する。
一人の歌手が「ビューティフル・ラブ」を歌った。
この歌、気持ちを入れ過ぎるとオペラの世界になってしまう。
いかにあっさいり歌うか。それがこの曲の生死を分ける。
さあ、この緊張の場面でどうするのか。
まるで脱臼したように肩の力を抜いて彼女は歌った。
私は、この時からこの曲のファンになったと言っていい。
同時に名前も知らない彼女に一目惚れした。
休憩時間、トイレに行くと彼女が出てきた。話しかけたかったが、出来なかった。
でも、俺は彼女の後のトイレに入れる。そのことがひたすら嬉しかった。
話というのはそれだけ。
今日はシーラの歌を紹介しよう。
シーラが「ビューティフル・ラブ」をやっていると話はうまいが、世の中そうはゆかない。
しかし、このシーラ、力が抜けている点では先の彼女と同等だ。
歌というのは、力が入っているけど、いかに入っていないように聴かせるかが大きなテクニックの一つになる。見えないテクニックだ。
見えるテクニックに腐心する大抵の歌手はそこが間違っているのだ。
と、エラそうに言ったが、このシーラ、とにかくそこが上手い。
デューク・エリントンの「アイ・ガット・イット・バッド」など歌いながら居眠りしているんじゃないか。
そうまで思わせる眠狂四郎の世界。この剣豪、眠りながら人を斬るからね。
あの甘苦い眠眠打破の常飲者である私なんかも眠りながら文章を書けたらなあと夢想する。
さてシーラの嬢、ロックのほうの出身の人である。
私は惚れた弱味、この人のロックのほうのCDも聴いてみた。「Something Happened」。ちっとも良くない。なんだ、これは。
ギョーン、ギョーンという汚らしいロックのギターを聴いて気持ちが悪くなった。
ロックってつくづく嫌な、下品な音楽だ。
それにシーラ嬢がちっとも居眠りしていない。ぱっちり目を開けてしっかり口を開けて歌っている。
それじゃあ、シーラじゃないんだ。
ロックの人がジャズのスタンダードを歌ったから良かったんだろう。
もう一つ良かったことがあった。
このCD、鎌倉にあるバッファロー・レコードという会社が輸入している。
私はバッファロー・レコードというネーミングが気に入った。
そのものずばりで音楽が匂ってくる。風景も見えてくる。
草深い草原に立っているような気がしてくる。
ライナーノートに、スモーキーで枯草の匂いのするシーラの歌、と書いてあった。
テキサスのオースチンで彼女は毎晩ジャズ・クラブに通っていた。
たまたま彼女の話す声を聴いたバンドのメンバーが「歌わないか」と誘ってくれたのだという。
声を聴いて、というのが凄い。
声の中に歌を見出したのだろうか。
それとも、声そのものが歌だったのだろうか。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年11月①/第22回 美しさが円を描く
2005年11月①/第22回 美しさが円を描く

昨日は久しぶりに国立の「ノー・トランクス」に行った。
ジャズ・バーである。私はジャズ・バーの店主だがたまに人の店へ行ってオダを上げないとフラストレイションがたまって仕方がない。
「よう、まだやってたなあ。つぶれて無いかと思ったよ。」
この第一声でせいせいする。気分が晴ればれする。
他人が私の店へやってきてこういう暴言を吐いたら許さない。
だが私と「ノー・トランクス」店主は師弟の関係にある。
私が37年前にジャズ喫茶「メグ」を開いた時、最初のレコード係が「ノー・トランクス」店主の村上寛だった。19歳の時だから、今56歳になる。
「当たり前じゃないですか。最近どんどん売上が上がって吉祥寺に支店を出そうと思ってますよ。」
そう言や、結構ムンムンした雰囲気である。ジャズ・バーというのはムンムンした空気が醸成できれば成功間違いなしと言っていい。
わが「メグ」を空気の歴史で言うと清涼そのものであった。
口惜しい。
ちょうどチェット・ベイカーの「サマータイム」がかかっていた。私が古今東西ジャズ名演奏のベスト10に入れている大傑作である。
「いいかぁ、ベース・ソロの後に出てくるトランペットのメロディー、よく聴いていろよ。これ、誰でも出せるものじゃない。こういうソロを最高のソロと言うんだからな。」
出た。店主自慢の梅酒の酔いが一拠に10倍くらい芳醇になった。
「まだ、そんな聴き方してるんですかぁ。ジャズっていうのはそういうものではないでしょう。メロディーっていうのはニの次、三の次。いちばん大事なのは状況でしょう。」
なにを言っているのかわからない。
こんなこと、教えたことはない。いつの間にバイキンが入ったのだろう。
これでよく日本一の名誉あるジャズ喫茶レコード係が勤まったものである。
いやはや、すっかり酔いがさめてしまった。
しかし、いったい「状況」とは何だろう。
どなたかご存知の方、教えて頂きたいものである。
それでは本日はノン・メロディー、状況オンリーの人、「ノー・トランクス」店主・村上寛にこの一枚を捧げることにしよう。
5曲目の「クエスチョン・アンド・アンサー」を聴いて頂きたい。
CDというのは最初に聴く曲が凄く大事である。良くも悪くもそれでアルバム全体の印象が決まってしまうのである。
一曲目から律義に聴いてゆくのは愚かというものである。
それでこの場合は「クエスチョン・アンド・アンサー」という新しい曲。
すでに現在日本で何十人かのジャズ・ファンがこの曲に注目し始めている。新しい最高の抜群の「スタンダード」として。
パット・メセニーの曲だ。あのジャズかフュージョンかわからないギタリスト。人気だけはやけに高い「こうもり・ミュージシャン」。
私は大嫌いだ。ギターのあの淡白なヘロヘロ・サウンドに馴染めない。ギターの音とはもっと硬質でなまめかしいものだろう。
しかしこの一曲で私はパット・メセニーという人を見直した。ギターは駄目だが、曲はいい。
ジャズの偉人と言われる人にこの手の人が多い。
デューク・エリントン、セロニアス・モンク、テナーのベニー・ゴルソンなどなど。
楽器は駄目だが、曲作りはうまい。
曲作りのうまさに惑わされて楽器の音もいいと勘違いされている人々。
パット・メセニーも、とうとうこの人たちの仲間入りが出来たのだ。大したものではないか。それもひとえに「クエスチョン・アンド・アンサー」のおかげである。
いやぁ、なんと言ったらいいのだろう。一口で言うと、美しさが円を描いて舞っているような曲。
私は、たちまちドン・フリードマンを思い出していた。1960年にあの傑作「サークル・ワルツ」を書き、演奏したピアニスト。
しかしこの「クエスチョン・アンド・アンサー」、抽象的な「サークル・ワルツ」より、もと美しさが具体的なのだ。
知性のフリードマンより、痴性のメセニーが勝ったのである。
いや、それにしてもシェリー・バーグというピアニスト、美しさで言ったら、美しいこの曲を弾くのに最もふさわしい一人だ。
ジャズに美しさは似合わない言葉だが、この場合は許そう。
美が美を弾く。その典型だからもう許す。
好きにやってくれ。
ただもうひたすら美の中に飛び込んで心中するしかないのだ。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年10月②/第21回 ジャズのミュージシャンはエロチックたれ
2005年10月②/第21回 ジャズのミュージシャンはエロチックたれ

諸君、元気か。
私は元気だ。多少、カラ元気だが、ジャズを聴いて弱っていられるか。ひからびていられるか。ジャズは私にとって水である。枯れ木にくれてやる水。
さて、マクラはこのくらいにして、今日はラテンの話をしよう。ラテン音楽。ラテンとジャズの話をしよう。ラテン音楽。ラテンとジャズの関係。
ラテンというと諸君はボサノバを思い浮かべるだろう。
あんなのはラテンではない。ラテンという庭に生えた隠花植物だ。
あんなジメジメしたラテンはあるか。あんなボソボソした冷飯みたいなラテンはあるか。あんな去勢された男のようなラテンはあるか。
ラテンというのはもっとエロチックなものだ。官能的なものだ。
男が女を見、女が男を見るような目を持ったのがラテン音楽なのよ。
サビア・クガード楽団、エドモンド・ロス楽団などがそういうエロチックな集団だった。
曲でいうと「ブラジル」「ベサメ・ムーチョ」「シボネー」「マイ・ショール」「オイエ・ネグラ」「タブー」「マラゲーニア」「マリア・エレーナ」「エル・クンバンチェロ」「カプリ島」。
などなど挙げていったらスモールなこのページなどたちまちのうちに埋まってしまう。
キューバや南米諸国で生まれたこうした何百曲という曲がアメリカに渡って、アメリカをエロチックな国にしたのだ。アーティ・ショーという有名なバンド・リーダーはラテン歌曲をレパートリーに取り入れてから奥さんを次々に替えていった。
「裸足の伯爵夫人」の大美人女優、エバ・ガードナーはその一人。全てラテン音楽のなせる技なのだ。
ボサノバでこうはゆくまい。
さて、エロチックな気分になったのはダンス・バンドのリーダーたちだけではなかった。
ジャズのミュージシャンたちにも波及したのだ。
有名なところを一つ挙げてみるとアルトのアート・ペッパーが「ベサメ・ムーチョ」を吹いた。あんなエロチックなペッパーは聴いたことがない。
ペッパーはウエスト・コースト・ジャズというジャンルにおけるほとんど唯一のエロチック奏者だった。
そこで今日はラテンに関連のあるジャズ・ミュージシャンのcdを紹介しよう。
ビクター・フェルドマン。イギリス出身ビブラフォン奏者。ピアノもよくする人だ。
しかしこの人、水気のない老人のように演奏に色気がないんだな。
そういえば彼がここで率いるウエスト・コースト・ジャズの主だったミュージシャンたち。
エロチックの要素に欠けるのだ。
現代のバークレー帰りと言われる若手の、一部のミュージシャンのように楽理が先走った。
女をかどわかすのが第一の仕事。音楽をやるのが第二の仕事と言われるミュージシャンが研究室の学者みたいになった。
今だに一部に強い支持者を持つウエスト・コースト・ジャズの弱点は楽理優先、ノー・エモーションというよりその結果生じたノン・エロチックだったのだ。
しかしこのCD、相当エロチックなのよ。
編曲だ、アンサンブルだ、オリジナル曲だ、そんなことばかりにかまけて日常を送っている彼らがラテン・ジャズをやることになった。
それだけで彼らは気分が変わった。
北の男が南の男に変身するのだ。
理性の男が痴性の男に変貌するのだ。
変化に追い打ちをかけたのは現地の打楽器奏者たちによるパーカションである。
モンゴ・サンタマリアやアルマンド・ペラーサといった人たち。
本格的なのだ。
ちなみにジャズの楽器の中で最も理性的なのはピアノ、最も痴性的なのはパーカッションとの説がある。以前、大西順子さんが言っていた。
選曲も本格的。
「ポインシアーナ」「スペインの姫君」「キューバン・ラブ・ソング」「ザ・ブリーズ・アンド・アイ」などラテン曲の王様が勢揃い。
エロチックにならざるを得ない。お聴きの通りである。
ジャズのミュージシャンはエロチックたれ。
エロチックになるにはラテンを演るに限る。
これが本日の教訓である。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年10月①/第20回 アルトひでりに恵みの雨
2005年10月①/第20回 アルトひでりに恵みの雨

さて諸君。元気かな。
今日は一つ、アルト・サックスの話をしよう。
アルト・サックスほど高い人気の楽器はない。ブラス・バンドの新入生は最初にアルトに群がるという。
この間、社会人ジャズ・バンドの発表会を観に行った。アルト・サックスの出演者がいちばん多かった。
ジャズ楽器の華がアルト・サックスなのだ。
ああ、それなのに、それなのに、だ。
ジャズ界では、現在アルト・サックスのスターがいない。
昔はいた。山ほどいた。石を投げればアルト奏者に当たった。
1950~60年代はアルト・サックスの時代と言ってもいいと思う。
チャーリー・パーカーがジャズ・アルトを立ち上げ、ジャッキー・マクリーン、キャノンボール・アダレイ、ルー・ドナルドソン、アート・ペッパー、ソニー・クリス、ソニー・スティット、並べてゆけば切りがない。
なぜアルト時代が築かれたのか。
目標がいたからである。その目標がチャーリー・パーカーだった。チャーリー・パーカーのように吹きたい。チャーリー・パーカーのように吹けたら死んでもいい。
上に挙げたアルト・サックス奏者たちはそのように願い、憧れ、サックスの練習に熱中した。
ジャズというのはそういう音楽なのだ。
ジャズ・ミュージシャンは「ああいう風に吹きたい」という単純、そして切実な願望から出発するのである。
一山当てよう、金持ちになってやろう。そんな志望者は一人もいない。
だから、ジャズは純粋な音楽なのである。
それはいいが、現在アルト奏者がいないという話。
目標がいないからである。
チャーリー・パーカーがいるではないか、と言うかもしれない。
しかし、今の若いアルト奏者にとってパーカーは余りに遠い。
夏目漱石のように書きたいと願う作家がいないのと同じである。若い作家なら村上春樹あたりを目指すだろう。
近くに神様的アルト奏者がいないのである。
それで現在のアルトひでりの現象が生まれたのだ。
アルトひでりに恵みの雨、それが本日のヒーロー青年、フランチェスコ・カフィーソである。16歳であるから少年と呼ぶべきか。ジャケットでみるとイタリアの修道院映画に出てきそうな穢れを知らぬ少年だ。
穢れを知らぬ人間に、穢れの音楽・ジャズが出来るか。
そんな風に反論してくる読者もいるだろう。今はそういう話ではないのだ。放っておいてくれ。
「ポルカ・ドッツ・アンド・ムーン・ビームス」を聴いてたまげてしまった。本当かなと我が耳を疑った。
アルトという楽器の本質を心得ていることにである。
アルトをどのように吹けばいちばん効果的にアルトの本質を引き出せるのか。
その最も大事なことを考えずに楽器を演ずる人たちの多い中で少年は傑出しているのである。
アルトは、ねっとりと吹けばいいのである。粘着性。これがアルト・サックスの最も美味しい特質である。
このせっかくの特性を嫌って冷やかに吹く人もいる。それは本道から外れた吹き方だ。
ねっとりと情熱的に吹けばアルトは99%の人を納得させられるのである。
少年の出自を考えてみた。
現代のミュージシャンらしくいろいろな人たちの影響が聴こえてくる。
フィル・ウッズが少年の大きなアイドルになっている。早い曲ではそこにソニー・クリス的色彩が加わる。
フィル・ウッズもソニー・クリスもねっとり情熱型で名を成した人たちだ。
驚いたのが「マイ・オールド・フレーム」だった。
アルト・サックスの「サブ・トーン」というのをあまり聴いたことがない。「サブ・トーン」はテナー・サックスの専売品である。
ところがこの曲でアルトのサブ・トーンをギンギンに出現させているのだ。
サブ・トーンというのは「スススス・・・・」または「ズズズズ・・・・」と聴こえるサックスの独特の奏法である。いや、この「スススス・・・・」の気持ちいいのなんの。病みつきになる。
楽器は、うまければスターになれるというものではない。うまい他に何かを持っていなければならない。
少年は持っている。それはスター性である。華である。念力である。
さらに音楽的に言うと、粘着性サウンドと同時に曲を歌わせる旋律力を持っている。
曲がこの少年の手にかかって他愛もなく服従しているのだ。
聴いてくれ。そして驚いてくれ。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年09月②/第19回 魔性の女
2005年09月②/第19回 魔性の女

さてと、毎回このページに群がる美男美女の諸君、皆さんは恋をしているか。
ジャズとオーディオに忙しくてそんなことしてる暇があるか、だって。
ああ、駄目だ、駄目だ。そんなことだから君の人生、おかしくなってしまうのだ。
恋とジャズ、どっちが大事か。考えてみるまでもなかろう。
恋があってジャズがある。これが最高である。ジャズがあって恋がない。これ、最悪でなくてなんであるか。
ここに一人、そう、歳の頃は70代の半ばくらいか。一人の男性ジャズ・ファンがいる。仮に名前を「鈴木さん」としておこう。
この鈴木さんが突如、恋に狂ったのである。狂恋である。
女性は20代の中半、中肉中背、絵に描いたような美女。鈴木さんならずとも恋愛衝動にかられて全然不思議はない。
しかし、普通、人間、70代ともなれば分別というものが働いてしまう。分別は聞こえがいいが、要するにオレなんかとても駄目だとおじけづいてしまう。間違いなく腰が引けてしまう。
しかし、鈴木さんの場合、分別を超えていた。敢然と立ち向かったのだ。
彼女の現れる場所に足を向けることから始まった。
同時に鈴木さんの服装が変わった。
鈴木さんはその長い人生を固い一方の職業に捧げてきた人である。当然、服装に遊びはない。
都内を夜な夜な徘徊し始めて三ヶ月、鈴木さんのコスチュームは完全に遊び人風のそれに変わった。
眼鏡もレイ・バーン風に変化した。
服装、眼鏡、特に眼鏡が変われば人は人が変わるのである。鈴木さんは自分を閉じ込めていた殻を破り始めた。言動が軽妙さを帯びてきた。
それまでほとんど口をついて出たことのない、冗談を連発する。
鈴木さんは自分の恋を隠さない。いや、隠せない。話したくて仕方がない。朝起きてはすぐに彼女のことを考え、昼、夜と、彼女について考えていない時以外はすべて考えている。
なにしろご隠居の身であるから暇なのである。
「いや、俺はもうじき振られるよ」
これが鈴木さんの口癖である。本当はそんなことこれっぽちも思っていない。思ってないから言える。人は恋の終わりが迫ったらそれを口に出来ないものだろう。
まわりの人々は皆、鈴木さんの恋を祝福している。
大体人はうまくいっている恋愛など心よく思わない。犬に食われて死んじまえ、である。
しかし、鈴木さんは例外。
なぜか。ある種一方的だからである。そして人は皆、鈴木さんの年齢になったら鈴木さんにあやかりたいと思っているからである。自分もそんな幸せを掴めるかな、と。
鈴木さんは、あたたかい幸せな風を人々に送っているのである。
さあ、もう皆さん、おわかりだろう。鈴木さんの恋の相手は近頃めきめき断トツ売出し中の女性歌手、MAYAさんだったのだ。
「ある恋の物語」をMAYAさんは最新作『Love Potion No.9』で歌っている。
いや、はや、これは数ある「ある恋の物語」の中でなんという絶品なのだ。
煮て焼いて料理して食べてしまいたいくらいだ。
こんな狂恋の表現をなぜ20代の女性に出来るのだろう。
本当は彼女は60歳なのではなかろうか。何百回も恋を重ね、その凝縮されたエッセンスが若い娘の型を借りて出てきたに違いない。
これでは鈴木さんならずとも、クモの巣の蝶状態になるのは無理はない。
まことにもって魔性の女、というしかない。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年09月①/第18回 ライブの楽しみ方を教えよう
2005年09月①/第18回 ライブの楽しみ方を教えよう

さて諸君、諸君はジャズのライブに行ったことがあるか。
行かれた方はわかるが、ライブは意外とむずかしい。
むずかしいのは演奏ではない。身の処し方である。演奏は動いている。スイングしている。じっとしているわけにはいかない。沈思黙考の士を決め込むわけにはいかない。
沈思黙考の士、彫像の王者で言えばマニアックなジャズ・ファンに勝るものはない。
ブルーノートやプレステージ、さらにはリバーサイドを語らせたら一時間でも二時間でも喋っている。
ブルーノートの『クール・ストラッライン』は1588番なんて、レコード全号まで知っている。
でもライブの乗りはからっきし駄目。0点。見るも無残に身動き不能。
さて、では、どうするか。
レコード鑑賞のジャズ喫茶ではとりあえずじっとしていれば格好がついた。
でもこれからはライブの時代。彼女に模範を示さなくてはいけない。
隣では彼女がリズムに合わせて手拍子など始めたら、キミの人生真っ暗だ。
さあ、どうする。
残酷な話のようだが、慣れるしかない。
何回も通うのだ。そして周囲を見渡して、見よう見まね、「乗り」の練習をする。
女性シンガーがバックの4ビートに合わせて指をパチン、パチンと打ち鳴らしたりする。格好よい。
パチン、パチンに合わせてキミも静かに音を出してみる。
そう、それがジャズの基本ビートだ。
ドラムのハイ・ハット・シンバルを聴くのもいい。「ンジャ、ンジャ」。
その「ジャ」の二拍、四拍のところでシンガーはパチン、パチンをやっているのだ。
手拍子もその二拍、四拍。
この手拍子がブルーノート派、プレステージ派にはむずかしい。そして恥ずかしい。死ぬほど恥ずかしい。
私も最初「ジャズ、やめたい」と思うほどつらかった。
しかしやっているうちに慣れてくる。
だんだん快感に変わってくる。
バンドのリズムの一部を自分が担っているという風に感じたらしめたものだ。
もう、こっちのものだ。
キミはライブの王者だ。
さて、ライブは当然のことながらミュージシャンと聴衆の二組で成立している。
ミュージシャンというのは、一般的に我々聴衆が考える以上に気が弱いものである。
聴衆を意識している。
我々もミュージシャンを意識している。
両方で意識しちゃったら「すくみ合い」になって演奏会はしぼんでしまう。
どちらかが音頭をとるしかない。
先日ジャズ喫茶「メグ」で行われたスライデング・ハマーズのライブは、誠に殊勝なことに聴衆側が音頭をとった。
姉妹が店内に入ってくる。
その瞬間である。拍手と声援が涌いたのだ。どよめきが起こった。
これが姉妹に通じないはずがない。
初めて日本に来て、風変わりな店で演奏する。心中に不安がないわけはない。
思いがけず、温かい拍手で迎えられた。
これがプレイに貢献しないわけはない。
演奏とは何か。心の中の動きである。温かい時もあれば、冷たい時もある。心中の動きが指先に伝わって楽器が鳴ったり、鳴らなかったりする。
良い演奏になったり、ならなかったりするのだ。
その夜のスライデング・ハマーズ。
いやはや、もう最高でした。
アンコールを二曲やって、最后の一音が終わると姉妹は抱き合い、天井めがけて跳び上がったのだ。それでなくても190センチ近くもある二人、危うく当店の天井が損傷するところであった。
さて本日ご紹介の姉妹盤、スウエーデンで吹き込まれた最新盤である。
この中からの曲がライブで多数演奏された。
スピーカーで耳慣れた曲を実際にライブ会場で聴く。これが格別にいい塩梅である。想像が現実のものとなる瞬間である。
「ジ・オールド・カントリー」がどうなるか。私はカタズを飲んで見守った。
そうか、お姉さんのミミ・ハマーズはこんな表情で歌っていたのか。
すっかり合点がいって私は幸せだった。
「歌うトロンボーン奏者」で言うと、古くはジャック・ティーガーデンという人がいる。
妹さんのカリン・ハマーズが私淑するフランク・ロソリーノという人がいる。
しかし、今までのところ女性で吹き、歌いする人を私は知らない。
ミミ・ハマーズをもって史上初の歌う女性トロンボーン奏者としていいのではないか。
実に歌手ずれしていない歌い方である。舌足らずの唱法が可愛らしい。あどけない。
思わずかけ寄って肩を、と言いたいところだがチビの私では届かない。
口惜しいのである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年08月②/第17回 聴く人を格好よくするジャズ ~ルー・ブラックバーン『ニュー・フロンティア』~
2005年08月②/第17回 聴く人を格好よくするジャズ ~ルー・ブラックバーン『ニュー・フロンティア』~

さて諸君、今回もジャズの話をしよう。
このページは公共の場である。
眉間に皴を寄せたジャズのマニアックが巣食う暗い穴倉ではない。
であるから、私は主としてジャズとはいったいどういう音楽であるのかを常に主題にして書いてゆきたいと願っている。
ジャズファン以外の美男美女がこのページを読んで、ジャズって面白そうだな、ヒマだから一つ聴いてみようかな、と思ってくれたら、これくらい望外の喜びはない。
さて、それでは、ジャズとは一体どんな音楽なのだろう。
これは難しい。
「スイングジャーナル」というジャズの専門誌がある。社長が亡くなる前、あるベテラン歌手の方と話をした。
「何十年もジャズを聴いてきたが、結局ジャズって何だか分からなかったな。」
結局、ジャズは分からないということが分かったのである。
しかし、一つだけ、こんなのはどうだろう。
ジャズは格好いい音楽だ。
言えなくはない。
全面的に格好いい音楽とは言いにくい。
フリー・ジャズなどという訳のわからないのもある。ロックあたりから影響を受けたロックまがいの非純粋ジャズは影響という要素ゆえに格好よくない。
おお、一つあった。立派にあった。
二管編成ジャズ。
これである。
トランペットとテナー・サックス、トランペットとアルト・サックス、あるいはテナー・サックスとトロンボーン。
つまり、フロントと言われる管楽器が二本にピアノ、ベース、ドラムスのいわゆるリズム・セクションが付いたものを二管ジャズと言う。
これが1950~60年代に流通、発展してジャズが黄金時代を迎えたのだ。
黄金時代の立役者は二管ジャズだったのである。
現在、大爆発中の東芝1500円ブルーノート・シリーズで売り上げ1位・2位を占める、ソニー・クラークの『クール・ストラッティン』、キャノンボール・アダレイ、マイルス・デイビスの『サムシン・エルス』などはまさにこの二管編成ジャズ。
サボイ・レーベルのベニー・ゴルゾン、カーティス・フラー『ブルース・エット』なんていうのも落とせない。ベニー・ゴルゾンといえばトランペットのリー・モーガンと組んだ『モーニン』もその例に漏れず。
名盤の影に二管編成あり、なのだ。
さて、では、二管ジャズのどこが格好いいのだろう。『モーニン』を例に挙げよう。
この曲のテーマをベニー・ゴルゾン、リー・モーガンが一人で吹いたとする。
想像するだけで薄ら寒くなる。なんとまあ、しょぼい曲なのよ。
ところが、二人揃って吹くと、おお、どうだろう、これは。実に堂々として一人が半人にしか聴こえないのに二人揃うと5人分くらいに聴こえてくるのだ。
つまりハーモニーが分厚くなってテーマ・メロディーが別人のように重層的に躍動するわけだ。
これ、作曲者がそうなるように作曲するからである。
二管で映えるメロディーの流れを考案するからである。
であるから、ちょっと難しくなるが、この二管編成とオリジナル曲とは切っても切れない関係にあるのである。
二管と旋律豊かなオリジナル曲のおかげでジャズは、50~60年代に最高峰に昇りつめた。そのことは先程お話した通り。
さて、本日は異色の二管ジャズをご紹介しよう。
なぜ異色なのか。トランペットとトロンボーンの二管で成り立っているからである。
あまり例がない。
大抵の二管は木管(サックス)と金管(トランペットやトロンボーン)の組み合わせである種の優しさと広がりを表現した。
ところが、ここは金管二本。当然音が鋭くなる。
しかし、ちゃんと理由があるのである。
聴けばわかる。
二曲目のタイトル曲『ニュー・フロンティア』。
ここはもうトランペットとトロンボーンのサウンドしかない。これしか考えられないというほどの鋭く格好いいアンサンブル・サウンドなのだ。
サックスではたちまち甘さが増してしまう。
甘さは一切お呼びでない。
鋭さと格好よさが欲しい。
では相手はトランペットしかないではないか。
リーダーのトロンボーン奏者、ルー・ブラック・バーンはそのように考え、異色の名演が誕生したのだ。聴いているあなたが格好よく見えるジャズ。それがこれである。
〔P.S.〕
現在、二管ジャズは多く見られない。
なぜか。
当時のミュージシャンは二管を格好いい音楽ととらえ、夢中で演奏した。
今のミュージシャンは形式の一つとして演奏しているに過ぎない。
それよりもっと大きい二管衰退の理由。
美しいもの、そして格好いいものはしょせん滅びるのだ。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年08月①/第16回 曲に合わせてダバダバダー
2005年08月①/第16回 曲に合わせてダバダバダー

アマチュア楽器練習者の成果発表会。私はこれを見に行くのが好きである。
途中で音が出なくなって立往生する。曲を間違えて泣きべそをかく。
こういう、見物人にとって最も幸せなシチュエーションを期待してやまないのだがしかし、べらぼーめ、誰一人として不幸な練習生は出やしない。
期待に応える者がいない。
皆、そつなくこなして拍手なんぞを山ほどもらって満面に笑みを浮かべて引き下がってゆく。
成果発表会は、根本的な何かを間違えているぞ。見物人を愚弄しておるぞ。
まあ、それほど教えるほうも教わるほうも技術が高くなったということだろう。
面白くない。
さらに面白くないのは譜面である。譜面に書かれたアドリブである。
練習生は譜面に書かれたアドリブを見ながら吹くのである。
先生がちゃんと書き記して、練習生は日夜腕を磨いて発表会に臨むのだ。
これが、最悪だ。
アドリブに聴こえないである。
アドリブというのは厳密に言えば即興的、即席的なものである。インスタント・ミュージック。
練習に練習を重ねた音符やフレーズなど、その場でポッと出たアドリブに聴こえるはずがない。
と、まあ、正論を吐いてみたが、何だか急にむなしくなってきた。正論を吐くとはむなしくなることである。
むなしくならないために、いつも私は独断論を吐いているのである。
それはさておき、次の話。
池袋の「マイルス・カフェ」に行ってきた。
店主のマイルスはトランペッターでトンボ眼鏡のサングラスをかけ、しゃがれ声で話し、しゃがれ音でトランペットを吹く。
トランペットを吹く時はマイルス・デイビスになりきっているのである。
そのマイルスが自分の店で「ジャズ講座」を始めたと思い給え。
私はその場に居合わせたのだが、チャーリー・パーカーの「ナウ・ザ・タイム」がかかった。
するとマイルスは聴講生に命じたのである。
「さあ諸君、歌って、歌って。曲に合わせてダバダバダーと歌って、歌って」
アドリブまでそっくりパーカーが吹くように皆して歌ってゆく。
「もっと大きな声で!」
美味しいアドリブのところは声が大きくなる。やっぱりメロディアスなフレーズは皆よくわかって、嬉しくて、大きな声を出すんだなあ。
曲を、そして、アドリブを、自ら歌って、何度も歌って身体で憶えさせる。
譜面は一切なし。
これがマイルスのジャズ教育法である。
私はジャズ練習法、ジャズ楽器練習法としてこれが見事な善だと思う。
実は私は、今、その善の道を真っ直ぐにひた走っている男なのだ。
本日ご紹介のカイ・ウィンディング。10曲「There will never be another you」。これである。
このアドリブ・パートを私はマイルス学校開設以前にマイルスの方法で練習していたのである。
誠に寛ろいだ感じのテンポが絶妙な幸せ感をリスナーにもたらす最高の演奏が終ると待っていましたの呼吸で出てくるカイ・ウィンディングの最初のソロ。
私はこれにしびれたのである。
これを歌わずにいられるのか。これを口ずさまずして死んでゆけるのか。
ソロの部分を何度も何度も聴く。そして歌ってみる。リモコンという機械はアドリブを憶えるために存在するのだ。
私はここでリモコン存在における深い真理を悟ったのである。
そしてさらに歌えるアドリブを演奏するミュージシャンが、ジャズという世界の最高のミュージシャンという事実に気付いたのである。
最後に実利的な情報をお教えしよう。
このCDは1958年の吹き込みながら、結局商品化されず、いわゆるお蔵入りしていたものなのだ。
掘り出して光を当てたのはアメリカのLonehill Jazz レーベルである。
このレーベル、結構ちゃっかりとベツレヘム盤などをジャケットを変えて再発しちゃったりして「危ない」レーベルなのだが、このCD発売に関して私はまったく興奮した。随喜の涙を流した。これまでジャズの文献の中で、カイ・ウィンディング、カール・フォンタナ、ウエイン・アンドレ、ディック・リーブの4人から成る4トロンボーン・グループの存在は知られていなかったのだ。
発掘ありがとう!
一声、大きく叫んで今回は終りとしよう。
おっと、最後に身をすくめながらもう一言。私の新刊が書店であなたを待っています。
『吉祥寺JAZZ CAFEマスターがおすすめするはじめてのJAZZ』(河出書房新社)
買って下さい。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年07月③/第15回 現代版ジャズボーカルの名曲を歌う ジャネット・サイデル
2005年07月③/第15回 現代版ジャズボーカルの名曲を歌う ジャネット・サイデル

さて諸君、諸君は「敵性音楽」という言葉を聞いたことがあるか。
ジャズである。ジャズ。
もちろん今時、そんなことを言う人はいない。
第二次世界大戦の頃、である。
ジャズは日本ではそんなふうに呼ばれていたのである。
であるから、私の先輩にあたる当時のジャズ・ファンは人に聞かれないよう、押し入れの中で布団をかぶって聴いていた。
でもついつい音が漏れてしまって近所の人が憲兵隊に密告したというようなことがあったらしい。当時は隣組みという名の密告制度が発達していた。
ついついボリュームを上げてしまうのが面白い。ジャズ・ファンというのは昔も今もついついの性癖の人種なのである。災を呼ぶ人種。
さて、時と所が変わって今度はジャズ喫茶。
さすがに密告というような暗い話はない。
しかし、私が店に出ていた頃、よく他のジャズ喫茶の悪口話が漏れてきた。
あそこの店はペギー・リーやダイナ・ショアをかけていたよ。ジャズ喫茶の風上にも置けないな。軟弱ジャズ喫茶もこれに極まれリ、だな。
1950年代、ジャズ喫茶全盛時代、白人ボーカルはまさに敵性音楽そのものだったのである。
威勢のいい、ハード・バップと呼ばれる、二管編成のジャズが硬派ジャズ喫茶の旗印だった。
私も硬派ジャズに疲れ、白人美人ボーカルが聴きたくなると店のいい装置でではなく自宅の音のよくないスピーカーで我慢しいしい聴いたものだ。さすがに布団はかぶらなかったが。
さて、現在。いい時代になったものである。ジャズという音楽にも民主化の波が押し寄せたのだ。
私のジャズ喫茶で、現代のペギー・リー、そしてドリス・デイとの評判が高いジャネット・サイデルをかけて非難する人はいない。後ろ指をさされることはない。
たまに苦笑する人はいるが、そこに悪意はない。
さて、今回のジャネット・サイデル盤、「スパニッシュ・ハーレム」を第一推薦曲として強力に押すことにした。
いきなり何だが、ジャネット・サイデルはこの曲を自分のレパートリーに入れたことでペギー・リーやドリス・デイに勝利したのである。
何故ならペギー・リーやドリス・デイの時代にはこの曲は存在せず、彼女たちは歌いたくても歌えなかったからである。
徒らに昔のアーティストたちを神棚に上げて奉り、現代の歌い手を認めたがらない人がたまにいるが、よくない傾向だ。
曲という観点からボーカルを評価したいのである。
それほど「スパニッシュ・ハーレム」は一聴、「ああ、いいなあ!!!」と思わせる曲なのである。
すぐれたボーカル曲とはどういう曲か。
ただひたすら人心に訴える曲である。
即ち、「ああ、いいなあ!!」。 これである。
ジャネット・サイデル自身によって書かれたコメントによると、彼女はこの曲を主として仕事場にしている有名なウエントワース・ホテルで歌っているらしい。
うーむ、私はすぐさま、シドニーのウエントワース・ホテルに直行したくなってきたぞ。
【P.S.1】 ジャネット・サイデル情報。
この輸入盤CDが発売された後、「マナクーラの月」がオーストラリアのラ・ブラーバ盤を経由し、日本のミューザックから出版された。
これが「スパニッシュ・ハーレム」を数倍凌ぐとんでもない出来映えなのだ。
彼女の天性の資質である地熱のような温かさが「あなたなしでは」「トワイライト・タイム」「リンガー・アホワイル」「ディープ・パープル」といった佳曲を通してあなたの心にじんわり浸透する幸せをあなたは一体どう享受すればいいのだ。
【P.S.2】
かなわぬことながら、「スパニッシュ・ハーレム」をペギー・リーとドリス・デイの歌で聴いてみたかった。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年07月②/第14回 チェット・ベイカーの「サマータイム」
2005年07月②/第14回 チェット・ベイカーの「サマータイム」
f
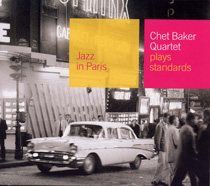
えー、諸君、元気かね。
いま、たまたま、手元にあるマイルス・デイビスの『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』、このライナーノートを読んでいたんだよ。
書いているのはジョージ・アバキャンという有名なプロデューサーだ。
「つまりマイルスは受け手の感情を利用したような、どこか不安を感じさせるお決まりのサウンドを作り出そうとしているのではなく、むしろ彼がインプロビゼイションによって起こってくる内なる緊張に対する応えを求めようとしているのである。表向きはリラックスしたようにも思えるこの矛盾をはらんだ緊張は、もともとレスター・ヤングによって高められた形式の賜物で、マイルスはトランペットでそれを新たに極めようとしている」
てなものなのよ。まあ私もあざとい人間だから、わざと七面倒くさいところを引用した。
それにしてもだよ。これはないだろう。
私はジャズを聴き始めて約50年、もうこの頃ではジャズの臓物部分の匂いまでも嗅げるようになった。
するとこんな文章など「しゃらくせー」と一声吠えてすぐに放り出せるのである。
しかし50年前にはそうではなかった。インプロビゼイションなどというお言葉が出てくるともうそれだけでハハァーと平伏していたのだ。
そして、レコードを聴いて一生懸命「内なる緊張に対する反応」を聴き取ろうとしたのである。
聞くも涙、語るも涙の物語とはこういうのを言う。
さて、何が言いたいか。
ジャズはある種ハイグレードの音楽だから、この種の「お勉強」をしても悪くない。「お勉強聴き」をして一向に構わない。どうぞおやりなさい。
でも、人に強制してはいけないよ。
これがジャズの正しい聴き方だ、などホザくなよ。
そしたら私、怒るよ。本気で。
まあ、今だから怒れるけど、繰返すが、約50年もの間、「正しい聴き方」の中で右往左往、アップアップしてきたのが私のジャズ人生なのだから、今こそ、そこから脱け出て思う存分私の聴き方で楽しもうと思うわけである。
苦しみを思い出すから、もう私はマイルスを聴かない。
代わりにチェット・ベイカーを聴く。
チェット・ベイカーは、いわば、B級品である。マイルスはジャズ史上超A級品である。
私はB級だからこそ、チェット・ベイカーを聴く。世の中になんとA級だけでジャズを聴いた気になってジャズから離れてゆく人の多いことよ。B級、C級の中にこそ面白いものが一杯あるのに。
チェット・ベイカーの「サマー・タイム」。数ある「サマータイム」の中で私はこのくらい愛する「サマータイム」はない。
トランペットのイントロが出てきただけで既に酔ってしまう。このイントロはメロディックという意味で「もう一つのサマータイム」だ。
この短いイントロの中にチェット・ベイカーの考える「サマータイム」がすっかり入っている。これだけで終わってもいいくらいなものである。
イントロが終わると当然ジョージ・ガーシュウィンの「サマータイム」が出てくるが、全然ワン・フレーズも崩してないのに作曲家の作りを感じさせない。言ってみれば、チェット・ベイカーの瞬間アドリブのようにも聞こえてくる。
本当のアドリブに入ってもアドリブがアドリブ、アドリブしていない。曲のように聞こえてくる。そこが凄いところである。
大抵のジャズ演奏というのはスタンダードの作曲家が作曲した主題の部分とプレイヤーが行うアドリブ部分とは物の見事にきれいに分かれている。それが悪いとは言わないが、普通はハイ、ここからがアドリブですよ、と提示されているわけである。
ところがチェットの「サマータイム」はそこが判然としない。
いや、この際、アドリブなどという言葉を遣うのはよそう。いわんやインプロビゼイションなどとんでもない。くそくらえ、だ。
全編、チェット・ベイカーの麗しき節、である。
ジャズに関するすべての技術用語などどうでもよくなってしまう、心からのチェット・ベイカーの麗しき旋律、を聴いて下さい。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年07月①/第13回 飽食の時代に聴く“無欲恬淡"のジャズ
2005年07月①/第13回 飽食の時代に聴く“無欲恬淡"のジャズ

ミュージシャンというのはまことに羨ましい。
一体彼らは一晩に何回拍手をもらうのだろう。
私は、自分の店がライブハウスだから分かるのだが、まず一晩30回は下るまい。
こんな人間はとてもいない。
我々凡人がひな壇で拍手の恩恵にあずかるのはせいぜい生涯に何回かというところだろう。
結婚式とかそういう時。
好きなことをして、晴れがましい毎日を送れるという意味でミュージシャンほど幸せな人種はいないはずだ。
しかし幸、不幸が交錯するのもまたミュージシャンである。
実入りである、実入り。幸せな拍手と引き換えに彼らの実入りの何と僅かなことよ。
私の店の最悪の例でいうとミュージシャン4人にお客が2人、結局一人一晩千円にしかならない日があった。駐車場代も出ない。
一部の超有名人を除いて現在日本のライブハウスで生活するジャズ・ミュージシャンの収入はこんな悲惨な状況だ。 新進ジャズ・ピアニスト、ハクエイ・キムもその例に漏れない。
率直なところを訊いてみた。
「そうですね、一日平均でいうと4,000円ぐらいのところではないでしょうか。それでは生活できないから印刷工場でアルバイトしたり、ホスト・クラブのハウス・ピアニストをやったり。」
そのクラブへ給料をもらいに行った。するといきなり閉店していた。前月分がそっくりパーになった。
しかし、ハクエイ青年はめげないのである。意気ますます盛んなりである。
ようし、やってやるぞ。がんばって日本一のジャズ・ピアニストになってやるぞ。
そういう強い気持ちを起こさせたまさに「事件」と言うにふさわしい出来事がつい最近あったのだ。薄幸な青年に降ってわいたような事件。
それが本日ご紹介のCDの発売である。
DIWから夢にまで見た初リーダー・アルバムがリリースされたのだ。30歳。
オーストラリアへ英語の勉強に行った。ロックのバンドでピアノを弾いていた。現地のライブハウスで観たジャズ・ピアノに惹かれた。
ジャズ・ピアニストになりたい。オーストラリアの有名ピアニスト、マイク・ノックの門を叩いた。
「弾いてごらん。」
一曲終わって振り向くとマイク・ノックがうずくまっていた。
「勘弁してくれ。それがジャズかい。出直していらっしゃい。」
一年間、がむしゃらにジャズを聴いた。バド・パウエル、ビル・エバンス、キース・ジャレット。
晴れてマイク・ノックの門下生になることが出来た。
3年の年月が流れる。
「テープをDIWに送ってみたら。」 ノック自ら推薦してくれた。
ハクエイ青年にとってレコード会社といえばDIWしかなかった。
いやまあ、何と言う潔い音楽なのだ。
武士は食わねど高楊子といった風情の音楽とはこのことだ。
貧乏生活とはこれで、さらばだ。CDで一山当ててやろうなどというさもしい気持ちはまるで見られない。
売れても売れなくてもいい。オレの音楽をわかるヤツにだけわかってもらえばいい。これがオレのやりたかった音楽だ。
さあ、聴いてくれ。駄目だったら放り投げてくれ。
これは、1950年代のハングリー時代のジャズ、と言っていい。現代の飽食時代、美食時代のジャズとは訳が違う。
飽食時代の甘いジャズに慣れた耳にはいささかごっついピアノの弾き方だ。ビル・エバンスが学者のようなピアノを弾くように、
ハクエイ青年は兵士のようにピアノを弾く。ハクエイ青年の撃ち出す鉄砲玉がもろ頬にぶち当たってくる。即死する人がいるかもしれない。
私も最初はたじろいだ。しかし慣れたいま、鉄砲玉の何と鮮烈に響くことよ。たまにはこういう致死量のジャズを聴け。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年06月②/第12回 女の戦いーピアノ・トリオ ブームー
2005年06月②/第12回 女の戦いーピアノ・トリオ ブームー

女の執念は凄い。
あの人に負けてなるものか。
男だって執念はある。しかし、しばらくすると他のことを考え、まあいいかで酒でも飲んで寝てしまう。
こういう複雑と単純の構造の上に女と男は出来ている。
女の複雑さが最も端的に現れたのが現代のピアノ・トリオ・シーンであろう。
以前、このページで安井さち子を紹介した。女の一念が彼女をしてピアノ・トリオ界の大きな一角にのし上げたという話。
これで、そろそろ執念は終わりかと思いきや、いやはや、どこまで続くぬかるみぞ、なのだ。
その上、執念の火付け役、大西順子まで戦線に復帰したというのだから、混迷の度合はますます広がり、女の戦い、いつ果てるともない状況に突入した。
いやしかし、これでなくてはジャズ界面白くない。戦いのないところに勝利なし。
さらに近頃、ライブハウスに見慣れない顔が出没するという噂がしきりなのだ。だみ声の酔っ払い親父の横で目つきの鋭い男がステージを凝視している。
レコード会社のプロデューサーである。どこぞにいいピアノ・トリオの玉は隠れていないか。熱心なレコード会社は未来の女性スターを求めて夜回りを欠かさない。
まさに今、女性ピアノ・トリオはブームの真っ只中にある。
そんなさなか、また一人、上等な玉が現れた。
この人、安井さち子の好敵手と言っていい。安井さち子もうかうかしていられない。いつ寝首をかかれるかわからない。
とにかく、作曲能力が大変なものなのだ。安井も作曲が得意である。まずこの点が真っ二つにぶつかっているから面白い。
スタンダード・ソング同様、いや、それ以上にオリジナル曲が美しく耳に響いてくるというのは、それだけでジャズ・ミュージシャンとして得難い素質である。楽想が豊か、ということだ。
今、我々ジャズ・ファンが求めているのは聴き応えのあるオリジナル曲である。ハッと一瞬、胸が高鳴るオリジナルである。決してピアノ奏法の細かい技術ではない。それはバークレー校の学内でやってくれ。
この二人が、オリジナル作りの俊才として目下のところ最前線にいるのだ。
「ザ・サンドストーム」が安井のこれまでのベスト曲なら、「タンゴ・ソレラッド」が三輪洋子の最高曲と私は思う。
いつまでも心に残るメロディーである。二、三度聴かなければわからないというジャズのオリジナル曲特有のものではない。
初めて聴いてわかり、すぐに喜びを感じ、この曲を自分の幸せの源にしようと考える曲だ。
聴き易い曲は飽き易いと言われるが、それは演奏が浅いからに他ならない。
二人の演奏は濃い。ディープである。
安井の外向的演奏、三輪の内向的演奏と分ければ二つに分けられる。遠心力のあるプレイと求心力のあるプレイと言ってもいい。
弾けてゆく演奏と内にこもる演奏。共に二つとも美しい。
私は昼に「ザ・サンドストーム」を聴き、夜に「タンゴ・ソレダッド」を聴く。私にかしずく昼の女と夜の女、である。
こんな美曲が現れるなら「女の戦争」どんどんやっていただきたい。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年06月①/第11回 “ラテンジャズ"の醍醐味
2005年06月①/第11回 “ラテンジャズ"の醍醐味

さて、諸君。
いきなり何だが、今、ジャズの世界に供給過剰の現象っていうのがあるんだがご存知だろうか。
ヨーロッパ風味なのよ。ヨーロピアン・フレイバー。ヨーロピアン・ジャズ・トリオなんていうグループの名前を聞いたことがあるだろう。いつもコンサートは満杯。
これ一種の流行現象なのだ。
えっ、ジャズって個性の音楽だから、ミュージシャン一人一人が独立していて皆一緒になって同じような音楽をやる流行なんてないんだろう?
こういぶかしむあなたの気持ちはよくわかる。
しかし、ジャズといえども大昔から流行り廃りがあったんだな。
何故かというとレコード会社が市場を操作するからだ。
つまり、その時々で売れるものを重点的に各社出して行く。60年代は各社こぞってボサノバ物を発売した。70年代のフリー・ジャズ全盛時代はつらかったぜ。
さて、そこで今はヨーロッパのピアノ・トリオ物。
これ、悪くはないんだが少し知的に過ぎる。フリー・ジャズもそうだけど、ジャズが知性に傾いたらろくなことがない。
何しろヨーロッパは、日本が明治大正時代の頃、盛んに知識情報を輸入した国々だ。頭のいい人間の住まう国だが、ジャズやるくらいの人間は少々バカのほうがもっけの幸いなのだ。
つまり、ジャズは痴性の音楽。
痴性とくればラテンである。欧州ではなく、南米、トロピカルである。
これを日本で流行らせなくてはいけない。知性と痴性のバランスをとらなくてはいけない。
さて、どうしたものか。 憂いていても始まらない。行動を起こすのみ。
私はウィリー・ナガサキさんを訪問した。ラテンのパーカッション奏者の方である。ミュージック・バードでディスクジョッキーをやっておられる方である。
おお、この方こそまさに痴性の方であった。見るからに全身に痴性が横溢している。
男世帯にうじが湧く、ではないが、台所には3日前の皿が散乱している。床には雑誌や単行本が乱雑に積まれている。よく見ると「右翼の歴史」「流れ者の果て」「九州大陸郷土史」といった一筋縄ではゆかない書物が顔をのぞかせた。
今時珍しい人相の方である。九州男子の顔である。セピア色の写真で見る明治時代の志士はすべてこのような凛々しい顔をしている。
平成の志士の話はとどまるところを知らない。とめどなく流れてゆく。
時々話がわからなくなる。そこがいい。
ウィリー・ナガサキさんはしばらく前にCDを吹き込んだ。
私はいまウィリーさんを思い出しながらCDを聴いている。
本日はそのCDをご紹介しよう。
このCDの一番いいところ。それはどれを聴いてもああこの曲はこういう曲なんだと瞬時にわかるところである。
そんな当たり前のことが特にヨーロピアン・ジャズには少ない。
ついでに言うと、ジャズという音楽は本来メロディーにケチンボ。半開きにしかしない。
対してラテンは満開、全開。さあ思いきって聴いてくれ、と。
ウィリーさんはもっと開く。痴性を丸出しにする。そのメロディーが実に麗しい。美味しい。噛んで行くとさらに美味しさが膨らんでゆく、そんな旋律。パーカッションの人なのに旋律美をとても大事にする人。
美旋律。そして、それと対照的な大胆不敵なパーカッションが聴く人の胸を大きく揺さぶる。
うーん、これなんだよなぁ。いま最もジャズに欠けている要素は。
私は歯噛みしながら何度もウィリーさんのCDに耳を傾ける。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年05月②/第10回 “演奏は体を表す"ジャズピアニスト、安井さち子
2005年05月②/第10回 “演奏は体を表す"ジャズピアニスト、安井さち子

さあて、皆さんお気付きだろうか。
一つの社会現象といってもいい出来事なんだが、日本の女性ジャズ・ピアニストたち。
この人たちが今、群をなしてのしてきているのだ。
その点、男はからきし元気がない。
女の元気の素はなにか。
闘争心である。
目標に向かって突き進む激しい心模様である。ようし、あの人に負けないようにがんばろう。
最初の大きな目標となったのは大西順子であった。
彼女の最初のCD「WOW」は5万とも10万とも言われる数字の売れ行きだったという。
さあ彼女に続けとばかりに現れたのが、アキコ・グレース、山中千尋、斉藤真理子、白崎彩子、早間美紀、といった面々であった。いずれも好評に次ぐ好評。
そしてここに真打登場、遅れてきた青年、いや遅れてきた美女が安井さち子なのだ。
音楽より前に彼女の性格をご紹介しよう。
安井さち子は私の店「メグ」に定期出演している。私はその行動をつぶさに毎回観察している。であるから結構詳しくご報告できるのだ。
汚れを知らぬ天使が地上に降り立ったようだ。
あけっぴろげである。と言っても少しも下品にはならない。大体からしてこの顔立ちでは何をやらかしても下品になりっこない。得な女人である。この顔かたちでツンとすまされたら世の中、大変に迷惑する。そういう顔面だから特に本人が気を遣っているというわけではない。
天然の天真爛漫なのである。
彼女の天然ぶりは司会にも表われる。早口で、時々言語がもつれたりもするが、聞いているうちにこの人本当にいい人なんだなあとわかってくる。
そういう性格がそっくり音楽に表われているのだ。
無邪気な音楽。楽しさ満開の音楽。高ぶらない平民的な音楽。
よし、はっきり言おう。安井さち子の音楽は先に挙げたピアニストたちの誰よりもわかり易い。そうした比較で言えば、先輩たちはむしろわかり難い。
安井さち子はわかり易さという武器をひっさげて、先輩たちに戦いをいどんだのだ。
さらに音楽以外の方法でも彼女は先達に挑戦した。
先輩たちがやらなかったことをやったのだ。
即ちレコード店訪問である。三軒や五軒ではない。
都内は勿論、全店訪問した。地方にも足を延ばす。
レコード店マップを片手に一日10軒も15軒も回る。レコード店全国行脚である。
彼女は大学を卒業後、有線の会社に職を求めた。そこで勧誘の仕事を担当した。楽な作業ではない。訪ねては断られ、断られては訪ねた。
レコード店を訪問し、にっこり笑って挨拶し、推奨打販売を依頼するなど彼女にとって朝飯前の仕事だったのだ。
大当たりをとった安井さち子のM&I第二作目が年末の発売を目指して目下進行中という。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年05月①/第09回 “スタンダード曲"をいろんな演奏で聴こう
2005年05月①/第09回 “スタンダード曲"をいろんな演奏で聴こう

さて、本日はサービス・デイである。我が皆さんに取っておきのサービスをしようというのである。私も安い給料でよくやるよ。
ジャズの秘伝をお教えしようというのだ。これさえ実行すれば死ぬまでジャズを愛し続けてゆけるというメソッド。
大抵の人は途中でジャズから去っていってしまう。せっかく1,000人、2,000人に一人という狭い門をくぐり抜けて目出度くジャズ・ファンになったというのに。
スタンダード・ソングを100曲憶える。これである。何だ、誇大前宣伝のわりには大したことねえな、と言わないで欲しい。
スタンダードを100曲憶える。たったこれだけのことだが、このことをこれまでに私のように表立って発表した人がいるだろうか。
そんな愚かな奴いるわけないだろ、だって?
まあ、そうかもしれない。しかし、これからのジャズ界は愚か者が必要なのよ。ジャズ文化が成熟して皆リッパでもっともらしいことしか言わなくなった。だからジャズがつまらなくなったのだ。大体ジャズっていうのは愚か者の音楽なんだから。利口な人はクラシックを聴けばよろしい。
さて、100曲。有名曲を100曲。
旋律通りに憶える。これが先決である。
ということはジャズの演奏を聴いたのでは駄目だ。ジャズは「くずしの音楽」だから。まず普通のミュージシャンは作曲された旋律のまんま演奏することはない。
ではどうしたらいいか。ヴォーカルがいい。ヴォーカルを好きになることがジャズ・ファンへの近道である。
それともう一つ。例えば、ジャッキー・グリースンみたいなストリングス・オーケストラを聴いたらいい。
今日は秘伝伝授の日であるから遠慮なく私のほうも宣伝をさせていただこう。
5月20日に東芝EMIから発売されるテラシマ・コレクション10枚の中に入っているジャッキー・グリースン、ネルソン・リドル、サム・ドナヒューの3ストリングス楽団。
これらの中にこれさえ憶えればという美味しいスタンダードが、数えてみたら38曲も入っている。もうこれだけで4割方クリアーできている。それに、男性ヴォーカルのボブ・マニングを加えれば、いやはや立派に50曲。
これで感謝と感謝の大交換会が成立したわけ。せちがらい世の中、時にはこのように上手くゆくものなのである。
さて、スタンダードの旋律を憶えた。いよいよ、ジャズで演奏されたスタンダードを聴いてゆく。
本日ご紹介の「a列車でゆこう」。最初に元祖家元のデューク・エリントン楽団で聴いてみよう。スイング・ガールズでもいい。
次にすかさずジャケットで展示されているデイブ・ブルーベック四重奏団に耳を傾ける。
すると、来るのである。驚き、が。
こ、こ、こんなに違うのか。ジャズの演奏におけるスタンダードのあしらいはまるでこんなに異なったものなのか。
こりゃクラシックやった人がたまに飽きてジャズの世界に飛び込んでくるわけだわ。あなたはきっとこんな風にたまげることだろう。
デイブ・ブルーベック・カルテットの演奏。ただもう、ひたすら「恰好いい―」なのである。明治・大正時代の人が急にNYの摩天楼を見ちゃったようなものである。
驚きを満喫するためには、そうです。「a列車でゆこう」の旋律を旋律通りに素直にようく知っておく必要があるのはもうおわかりだろう。
知って何度もたまげてしまうと、あなたは面白くなってもうジャズから離れられない。
次々にたまげたくてCDに触手を伸ばしてゆく。
死んでも死に切れないのである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年04月②/第08回 楽器こと始めでジャズの耳慣らし?!
2005年04月②/第08回 楽器こと始めでジャズの耳慣らし?!

前号に続き楽器関連の記事でゆきたい。
さあ、さあ、苦しうない。もっと前へ。
よく、楽器を始めるとジャズの聴き方が変わる、というよね。
「いやあ、もう全然変わっちゃったよう。オレ、今までなに聴いてたんだろうね。」
顔をホクホクさせて、こうのたまったのは数年前にドラムを始めた「イントロ」の茂串さんである。言わずと知れた高田馬場のジャズ喫茶店主。
5年前にトロンボーンを開始した私の場合はどうか。
まず、レコードに対する尊敬の念が高まった。
例えば、である。本日ご紹介のJ.J.ジョンソン『ブルー・トロンボーン』。
もう実に名作。トランペットがマイルス・デイビスの『カインド・オブ・ブルー』であり、テナー・サックスがソニー・ロリンズの『サキソフォン・フロサス』であるように、トロンボーンはJ.J.『ブルー・トロンボーン』なのだ。
有無を言わせぬ力があった。
しかし、いくら名作でも毎日聞かされるとねえ。私はその頃現場を預かるジャズ喫茶のオヤジ兼レコード係であった。
しかし、楽器を始めてから聴いた一曲目の「ハロー・ヤング・ラバーズ」。
まさに、ウワッーである。いい年をしたオッサンが驚愕と歓喜の声を上げたのだ。
私はその頃、リチャード・ロジャースが「王様と私」の中で使ったその曲の見目麗しい旋律とそれと全く対照的な荒々しいマックス・ローチのシンバリングぐらいしか聴いていなかった。
でも今は。このアドリブ・フレーズは一体何なんだようという、これは化け物だようという驚き。
これは間違いなくJ.J.ジョンソンのアドリブ芸術の最高の一つだ。私はそう確信したのである。
細部に目がゆくようになった。ピアノのトミー・フラナガンが8小節のイントロをつける。そらゆけという感じでマックス・ローチがコチンと合図の一発を送る。
そこですかさずJ.J.がプッと最初の一音を発するのだが、そのタイミングが実に巧妙、これ以上0.1秒遅れても早くてもいけない絶好の間合いぶりにしびれるのだ。
私も合わせて吹いてみる。何度やっても合わない。
最初の8小節と次の8小節は同一メロディーながら微妙にニュアンスを変えて、ただ単純に吹いているんじゃないんだなぁ。即興のようでありながら、そこには前もっての深い考察があるんだなぁ、と。
そして、先述のソロ・ワークである。以前はソロなどろくすっぽ聴いていなかった。
今度は聴いている。ソロのフレーズを盗み取ろうとしているから。あわよくば、そっくりそのまま吹いてやろうと。
これが、凄い。絵に描いたようだ。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年04月①/第07回 CDデビューはライブ・ハウスから
2005年04月①/第07回 CDデビューはライブ・ハウスから

今や、ジャズは聴く時代ではなく、演る時代である。
このままでゆくと聴く人はどんどん減り、演る人はどんどん増えてゆく。
さて、そこであなた。あなたもなにか楽器をやるでしょう。私は当たるを幸い、いろんな人に訊いてみる。
「いや実はトランペットをちょっと。」
「えー、私はギターを少々。」
「クラリネットをブラス・バンドで。」
得意そうに鼻をうごめかす。人は得意になると本人の自覚なしに鼻が動くのである。
それはともかく。
楽器を演る人は多いが、実は、成就する人はまことに少ない。100人に一人というところだろう。
成就するにはどうしたらいいか。ある有名なミュージシャンに訊いてみた。「楽器がうまいと女にもてる。」この一念を失わないことだそうだ。
さて、あなたが一念を捨てず一丁前になったとしよう。すると今度はCDを出したくなる。これはしかし難関である。一万人に一人といっても過言ではない。
でもこれはいわゆるメジャー・デビューの話。マイナー・リリースでよければ幾らでも話はある。
よろしい。本日はその話をしよう。あなたが目出度くCDを世の中にぶっ放すにはどうしたらいいか。
ライブ・ハウスに出演するのである。どこのライブ・ハウスでもいいわけではない。
厳選の限りを尽くす必要がある。
どういうライブ・ハウスを選んだらいいか。
CDをリリースしているライブ・ハウスである。
当然のことながら、そう何軒もあるわけではない。
ニューヨークでいえば「スモールズ」がある。有名な「ブルーノート」のそばにある若年ミュージシャンの登竜門といわれるライブ・ハウスで、ここは最近バンバン若年のCDを発売し始めた。
しかし、ニューヨークは遠い。
近間で探さなければいけない。
赤坂の「ビー・フラット」。ここが現在、自店に出演のミュージシャンの作品を世に問い出したのだ。
レーベル名は「セブン・ステップス」。マイルスが演奏した有名な「セブン・ステップス・トゥ・ヘブン」という曲がある。「天国への七つの階段」だ。
すでに何枚か出版していずれも順調な歩みをたどっているという。
今日はそのうちの一枚をご紹介しよう。
CDの主人公4人はライブ・ハウス「ビー・フラット」の主要出演メンバーだ。
アルト・サックス、バリトン・サックス、ベース、ドラムスのカルテット編成でピアノ抜き。なぜピアノがないのか。
ピアノはソフトな楽器のイメージだが意外にもゲンコのような音を出す。これが入る入らないでトータルの音が全然違ってきてしまう。ピアノが入らないと全体のサウンドが実に柔らかく感じられる。4人はリクイッド・サウンド、つまり流体的ソフト・フォーカスの音を狙ったというわけだ。
流れるような柔らかいサウンドで似合う曲といったら「センチメンタル・ジャーニー」の右に出るものはない。
録音のほうの音は、いまいちだなぁ、と言う人がいるかもしれないが、いわばスッピンの音。
化粧をしていない音ということだ。
お金持ちメジャー・レーベルではないから機材にお金がかけられない。
でもスッピン・サウンドが逆に幸いした。
いかにもライブ・ハウスで録音したんだなとわかるザワッーと反射する音。
作られたという音からいちばん遠い音。
自然主義リアリズム、ここに極まれるなり。
志賀直哉の文章のような音なのだ。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年03月②/第06回 “聴く"こそものの上手なれ?!
2005年03月②/第06回 “聴く"こそものの上手なれ?!

あなた。そう、あなたです。なにか楽器やりますか。
トランペット、トロンボーン、テナー・サックス、触ったこともないでしょう。
今からでも遅くはない。ぜひ、おやりなさい。
いや、オレなんか歳をとってるから駄目だあ。若いやつの音感にはかないっこない。
多分あなたはいま、そう考えたはずだ。
そりゃ、少年少女に音感ではかないっこない。憶えは遅い。しかし、あなたにはキャリアというものがある。
長年ジャズを聴いてきたではないですか。
少年少女は聴いていないんですよ。
例えば「ダニー・ボーイ」という曲がある。
あなたがピアノでこの曲を弾いてみたいとする。
少年少女は聴いていないからどう弾いていいかわからない。
ところがあなたには「ダニー・ボーイ」ならこういうふうに弾いてみたいというイメージがある。例えば、すすり上げる感じでやってみたいとか。
私は、こういうイメージはひょっとして音感よりも強い武器になるのではないかと思う。
少なくともジャズはフィーリングの音楽であるから「ダニー・ボーイ」を知らない少年少女が譜面を見ながら弾くより、つっかえつっかえながらもイメージを持って演奏するあなたの方に分があるように思えてならない。
これが私である。私は今、トロンボーンで「ダニー・ボーイ」を練習している。ものの見事につっかえ、つっかえ、である。
でもあの少女よりはオレの方がマシだなと思っていつも自分をなぐさめている。
その少女は私の通うジャズ学校で「ダニー・ボーイ」を吹いていた。
譜面を見ながら、淀みなく吹いていた。しかし、それは音楽として伝わってこなかった。音符の羅列に過ぎなかった。
小学生の棒読み、といった塩梅。
さあ、あなた、幾分勇気が湧いてきたでしょう。
いろんなミュージシャンの「ダニー・ボーイ」を長年にわたって聴いてきたあなた。
あなたがテナー・サックスが好きなら、ゆったりとしたペースでサブ・トーンをきかせながら、例えばベン・ウェブスターのように吹いてみるのもいい。
私は、楽器とは長年ジャズを聴いてきた人こそ手がけるものではないかと思う。
「イメージを持っていることほど強いものはない。」
これは私のトロンボーンの先生がいつも口にする言葉である。私はこの言葉にすがって練習に励んでいる。
60年以上もジャズを聴き続け、有り余るイメージを持った方が今度、トロンボーンを始めることになった。
岩浪洋三さんである。日本のジャズ評論界の第一人者。
この方が71才でこれまで触ったこともないトロンボーンを練習してゆくことになったのである。
「最初に何を吹いてみたいですか」
「『ダニー・ボーイ』」
私は感動した。感動してドクター3の「ダニー・ボーイ」をお聞かせした。
「こんなふうに吹いてみたいな。」
私は皆さんにお約束する。一年もしないうちに必ずうまくなる。
うまくなった岩浪さんの「ダニー・ボーイ」をPCMジャズ喫茶で全国に流す。
その日を首を長くして待っていてくれ。
寺島靖国(てらしまやすくに))
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年03月①/第05回 ビギナーはボーカルから
2005年03月①/第05回 ビギナーはボーカルから

さてと、ジャズ・ファンではないあなた、こちらへいらっしゃい。ジャズ・ファンのあなたもいらっしゃい。さあ、どうぞ。
私くらい両方の人に気を遣っている人間もいないのである。
ジャズ・ファンではないあなた、ジャズって聴いてみたいでしょう。でも何から聴いていいかわからない。このこと、皆さんそう仰るのである。口裏合わせたみたいに。
そこで私はすかさず、ボーカルからお聴きなさいと申し上げたい。
何故か。曲の旋律がはっきりわかるからである。ジャズの楽器演奏の難しさは第一にメロディーがはっきりしないところにある。
どうしてはっきりしないかというと、ジャズのミュージシャンがはっきりさせるのを嫌うからである。その通りやるとジャズにならないと思っているらしい。そんなことはないんだが。
曲の旋律がわかる。どんなジャンルの音楽もそうだと思うが、初めて聴いて曲のメロディーがわかるくらい嬉しいことはない。ジャズは特にそうなのである。
あなたが何かジャズでも聴いたとしよう。ああこういう曲か。わかったらあなたはいっぱしのジャズ通といってよい。
半分お世辞だけど、まあそのくらいジャズの曲というのははっきり言ってわかり難いものだ。
ジャズ・ミュージシャンの中にはどうせ儲からない音楽やってんだからわざと難しくしてやれ、なんてね。 そこでボーカルである。たいていのボーカリストはスタンダード・ソングを歌う。1920年代くらいからアメリカで続々と作曲されたアメリカの流行歌。それらを自分の個性で歌うのがジャズ・ボーカルと言われるものだ。 何だい。ボーカルっていうのは人を楽しむのか、曲を楽しむのかい、どっちだい。そういう疑問を持つ人もいるだろう。
いい疑問である。私なら最初に曲を聴けと言いたい。始めに曲ありき、なのだ。
曲とボーカルは仲のよいカップルあるいは夫婦の関係にある。だからジャズを志すビギナーは曲の旋律のはっきりわかるボーカルを聴くに限るのだ。
さて、では、どんなボーカルCDを聴いたらいいのだろう。
まず勿論、いい曲の入ったもの。美声の持ち主であること。そしてこれが一番大事なのだが美人であること。さらに重要なのがジャケットの抜群なこと。
これらの要件をピタリ200%実現してしまったのが本日のヒロイン、ジェーン・モンハイト。ご覧の通りの美貌であります。
これはボーカル日照りの続く昨今の相当な見っけもの。砂漠の中の満々と水をたたえた泉であります。 いま人気No.1のダイアナ・クラークより断然こちらを推薦したい。私はあのおばさん声にげんなりである。それに比べておお、こちらは私の大好きな処女の声なのだ。
であるから年季の入ったジャズ・ファンにもおすすめ出来る。ジャズ・マニアほど処女の声を愛する人種はいないのである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年02月②/第04回 サンバ・カンソンの女王、マイーザ
2005年02月②/第04回 サンバ・カンソンの女王、マイーザ

いやあ、しかし諸君。考えてみるとジャズってのは大変な音楽なのだ。
最初はちょっと難しい。でも、少してこずったりしてそのうち目の前の霧が開けるようにジャズがわかってくると、さあ今度は鬼の首でもとったような気分に陥って世界で一番ジャズがわかるのはオレじゃないか、みたいな気分になってしまう。
さらにどっぷり漬かると今度はジャズが特殊な音楽に見えてくる。最上級の音楽、さらには音楽を超えた音楽、てな具合に映ってくるのだ。音楽の神。
感極まって「ジャズより他に神はなし」と絶叫したのが奇人、平岡正明。 勿論、現在はこういう人たちは非常に少ない。でも1950~70年代のジャズ全盛時代はそのへんにうようよしていたのだ。あぶない目つきをした人が。
ジャズ論議の果て、相手をボコボコに殴っちゃったり。刃傷沙汰にも及んだらしい。
まあ要するに、ジャズとはそのくらい魅力的な音楽なのだ。それは、今も昔も変わりない。
私はそれを言いたかったのだ。私だって今、時々ジャズの話をしていてムカッとする時がある。相手があんまりわからんことを言うとね。いや、これはちょっと尊大な言い方だった。単純にジャズの聴き方の違いというすれ違い。
ジャズというのは、なかなかストレスの多い音楽だなあと思うだろう。ストレスを感じるくらい魅力的な音楽なんですよ。また言ってしまった。
ストレスを感じたら何を聴くか。これが今日の課題である。ストレスなんかないって?
それはそうでしょう。現代っ子の皆さんはいろんな音楽を聴くから。
しかし、ジャズしか聴かない私には時折特効薬が必要になる。最近いい薬を見つけた。
マイーザ、である。これがリラックスの素なのだ。ごらんの通りのすさまじい美人である。見ているだけで別の世界に連れていかれるようで浮世の垢が落ちてゆく。
ブラジルの人である。従って、ジャズではない。ジャズではないのがいいのである。
良家に生まれ、ブラジルで十番目に金持ちの家に嫁いだと言う。1950年代半ば、当時まだボサノバは誕生せず、その前身ともいえるサンバ・カンソンというリズムで歌っていた。上流階級でポピュラー音楽を歌うことに軋轢があったらしい。何かの拍子に酒びたりになり、あげく40歳で事故死。破滅型の歌手の典型だ。ブラジルのビリー・ホリデーと呼ばれる。
破滅歌手だろうが酒びたりだろうが、これが私にとっては魂の救済なのである。一曲目「崩れた世界」のボタンを押すと私はもうそのままたちまち天国に運ばれてゆく気分だ。
洗濯板を幼児が優しくさするような、サンバ・カンソンのリズムに乗って物憂げに歌うマイーザの旋律を聴いていると、身体が琥珀色に染まってゆくのを感ずる。この歳になってえらいものを見つけてしまった。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年02月①/第03回 “ジャズの本質"の楽しみ
2005年02月①/第03回 “ジャズの本質"の楽しみ

やあ諸君、おめでとう。今年も面白くて為になる記事を大いに書いてゆくぞ。
なんたってこの世の中、見渡せば面白くなくてひたすら為になる文章ばかりだからな。
そういえば最近、講談社現代新書、清水義範の『大人のための文章教室』を読んだ。
文章というのは①言いたいことが曇りなく読み手に伝わるかどうか。②文章を書いている自分が利口そうにみえるかどうか。この二つのことを書き手というのは意識的無意識的に置いて書いているというのである。
ところが考えてみるとこの二つの要素は相反していて同時に成立させるのは無理な話なのだ。
言いたいことをストレートにやさしく書くとあんまり利口にはみえないのである。
例えば、私のいつもの文章である。
とてもお利口には見えないよなあ。
まあいい。バカはバカなりに書いてゆくしかない。それを悟っただけでもリッパなものだ。
さて、上のジャケットをとっくり眺めていただきたい。あなたはこのCDを知っているか。
知っていたら私に連絡しなさい。10万両差し上げよう。
知っているわけないんだ。ジャズ評論家多しと言えどもご存知なのは一人か二人だろう。もち、私だって知らなかった。
そんな、誰も知らないようなCDをなんでこのページで紹介するんだ、このやろう、なんてあなたはお思いだろう。
そこがつけめ、なのである。たまにこういうわけのわからないディスクを俎上にあげないとジャズの楽しみの本質が見えてこない、ということだ。
ジャズの楽しみの本質とはなにか。
さあ、言うぞ。こういう誰も知らないディスクを夜中の2時頃、「ヒッ、ヒッ、ヒッ」と笑いながら一人静かにライブラリーから取り出しトレイに収め、この盤の聴きどころは5曲目の「ノー・ベース」にあるのだぞよ、知らないだろう、知っているのは全世界でオレを含めて三人ぐらいだろうなあ、とホクソ笑んで一人悦に入る。
それがジャズの楽しみの極限的本質というものなのだ。
ジャズというのはそういう音楽なのである。そういうインビな性質を持って生まれついているということだ。いや、いや、皆さんはいいんだ。心配しなくてもいい。ビギナーのあなた。ビル・エバンスやキース・ジャレット、マイルス・デイビスやジョン・コルトレーン。そういう有名人を聴いていてけっこう。
でも、そのうち、なにかの拍子になにか変わったものを聴いてみたいなあ、と思った時、その時がジャズの楽しみの本質の門の前に立った時なのだ。100人のうち99人までが門の中に入れずジャズから去ってゆく。
最後の一人にあなたはなりたいとは思わないか。いや、なって欲しい。そしてジャズの極限的楽しみを心ゆくまで味わって欲しいのだ。
今回のピアノ・トリオ盤、極限などと言うからさぞ、難しい一枚だと思われたろう。
なんの、なんの。ミュージシャンの言いたいこと、伝えたいことが曇りなくリスナーに伝わり、なおかつお利口に見せようなどということは何一つ演っていないというまさに名演の名に恥じないもの、と言っておく。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年01月②/第02回 “オーディオ快感"をジャズで体感
2005年01月②/第02回 “オーディオ快感"をジャズで体感

さて、諸君、今回もこのページに目を止めてくれてありがとう。前々回は見当たらずさぞ寂しい思いをしたことだろう。陰謀なのだ。この雑誌の編集者の。私だって悲しかったぞ。
さて、今回はオーディオの話とゆこう。
おっとっと、早くも逃げようとするあなた。待ちなさい。大事なんだよ、オーディオっていうのは。
ライブは舞台から音が聞こえてくる。
オーディオはスピーカーから音が流れる。同じなんだ。要するに出来るだけいい音でCDを聴こうっていうのがオーディオ。
ところがオーディオ雑誌っていうのは位相だ定位だと専門用語をふりかざしてくる。無視、無視。そんなの評論家の自己満足。テクニカル・タームを使わずに音の本質そして楽しさを伝えるのがアンタたちの役目だろう。エッ、文句あるか、なんて私なんかはついけんつくを喰わせたくなってくる。
それはさておき、ジャズの音でいちばんわかり易いのがドラムの音だということをまずお伝えしよう。
ついでに言うと演奏の上手下手のわかり易いのもドラムという楽器。ドラマーは大変だ。
ジャズ・ファンだったら誰だっていい音で聴きたいのがシンバルだろう。クラシックにもない、ロックにもない、シンバルの規則的な連打こそジャズの特質である。これがジャズの最も美味しいところの一つ。
それからその規則的な右手の連打に合わせてドラマーの叩く不規則な左手のスネア・ドラムもまた大きな魅力。
さらにその規則的と不規則的の微妙な交錯がジャズの最大魅力と申し上げたい。――交錯と言うか愛憎。
しかし、こんな話を得意そうにしていると今度は私がけんつくを喰わされる番になってしまう。
今回のCDでは近頃最も微妙な交錯を天才的に行うブライアン・ブレイドをご紹介しよう。
CDをお買いになったら迷わず・のボタンを押してくれ。リーダー、北川潔のオリジナル曲で「Time to go 」。
ピアノ・トリオながらピアノは現れず、ドラムとベースがヨーイ・ドンで走り始める。この二人駆けっこがまたジャズの魅力点の一つなのだが、問題はその音。ドラムの音。スネア・ドラムの音。
「コーン」と弾けるのだ。これが滅茶苦茶気持ちいいのだ。単なる「コーン」ではなく、その内部にマグマのようなエネルギーが詰まっている。
だから「コーン」という音が出るとまわりの空気が思わず振動しなくちゃいられなくなるわけ。で、震える。
「コーン」という音と同時にこの震える空気をあなたに聴いてもらいたいのだ。これがオーディオの快感と言わずしてなんと言おう。
オーディオ用語で「空気感」と称する。これはわかり易い。これなら許せる。
ケニー・バロンのピアノも青いサファイアのようだ。「君は変わったね」などという絶妙のバラードも入っている。しかし私にとっての最大の聴きどころはなんといっても「Time to go 」の出だしの数小節。これに尽きるのだ。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ
 2005年01月①/第01回 「音の四大要素」を実証したトロンボーン奏者、神田めぐみ
2005年01月①/第01回 「音の四大要素」を実証したトロンボーン奏者、神田めぐみ

さて、皆さん。ジャズの世界へようこそ。ジャズの伝道師、テラシマです。
ところで「音楽の三大要素」ってあなたはご存知か。音だろうって?おお、あなたは立派です。実は、本当は、リズム、旋律、ハーモニーなんだが、私に言わせりゃ、音、つまりサウンドが要素の一つとして欠けているんだね。これを加えて「四大要素」にしなけりゃいけない。
だってどんなミュージシャンだって音を作るのに凄く苦労するのである。案外これが忘れられているのである。ミュージシャンは音を一番大事にする。演奏する時に。ファンは音を一番大事にしない。聴く時に。
この間、エリック・アレキサンダーという、今日本で人気第三位のテナー・サックス奏者にインタビューした。 「どんなミュージシャンになりたい?」 「一音でエリック・アレキサンダーだとわかってもらえるミュージシャンになりたい。」
もちろん、さまざまな演奏法を含んでの話である。でも彼の言う演奏法の最も重要な要素が楽器の音なのだ。
さて、本日ご紹介の神田めぐみさん。私はこの方を紹介するのを名誉に思う。すばらしい音を出している方なのである。こんな音が出たら死んでもいい、というくらいのいい音である。オーディオ装置でいうと一千万円クラスのスピーカーから出る音、と言ってもいい。 要するに天使のサウンドなのだ。
昔、トミー・ドーシーというトロンボーン奏者がいた。この人が天使のサウンドを出現させていた。どうしてこういう音が出るんだ。バンドのメンバーがいぶかしんで彼の楽器を調べたという。もちろん何も出てきやしない。スライドの内側に薄いビロードか何かを張ったんじゃないかと疑ったらしい。
まあ、一種の伝説話だろう。しかし、この伝に習えば私は彼女の口の中には何か特殊な装置が施されているように思えてならない。もちろん装置なんてありゃしない。あるのは工夫である。努力の結果である。長年の研鑚の賜である。白鳥に例えよう。湖面を優美に泳ぐ白鳥。しかし水面下の足は結構不様にもがいている。彼女の口の中ももがいている。天使の音の源泉は彼女の口の中のもがき、にあるのだ。それと息の流し方。舌は上へ行ったり下へ行ったり。急速な上下運動を繰り返している。
録音も味方した。1940年ぐらいのトミー・ドーシーの頃と比べ、現代の録音は空気感をディスクに採取できるようになった。おかげで楽器の響きが一段と麗しくなった。
確かに彼女の演奏にはジャズ的に「汚れた」部分が少ない。ジャズ・ファンはその点不満だろう。なにせ彼女はアメリカのクラシック交響楽団の首席奏者だ。
しかしトロンボーンとはこんな美しい音色を出す楽器なのか。このCDを聴いて初めてそのことに気付くジャズ・ファンが多いんじゃないだろうか。つまりトロンボーン再発見。
私に言わせれば楽器は音で聴くべし、なのだ。彼女はそれを鮮やかに実証してみせた。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ