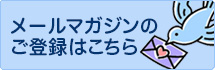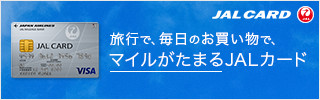コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」
<雑誌に書かせてもらえない、ここだけのオーディオ・トピックス>
ミュージックバード出演中の3名のオーディオ評論家が綴るオーディオ的視点コラム! バックナンバー
第53回/オーディオの音、生の音 [鈴木裕]
|
2014年3月15日。 |
 エリアフ・インバル |
念のためにこれは強く書いておきたいのだが、東京芸術劇場がコンサートホールとして音が悪いとか、都響の音が芳しくないということでは一切ない。自分の問題だ。要するに鈴木裕が不感症になってしまったのかと思ったのだ。オーディオにうつつを抜かして、生のオーケストラでいけない奴。
自慢話のようになってしまって恐縮だが、ここのところうちのオーディオの調子は良く、SACDとかハイレゾの音源でオーケストラを聴いているとコンサートホールにいるような空気感が出てくる。以前であれば、いくらオーディオで音楽を聴いていてもコンサートホールに実際に行って、オーケストラのチューニングが始まっただけで「そうそうこの感じ」と心持ちが良くなる感覚があったが、それがその日にはなかった。いいオーディオの音に慣れすぎて、麻痺しているのかもしれない。
慣れすぎは美しくない生き方である。生の音楽を聴けないカラダになってしまったのか。それは人としてどうなのか。オーディオを通してしか音楽を聴けないのか。危機感を持ったのだった。
ただ、さすがに客観的に考えて思い付くのは、聴いたのが東京芸術劇場の3階というと、たしかにオーケストラからの物理的な距離は近くない席だ。長い空気の層を音が伝わってくる位置なのは間違いない。上記したようにバランスもいいし、音量感も悪くはないが、それでも音のエッジが微妙に鈍っているようにも感じられた。
2014年7月21日。
サントリーホールでインバル指揮/東京都交響楽団の演奏でマーラーの第10交響曲(クック版)を聴いた。インバル/都響で感じた不感症の疑いは、やはり彼らに払拭してもらわなければならない。しかも10番である(このあたり、10番について厚く熱く語りたいが、もう既に相当暑苦しくなっているので割愛)。今度は1階の、前から4列目の席が取れた。1stヴァイオリンの前から3組目(プルト、という言い方をするが)の位置が正面に見える席だ。1
プルから5プルまでが、自分の左右40度ほどの視界に入っているし、さらにその奥にはハープがいる。たぶん一番近いプレーヤーとは5メートルほどの距離。なにしろ近くで聴きたかった。
かつて大学生の頃、編成の大きい曲をやりたがる学生オケに在籍してヴァイオリンを弾いていたせいか、オケの音は大きいという刷り込みからどうも抜け出せない。ショスタコーヴィッチの第5交響曲、ストラヴィンスキーの「火の鳥」、ラフマニノフの「交響的舞曲」、レスピーギの「ローマの松」。どれも自分の弾いているヴァイオリンの音が聞こえなくなる瞬間のある曲だ。そんな曲ばかりやっていたのだから。
演奏自体も9番の時に較べて10番の方がさらに集中力があるように思ったが、やはりオケに近いことが自分にとっては重要だったようだ。圧倒的な音の洪水があり、肌や内蔵や骨格に響く低域の音圧があり、あるいは超高域の、ダイレクトに脳に飛び込んでくる倍音成分が音楽に異様なヴァイタリティを与えているようにも感じた。
特に、他人が補完したとは言え全5楽章として成立している第10交響曲において僕が重要だと思っているのは、5楽章冒頭からのグランカッサの強打である。第6交響曲の終楽章において、巨大な木製のハンマーが運命の鉄槌のごとく2回(初稿では3回)振り下ろされるが、あれ以上に虚無感を持って、生きていたことへの甘美な想いやある種の平穏さを打ち砕く、それこそ言葉の意味として二重にデッドなグランカッサ。あの音が本気で痛かった。心臓が止まりそうだった。
現代の、世界で一番すごいオーディオを持ってきてもこの日の、あの席で聴いたマーラーは再現できないだろう。あまりにも当たり前で恐縮だが、生でしか聴けない音があり、生でしか経験できない音楽がある。その当たり前が揺らいでいたのだが。
人としてまだ生きていけると思った。
(2014年7月31日更新) 第52回に戻る 第54回に進む
コラム「ミュージックバードってオーディオだ!」バックナンバー