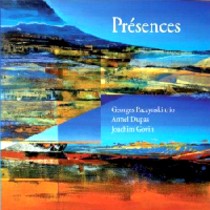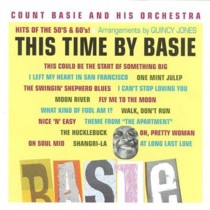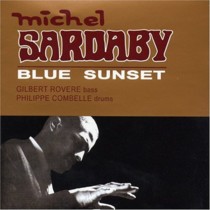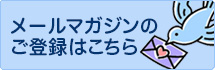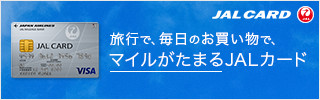新しいジャズ雑誌が創刊されるという。
『ジャズ・ジャパン』。
案内状によると「ジャズ・ドキュメント」誌をコンセプトに、ジャズ・ファンありき、音楽ファンありきの初心に立ち戻って出発するとのこと。
いい話である。つい先日「スィング・ジャーナル」誌が休刊となり、くさっていたところへのビッグニュース、新雑誌のスタートを歓迎したい。
この際、ジャズの雑誌とは何かについて考えてみようじゃないか。ちょっと突飛な発想かもしれないがジャズの雑誌は「雑誌のためのジャズ」を作っているのである。私は嫌味な人間だが、嫌味で言ってるんじゃない。要するに雑誌が存続してゆくためには買ってもらうことが前提になる。買ってもらうためにはどうしたらいいか。教科書化することである。読者は生徒なのだ。ジャズの聴き方の法則を作って生徒に教え込む。
法則といえば、むかし私は『ジャズの聴き方に法則はない』という文庫本を出した。ぜんぜん売れず、すぐに絶版になった。聴き方に法則あり、としなければいけなかったのだ。
特に新しいジャズ・ファンは法則を求めて雑誌を買う。ビ・バップ、ハード・バップ、新主流派などという演奏スタイルの呼称があるが、この呼称に添って雑誌のCD評は成立してきた。「スィング・ジャーナル」のレコード・レビューアーはこの法則にのっとり、そこから一歩も抜け出せなかった。
ところがである、初めのうちこそ読者は法則に従って聞いているが、当然そういう聴き方をしていてジャズが面白いわけが無い。もっと根本的に聞くべき要素があるだろう、と。スイングであり、メロディーであり、からみ合い、睦み合い、そして楽器のサウンドである。大体5年くらいといわれているが、読者が「雑誌の聴かせ方」と「自分の聴き方」のへだたりに気付いた時、別れが待っているといえるのだ。
かと言ってである。「法則」を無視して雑誌は成立しない。雑誌も大変である。
『ジャズ・ジャパン』の社長兼編集長はスィング・ジャーナル誌の編集長を務めた三森隆文氏。どのような辣腕をふるうのか。これ、ワクワクせずにおられるか、といったところだ。
そんな風雲急を告げるジャズ・シーンに、これはまたのんびりとお出ましなのがバリー・ハリス。スィング・ジャーナル流に言えば「ビ・バップ流派の引き継ぎピアニスト」ということになるが、そんな法則は頭の片隅に追いやってひたすら1曲目の「She」を聴いて欲しい。ジョージ・シアリングの作曲で、さてどんな『She』がきみの頭に浮かぶのか。
私の場合はジーナ・ロロブリジーダだった。
きみ知るか、この往年の豊満イタリア女優。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ