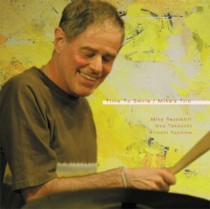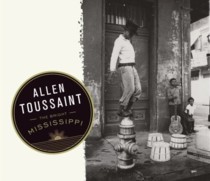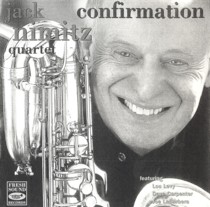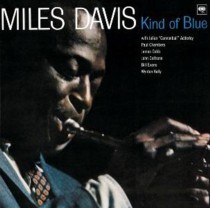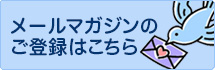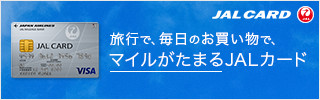「PCMジャズ喫茶」はゲストに頼っているところがある。私と岩浪洋三さんだけではお手上げである。長いお付き合いなのでお互い一言発すれば次の展開が分かってしまい、そうなると次に陥るのはいつもの恐るべきマンネリズムで、にっちもさっちもいかなくなってしまう。
アルトサックスのジャッキー・マクリーンやピアノのバリー・ハリスが紡ぎだすあのマンネリ・フレーズは「あっ、また出た」と言って嬉しく手を叩けるような芸の域に達したもので、これはこれで賞すべきだが、我々二人のフレージングは当然そうはゆかない。
そこで苦しい時の神頼み、ゲストの登場になるが今回の茂串さんは面白かった。茂串さんはご存知のようにジャズ喫茶「イントロ」他数店の経営者である一方、ジャズの論客、文章家としてもよく知られている。茂串さんは数枚のCDを用意してきた。その中にウィントン・ケリーの、よく我々が『ハシゴのケリー』と呼んでいたリバーサイド盤があった。
ウィントン・ケリーも、そういえば臆面もなく発する数々のマンネリ・フレーズを芸術の域に昇華した人である。それは別にして茂串さんは「このリバーサイド盤に興味深い別テイクが一曲見つかった」と言った。よくある話であり、だから最近再発のCDはうっかり出来ないのである。
実はこのCDにはドラム入りとドラムレスの曲が混在している。ドラマーはフィリー・ジョー・ジョーンズである。昔のジャズ・ミュージシャンは概してちゃらんぽらんだから、その性格がうまく演奏に加味された時に名演が生まれるが、この一作もその伝で、名作なのだがちゃらんぽらんの名手フィリー・ジョーが録音スタジオに遅れてきたかどうかして、とにかく何曲かには彼が参加していない。
茂串さんが言うには、今回発見された別テイクにはフィリー・ジョーが加わっている。しかしどうも聴くところ、若干フィリー・ジョーの匂いが薄い。皆さんの耳のいいところでそこいらあたりを判別してくれ、と言うのである。
よっしゃ、まかせてくれ!こちとら50年以上もジャズを聴いているんだ。まして私は以前から大のフィリー・ジョー・ファンである。聴いてみると、たしかにフィリー・ジョーにしては納豆が糸を引くような粘りが希薄である。グルーヴ感もいささか後退している。音にも1950年代から60年代の古めかしさがない。しかし最新24ビットの近代的マシーンを通した再発CDの音というのは驚くほど新鮮だ。
岩浪さんはどうもフィリー・ジョーらしくないと言う。フィリーにしてはあっさりしすぎていると。しかし私はフィリー・ジョーと確信した。フィリーだって元気のない時もあるさ。だからお蔵入りになって今頃現れてきたんだ。
演奏が終わり、茂串さんが笑い出した。
「これ、オレなんだよね。オレが叩いているんだよ」
一計を案じたのである。
ドラムレスのトラックに自分で叩いたドラムをかぶせたのである。
これはしくじった。完ぺきに一杯くわされた。なんという口惜しさだ。私は、茂串さんが10年以上もドラムを練習し近頃は玄人はだしの腕前になっているのをすっかり忘れていたのである。
寺島靖国(てらしまやすくに)
1938年東京生まれ。いわずと知れた吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のオーナー。
ジャズ喫茶「MEG」ホームページ